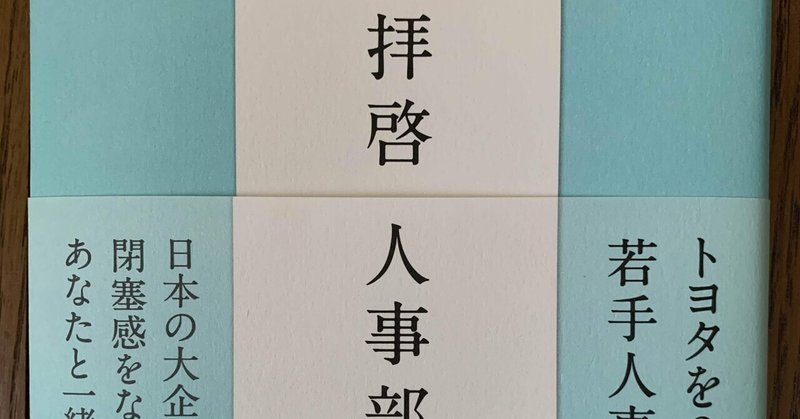
『拝啓 ○○殿』~私は旅の終わりに誰に手紙を書くのか?~
『拝啓 人事部長殿』という本を手に取る
この本はひとことで言うと、
理想の人事制度を求めて旅に出たある人の旅の記録です。
内容を端的に言うと、
大企業トヨタに入社し、意図せず人事部に配属された著者が、疑問や閉塞感を抱え、サイボウズという自由な会社に転職し、他社の多様な人事制度を集め、自身なりの答えを見出す話です。
サイボウズは興味ありますが、その人事制度なら知っています。
本のボリュームも金額も大きいので、ただそれだけなら買って読もうとは思いませんでした。
あまり期待もせず試しにページをパラパラめくると、
最初に『人事部長』に充てた手紙が書かれていました。
ぼくがいま、この手紙を書いているのは、どうしてもトヨタの人事部長であるあなたにお伝えしたいことがあるからです。
それでもぼくはあきらめたくありませんでした。なぜなら、トヨタという会社の目指す理想や大切にしていることに共感していたからです。モビリティ(移動)を通じて社会に価値を、幸せを提供していくこと。そのために、「現地現物」で物事の原因を見極め、改善を続けていくこと。
時間や場所の自由は利かず、コミュニケーションは一方通行で限定的。健康管理の支援は期待できず、突然、想像もしていなかった部署に異動させられてしまうかもしれません。数多ある一律の研修を潜りぬけてうん十年と年齢を重ねてもなお、気づけば専門性はなく、そのころには評価の軸が変わっている可能性だってあります。(略)
ぼくは本当に今の思いを持ち続けたまま、いつかトヨタの会社のしくみを改善することはできるのだろうか。
どんな思いでトヨタを飛び出したか、何を学ぼうとしたか、著者の想いがどんどん入ってきました。
採用、配置・異動、時間、場所、コミュニケーション、健康管理……。
ぼくは薄々気がついていました。こうした会社のしくみにおいて、個性が重視されていないことが、じわじわとぼくの「1人の人間として重視されている感覚」を奪っている、ということに。
その想いは、私の持っているモヤモヤとも共鳴したのです。
手に取って一緒にこの本で旅をしてみたいと思いました。
そして初めからこんな予感がありました。
◆私も誰かに手紙を書くことになるだろう。
◆読了したところから私の旅はスタートするだろう。
私のいる場所
著者が感じた「1人の人間として重視されている感覚の薄さ」は、今まで私も会社組織の中で感じてきたことです。
マジョリティの著者と違い、私は新卒入社したものの、そのあと派遣社員として色んな会社を転々としてきました。キャリアがつくこともなく毎回リセットされます。
出産後に働こうと思っても、小さい子供がいると時間や勤務地の制約があり、なかなか仕事がみつからず(ワンオペだと急な早退やお休みがあるので敬遠されがち)工場の歯車として働いたこともあります。
キャリアを描くというより、お金を稼ぐためにその時の仕事にあわせて最適な仕事をしてきたのが精いっぱいでした。やりたいことなど考えてませんでした。安定して働けるだけでいいと思っていました。
今、社員として安定して働けるようになると、モチベーションやキャリアを考えていく機会ができます。ここで初めて仕事とはなにか?が芽生えてきました。そして会社と自分の関係を初めて考えます。
◆私は会社にどんな貢献ができるだろうか?
◆会社は私になにを求めているのか?
ところが、面談などで聞いてみてもはっきりとした回答が得られません。
同じ成果なら誰でもいいのだとすると、必ずしもそこにいる理由はないはずです。
年2回の形だけの評価面談。コミュニケーションの薄さ。発信した様々な意見は誰に伝わってどこまで影響を与えたのかの情報のなさ。私が日々なにを感じてなにを会社を通して得ているのかは、求められていません。
◆会社は私の個性を必要としないのか?
こうして「1人の人間として重視されている感覚の薄さ」を感じるようになりました。
モチベーションを高めるために資格勉強をしたり本を読んだりしました。
他の会社や制度など、外に目を向けてみることにしました。
(サイボウズの制度はその時知りました)
それをもとに上司に意見したこともあります。
「うちは、サイボウズじゃないからね。」同じことを言われました。
◆なぜサイボウズだからできるのか?うちの会社との違いは何か?
◆サイボウズのなかでなにか問題はあるのだろうか?
いくつかの疑問をもちながらページをめくっていきます。
なにか答えがみつかるだろうか?
人事制度という旅に出る
著者は人事側の人として、自分なりの3つの疑問をもとに日本の人事制度を紐解いていきます。
私は今までも(多分これからも)人事側の人ではないので、いち社員としての目線で日本の人事制度をみていきます。
この本では、会社の仕組みを年代の変遷とともに
人事制度の内容を各パーツにわけたマトリクスに当てはめていきます。
あつめる:採用
きめる:契約・時間・場所
はたらく:健康(安全配慮)・コミュニケーション/風土・育成
配置/異動・報酬/評価
はなれる:退職
●1930年代~1950年代
人事制度を一律にすることで労働者の平等を保ったこと。
●1960年代~1980年代
経済成長期とともに変革や改革が試行錯誤されつつも、日本の人事制度は有効だったこと。
●1990年代~現在
伝統的な人事制度ではうまくいかなくなっていること。(閉塞感やもっと深刻な問題も)
制度の変遷などは理解しましたが、あまり詳しくは書きません。
この本を読む目的は、私の疑問に答えが見つかるかが知りたいからです。
現在の社会と人事制度が乖離しているなかで、他にも改革を進めている企業はいるのか?という点で、12の企業の例が紹介されていました。
個々の企業がどんな制度をつくったか見ていくと、共通点がありました。
答えはそこにあったか?
◆なぜサイボウズだからできるのか?うちの会社との違いは何か?
12の会社それぞれの制度を見ていくとき、一番気になったのはどうしてそれが可能だったか?でした。共通していたのは2つのことです。
1.経営層(社長)が理解をしめしたこと
●当社の組織文化として、まずやってみよう、もし間違っていたら修正すればいいという考え方がベースにあるのは幸いでしたし、社長が変わって改革を一気に後押ししてくださったのも大きかったと思います。ー富士通
●弊社では、現社長の谷田千里が就任当時から率先して挑戦する方向への舵取りをしてきました。ータニタ
●2014年にイタリア出身の社長が着任したのですが、彼はビジネスの成長に情熱を傾けるのと同じくらい、人に関心を持っている人だったんです。ーユニリーバ・ジャパン
●その前年、代表取締役社長が宮坂学に代わり、「才能と情熱を解き放つ」を人事施策のコンセプトに掲げました。ーヤフー
●経営層の現状に対する危機意識や制度のしくみについて、社内のウェブサイトに役員のメッセージを掲載するなど、さまざまな制度理解の機会を設けました。ーNTTデータ
●2017年からさらに健康経営に注力したのは、西井(孝明 代表取締役社長)が過去に人事部長を務めていたこともあり、健康に関する意識と理解があったのも大きな要因だっと思います。ー味の素
●もともとは、代表取締役社長である三村(真宗氏)の強い危機感から始まった取り組みです。組織が急速に拡大していくなか、経営戦略として社員の「働きがい」に注力することになりました。ーコンカー
「サイボウズだからできる」と言っている限り、うちの会社の経営層は考え方のアップデートができないと思います。会社の成長のことも、社会のニーズも、従業員の個々のニーズも、今なにが起きているのか・これからどうなるのかといった広い視点で見る必要があります。
経営層の考え方をアップデートさせるには?はたしてそれは可能なのか?
新たな疑問がでてきます。
2.経営理念・ビジョンが根付いていたこと
●なにか成功する理由があったとすれば、5つのカギがあったと思うんです。1つ目はビジョンからスタートしたこと。だれもがいきいきと自分らしく働いて、豊かな人生を送れるような新しい働き方を実現しようと。ーユニリーバ・ジャパン
●これは新しく制定した理念ではあるのですが、実はもともと創業当初から脈々と受け継がれてきた考え方を新しい言葉で再定義したものです。ーソニーグループ
●この考え方に至った経緯としましては、味の素では、コーポレートメッセージとして「Eat Well,Live Well」を掲げてきました。創業以来一貫して事業を通じて社会課題解決に取り組み、社会と共有する価値を創造することで経済価値を向上させてきたのです。ー味の素
さまざまな会社を取材するにあたって、ぼくは事前に、それぞれの企業が掲げている理念を読み返してみました。
(略)
これらの企業理念はすべて、この社会を豊かにし、そこで生きる人の理想をかなえる(人を幸せにする)ことにつながっています。
会社が「理念をともにする仲間の集まり」であること。素晴らしいと思える理念があってこそ、その会社に深く関わり貢献したいと強く思います。(残念ながらこの点、うちの会社の弱いところです)
著者が一貫してトヨタの理念に共感し、トヨタを離れても実践していることに羨ましくさえ思います。
◆風土はどうしたら生まれるのか?
チームワークあふれる社会を創るーサイボウズ
チームワークを高めるには「風土」がなければならないとあります。
サイボウズでは「公明正大」として徹底して情報を公開しています。
心理的安全性や信頼関係という「風土」があってはじめてコミュニケーションが活発になりチームワークが育ちます。

この「風土」はうちの会社にはまだ整っていません。徹底した情報の公開が必要であり、公開範囲が広いほど上層部は勇気と覚悟が求められるからです。(情報をもっていることの優越性や保身を放棄するわけですから)
だから、単に、新しい制度を採り入れれば会社が生きるのではなく、身を削って痛みも伴う覚悟で行う必要があります。ボトムアップだけではダメで、経営層が変わらないと風土も変わらないのです。
トヨタとサイボウズで違ったところはどこか。最初に驚いたのは、とにかく「社内の情報共有が徹底されている」ことでした。サイボウズでは、プライバシーとインサイダー、第三者に権利が帰属する情報(顧客の情報など)を除く、ほぼすべてのコミュニケーションが公開されています。
◆サイボウズのなかでなにか問題はあるのだろうか?
経営層の会議まで、これだけ徹底して情報が公開されているとは驚きです。大抵のことが知らないところで決まって、直前になって情報を教えてもらい、それに従うしかない現状。そんな立場からすると夢のようです。
そんな、情報をいつでも取りに行けるような環境で、なにか問題は起こるのだろうかと以前から疑問でした。
このことは「これからのサイボウズの課題」として本に記載されています。
情報が氾濫していること、(必要な情報の選択など)主体性が欠かせないことなど、インターネット社会と同じ問題は想像ができます。なんとなく問題はつかめました。(本当はサイボウズに飛び込んで体験してみたいとも思っているのですが…)
本を読み終えて私は自分に手紙を書きたいと思いました。
拝啓 あのときの自分
不幸だと思ったり、孤独や閉塞感を持っていた自分。
見識も行動も狭くて、届く範囲でしか物事をみていなかった。
いま、広く見渡してみると、会社は1つだけではない。
私が会社に何を求めているのか考えてみるべきだ。
ひとりでは変えられないが、同志は会社内の人だけとは限らない。
世の中には、よりよい明るい未来にするために、
真剣に考えている人たちがいる。
自分なりのできること、やりたいこと とつながる
世の中で求められること はあるはず。
◆私は会社にどんな貢献ができるだろうか?
◆会社は私になにを求めているのか?
◆会社は私の個性を必要としないのか?
答えはまだ探し中です。
私はもう少しモヤモヤとつきあいながら旅を続けます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
