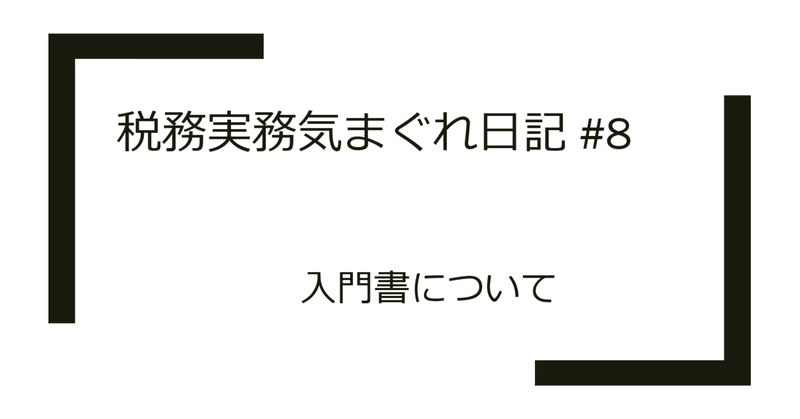
税務実務気まぐれ日記 #8(入門書について)
※この記事は約1,000文字の日記のため目次は入れていません。
今日、本棚を眺めていたら税務の入門書というかビジネス書というか、わかりやすく書かれた本が意外と多いことに気づいた。
日ごろは仕事柄堅い本を読むが、やわらかい入門書も結構読む。やわらかい入門書を読むと、堅い本と読者の対象が異なるため説明が丁寧で参考になる。
私のように税理士法人で働いている人からすると、どうしてもクライアントに分かりやすく伝えなければならない場面が出てくるが、その際に入門書は役立つのである。
日ごろ実務にあたっていると、こちらとしては当たり前のことでも、クライアントからは理解できないという論点に出くわす。その際に、いかに噛み砕いて分かりやすく伝えるかということが専門家には求められると思う。
ただ、そんな私は説明するのは苦手だ。しかも口頭ベースだと特に苦手である。
論理立てて説明するように心がけているが、いつも論理が飛躍してしまう。逆にメールなどの文章で説明する場合は、何度も推敲するため、論理的に説明することが口頭のときよりはできる。
なので、実務上はテキストベースのやり取りを主に使っている。
昔、ピーター・ドラッカーの"自己探求の時代"という論文の中で、「仕事の仕方にはいくつかの要素があり、最初に知っておくべきことは、読んで理解する人間か、聞いて理解する人間か、ということである」と書かれていた。これを文章で説明する人間か、口頭で説明する人間かに言い換えると、私は圧倒的に文章で説明する人間なのだと思う。
少し話は逸れたが、入門書は初学者を対象としているため、圧倒的にわかりやすい。
会計士の受験生だったころは、会計や税務の入門書的な本はもう自分に必要ないと思ったりしたこともあったが、今思い返すと、あの頃は無知だったと思ってしまう。今では入門書だからこそ参考になる言い回しや、比喩表現を学ぶことができて重宝している。
今回、入門書に関係する日記を書こうと思った背景が、入門書が並べられた本棚を眺めながら少し満足感を覚えたためであるため、その本棚の写真を紹介させていただきたい。
入門書というよりは、税務関係のビジネス書といったほうがこれらの本の特徴を表している気がしないでもないが。今後もこのような本を読み、わかりやすく伝える技術を上達させられるよう励んでいきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
