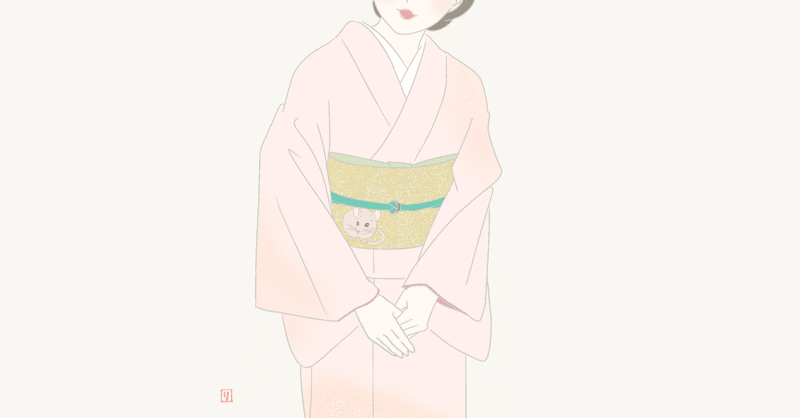
「義母のようにはなれない」 〜先代を踏襲できなかった私の苦悩〜
noteではたびたび書いているように、店の3代目を務める今の夫と働きはじめたばかりのころの私は、暇で暇でしかたない店をなんとか盛り立てようと、メニュー開発や集客方法の改善などありとあらゆる改革に取り組んでいました。
ときに私の思いが強すぎて夫にきついものの言い方をしてしまったこともありましたし、外様だからこそ見えることを生かした改革はときに周囲を戸惑わせてしまうこともあったんだろうと思います。
しかしさまざまな改良を行いはじめて1年ほど経ったころから次第に売り上げは上向きはじめ、相変わらず突拍子もない発案をして夫を驚かせたりしながらも、さらなる改革を進めて突っ走っていました。
その中でひとつだけ変えられないもの、というか自分自身どうしたら良いのかわからないまま「不正解」にだけならないよう気をつけつつ、無難にやり過ごしてきたことがありました。
それが、既存のお客さまへの接客です。
*
もともとうちの店の接客の要は、私が働き出す直前に亡くなった先代の義母でした。
古いしきたりによって女性というだけで蕎麦打ちはさせてもらえなかったものの、その分お客さまの信頼をつかむことに関しては天下一品だったらしく、亡くなって8年ほど経った今でも「あのときこんなことしてもらった」「本当に素敵な人だった」と多くの方からエピソードを聞かされます。
本人はあまりプライベートで人と会ったりするのが好きじゃなかったそうですが、葬儀には予想に反して100名以上の方が参列されるなど、少なくとも周囲からはとても愛された人でした。
店とは人である、と言われるように、偉大な義母が作り上げてきた店はまさしく義母そのもの。
店のルールやしきたりについて何も教わっていない私は、その雰囲気を、イメージを、なるべく壊さないよう接客においてだけは非常に慎重に行なっていました。
私の言葉や態度ひとつで「この店変わっちゃったな」「前の女将さんがいるときは良かったのにな」と言われないように、かといって義母のやり方をそのまま踏襲できる自信なんてまるでなかったので、少なくとも接客業として間違いだけはないようにと、細心の注意を払いながら恐る恐るお客さまと接していたように思います。
メニューやらスタッフの教育方針やら、ありとあらゆることを変えてきたのに不思議な話です。
腰を低く、どんなときも笑顔で、正しい日本語とマナーに気を配る接客を続けていると、たしかに一部のお客さまからは「いいお嫁さんもらったのね」「あなたの接客は気持ちがいいわね」と褒められることもありました。
しかしどこか無個性で、自分らしさのかけらもなかったように思います。
私は長らく関西に住んでいたことから普段は関西弁が出ることも多いのですが、意識して標準語を話すようにもしていました。自分の言葉で話すような場面なんてほとんどありませんでした。
*
表に出す自分と本来の自分との間にできた差がどんどん広がっていくにつれて、次第に私の中で接客はしんどいものになっていました。
先代の後を継ぐことで感じる、プレッシャーや責任感とはこういうものなのかと知った瞬間でもありました。
私はべつに夫から一緒に働いてほしいと懇願されたわけではなく、自分の意思でみずからやりたいと申し出たんだから仕方ないよな、という気持ちと、こんな接客でこのさき何十年と持つのだろうか、という疑問が日に日に募ります。
そしてある日、改革改革と騒いでいた私は、内心に抱えていた接客への不安を初めて夫に吐露しました。
「私の接客は本来の自分とかけ離れすぎていてしんどいし、お義母さんのようにもなれない。このまま続けていくとどこかで心が折れてしまうかも」
口にしてすぐに、こんなこと言って私は何がしたいんだろう。なんて言ってほしいんだろう。答えに困らせてしまうな、と反省しました。
ところが夫からは意外な答えが返ってきます。
「これからは俺ら2人の店なんだから、気にしなくていいんじゃない?俺らには俺らの色があるんだから。自分で自分のお客さんを作ればいいんだよ」
ほっとしました。肩の荷が半分ぐらい降りた気がしました。
おそらく私なんかの何十倍もプレッシャーを抱えているのだろう3代目の彼も、自分自身に同じことを言い聞かせてここまで来たのかもしれません。
継いだ店だけど、新しい店を作る気持ちでいいんだと彼は付け加えました。
私があれこれ変えようとすることの多くに、疑問を呈しつつも概ね認めてくれたのは、やはりこうした考えがあったからなんだろうと思います。
*
性格なのか、しばらくは丁寧すぎて面白みに欠ける接客から抜け出すことができませんでした。
ただこの一件で、自分っぽさを出していくことに少しだけ前向きになれたように思います。
こんな応対をしたら義母が天国で怒ってるんじゃないだろうかと、過度に心配することも減りました。
生前の義母の口グセは「これからは若い人の時代だから」だったそう。
「過去には過去の色があって、今には今の色がある」という夫のこの言葉には、どうやらそんな義母の思いがきちんと継承されているようです。
今でもずっと、私のお守りのような言葉になっています。
頂いたサポートでほかの方の記事を購入したいと思っています。知見を広め、より良い記事作りを目指します!
