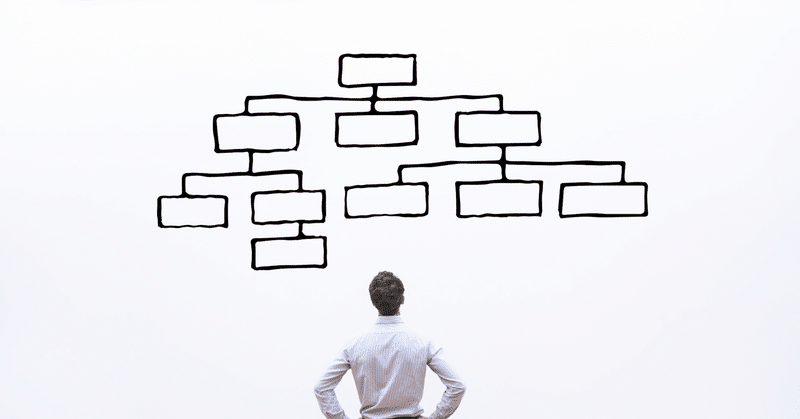
組織の壁という都合の良いフレーズ
あじゃてくアドベントカレンダー12/12は、元あじゃてくオーガーナイザーの「こげばやし」が担当します。去年まで銀行でアジャイルの推進を担当し、今年はガラッと変わって外資系クラウド事業会社での会社生活でした。今回の記事では、この会社の文化やメカニズムに軽く触れ、「組織の壁」とは?という本題に入っていきたいと思います。
ステークホルダーはどこにいますか?

今の会社に入り、新しいサービスを企画して実際にお客さんへ提供しているのですが、直属のマネージャーと議論しただけで、正式なサービスとして認定されお客さんに提供されていく。ステークホルダーはサービスの中身を吟味できる必要最小限にされていて、他の組織からフィードバックをもらいたければ、自分で彼らの時間を押さえて新サービスの紹介をしにいくという感じでした。元銀行員の私からするとこれは衝撃的な状態でして、「会社としてちゃんと見なくていいんすか?」と何回もマネージャーに確認したのを覚えています(笑
今の会社では、ステークホルダーとなるべく人は、サービスの内容や社会の状況により変化するため、会社でレビューポイントを整備するのではなく、主担当の人間が自分で見てもらうべき人を判断するという「セルフサービス方式」になっています。この仕組は、ここでお話した新規サービスだけでなく、ほぼ全てのプロセスで同じ考えが適用されていて、社員のオーナーシップを尊重したポリシーで社内ルールが形成されています。
アジリティの高い組織を作るには、まずは社員を信じてチームに裁量権を渡すというところが重要だと感じていましたが、この会社にきて改めて重要だと感じました。そもそも、社内プロセスを性悪説で作っている会社ってよくよく考えてみるやばいっすよね?(笑 なんで信用もできない奴ら雇ってんの??って思いますよね。。。
気がつけば誰かがやっている
ほんとにこの一年働きやすいなって思うのが、同僚に「今は忙しくて手が回らない」という話をすると、次の日にその仕事を終わらせてくれていたりします。手が空いている場合は、休むのではなく、率先して他の人の仕事をサポートするという考え方がとても良く浸透しているので、お互いに助け合いながら非常に効率よく仕事をこなしている感じです。
これまでの職場だと、自分の担当以外は手を出さないことが多い(色んな意味で・・・)。しかし、今の職場だと同僚は色んなものに興味を示し、困っている人がいたら、暇だったら手助けするみたいな、大学のサークルっぽいノリみたいな雰囲気の今の会社は個人的には好きですね。
自分から頼むのではなく、「これやっとくよ」とか「やっちゃいました」とかこんなフレーズはこれまでの会社ではチーム内か体制内でしか聞いたことがないですね。チーム外の人が気楽に言ってくる感じが、個人的には新鮮でした。
やりたいことは自分で選ぶ
実は私はこれまでの会社で、自分がやりたいことはあまり周辺に伝えていないことが多かったです。その理由として、やりたいと言っても自分のキャラクターとスキルセットがフィットする重要な案件があれば、本人の意向に関係なくアサインされると思っていたからです。やりたいことよりもやってほしいと思われることを期限通り終わらせる方が評価されると考えていました。
今の会社はアジャイル導入のコンサルとして採用してもらいましたが、これまでにやった案件の8割ぐらいがアジャイル関連ではありません。なぜかというと、アジリティの高い組織を作り上げる上でのヒントが社内にあると思ったので、アサインする案件はアジリティを向上する上で重要な要素となるアーキテクチャ、品質管理プロセス、体制整備、要件定義/基本設計等、最近遠ざかっていたテーマをベースに案件で復習を行っていました。
一方でアジリティの高い組織がどうあるべきかは、今の会社の文化やメカニズムを学ぶことで大きなヒントが得られると思っています。そもそも、この会社に入った目的は、何か大きなことを成し遂げるのではなく、この会社のやり方を学ぶことです。かなり参考になることが多いでので、近い将来、何らかの形で紹介できればと思ってます。
本題の組織の壁
これまで色々企業のアジャイルの取り組みをみて、組織の壁が課題と言っている人たちは、ほぼ言い訳に使っていると思っています。アジャイル開発の推進を実際にやれば解ると思うのですが、組織の壁という粒度の課題は出てこないはずです。何が言いたいかというと、壁を実体化させているのは当事者であることが多い、「なぜアジャイル開発が浸透しないのか?」という問いに対し、もし「組織間の・・・」「組織の壁が・・・」みたいな回答をした時点で、組織の壁が実体化します。
結局のところ、組織の壁は体制や構造の問題ではなく、各社員のマインドの問題だと考えています。先に話した今の会社でも、実は複雑な組織体系があり、一見すると組織の壁がありそうな印象を受けます。ただ、各チームや社員に裁量権を与えることにより、自己責任であるという認識が社員に目覚め、結果的にその時々に最小限必要となるステークホルダーを自身で設定して推進を図るようになっていく。
実は日系のエンタープライズ企業でもそれほど厳密に組織を意識せず物事を進めている事例もあります。よく同期入社の同僚に組織を超えてコミュニケーションをとることがあると思います。これってもう組織の壁なんてない状態ですよね?私の銀行員時代に感じましたが、組織を意識する時って実は自分の昇進を考えた時ぐらいなんじゃないかなと。上司を意識するのって、そういう時ぐらいですよね?
という風に考えると、上司やそのまた上の上司を意識しているが故に、組織の壁が登場しているケースが多いのではと私は考えています。
私が新卒入社1年目に「組織とか良く解らないうちに、好きにやっちゃえばいいと思うよ」と上司に言われたことがあります。当時は残念ながら意味を正しく理解できていいませんでした。この上司が言いたかったことは、組織を意識しない方が、可能性が広がるということを伝えたかったんだと思います。同じ会社の社員なのですから、いくらでもコミュニケーションは取れるわけで、聞きたいことがあれば聞けばいいだけ、何かを進めようとした時にもし壁を意識する必要があれば、そこで始めて壁の壊し方を考えればいいだけ。ただ、私がこれまで経験した中では、結局は「話しにくい」とか「誰かが否定的な意見を言っていたと聞いた」とか、「この人こういう人だから話を聞いてもらえない」とか、前評判で判断し相談しに行かず、「組織の壁が問題です」と上司に報告しているパターンを良くみます。
結局はステークホルダーとなりうる人を自分で選び、対応が必要だと思うことを自分自身で取り組み、共感した人は勝手にジョインしていくという今の会社の文化は、前述したような組織の壁っていうものを簡単に壊す方法なんだなとこの1年働いていた思いました。まだまだ、今の会社から学ぶことが多いので、また記事に書いて共有したいと思います。
これから寒い季節に入りますが、
皆様どうかお体に気をつけてお過ごし下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
