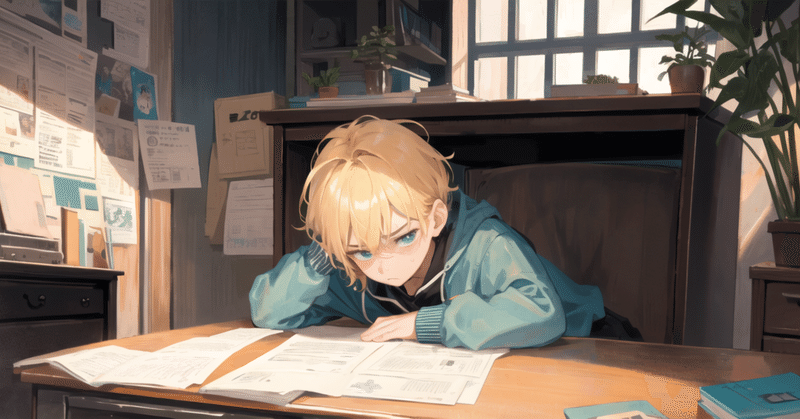
ChatGPTのようなAIによって変化する「人の考える力」と「人が作り出す価値」
最近AIが、世界を変えるレベルで進化しています。
特にChatGPTの勢いが凄いですね。たった数ヶ月で1億ユーザーを突破したそうです。自分もGPT-4を使ってみましたが、以前と比べ物にならないほど回答の精度が高くなってました。
これは「AGI(汎用人工知能)」の初期段階モデルだ、という声もあります。つまり、何にでも使えるAIの卵ですと。今後このようなAIが、あらゆる営みに活用されていくのは明らかです。
「AIを使いこなす方法」の記事は既に飽和しており、情報の劣化も早いので、このnoteではもっと俯瞰して、本質的な変化を整理してみます。
今回は、誰かに読んでもらうためというより、どちらかというと自分の思考整理のための文章です。すごく長いです。
人の「論理的に考える力」は衰える
これほど便利なAIを見ると、ふと不安がよぎります。「今後、人の "考える力" が衰えてしまうのでは?」と。答えは、確実にイエスだと思います。
今までは自分の頭で考えるしかなかった課題も、ChatGPTに聞けば数秒で答えてくれます。多くの人が、そうして楽な方に、頭を使わない方に流れていくのは確実です。
AIの性能が上がり、適用範囲が広がるほど、人の考える時間は減っていきます。そして、筋力と同じように、考える力も、使わなければ衰えます。長い目で見れば、これは避けられません。
人が今持っている力が衰えていくのは、一見、残念なことのように思えます。でも、それを不安視する必要は全くないでしょう。理由は2つあります。
1つ目は、AIに任せられるのは、「論理的に推論できる問題」に過ぎないから。ちょっと大げさに言うと、すごく時間をかければ、誰にでもできる作業だからです。大量の情報を延々と調べて、関係性を考えて、論理を組み立てれば回答できる問題。電卓に数値計算を任せるのと近いです。
これは、経験や感情のような、一人ひとりの人間が持っている素敵な要素が活かされない作業です。限りある人生の貴重な時間を、誰がやっても同じような結果になる作業に使うのはもったいない。
それでは、例えば「AIが、スティーブ・ジョブズの代わりに iPhone を生み出せたか?」というと、限りなく難しいでしょう。
それは、推論で導き出せるものではありません。誰も「スマホ」の存在を知らず、欲しいとも思っていない状況で、それを生み出す論理がありません。
AIによって量産される新アイデアの1つとして生まれる可能性はありますが、論理だけでは採用できないでしょう。初めてiPhoneが出てきたときですら、多くの人間が「これは売れない」と考えたのですから。
つまり、人間の「こういうものを作りたい」という想いや、「美しさへのこだわり」などがあって初めて実現できるものです。
人間は、そういった一人ひとりが個別に持っている(いい意味で、偏っている)要素が活かされることに注力すべきであり、推論で解決できる程度の作業は、AIに任せてしまえばよい、という考え方が広がっていくと思います。
2つ目は、環境に合わせて必要な機能や性質が変わるのは、よくある話だからです。
例えば、誰もが肉体労働していた時代と比べれば、現代人の筋力は衰えているでしょう。かといって、「当時のような筋力を付けないといけない」と考える人はそういません。必要なくなったからです。
極端な話、猿から人間に進化して、体毛や尻尾がなくなったのも、環境が変わって必要なくなったから。「体毛がもっと濃くなればいいのに」と考える現代人はいません。体毛フェチの人はいるかもしらんけど。

同じように、AIを使うことで人間の考える力が衰えても、はるか未来では、それを嘆く人がいないことは容易に想像できます。世代が完全に変わるまでは、一定数いるとは思いますが。
現代人から見れば、未来では「そんなことも自分で考えないのか」と感じてしまうレベルの人が増えるはずです。でもそれは、猿が人間を見て、「そんな薄毛で冬が越せるのか」と感じるようなもの。
もちろん、自分で考えられるに越したことはありません。今も、Excelが計算してくれる世の中ですが、暗算が早いと便利です。スマホが翻訳してくれる世の中ですが、自分で英語が話せると便利です。「考える力」も、いずれはそういう扱いになっていく気がします。
そうして論理的な思考作業から開放された人間はきっと、「僕らは、本当は何がしたかったのか?」という疑問に、より真剣に向き合うことになります。
そして、自分の経験や感覚を元に、AIを駆使しながら、より高いレイヤーの課題を解いたり、新しいものやサービスを生み出したりするでしょう。
また、AIはものを学ぶのに非常に便利なので、基礎的な学力も底上げされます。いつでも、何度でも、わからない部分をピンポイントで答えてくれる有能家庭教師が全国民につくようなものです。
時代が変わり、今ある「考える力」が衰えたとしても、人々が環境に合わせて必要なものを獲得していくのは、間違いありません。
人が作るものの価値はどうなるのか

他にも不安がよぎるのが、「人が作り出すものの価値の低下」です。
以前は、「クリエイティブの領域は、AIには代替されない!」なんて言われていましたが、フタを開ければ、AIが小説もイラストもスラスラと生成し始めています。
ChatGPTも、今はテキスト主体ですが、すぐに画像や動画などを学習し、より高度なアウトプットが可能になっていくでしょう。クリエイティブ以外の業界でも、AIが作るものが溢れていくはず。
では、AIが何でも作ってくれる時代に、僕ら人間が作れる価値とは何なのか?
これは大きく2つの視点で考えられます。1つは「AIにできないことは何か」、もう1つは「AIを使って、できるようになることは何か」です。
◆AIにできないこと
「AIにできないこと」は、短期的な話と長期的な話で考えられます。
①短期的な話
例えば現時点のChatGPTは、いくら性能が良いとはいえ、間違えることもあれば、期待どおりに回答できないこともまだまだあります。
だから、AIの間違いに気づいて訂正できる人や、AIに期待通りに回答させられる人は貴重です。「これ、網羅性が足りなくない?」とか「ここ、間違ってない?」といった指摘ができる人が求められます。
でも、AIは進化し続け、そのうち人によるサポートは不要になるでしょう。曖昧なインプットでも、期待通りの正確なアウトプットが出せるようになっていきます。
つまり、「AIが苦手な部分をサポートすること」には価値が生まれるけど、それは短期的だということです。
画像生成AIも同じで、今はまだ「手」や「複数の人」を描くのが苦手なので、手描きで修正できる人や、適切にプロンプトを与えてAIを使いこなせる人に価値が生まれます。でも、AIはどんどんそれらの課題を克服していくでしょう。
過去と比較しても、テクノロジーの進化はどんどん早くなっています。朝起きたら、自分の得意なタスクを、全部AIができるようになっていた、なんてことがあり得るという危機感は、持っておいた方がよいかもしれません。
②長期的な話
長期的に、「AIが(ある程度進化しても)できないこと」を考えてみます。一言でいうと、AIには「人生がない」ことが大きなポイントかと。
AIは、人が作った大量のテキストや画像データをインプットし、ひたすら学習しています。その中で各情報の関係性を計算し、推論し、あたかも人間のようなアウトプットを出力します。
一方で人間は、生物としての本能を持ち、限られた寿命があり、五感を使い、他者とコミュニケーションを取りながら、日々様々な感情を抱いて生きています。それは、切り取った情報を与えられ続けるようなシンプルなものではありません。
楽しい思い出も、ときめく恋も、おいしい料理も美しい景色も、人が生物として生きているから、感動できるのです。そうして人生の中でいろんなことを感じてきたから、「こうありたい」「こうしたい」という意思が生まれるのです。
なので、今後いくらAIが進化して、まるで人のような受け答えができるようになったとしても、人生を経験せずに、人間と同等のアウトプットやコミュニケーションを行うことは、厳密にはできません。
「誰かを喜ばせたい」とか「美しいものを作りたい」なんて想いは、AIからは生まれません。出発点は、人間です。そしてその想いは、AIにとっては何の関係もない情報を繋ぐきっかけを作り、新しいものが生まれていきます。
肉体的な話もあります。例えば先日バス停で、「軟骨がすり減ってきてねぇ」という話題で盛り上がっているお婆ちゃんたちがいましたが、AIは、そんな話に共感することもできません。年も取らないし、軟骨もないので。
人生を通じて得た経験や感情に基づく創造や共感のような力は、AIには本質的に学べないものであり、人が大切にしていくべき要素です。そうした要素を、自分の作るものに強く反映させることで、確実に価値は生まれます。
いずれAIが人間の見た目や動きを極限まで模倣したとしても、そこには違いが残ります。ただ、これは「人」と「AI」を別物と捉えているときの話です。
いつか、AIが五感を持ち、命の終わりを手に入れ、人と同じように人生を経験していくようになったとき、そして人とAIが融合していく時代が来たとき、大きく変わっていくでしょう。

◆AIを使って、できるようになること
では、「AIを使って、できるようになること」は何か。これもまた、2つの視点で考えてみます。1つは「クオリティと生産性の向上」、もう1つは「新しい価値の生成」です。
①クオリティと生産性の向上
これはAIが、既にある営みのクオリティや生産性を向上させる、という話です。
例えば僕は今、「ChatGPTのような便利なAIが流行ると、未来はどうなるんだろう」と考えたことを整理して言語化したい!という想いから、この文章を書き始めました。よくあるnoteの執筆作業です。
でも普通にキーボードで打つのではなく、音声入力した内容をChatGPTに文字起こしして整形してもらい、さらに評価してもらい、指摘を元に修正するという流れで書いてみました。
こうすることで、自分だけで書くよりもクオリティや効率がアップします。AIは全世界のデータを学習しているので、数十年生きただけの一人の人間より多くの知識を持ち、それをかけ合わせて無限のアイデアを生み出せます。しかも、作業時間は数秒。コストも安い。最高のアシスタントです。
こうした変化が、仕事でも創作でも、あらゆるジャンルで起きるでしょう。全世界の人がAIを使いこなし始めたときのクオリティや生産性は、きっと凄まじいものになります。
ただし、誰もがAIでクオリティの高いコンテンツを量産できるようになると、価値の基準が上がり、さらにコンテンツが飽和します。すると、1つ1つの価値は相対的に下がります。
そのため、作品やプロダクトの価値を多くの人に認めてもらう難易度は、逆に高くなります。現に、イラスト界隈では既にそれを感じます。「AIができること・できないこと」の理解や「AIによって生まれる新たな市場」を把握しておくことが、極めて重要になってきそうです。
②新しい価値の生成
これは、今は存在しない価値を生み出す、新しい営みの話です。
歴史を振り返ると、様々なテクノロジーの発展の度に、新しい価値が生まれています。例として、PC(パソコン)が生まれたときを考えてみます。
PCは、人が入力したデータに対し、決められたロジックで計算を行い、計算結果を出力します。
これによって、タイプライターや手書き文書などの需要は低くなり、逆にPCを構成するハードウェア、PC上で動くシステムやソフトウェアの開発に価値が生まれました。
今までは人がやっていた「(人が決めた)ロジックに基づく計算処理」という知的労働を、個人のコンピューターにアウトソースしたことで、新しい価値が生まれたということです。
ここで、少し詳しく見てみます。ハードウェアはPCの構成要素ですから、必要になるのは当然です。でも、「ソフトウェア」はなぜ必要になったのか?
それは、人間との橋渡しが必要だからです。高速に計算できるだけのシステムは、一般人には扱えず、便利な使い方もわからない。だから、誰でも使える「ソフトウェア」という形にして、様々な機能を提供することに、価値が生まれたわけです。
では、AIについても同様に考えてみます。AIは、人が与えたデータを学習し、データ間の関係性を元に、推論結果を出力します。
これは、「(人が決めた)ロジックに基づく計算処理」ではなく、「学習結果に基づく推論処理」です。これはPCと比べて、アウトソースできる知的労働の範囲が、大きく広がったと言えます。
そのため、人間による「知的労働」の需要は低くなります。では、そこから新しく価値が生まれる営みは何か?PCでいう、ハードウェア開発とソフトウェア開発にあたるものは?
前者にあたるのは、AIの構成要素である膨大なマシンリソースや学習モデルの開発、そして後者にあたるのは、推論結果を使いやすい形で提供するプロダクトの開発などでしょう。いくら高性能でも、自由の高いAIは、一般人には扱いにくいのです。
AIは、「推論できる問題」全般について、業種問わず活用できます。さらに、リアルタイムでインタラクティブに動作できるので、そのインパクトは計り知れません。メタバースのような、自由に制御可能な仮想空間とも相性が良いでしょう。
活用しやすい具体的なタスクは、コンテンツ生成、アイデア生成、情報収集、情報整理、課題解決、教育・学習、コミュニケーションサポートなどでしょうか。どんな業種でも必要なタスクばかりです。
それらを機能として提供したり、機能の使い方について教育したり、それを前提とした業務プロセスを構築したり、といった、人々がAIを使えるようにするためのあらゆる活動が、新しい大きな価値になります。
資本主義である以上、AIを使う流れは止められないので、知的労働を基盤として生活している人は、早めにこの辺りに目を向けた方がよさそうです。僕もですが。
さらにその先の変化

AIの進化単体を見ると、上で挙げたような変化が想像できますが、さらにその先はどうなるのでしょうか。
PCの例で再度考えてみると、インターネットと繋がることで、Webサイト、オンラインショップ、コミュニケーションツールなどが発展しました。その後、小型PCとも言えるスマホが生まれ、SNSや端末決済などが普及しました。
AIでも似たようなことが起きると想定できます。例えば、専門分野の異なるAI同士によるコラボレーションは確実でしょう。現時点でも、ChatGPTと画像生成AIをコラボさせれば、ユーザーの入力に応じてシナリオや映像が自動生成されるゲームぐらいなら実現できます。
他にも、世界中の人が独自に学習させたAI同士でゲームが行われたり、あらゆる電子機器に組み込まれたAIが生活を完全サポートしてくれたり、さらにはAIが人間の脳に組み込まれたり、、のように、可能性は限りなく広がっていきます。
言語や画像だけでなく、五感で感じているもの全てがAIで予測・解析できるようになると、人が触れているもの全てがパーソナライズできるようになり、あらゆる行動において摩擦がなくなっていきます。特に仮想空間内では、流れる水のように滑らかに生活していくイメージに近くなりそうです。
このような大きな変化はとても楽しみですが、不安もあります。AIに代替されるのが推論作業に過ぎないとしても、現時点ではそれが多くの人々の仕事になっているのも事実です。
仕事が一瞬でなくなるようなことは歴史的に考えにくいですが、徐々に変化していきます。そして多くの人が、「自分の価値って何だろう」という問題に直面します。
とはいえ、自分一人で急に世界を変えたり、変化を止めることはできません。まずは地道に、AIのことをしっかり理解して、変化に適応しながらも、人間として人生を楽しむことが大切なのではないかと思います。
まとめ
…という感じで、ひと通り考えは整理できたので、この辺で終わりたいと思います。最後にざっくりまとめます。
人の「考える力」
・次第に衰える(論理を組み立てて推論する部分が)
・やりたいことを見い出し、AIを駆使して実現する力が強化される
・一般的な基礎学力が底上げされる
人が作るものの価値
【人が提供できる価値】
・短期的には、AIをサポートすることに価値がつく
・長期的には、人の経験や感情に基づく創造や共感に価値がつく
【AIを使うことによる変化】
・クオリティや生産性は急激に向上する
・量産により1つ1つのコンテンツの価値は相対的に下がる
・AIの開発や、人々がAIを使えるようにする活動に価値が生まれる
AIの今後
・AI同士が繋がったり、誰もが自分でAIを作ったり、いろんなものにAIが組み込まれたりして、世界が大きく変わっていく
以上です。
こんな長文を読んでいただいてありがとうございました。変化の激しい時代ですが、一緒に楽しんで生きましょう。
最後に、最近のAI周りの動きで気になる記事をいくつか。
半年間AI開発やめて準備したい話
日本もAI頑張るぜ活動
業務でAI利用するためのガイドライン案
社員向けのAI関連補助(これが早くできる企業は強くなりそう)
OpenAIのCEOインタビュー
これはやや古い記事ですが、人間の知性とAIに関するお話
こちらは人間の脳とAIに関するお話
岸田首相とサム・アルトマン面会
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
