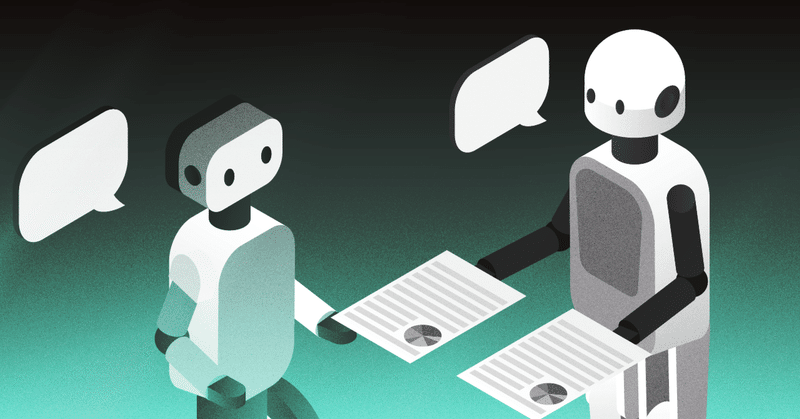
AIプロデューサー
仕事を立体的にとらえられるようになった。
シングルマザー就労支援をミッションとするNPO法人JW-UPをやるようになって、これまでどちらかというと仕事の「外側」・・・マーケティングやブランディングをとらえていたのが、「内側」に目が向き始めた。

2022年のいま、「仕事」といえば、やはりAI(人工知能)との兼ね合いにならざるを得ない。ぼく自身、たとえばスーパーやコンビニのレジのマシン化、ファミレスのオーダー、配膳ロボット、コールセンターなどで「人間の職が奪われる」方面にばかり目が行ってた。
しかし、それは一面的な見方だ。社会は変化している。しているのであれば、新しい職がその中から生まれているはずだし、創造していけるはずなのだ。そして、AIとの付き合いかたも、「人間の代替」というのは限定的なものだとわかった。
むしろ「AIと共働きする」スタンスが必要なのだ。
そういう目で見てみると、AI導入の先進・金融業界のMUFGは「共働き」している。

住宅ローンの事前審査はAIがたちどころにやってしまう。顧客のインターフェースのうち、「時間」を高速にしたわけだ。これ、大事だよね。
MUFGは支店から本店への問い合わせもAIが対応している。前さばきすることで、事務の効率化をする。そして人間は人間にしかできないことをやる。
AIの性能がどれだけ優れているか、という観点で見られることが多いが、これも限定的なものの見方・考え方だと思う。
大事なのは、AIと一緒に仕事することで、どれだけ大きな変化を生み出せるか、その変化量だ。
考えてみれば、すべての仕事というものは「変化」を生み出すためにある。
増やすか、減らす。利益を増やす。売上を増やす。顧客を増やす。顧客の不便を減らす。顧客拘束時間を減らす(住宅ローンの事前審査)。その変化量が大きいほど、良いわけだ。
人間だけで生み出せる変化量より、AIと共働きすることでより大きな変化量を得られるのであれば、AI導入投資コストを回収できる。
これからのマネジャーは「人間」だけではなく、「人間とAIのバディ(相棒)」をマネジメントするようになる。AIプロデューサーとしてのスキル&センスが求められる。
そう、各現場で「AIとどう共働きするか」について企画できる人、「AIプロデューサー」、これからどんどん需要が高まってくるはずだ。
AIを「作る」人は多い。
しかし、AIを「使う」達人は少ない。
こういう新しい職業は、ワクワクするね。
ところで、ELYZA Digest(イライザ・ダイジェスト)はすごいよ。
ぼくのnote「胸キュン!」
を、瞬時に要約してくれた。それも作者のぼくより素晴らしい品質。

面白いので、ブログもやってみた。
こうなった。

イマドキのAI、ほんと、優秀だね。びっくり。
AIプロデューサー、もっと社会に認知されて欲しい。「英検2級」とか「簿記1級」とかみたいに。なので社団法人立ち上げて「AIプロデューサー認定協会」みたいなの、やろうかと思ったが、身体がモタないので、誰かやって(笑)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
