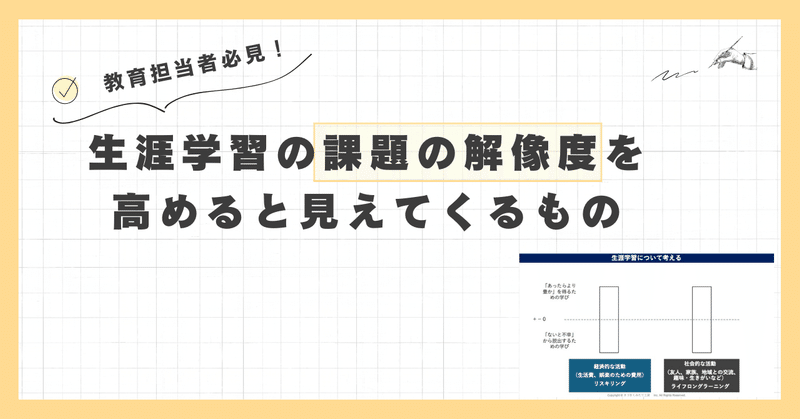
生涯学習の課題の解像度を高めると見えてくるもの
おはようございます。森本です。今日も元気に生涯学習について考えています。
私の仕事を一言でまとめるのであれば、「人のパフォーマンスを上げることを通じて、組織のパフォーマンスを高め、社会の課題を解決すること」ということになるかなと思います。
もともとは小学校の先生をしていましたが、その後、企業研修、社会人教育と領域を大人にも広げて活動しています。今は大人を中心に仕事をしていますが、次は、海外の大人や子供にも活動を広げようと鋭意、勉強、活動中です。
そのような中で、ここ最近、「リスキリング」や「生涯学習」といったキーワードを目にすることが増えてきました。
これは、主に、人の寿命が伸び、働く期間が増えてきていることと、それに伴い社会で必要とする知識や技術の移り変わりが大きいことがその背景にある要素と言えます。
社会の様子を見る限り、人はそこまで学習に興味があるわけではないことが見て取れる中で、人々が豊かに生活をしていくためには、必要とされる学習が適切に生み出されるような工夫や支援が求められています。
私のところにも、リスキリングや生涯学習というキーワードのもと、主にベテラン社員向けの教育の相談がやってくるのですが、その際、人によって求めているものに少しずつズレがあり、議論が絡まっているのを感じたので、今回は、私なりに課題を整理してみようとこのエントリーを書いてみることにしました。
①生涯学習を4つに分けてみる

生涯学習をテーマに考えた際、まずは、経済的な価値のための学習と社会的な価値のための活動に分けることができます。
また、それらの2つも、マイナスからニュートラルまで高めるための学習とニュートラルからプラスへと高めていくための活動に分けることができます。
一般的に、リスキリングという言葉で、企業がなんとかしたいと思うのは、ここで言う左側の軸で下から、真ん中、そこからさらに上へと目指そうとする活動と言うことができます。
②その学習の費用を誰が払うかを考えてみる

先ほど、企業研修においては、リスキリングを行おうとするという話を書きましたが、では、そのほかの領域のを誰が行おうとするかと考えた時に、この図にある「個人が払う」「親が払う」「企業が払う」「国家が払う」という4つに分類することができるかなと思います。
そのほかにも、親戚が払うとか、地方自治体が払うとか、そのほかの誰かが払うとかあるかもしれませんが、上記の4つのどこか近いところにまとめられそうなのと、そこまで件数も多くないことが想像されるため、ここでは特に影響が大きそうな4つにまとめています。
③生涯学習についてコストを払う人ごとの特徴を考えてみる

先ほど、支払い元として4つの可能性があるという話を書きましたが、それぞれメリット・デメリットがあるなと思い、ざっと整理してみました。
これ以外にもいろいろとあると思うので、もしよろしければ「こんな要素もあるんじゃない」と言った形でコメントなどいただけたらと思います。
ざっとまとめますと、
自分で払う場合、自分のニーズやウォンツに沿って行えるため、意欲は高くなりやすく、成果につながりやすい。ライフロングラーニングにとても向いている。
一方で、リスキリングとして経済的な価値に繋げられるような学習をしていく人はかなり限られていそう。
自分以外の他者が払う場合、社会からの要請ベースで物事は進み、課題解決のためのリスキリングには良いかもしれないが、個人の関心に沿って行えるかは何とも言えず、成果に結びつくかどうかは個人や教師側のモチベーションを上げる工夫によるところが大きい。
と言った感じでしょうか。
冒頭、私の仕事を一言でまとめるのであれば、「人のパフォーマンスを上げることを通じて、組織のパフォーマンスを高め、社会の課題を解決すること」と申し上げましたが、私の仕事で成果をあげようとすると、いかに子供でも、大人でも、学習者の学習への動機づけ、モチベーションの向上を上手に行っていくかが鍵になってくるかなと思います。
私が日頃から、レゴシリアスプレイやプロジェクトアドベンチャー、ストレングスファインダー、ストップモーションアニメ作りと言った興味関心を引きやすい手法を学習の入り口とし、そこから派生する対話を通じての学びの場作りをしているのも、まさに上記の課題を解決するための工夫ということができるかなと思います。
まとめ
ということで今回は、生涯学習とそれにまつわる課題について書いてみましたが、この領域においての課題解決も全く簡単なものではなく、多方面からの工夫や研究、技術の向上が求められるかなと思います。
私も日本社会のお役に立てるようにと、直近、2024年の5月ではこんな2つのイベントを実施しようと計画中です。
1つは、フィンランド生涯教育研究家の石原侑美さんを先生に迎えて、生涯学習の先進国であるフィンランドから学びを得ようと取り組み。(参考までに、侑美さんとの実践はこの記事の下に貼っておきますので興味がある方はぜひ)
もう1つは、プロ経営者として、複数の組織で様々な成果の創出を行ってきた濱暢宏さんの実践から学びを得ようと言う取り組みになります。
どちらも無料のオンラインイベントです。
少しでも多くの人に、時代が必要とする学びの機会を届けられたらと思っていますので、お時間の都合がつく方はぜひご参加いただけると嬉しいです。
ということで今日も素晴らしい学びの機会をどうもありがとうございました。
以下、本件にまつわるエントリーです。お時間ある時にぜひ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
