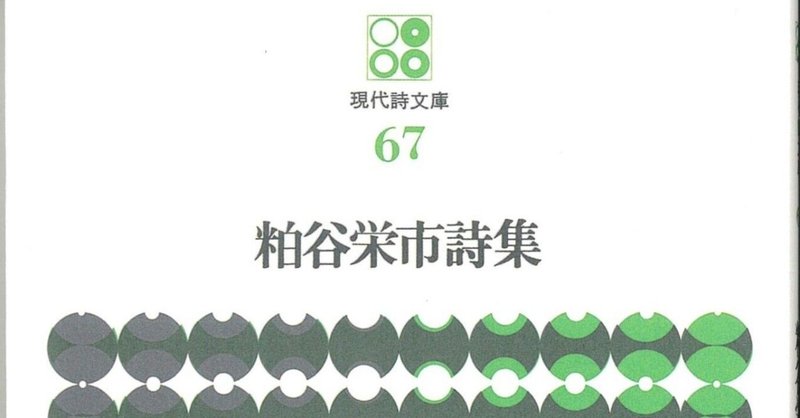
死と愛 粕谷栄市詩集『世界の構造』より
粕谷栄市さんが詩集『楽園』で、第42回現代詩人賞を受賞なさった。粕谷さんの詩は、以前から好きなのだけれど、意識的に読んだことがないので、先ずは現代詩文庫67(1976年初版・思潮社)を購入。こちらには、第一詩集『世界の構造』(1970年、詩学社)と未完詩集やエッセイなど、初期作品が収められている。『世界の構造』から、一篇、挙げてみる。
死と愛
死んでしまった一人の少女に就いて、書いて置きたい。私の育った町の大きな家具屋の娘で、幼なじみであったのだ。
変わった少女で、稚ない頃から、卵が嫌いだった。否、寧ろ、憎悪していた。卵と卵に関するものなら、何でも、見つけ次第、叩き毀したり、引き裂いたりした。沢山の卵を盗んで、溝に捨てた。鶏を見ると、嘔いた。
それは、恐怖だった。或る時、卵を運ぶ老婆を、橋から突き落したことがある。成長しても、それは癒らなかった。毎日、卵を凶器にして、人々と自らを傷つけた。いつからか、彼女は、狭い一室に閉じこめられて、生きねばなかなかった。
呼ばれて、時々、私は逢いに行った。彼女は美しく、私に優しかった。何故、私が呼ばれたのか、私には判らない。私に逢っても、彼女は、泣くばかりであった。聴くに耐えぬ言葉で、卵の存在を罵った。激昂して、窓枠を割った。そして、私に謝ったのだ。
いつまでも、私たちは、闇の降りる部屋に、静かに坐っていた。…
彼女の死の前年、私は、家族と共に、他の町に移った。二度と、彼女に逢えなかった。彼女は、次第に狂暴になり、完全な廃人になったという。
或る朝、部屋を脱け出し、郊外の線路の上で、冷たくなっていた。勤め先の冷酷な商店で、私は、それを聴いた。
数年後、私は、兵士として、前線にいた。死の溢れる線上で、ただ彼女を想うことが、私の支えであった。迫って来る巨大な白い卵に向かって、必死に射撃を続けながら、私の頭には、狂った少女のかぼそい肉体しか無かったのだ。
(全文)
タイトルのせいもあろうが、私はこれを、青年期の恋の詩として読んだ。卵の殻の中には「命」が宿っている。卵型と言われる円いフォルムや、人間の皮膚に似た殻の手ざわりに、私は、性の臭いを感じる。「性」は「生」の根源である。卵から生まれて、死んでゆく。生まれなければ死ぬことはない。命を宿すということは、死を孕むことに等しい。愛もそう。実らなければ、失うこともない。肉体として結ばれて一つになるからこそ、離れ離れになることの切なさを知る。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
