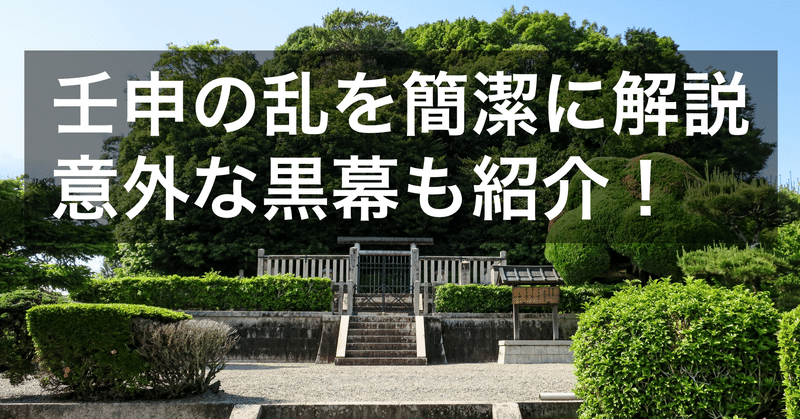
壬申の乱を簡潔に解説、意外な黒幕も紹介!
古代日本で起こった、壬申の乱をご存知だろうか?
壬申の乱とは、672年の飛鳥時代に、大海人皇子が大友皇子を排除し、天皇につくべく起こした争いである。
乱の内容、戦況、黒幕説などを簡潔に解説したいと思う。
壬申の乱の内容
壬申の乱とは、672年の飛鳥時代に、大海人皇子が大友皇子を排除し、天皇につくべく起こした争いである。
大海人皇子は、668〜672年まで在位していた天智天皇の弟であり、大友皇子は息子である。
壬申の乱は、叔父と甥の争いということになる。
起こった原因
主な原因は、天智天皇が大海人皇子ではなく、息子の大友皇子に皇位を継承しようとしたからである。
不満に思った大海人皇子自身が、壬申の乱を起こした。
日本書紀には、朝廷が美濃(現:岐阜県南部あたり)・尾張(現:愛知県南部あたり)で、労働者に兵器を持たせていることを知り行動に移したとある。
しかしこれは、壬申の乱を正当化するために書かれたと考えられる。
当時は兄弟に継承される習慣があり、二人の素質の差、大友皇子の母の身分が低いなど、大海人皇子が選ばれる流れだった。
天智天皇は、自分の息子に継いでほしいという思いがあったのである。
だが、天智天皇が亡くなる直前に大海人皇子を呼び、皇位を継承してほしいと言っている場面がある。
大海人皇子はそれを不審に思い、提案を断った。
その後、大海人皇子は妃の鵜野(後の持統天皇)と共に、吉野(現:奈良県吉野町)にある吉野宮へ出家した。
出家した理由は、皇位を力尽くで手に入れるために、離れた地で準備するためだと考えられる。
大海人皇子が皇位を継承するために、反乱を起こしたことが壬申の乱の始まりである。
どっちが勝った
勝敗は大海人皇子の圧勝であり、戦いは一月ほどで終わった。
周到な準備、人徳の差で勝敗は決していたと言える。
大海人皇子が皇位を継ぐ者と期待が寄せられており、大友皇子の継承は期待されていなかった。
663年に起きた、白村江の戦いで敗北して以降、朝廷は数々の改革を行い、苦労させられた人民や豪族たちは朝廷に不満を抱いていたであろう。
朝廷への不満、大海人皇子への期待が合わさり、一帯の兵士たちを集めることができ、兵力差を広げることができた。
上記での、日本書紀にある労働者に兵器を持たせた記述は、戦う恐れのあった新羅戦用で用意された農民兵だと考えられる。
白村江の戦い以降、中国や新羅などの侵攻を警戒し、早急に兵力を確保する必要があった。
大海人皇子は朝廷にバレないように、その兵士たちを上手く自軍に取り入れたのである。
その結果、大海軍の方が兵力を大きくでき、有利に動くことができたのである。
壬申の乱の戦況

図のように、壬申の乱の戦場は、美濃、近江、伊勢、伊賀という近畿地方一帯で行われた。
重要な2つの戦いを解説しようと思う。
息長横河の戦い
この戦いはお互いの主力軍同士の戦いであるが、戦力差によりあっけなく大海人側の勝利で終わってしまう。
各地で戦いは始まっていたが、主力軍同士は動かず睨み合っている状況が続いていた。
どちらかが先に動き、戦いが始まったと考えられる。
主力軍なので重要な戦いではあるが、朝廷側の司令部の崩壊、兵力差などから、あっけなく大海人軍が勝利した。
日本書紀には、境部薬という朝廷側の将が斬られるという記述がある。
将が斬られるということは、陣営の奥まで攻め込まれたと考えられる。
朝廷軍は退却し、大海人軍はここから追撃戦を始めることになる。
瀬田川の戦い
壬申の乱においての最終戦であり、場所は現在の滋賀県大津市唐橋町にある、瀬田の唐橋付近である。
朝廷側は、左右大臣と大友皇子自らが最前線に立つという、限界まで追い詰められた状況だったと言える。
瀬田橋は交通と防衛上の重要地であり、大海人軍が橋や河を渡りきれるかが重要であった。
結果、橋は突破され、智尊という、この戦いの朝廷側の将は斬られた。
朝廷軍は逃走し、そのときの都である大津宮が焼失した痕跡がないので、都で戦いはなかったのであろう。
大友皇子は西に向けて、少数の従者を引き連れて逃走した。
だが、逃走先に大海人軍が待ち構えており、観念した大友皇子は自害し、戦いは終わった。
戦後の影響
673年2月に天武天皇となった大海人皇子は、皇親政治という天皇と皇族を中心とした体制を作り、律令国家に向けて尽力した。
壬申の乱のような争いを起こさせないために、皇族や各豪族を手中に納める体制を目指した。
個人の能力などを重視する官僚制や、新たな身分秩序である八色のかばねなどの制作を行った。
反乱が起きたら、早急に兵を集められること、王位継承者を1人に限定して争いを生ませないなど、壬申の乱の影響を強く受けたと考えられる。
鵜野(持統天皇)黒幕説
壬申の乱は、大海人皇子の妃である、鵜野皇女が乱を起こした黒幕だという説がある。
一般的には、大海人皇子自身が皇位を継ぐために乱を起こしたのだが、わざわざ武力で皇位につく必要はなかったとも言える。
当時は群臣による推薦で選ばれていたので、天智天皇が亡くなった後、待っていれば自分に皇位が回ってくるからである。
だが、鵜野の思いとしては、息子の草壁皇子を天皇にしたい思いがあった。
流れとしては、大海人皇子が皇位についたら、次は葛野王や大津皇子といった、鵜野とは違う妃の息子も候補に上がる。
正妃は鵜野ではなく大田皇女だったので、その息子である大津皇子が選ばれる可能性があったであろう。
鵜野としては、草壁を確実に皇位につかせるためにも、他の候補者を排除する必要があった。
だから、大友政権を崩し、大津皇子を危険に晒すべく、大海人皇子をそそのかして乱を起こしたと言える。
大海人皇子としては、葛野王や大津皇子も実の息子なので、特別草壁皇子を天皇にする必要もなかった。
鵜野皇女の息子への思いで、壬申の乱は起こった可能性がある。
まとめ
・壬申の乱とは、672年の飛鳥時代に、大海人皇子が大友皇子を排除し、天皇につくべく起こした争いである
・主な原因は、天智天皇が大海人皇子ではなく、息子の大友皇子に皇位を継承しようとし不満に思ったからである
・勝敗は大海人皇子の圧勝であり、周到な準備、人徳の差で勝敗は決していた
・壬申の乱の戦場は、美濃、近江、伊勢、伊賀という近畿地方一帯で行われた
・観念した大友皇子は最後に自害した
・乱の後に天武天皇になった大海人は、律令国家制定に向けて尽力した
・壬申の乱を起こした黒幕は、大海人皇子の妃である鵜野皇女という説がある
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
