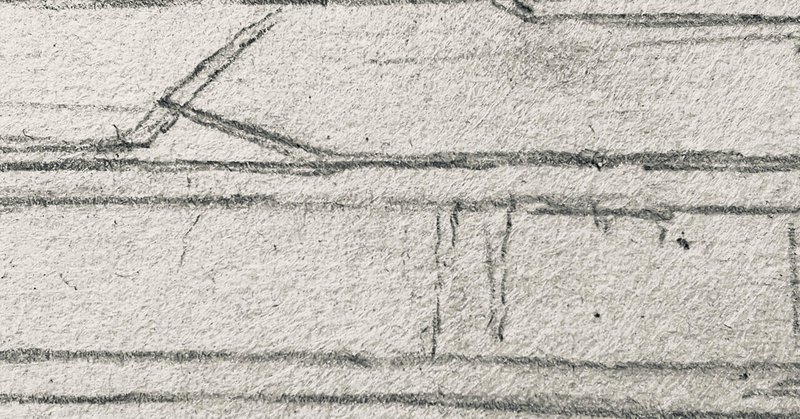
【アナログ絵制作記11】かみにやさしく
日本画を制作しているほぼリアルタイム記録です。
【これまでのアナログ絵 制作記】
[イメージをふくらませる/想像]
その①初回:アイデア・ネタ出し、テーマ決め
その②資料を探して三千里以下
[ラフや下絵をつくる]
その③よし、一発だ
その④もくもく下絵をつくります
その⑤デジタルの恩恵
その⑥勢い・見切り・鮮度
[紙の準備をする]
その⑦アレしてる間にコレ
その⑧宇宙と一体化する
[下絵を本番の紙に写す]
その⑨じりじりチクチク
その⑩下絵続きwith手間賃とやら (前回)
⑨から続いております、じりじりチクチク下絵を本紙に写す作業です
前回ちょっと書きましたが、しばらくやることは変わりません
細かいところは目がしぱしぱします

写し終わってからも、こういう線やシルエットがいいな、合うなと思ったら変えていきます。
難しいところですが、同じサイズの下絵の紙(コピー用紙とか安い紙)と本紙では風合いが違うので、よりしっくりくるようにしています。
のちのち鉛筆線を墨でなぞる工程があります。
そのときにも、鉛筆のときよりしっくりくる線や描き方を選びます。
さて、いまやってる「鉛筆で写す作業」が修正できる最終ラインですが、限度はあります。強く書くと紙に鉛筆の粉が埋まって消せなくなります。
油断して何度も描きなおすと弁天様も四度目くらいから琵琶でバチコンしてくるかもしれません
かつ、消すときも、消しゴムでオラァ!とごしごししてはいけません
⑦で引いたドーサが剥がれてしまいます
本紙で頻繁に描いたり消したりするのは実は良くないのです
だから下絵をバチっと作っておくのです
そーっとそーっと、擦らず
左手も右手もそえるだけ……
意識と力を飛ばして紙に顕現させてゆく……!
とはいえ線を整理していかないと自分でわからなくなります
特に建物の輪郭のような、間隔が狭く長い直線がわたしは迷子になりやすいです。
メインでBくらいの鉛筆を使っていますが、ところどころ2B鉛筆に変えて筆圧を下げるなど工夫をしています

芸術の神に拾ってもらい、紙にやさしくするためにも、上手いに越したことはないですね。
困ったら技術が助けてくれます
技術に困ったら、きっと想いが助けてくれます
今日はここまで!
お読みいただきありがとうございます。皆さまからのあたたかなスキ・コメント・シェアは心の栄養に、サポートとご購入で制作が続けられます。
