
【アナログ絵制作14】手ごね白玉
日本画制作の撮って出し投稿です。
午前中は前日の続き、墨入れをしてました
【これまでのアナログ絵 制作記】
[イメージをふくらませる/想像]
その①初回:アイデア・ネタ出し、テーマ決め
その②資料を探して三千里以下
[ラフや下絵をつくる]
その③よし、一発だ
その④もくもく下絵をつくります
その⑤デジタルの恩恵
その⑥勢い・見切り・鮮度
[紙の準備をする]
その⑦アレしてる間にコレ
その⑧宇宙と一体化する
[下絵を本番の紙に写す]
その⑨じりじりチクチク
その⑩下絵続きwith手間賃とやら
その⑪かみにやさしく
[墨を入れる]
その⑫線、線、面!
その⑬墨と紙 (前回)
今日は胡粉作業なので前夜に膠をふやかしてます。
膠(にかわ)というのは顔料を和紙に定着させる接着剤の役です。ないとやっていけません
膠ってこんな


湯せんは熱燗つくるやつが便利です。量もワンカップ容器で測りやすいです
膠もできたので胡粉作業
胡粉(ごふん)は日本画の白顔料です
いるもの

あると便利:汚れてもいい服、どうなってもいい安筆
胡粉のつくりかた

②すり鉢などで粉状になるようすりつぶす。すり鉢に残った胡粉は安筆でしっかりあつめる
③絵皿に出す
↓

★少しずつ=2~3滴
まるで滴水刑のようですね。
↓

写真はちょっと固めなので1滴ずつ膠を入れて微調整します。
※ここまで約30分かかっています
↓

↓

一気に溶かさない
(白玉から溶きあがるまで約10分)
溶きあがったら刷毛で画面全体に引きます。
画面に胡粉を引く目的は2つ
①絵具の発色をよくする
②ドーサを安定させる
②はなんだっけな
胡粉の原料が貝殻で、貝殻の炭酸カルシウムでドーサの酸性を中和させるとかそんなだったと思います
制作に戻り
×枚数 引きます
胡粉を引いて乾かしている間に別の制作を走らせます。
乾燥中にやるのは制作でなくてもいいんですが、時間をうまく使えるようにがんばるのです…!
ほんとは丸一日乾かせるとベストです
今日はヒーターの上に乗せて時短

あれ?肉眼だと胡粉ビフォーアフターの違いがはっきりわかるのに写真だと昨日と同じに見えますね。おしゃしん むずい
完全に乾いたら必要に応じてもう1~2回胡粉を引き、胡粉作業はおしまいです
さてお気づきだと思いますが、ここまでで、絵具で色を塗る作業はひとつもありません。
⑦から始まり紙の準備とパネル等で丸2日、ほか墨入れ、胡粉引きなど、「色が塗られる状態」にするまでにいろんな準備があります。
面倒です。
それもまた、制作です。
今日はここまで!
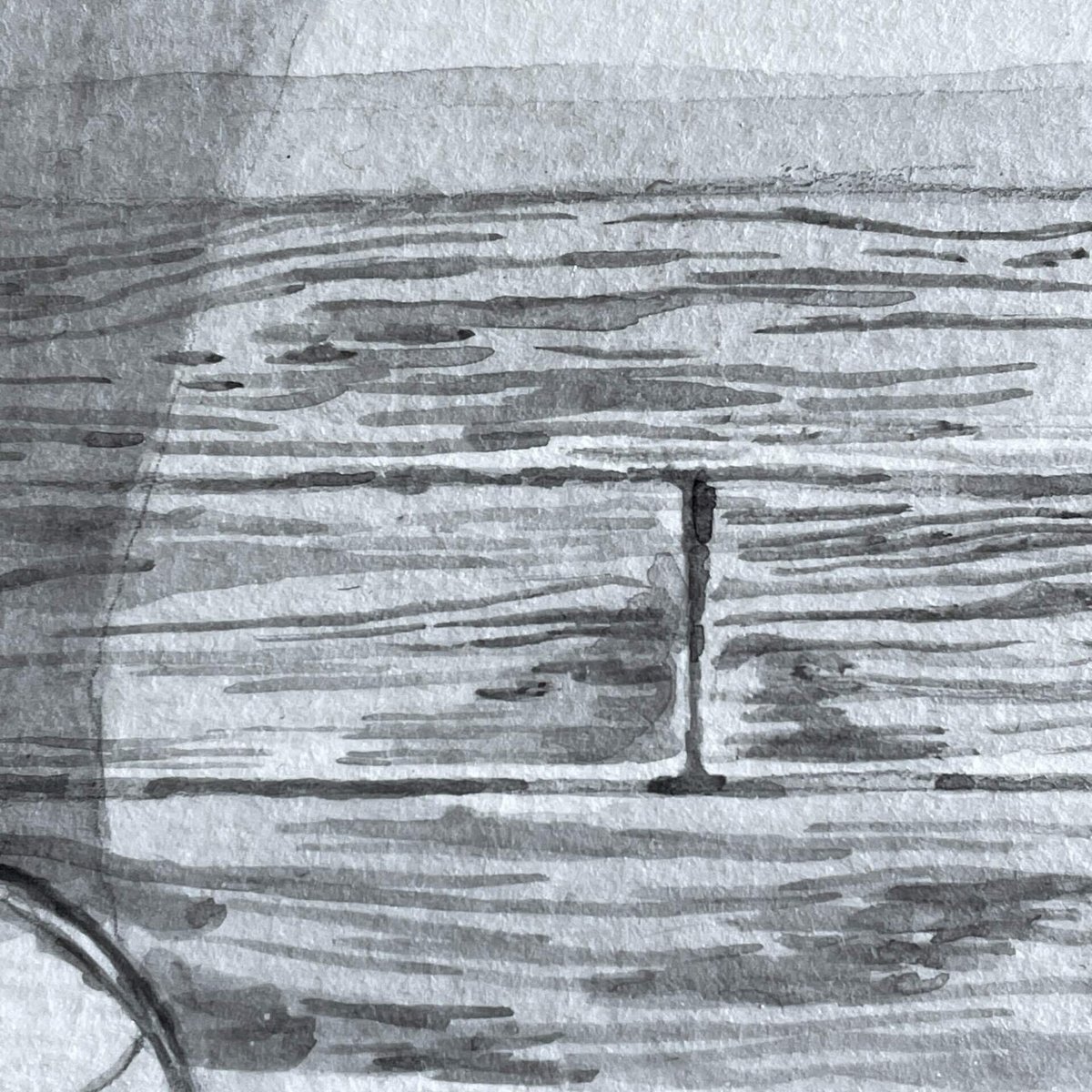
お読みいただきありがとうございます。皆さまからのあたたかなスキ・コメント・シェアは心の栄養に、サポートとご購入で制作が続けられます。
