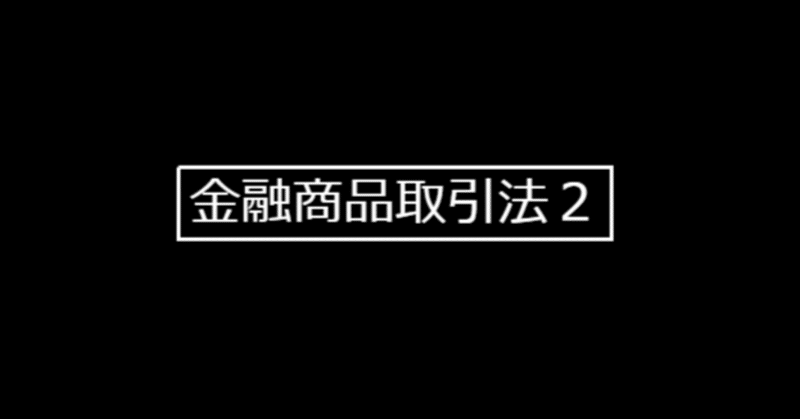
金融商品取引法2
おはようございます。
キツネの目と申します。
本日も「金融商品取引法」について記載していきます。
よかったら参考にしてください。
投資運用業・金融機関・仲介業
・投資運用業

投資運用業とは、投資一任契約を締結した顧客の資産や投資信託・ファンドの資産の運用を行うことです。
投資運用業も金融商品取引業者なので登録が必要になります。
・投資運用業の行為規定

投資運用業務は、いずれも顧客との高い信認関係を前提としていることから、利益相反の防止をはじめとする高度な受託者責任を負うべきという点で共通の性格を有しています。
金融商品取引法では、これらの業務に対して横断的に規制しています。
・忠実義務・善管注意義務
金融商品取引業者等は、権利者のために忠実に業務を行い、善良な管理者の注意をもって投資運用業を行わなければなりません。
・運用権限の委託(自己執行義務)

投資運用業を行う金融商品取引業者等は、すべての運用財産について、その運用に係る権限の全部を委託してはいけません。
ただし、次にあげる契約等については、内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のために運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る)に委託することができます。
投資法人の資産の運用に係る委託契約
投資一任契約
投資信託契約
自己運用を行う集団投資スキームに係る契約等
・運用報告書の交付義務

金融商品取引業者等は、定期的に運用報告書を作成し、権利者に交付しなければなりません。
そのほかにも、分別管理義務や金銭又は有価証券の預託受入れの禁止などがあります。
・ファンド規制

ファンド規制とは、集団投資スキーム持分というこれまで規制の対象になっていなかった「投資ファンド」を金融商品取引法で規制の対象にしたものです。
・集団投資スキーム持分
集団投資スキーム持分は次の3つの要素を満たしているものをいいます。
投資者から金銭の出資・拠出を受け
出資・拠出された金銭を用いて事業・投資を行い
当該事業から生じる収益等を出資者に分配するというスキームに対する権利
(具体例)
組合契約に基づく権利
匿名組合契約に基づく権利
投資事業有限責任組合契約に基づく権利
有限責任事業組合契約に基づく権利
社団法人の社員権
※有価証券に該当するものは除く
投資信託の受益証券、合同会社の社員権、信託受益権等、金融商品取引法上有価証券として扱われるものは、集団投資スキーム持分に該当しません。
・適格機関投資家等特例業務の特例
いわゆるプロの投資家等のみを対象とするファンドを取り扱う場合は、原則として、契約締結前の書面交付義務等の行為規制は適用されません。
ただし、虚偽告知や損失補てんについては、適格機関投資家等特例業務についても適用されます。
・金融機関の業務範囲

原則として、銀行等の金融機関は、有価証券関連業または投資運用業を営むことはできません。
ただし、一定の条件の下でこの規制が緩和されています。
【金融機関による有価証券関連業又は投資運用業として認められているもの】
顧客の書面による注文を受けて行う、顧客の計算における売買
国債・地方債などの、売買等の媒介・取次ぎ・代理・募集の取扱い
投資信託・外国投資信託の売買の媒介・取次ぎ・代理・募集または売出しの取扱い
有価証券の売買等について、有価証券等精算取次ぎを行うこと
【金融機関による金融商品仲介業務】
銀行等は、株券や社債券など全ての有価証券の取扱いが、売買の媒介・募集等の取扱いの範囲で可能です。
ただし、株券等は金融商品取引業者等からの委託を受けて行うものに限られます。
・金融商品仲介業

金融商品仲介業とは、金融商品取引業者等から委託を受けて、以下の業務のいずれかを行うことをいいます。
有価証券の売買の媒介
取引所金融商品市場等における売買等の委託の媒介
有価証券の募集もしくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
金融機関以外の者は、法人・個人を問わず、内閣総理大臣の登録をうければ金融商品仲介業を行うことができます。
金融商品仲介業者は、金融商品仲介行為以外の金融商品取引業務を行うことはできません。
また、金融商品仲介業者が金融商品仲介業で顧客に与えた損害の賠償責任を負います。
・金融商品取引所の適切な運営
・金融商品取引所

金融商品取引所は、内閣総理大臣の免許を受けて、金融商品市場を開設する会員制法人または株式会社です。
免許なのか認可なのか登録なのか
この違いが大切です。
東京証券取引所などがこれに該当します。
・投資者保護基金

金融商品取引法では、顧客資産の分別管理など、投資者保護の制度を設けていますが、それでも金融商品取引業者等がルールを破っていた場合などに備えて、投資者保護基金という制度を設けています。
金融商品取引業者は、必ずどこかの1つの基金に加入することが義務付けられています。
【補償内容】
破たんした金融商品取引業者が弁済できない以下のものについて、1,000万円を限度として、適格機関投資家を除く一般投資家の請求に基づき補償します。
先物取引の証拠金、信用取引の保証金とされている金銭及び有価証券
一般投資家から預託を受けた金銭または有価証券
保護預りの対象である金銭または有価証券 など
なお、1,000万円を超える部分については投資者保護基金では補償されません。

・市場阻害行為の規制
市場阻害行為の規制とは、簡単に言うと不公正取引の規制と考えるとよいでしょう。
不正行為があると、市場の機能そのものが阻害される恐れがあるので、こうした規制を設けています。
・包括規定
・不公正取引禁止の包括規定
不正の手段、計画または技巧をしてはならない。
・虚偽又は不実の表示の使用の禁止
重要な事項について虚偽の表示または重要な事実の表示が欠けているものを使用して、金銭その他の財産を取得してはならない。
・虚偽の相場の利用の禁止
有価証券の売買やデリバティブ取引等を誘引する目的で、虚偽の相場を利用してはならない。
・相場操縦
相場操縦とは、有価証券等の価格を意図的に歪曲させる行為で、厳しく禁じられています。さらに、相場操縦によって損害を受けた人がいた場合は、賠償責任を負います。
以下の取引は、実質的には取引がなかったのと同じであるにもかかわらず、活発に取引が行われていると見せかける行為であることから、これらの行為を行うこと、委託することは禁止されています。
・仮装取引
他人を誤解させる目的で、権利の移転や金銭の授受を目的としない仮装の取引を行うこと。(同一人物が売りと買いの両方を演じる)
・馴合取引
自分が売買するときと同時期に、同じ価格で他の人が買売することを予め通謀して取引を行うこと。
また、証券会社が架空の注文を出して、売買が成立しそうになると取り消すという行為(見せ玉)も、相場操縦行為として禁止されています。
・内部者(インサイダー)取引の規制

有価証券の発行会社の役職員やその関係者から、その会社の重要事実の情報を容易に入手できる会社関係者が、その立場を利用して入手した情報を利用して、それらが公表される前に当該会社が発行する有価証券の取引を行うことは禁止されています。
内部者取引となるかどうかについては、以下の要件で決まります。
・重要事実
募集株式・新株予約権の募集
資本金の額・資本準備金・利益準備金の額の減少
自己株式の取得、株式無償割当、株式の分割、剰余金の配当、株式交換、株式移転、合併、会社の分割、解散
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、新製品又は新技術の企業化
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
主要株主(議決権の100分の10以上の議決権を保有している株主)の異動
(重要事実は子会社に生じたものについても親会社同様規制の対象となります)
・会社関係者
当該上場会社の役員、代理人、使用人との他の従業者
当該上場会社の帳簿閲覧権を有する株主や社員
当該上場会社と契約を締結している銀行、公認会計士、弁護士、引受人など
以前会社関係者であった者で、会社関係者でなくなってから1年以内の者
これらの役員等には、親会社・子会社の役員等も含まれる
第一次情報受領者(上記会社関係者より情報の伝達を受けた者)
・公表される前
2つ以上の報道機関に公開され、かつ公開したときから12時間を経過しなければ公表されたとはみなされません。
ただし、金融商品取引所等に通知し、重要事実が適時開示情報伝達システムによって公衆の縦覧に供された場合は直ちに公表されたものとみなします。
・適用除外
以下の場合は適用されません。
・株式の割当てを受ける権利を有する者がその権利を行使して取得する場合
・新株予約権を有する者がその権利を行使して取得する場合
・重要情報を知る前に締結された取引
・報告義務
上場会社の役員及び主要株主(議決権の100分の10以上保有する株主)は、自己の計算で売買を行った場合は内閣総理大臣に報告しなければならない。
・短期売買規制
上場会社の役員及び主要株主が、当該会社の特定有価証券等を売買した後6ヵ月以内に買売して利益を得たときは、当該会社はその利益の提供を請求することができる。
※重要事実について
重要事実については、行うと決定したことはもちろんですが、一旦行うと発表したことを行わないと決めたときも重要事実に該当します。
・その他の不公正取引
・風説の流布の禁止
相場を操縦する目的で、風説を流布したり、偽計を用いたり、暴行・脅迫をしてはならない。
・空売りの規制
有価証券を保有しないで売付を行うこと(空売り)は禁止されている。
ただし、信用取引・先物取引など制度として確立されているものは除く。
・場外差金取引の禁止
取引所を通さず、市場の相場によって差金授受のみを行う行為は禁止されている。
・一定配当等の表示の禁止
一定額の配当が確実であるように誤解させる表示はしてはならない。
・有利買付け等の表示の禁止
不特定多数の者が取得した有価証券を、特定額以上の価格で買い付けるとか、売付けることを斡旋することや、そのような趣旨と誤認されるおそれのある表示は禁じられている。
・安定操作取引
企業による資金調達のために、金融商品取引法において例外的に認められている取引(安定操作)。
人為的に価格を安定させることは相場操縦であり禁止されているが、募集又は売出しにより大量の有価証券が一時に市場に放出されると、需要と供給のバランスが崩れて資金調達が困難になることから、一定の制限のもとに認められています。
本日は以上です。
自分達が関わる金融商品取引法について少しでも知っておくのはいいことだと思います。
FXに限らず今後は株式や世界経済など幅広く知識を身に着けることで皆さんの投資がより豊かになることを願っています。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
