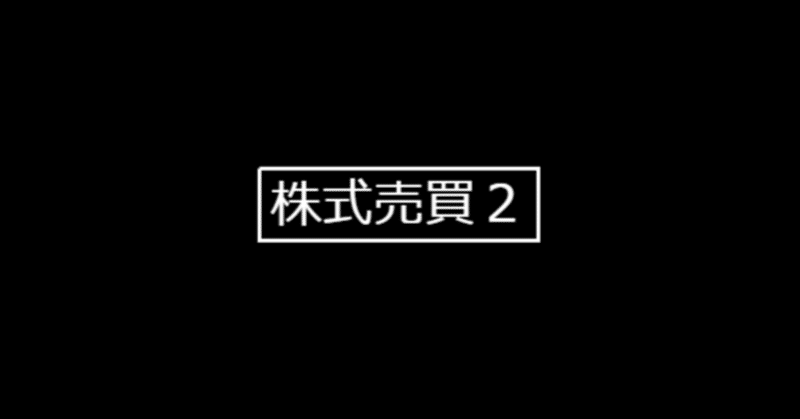
株式売買2
おはようございます。
キツネの目と申します。
本日も前回と引き続き「株式売買」について記載していきます。
よかったら参考にしてください。
・株式分割

株式分割とは、すでに発行されている株式を2株とか3株などの一定の比率で分割することです。
株式分割をすると、発行済み株式数が増えますが、株主資本は変わらないため、株価は下がります。
例えば、1:1.5の株式分割の場合、1,000株保有している株主に500株が新たに交付され1,500株になります。
このとき、理論的には株価が1.5分の1に値下がりします。
・権利付相場、権利落相場
権利付相場=株式分割の権利を含んだ価格
権利落相場=株式分割の権利がない価格


上記の権利落相場 = 1,500円÷1.5 = 1,000円
・分割後の株価の損益計算
上記の計算はあくまでも理論上の計算で、実際には上記の公式通りの株価にならないことがあります。
その場合、権利落後に損得が発生しますが、次のように計算します。

・株式投資指標
・株式利回り

投資金額に対する年間の配当金の割合のことです。
株価4,000円 年間配当金50/年の場合、利回りは「1.25%」となります。

こちらが計算式です。
・採算株価
希望の利回りを確保するには、いくらで買えばよいかという株価を採算株価といいます。
希望利回り「2.0%」 年間配当金50/年の場合、採算株価は「2,500円」となります。

こちらが計算式です。
・自己資本利益率(ROE:Return On Equity)

株主が投資した資金がどれだけ成果を上げているかを見る指標です。
この値が高い方が株主にとって魅力があるといえ、一般の金利水準より高い率であれば投資している価値があると言えます。
逆に一般の金利水準より低ければ、この会社に出資する魅力がないとも言えます。
Q:期首自己資本2,000万円、期末自己資本2,400万円、当期純利益額が400万円の会社の自己資本利益率はいくらですか?(少数第3位以下切捨て)
400万円÷(2,000万円+2,400万円)÷2=自己資本利益率(%)=18.18%
・株価収益率(PER:Price Earnings Ratio)

1株あたりの利益に対する株価の水準を表す指標です。


Q:次のA社の株価収益率はいくらですか?
<A社のデータ>
当期純利益250億円、株価500円、発行済株式数5億株
(解答)
1株あたり当期純利益 =250億円/5億株= 50円
株価収益率(倍) =500円/50円= 10倍
・株価純資産倍率(PBR:Price Book-value Ratio)

1株あたりの純資産額に対する株価の水準を表している指標です。
株価純資産倍率が1倍のとき、その企業の株価は資産価値(解散価値)と同じ水準であるということになります。

Q:次のB社の株価純資産倍率はいくらですか?
<B社のデータ>
株価400円、発行済株式数2億株、総資産600億円、総負債200億円
(解答)
1株あたり純資産 =600億円-200億円/2億株= 200円
株価純資産倍率(倍) =400円/200円= 2倍
・株価キャッシュ・フロー倍率(PCFR:Price Cash-Flow Ratio)

キャッシュ・フローとは、企業が期中に生み出した自己資金のことで、これを発行済株式数で除したものが1株あたりキャッシュ・フローとなります。
PCFRは、高ければ株価は割高、低ければ株価は割安と言えます。
なお、PCFRの計算で用いるキャッシュ・フローの額は、一般に税引後純利益に減価償却費を加えたものを使います。
キャッシュ・フローの厳密な計算とは異なるので注意してください。
Q:次のC社の株価純資産倍率はいくらですか?
<C社のデータ>
株価1,200円、発行済株式数2億株、当期純利益(税引後)100億円、減価償却費20億円
(解答)
1株あたり
キャッシュ・フロー=100億円+20億円/2億株= 60円
株価キャッシュ・フロー倍率(倍) =1,200円/60円= 20倍
・株価益回り

株価益回りとは、株価に対する税引後利益の比率のことです。
以下の式を見て分かる通り、株価収益率の逆数になっています。

・イールドスプレッド

株式益回りと長期国債などが示す長期的な金利水準との比較を行う指標です。
イールドスプレッドが小さくなるほど、株価は割安感が強くなります。
・EV/EBITDA

EVとは、企業価値(Enterprise Value)の略で、次の式で求めます。

EBITDAとは、「金利・税金・償却前利益」の略で、国際的な収益力を比較するために考えられた指標です。
金利・税金・償却方法などは国によって制度が異なるため、それらの影響を最小限にして比較するために作られました。
式の税引前利益のところに注意してください。

このEBITDAに対して企業価値(EV)が何倍に相当するかを表すのが、EV/EBITDA倍率です。
・株式売買の受渡金額

普通取引の場合には、株式の売買が成立すると、約定日から起算して3営業日目の日に代金の決済が行われます。
(1) 買い注文の場合の支払金額
約定代金+委託手数料(消費税を含む)
〔例〕1株1,000円の株式を8,000株購入した。
委託手数料は、約定代金総額×0.7%+12,500円とする。
なお、委託手数料には10%の消費税が加算されるものとする。
この場合の受渡金額を計算しなさい。
・約定代金:1,000円×8,000株=8,000,000円
・委託手数料:8,000,000円×0.7%+12,500円=68,500円
・消費税:68,500円×10%=6,850円
受渡金額:8,000,000円+68,500円+6,850円=8,075,350円
(2) 売り注文の場合の受取金額
約定代金ー委託手数料(消費税を含む)
〔例〕1株1,000円で8,000株の株式を売却した。
委託手数料は、約定代金総額×0.7%+12,500円とする。
なお、委託手数料には10%の消費税が加算されるものとする。
この場合の受渡金額を計算しなさい。
・約定代金:1,000円×8,000株=8,000,000円
・委託手数料:8,000,000円×0.7%+12,500円=68,500円
・消費税:68,500円×10%=6,850円
受渡金額:8,000,000円ー68,500円ー6,850円=7,924,650円
・株価指標
株価指標とは、個々の銘柄ではなく、市場全体の動きを捉える事を目的とし、運用成績の評価基準となるものです。
取引所に上場されている株式は、毎日株価が上下します。
銘柄によって、売買の出来高にも差があります。
このような市場動向を目で見える形でまとめてあるのが株価指標です。
最も重要な指標として、日経平均株価と東証株価指数の2つを押さえておきましょう。
・日経平均株価(日経225)

日経平均株価(日経225)は、東証プライム市場に上場している銘柄の中から市場を代表する225銘柄を選び、これらの株価を単純平均し、かつ連続性を失わせないため、権利落ちなどを修正して計算した株価指数です。
【特徴】
対象銘柄の値動きや、配当・株式分割などの権利落ちの影響を修正しているため、指標の連続性は保たれている。
過去と現在の相場の動きを比較することができる。
225銘柄の株価で指数を算出していることや単純平均であるため、株価の高い銘柄(値嵩株)の値動きに大きく影響を受ける。
・東証株価指数(TOPIX)

東証株価指数(TOPIX)は、2022年4月の東京証券取引所の新市場区分移行までは、東証1部上場の全銘柄の時価総額を合計し、1968年1月4日を基準日に、当時の時価総額を100として算出されていました。
しかし、2022年4月以降、新市場区分に移行されたことから、構成銘柄については市場区分と切り離し、流通株式時価総額100億円未満の銘柄(段階的ウェイト低減銘柄)については段階的にウェイトが低減される見込みとされています。
【特徴】
東証株価指数は、加重平均になるため、大型株に影響されやすい。
日経平均に比べて、特定業種・株価の高い企業の値動きによる影響を受けにくい。
本日は以上です。
次回は「債券」について記載していきます。
よかったら参考にしてください。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
