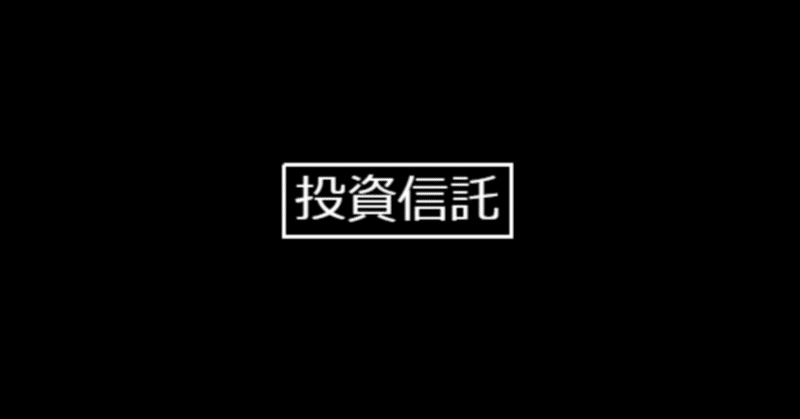
投資信託について
おはようございます。
キツネの目と申します。
4月20日のセミナーの書籍の原稿を書き上げるため、こちらのnoteの更新がおろそかになっておりました。
もし、楽しみにしてくれている方がいらっしゃいましたら申し訳ございませんでした。
本日よりまた投稿を再開致します。
本日は「投資信託」についてです。
投資信託について、言葉は知っているけどよくはわかっていないな。という方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしてください。
・投資信託とは
投資信託とは、多くの投資家から資金を集め、第三者である専門家が運用・管理する仕組みです。
このような仕組みを「集団投資スキーム」といいます。

・投資信託のメリット

・少額の資金で分散投資が可能
通常、分散投資をする場合、多くの資金を必要としますが、投信信託は、複数の投資家から資金を集めてファンドを組成するため、一人ひとりの資金は少なくても、投資信託全体としては分散投資が可能となり、結果として少額でも分散投資の効果を享受することができます。
・専門家による運用
一般の投資家個人が、市場経済の変化に対応しながら資金運用を継続するのは困難であり、また派生商品など個人が投資できないものもあります。
投資信託では、専門家に運用を任せることにより、一投資家にはできない運用が可能になります。
・適切な投資家保護
投資信託の資産運用会社には、忠実義務・善管注意義務が課せられています。
また、様々な法律により適切な投資家保護が義務付けられています。
※忠実義務・善管注意義務
忠実義務:資金の運用は受益者(投資家)の利益のみを考えて行なわなければならないという義務
善管注意義務:善良な管理者の注意をもって各業務を行なわなければいけないという義務
・市場を通じた資金供給への寄与
投資信託は、投資家が直接企業や不動産などに資金を投じるのではなく、集めた資金を様々な金融商品に提供することから、いわゆる市場型間接金融における中核的な商品といえます。
投資信託により、市場参加者の厚みが増し、リスク配分の効率化とリスク負担能力の向上という重要な役割を果たしています。
・投資信託のリスク

投資信託に限らず、金融商品で「リスク」といえば、「値動き」または「値動きの大きさ」のことをいいます。
簡単にいうと値下がりする可能性があるということです。
・価格変動リスク
投資信託は、株や債券などに投資をするため、銀行預金と違い元本割れ、値下がりリスクがあります。
また、ファンドの構成によって、金利、景気、為替など様々な影響を受け、値上り・値下がりが起こります。
・信用リスク
債券や株式と同様に、投資信託にも信用リスクが付いて回ります。
投資先の債務不履行リスクに影響を受けます。
・為替変動リスク
為替が変動することで、金利が変化したり、資金需給のバランスが変化するなどして、投資信託も影響を受けます。
・投資信託の分類

・投信法
投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下、投信法という)により規定されています。
投信法では、投資信託を委託者指図型と委託者非指図型に分類し、さらに投資法人についても定義しています。

・投資信託の分類方法
投資信託には、以下のように複数の分類方法があります。
・募集対象人数等による分類
公募/私募
・設立形態による分類
契約型(委託者指図型/委託者非指図型)/投資法人
・解約の可否による分類
オープン・エンド型/クローズド・エンド型
・追加設定の可否による分類
単位型/追加型
・投資対象による分類
証券投資信託/不動産投資信託/証券投資信託以外の投資信託
【分類のイメージ】

・募集人数等による分類
投信法では、次のように公募と私募を定義しています。
・公募
多数の者(50名以上)に対して申し込みの勧誘を行うもの
適格機関投資家私募を除く
・私募
適格機関投資家私募
1,適格機関投資家のみに勧誘を行うもの
2、特定投資家のみに勧誘を行うもの
一般投資家私募
公募、適格機関投資家私募のどちらにも該当しないもの
・設立形態による分類
設立形態による分類は、基金(ファンド)に関する法的スキームの違いによる分類です。
設立形態は契約型と会社型に分けられ、さらに契約型には委託者指図型と委託者非指図型に分類されます。

・契約型
委託者と受託者が締結した投資信託契約に基づき基金(ファンド)が設立される
受益権は投資家が取得する
法人格がない
・会社型
資産運用を目的とする法人(投資法人)を設立する
投資家はその法人が発行する証券を取得する
法人格がある
上記のような違いがあります。
※委託者指図型と委託者非指図型の違い

・解約の可否による分類
投資信託の解約とは、受益者が解約を請求すると、委託会社は投資信託財産から直接取り崩して支払いに応じることをいいます。
つまり、簡単に言えば解約が発生すると基金(ファンド)のお金が減少します。
解約の可否による分類とは、投資信託を解約できるオープン・エンド型と解約できないクローズド・エンド型に分けられます。
・オープン・エンド型
投資家は解約できる(委託会社が発行証券を買い戻すことができる)
買い戻し価格は基準価格
→ 基金が減少する
一定期間解約できない期間(クローズド期間)を設けているものもある
・クローズド・エンド型
投資家は解約できない(委託会社は買い戻す義務がない)
→ 基金が安定している(減少しにくい)
投資家が換金する場合は市場で売却するしかない
・追加設定の可否による分類
追加型と単位型の区分は、基金(ファンド)が設立された後に追加の資金が設定(追加の募集)されるかされないかの違いです。
最初の設定時には、どちらも期間を区切って募集するのですが、追加型はその後も追加の設定があり、単位型は追加がありません。
・追加型
基金設立後も追加資金を募り続ける。(投資家は設立後も買える)
→ 資金が追加される
(原則)解約・売買が自由に行われる
・単位型
最初の募集期間のみ申し込み可能
→ 資金の追加がない
解約については、いつでも解約できる商品やある一定期間解約ができない商品など商品ごとに異なります。
・単位型投資信託の種類
1、ファミリーファンド・ユニット
継続して定期的に同じ仕組みの投資信託を設定していく
2、スポット投資信託
投資家のニーズや市場状況に応じて、その時々に適した投資信託を設定する
最近はスポット投資信託が主流になってきています。
・契約型投資信託
・投資信託約款

投資信託は、投資信託約款に運営の基礎となる内容が定められています。いわば、投資信託の設計図または企画書のようなもので、当該投資信託の具体的な内容を定めたものです。
投資信託約款には主に次の事項が記載されています。
・委託者及び受託者の商号、名称、その業務
・投資の対象とする資産の種類、その他信託財産の運用に関する事項
・投資信託財産の評価の方法、基準・基準日に関する事項
・信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
・信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
・信託報酬その他の手数料の計算方法
・投資信託約款の変更に関する事項
・委託者における公告の方法
など
投資信託委託会社(委託者)は、あらかじめ投資信託約款を内閣総理大臣(金融庁長官)に届出なければなりません。
・投資信託約款の交付

委託者は投資信託を取得する者に対して、投資信託約款を書面で交付しなければなりません。
ただし、以下の場合は書面による交付を省くことができます。
目論見書にその内容が記載されている場合
適格機関投資家私募により行われる場合
すでに同じ投資信託を保有している場合
同居者への書面交付している場合
交付しないことについて同意している場合
・投資信託約款の変更

委託会社は変更内容を内閣総理大臣に届け出る必要がある
重大な変更は受益者の特別多数による書面決議が必要
・投資信託契約の解約(ファンドの償還)

投資信託は、投資信託約款に定められた信託期間が終了すると償還(満期償還)されます。
また、多くの約款では、一定の条件(一定の残存口数を下回るなど)で繰上償還することを定めています。
このように、投資信託契約を解約し、償還しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(金融庁長官)に届け出る必要があります。
また、繰上償還を行う場合は、受益者の書面による決議が必要です。(議決権を行使できる受益者の3分の2以上の多数をもって行う)
繰上償還に反対した受益者は、自己の有するファンドを買取を請求することができます。
・証券投資信託の関係者
証券投資信託は、投資家(受益者)、 販売会社(証券会社・銀行等金融機関)、委託会社(委託者)、受託会社(受託者)で成り立っています。

受益者
投資信託の利益を受ける権利を持つ者
受益権の口数に応じて均等の権利を持つ
販売会社
金融商品取引業者、銀行等の金融機関
委託会社が直接販売することも可能
委託会社から契約により指定される
委託会社
受託者と投資運用契約を締結する者
投資運用業として登録が必要
投資信託約款の届出を行う
投資信託財産の運用の指図を行う
投資信託財産に組み入れられた有価証券の議決権等の指図行使
目論見書、運用報告書を作成する
投資信託契約の解約(償還)を行う受託会社
信託会社または信託業務を営む認可金融機関
投資信託財産の管理
ファンドの基準価格の計算(委託会社との照合)
固有財産と信託財産の分別管理
信託財産の名義人
※証券投資信託の定義
「証券投資信託」とは投資信託の分類の一つで、投資信託財産の総額の2分の1を超える額を有価証券等に投資して運用することを目的とした委託者指図型投資信託です。
・会社型投資信託
投資を目的とする法人(投資法人)を設立し、投資家が投資法人に出資をしたうえで、投資法人からの収益の分配を受けるタイプの投資信託を投資法人といいます。
基本的な構造は株式会社と同様で、法人格を有します。
・投資法人の設立と概要
・設立
投資法人は、設立企画人が規約を作成することから始まります。

規約を内閣総理大臣に届出を行い、届出が受理されると規約の効力が生じます。
その後、設立法人は設立登記によって成立します。
投資法人の設立時の出資総額は、設立の際に発行する投資口の払込金額の総額で、1億円以上と定められています。
・投資法人の運営

投資法人は、資産運用のための器としてのみ機能し、実際の資産運用業務、資産保管業務及びその他の一般事務については、外務委託をすることが義務付けられています。
資産運用
投資法人は自ら資産を運用することはできません。
必ず外部の資産運用会社にその資産の運用に係る業務を委託しなければなりません。
資産運用会社は、資産運用に係る権限の全部を再委託することは自己執行義務の観点から禁止されています。
ただし、投資法人との契約でその一部を再委託することは可能です。
資産運用会社は投資運用業を行う金融商品取引業者でなければなりません。
資産の保管
投資法人は自ら資産の保管を行うことはできません。
資産保管会社に保管業務を委託しなければならない。
資産保管会社は、信託会社等、有価証券等管理業務を行う金融商品取引業者に限られます。
一般事務
投資法人は、資産の運用や保管以外の事務についても一般事務受託者に委託しなければなりません。
販売
投資法人の投資証券は、金融商品取引法上の有価証券なので、その募集・販売の取扱いは、金融商品取引業者等が行います。
計算書類の作成及び監査
投資法人は、決算期ごとに計算書類等、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書並びにこれら書類の付属明細書を作成し、これを会計監査人に提出し、その監査を受けなければなりません。

・投資法人の機関
・投資主総会
投資主総会では、執行役員の選任や規約の変更など、投信法に定められた事項と規約に定められた事項を決定します。
原則として執行役員が招集します。
【主な決議事項】
執行役員、監督役員、会計監査人の選任・解任(普通決議)
規約の変更(特別決議)
資産運用業務委託契約の承認
投資口の併合(特別決議)
吸収合併・新設合併契約の承認
解散(特別決議)
・執行役員

執行役員は、投資法人の業務を執行し、投資法人を代表します。
執行役員の人数は、1人または2人以上であればよいとされています。任期は2年です。
外部の資産運用会社等との間で契約を締結する権限を有し、投資主総会を招集し、決算期ごとに計算書類等を作成し会計監査人による監査を受けるなどの業務を行います。
・監督役員

監督役員は、執行役員の職務を監視する役目があります。
投資主総会で選任され、人数は「執行役員数+1人」以上と定められています。
任期は4年を超えることができません。
監督役と執行役員は兼任できません。
・役員会

役員会は執行役員と監督役員からなる会で、執行役員が重要な業務執行を行う場合には役員会の承認が必要になります。
・投資信託の種類
・投資対象による分類
投資信託の投資対象である特定資産は、主に5種類に分類されます。
有価証券
不動産
有価証券以外の金銭債権
商品
インフラ設備
これらのどの資産に主に投資するかによって、証券投資信託、不動産投資信託、証券投資信託以外の投資信託、インフラ投資信託に区分されます。
・証券投資信託

証券投資信託は、投資信託財産の総額の2分の1を超える額を有価証券等に対して投資する委託者指図型投資信託と定義されています。
同様に、投資信託財産の総額の2分の1を超える額を有価証券等に対して投資する投資法人を証券投資法人と定義しています。
なお、委託者非指図型では、証券投資信託を設定することができません。
証券投資信託は、投資対象の違いによって、株式投資信託と公社債投資信託に分けられます。
・株式投資信託
約款の投資対象に株式が含まれているもの
基本的には株式を中心に運用されるが、株式が一切含まれない投資信託でも、約款の投資対象に株式が記載されていれば株式投資信託になるので注意が必要
・公社債投資信託
国債、地方債、社債、コマーシャル・ペーパーなどに限って運用するもので、株式を投資対象としていないもの。MMF、MRF、中期国債ファンドなどが代表例
・不動産投資信託

不動産や不動産関連の権利及び不動産関連商品を主な投資対象とするものを不動産投資信託といいます。
ルール的には契約型でも会社型(投資法人)でも設立は可能ですが、実際は会社型である投資法人で組成されています。
日本の不動産投資法人は、J-REITと呼ばれています。
不動産は通常、換金しにくい(流動性が低い)資産なので、不動産投資法人は、通常、解約できないファンドとして設立される一方で、投資家が換金できるよう、不動産投資法人が発行する投資証券が取引所に上場させ、市場で売買できるようにしています。
・証券投資信託以外の投資信託
有価証券以外の金銭債権や商品を主要投資対象とする投資信託です。
・インフラ投資信託
インフラ設備を主要投資対象とする投資信託です。
比較的新しいカテゴリーで、2015年に東京証券取引所に、太陽光発電施設などのインフラ施設を投資対象とするインフラファンド市場が開設されました。
・その他の投資信託
・外国投資信託
外国投資信託とは、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託と類似のものをいいます。
注意すべき点は、どこの法令に基づいて設定されているかで、投資対象が外国証券かどうかではないということです。
日本国内の法令に基づいて設定された投資信託を外国投資信託と区別して呼ぶ場合は国内投資信託といいます。
・マザーファンド
ファミリーファンド方式(=マザーファンド方式)で運用する場合に利用されるファンドで、他の投資信託(ベビーファンド)に取得させることを目的とする投資信託をマザーファンドといいます。

・ファンド・オブ・ファンズ
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託及び外国投資信託への投資を目的とする投資信託をいいます。
通常の投資信託は複数の株式や債券などで運用しますが、ファンド・オブ・ファンズは複数の投資信託を組入れて運用します。
※ベビーファンドとファンド・オブ・ファンズの違い
一見両方同じように見えますが、主に次の点で違いがあります。
説明を分かりやすくするため、次のような設定をします。
Aさん:ベビーファンドaを購入、マザーファンドはb
Bさん:ファンド・オブ・ファンズeを購入、eの投資対象である投資信託はfとg
「マザーファンドは信託報酬を徴収しない」
→Aさんは、ベビーファンドaの信託報酬だけ負担する
→Bさんは、eの信託報酬を負担するとともに、間接的にfとgの信託報酬も負担している
マザーファンドは信託報酬を徴収しないので、通常マザーファンドとベビーファンドは同一の運用会社が設立したものとなるのに対し、ファンド・オブ・ファンズは、他社の投資信託でも外国籍の投資信託でも組入れることができます。
・ETF(上場投資信託)

ETF(Exchange Traded Funds)は、投資成果が東証株価指数や日経平均株価などの株価指数や商品価格などの指標に連動するように設定され、取引所に上場している投資信託です。
以下のような特徴があります。
売買価格は、他の投資信託と異なり、基準価額に基づく価格で購入や換金されず、取引所において上場株式と同じように市場価格で売買されます。
指値注文や成行注文が可能であり、信用取引も行うことができます。
税制上の取り扱いは、基本的に上場株式と同じであり、普通分配金や特別分配金(元本払戻し)の区別はない。
・分配型
投資信託は決算ごとに分配を行います。
その分配の頻度は、毎月分配、隔月分配、年1回分配などいくつかの種類があります。近年の主流は毎月分配です。
分配金の額は確定していませんが、ファンドの方針によってなるべく安定した分配を行うこともあり、ときには収益が少なくても一定の分配をするため、分配金の一部または全部が元本の一部払戻しに相当する場合があることを理解しておくことが重要です。
・通貨選択型
通貨選択型とは、投資対象に外貨も選択できるように設計された投資信託です。この場合、通常の投資信託のリスクである価格変動リスクや信用リスクなどに加えて為替リスクも発生します。
本日はここまでにします。
次回以降も引き続き「投資信託」について記載していきます。
よかったら参考にしてください
ここまで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
