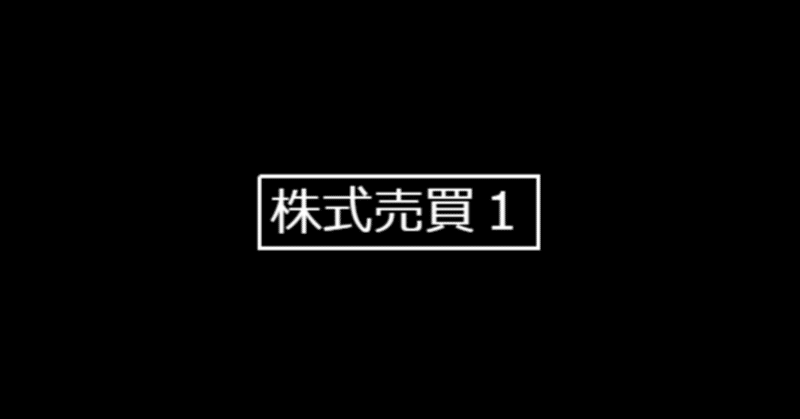
株式売買1
おはようございます。
キツネの目と申します。
本日は「株式売買」について記載していきます。
よかったら参考にしてください。
・株式と証券会社
株式には、上場株式と非上場株式があります。

上場株式は取引所取引と取引所外取引で取引されています。
非上場株式は取引所外取引と店頭取引で取引されています。

金融商品の取引(ないしは金融商品取引業者)は、大きく以下の3つの法律や規則のもとで取引が行われています。(もちろんこの他にも沢山の法律等に関係します)
金融商品取引法 ・・・ 金融商品取引業者として
協会定款・諸規則 ・・・ 日本証券業協会の会員として
取引所定款・諸規則 ・・・ 取引所の参加者として
・取引の種類、売買形態
取引の種類には、以下の3つの種類があります。
これは「どこで」取引されているかを意識して考えると分かり易いです。
・取引所取引
証券取引所で行われる売買(上場株式)
東京、名古屋、福岡、札幌の各証券取引所
大阪取引所はデリバティブに特化した取引所
・取引所外取引
取引所外で行う上場株式等の取引
・店頭取引
店頭取引は以下の2つの意味でつかわれることがある
・上場していない株式の取引
・取引所外で行われる取引全般(上場・非上場)
・売買形態

1.株式の売買(自己取引)
金融商品取引業者が自己の計算で行う売買のこと。
つまり、証券会社が自身のお金で取引を行う場合を自己取引といいます。
2.株式の売買の取次ぎ(委託取引)
顧客の計算において、金融商品取引業者の名で行う取引のこと。
顧客から依頼されて取引所で取引する場合は、通常この取引にあたります。
3.株式の売買の代理
顧客の名で、金融商品取引業者が代理人であることを明示して執行する取引のこと。
顧客と金融商品取引業者の間で代理人契約を締結して行います。
4.株式の売買の媒介
売り手と買い手の間で、売買の成約に尽力する行為のこと。
顧客からの要請により、取引所市場外で売買の仲立ちを行うことなどがこれにあたります。
5.取引所金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
取引所の参加者でない金融商品取引業者が、顧客から有価証券の売買注文を受託した場合に、その取引所の取引参加者に再委託して売買を執行してもらう方法のこと。
・売買の受託
有価証券の売買の受託の際には、投資者保護及び不公正取引防止等のコンプライアンス上の観点から様々な確認義務が設けられています。

・顧客の調査と本人確認
金融商品取引業者は、有価証券の売買その他の取引を行う顧客について以下の義務があります。
顧客カードの整備
氏名、住所、連絡先など
本人確認
本人確認書類の提示、取引を行う目的や職業などの確認
・投資勧誘
投資勧誘にあたっては、適合性の原則を徹底しなければなりません。
【適合性の原則】
顧客の投資に関する知識・経験
財産の状況
投資の目的
その他顧客の意向や実情に応じた勧誘
【契約締結時の義務や規制等】
顧客に対して、投資は投資者自身の責任において行うべきものであることを理解させる
契約締結前交付書面の交付(損失の生じる恐れがあることなど)
顧客が迷惑な時間に電話や訪問によって勧誘してはならない など
・契約締結前書面の記載事項
契約締結前書面には、以下の内容を記載しなければなりません。
・基本的な記載事項
金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所
金融商品取引業者等の登録番号
・全般的な注意事項
取引の概要、手数料・報酬等
相場の変動等により損失の生ずるおそれがあること
損失が預託すべき委託証拠金等の額を上回るおそれがあること
その他顧客の注意を喚起すべき事項
・交付対象
一般投資家(特定投資家は対象外)
さらに、以下のような取引については、それぞれの取引ごとに留意事項があります。
・信用取引及び発行日決済取引
信用取引については、取引開始基準を定め、適合した顧客から信用取引を受託しなければなりません。
この基準は各金融商品取引業者が定めます。
・外国証券取引
外国証券の取引の注文を受ける場合、顧客と外国証券の取引に関する契約を締結しなければなりません。
その際、外国証券取引口座に関する約款を交付し、当該顧客からこの約款に基づき取引口座の設定の申込書の提出を受けなければなりません。
・安定操作期間中の注意事項

原則として、人為的に価格を安定させることは相場操縦であり禁止されていますが、募集又は売出しにより大量の有価証券が一時に市場に放出されると、需要と供給のバランスが崩れて資金調達が困難になることから、一定の制限のもとに安定操作取引が認められています。
安定操作期間中には、以下の行為が禁止されています。
・元引受金融商品取引業者の禁止行為
自己の計算による買付け (ただし、株式累積投資及び株式ミニ投資は除く)
他の金融商品取引業者等に買付けの委託等をする行為
安定操作取引に係る有価証券の発行者である会社の計算による株券の買付けの受託等 など
・安定操作取引またはその受託をした金融商品取引業者の禁止行為
顧客に対して安定操作取引が行われた旨を表示しないで買付けを受託すること、売付け又は当該有価証券の売買に係る有価証券関連デリバティブ取引の受託等
・期間の区別
安定操作取引では、安定操作期間とファイナンス期間という2つの期間が存在します。
いずれも「いつからいつまで」なのかをしっかり区別して覚えておきましょう。
安定操作期間
募集・売出しの価格決定日の翌日~申込最終日
ファイナンス期間
募集・売出しの発表日の翌日~払込日

・空売り規制
空売りとは、保有していない株券や借りてきた株券を売ることです。
空売りは、相場操縦に繋がる恐れがあるため規制されています。
顧客から有価証券の売付けの注文を受ける場合では、当該注文が空売りであるか否かの確認をしなければなりません。
同時に顧客の側にも、空売りであるか否かを明らかにする義務が課せられています。
空売りに該当する場合は、金融商品取引業者が取引所に報告しなければなりません。
・注文の執行と受渡し
注文を受けて受け渡すまでのには、以下の事項をそれぞれの決まりに沿って行う必要があります。

・委託注文内容の確認
株式の委託注文の場合、顧客は金融商品取引業者に有価証券の売買の委託の都度、以下の事項を指示しなくてはなりません。
・売買の種類
普通取引・当日決済取引・発行日決済取引の取引の区分
現物取引・信用取引の区分
立会内取引と立会外取引の区分
・銘柄
銘柄コード
・売買の区別
「売り」か「買い」
・数量
10,000株など数量を指定
・値段の限度
指値注文か成行注文 指値の場合は値段
・売買を行う時
寄付き、引け、ザラ場など
・委託注文の有効期間
本日中、〇〇日までなど
・現物取引又は信用取引の別
「現物取引」か「信用取引」
さらに、以下の事項についても確認する必要があります。
取引をする市場
信用取引の場合は、制度信用取引・一般信用取引の別
自己向い・委託の区別
売付けの場合には、空売りか否か
決済方法
※委託注文内容の確認
上記の確認事項等は株式の場合について記載しています。
このほかにも指数先物取引やオプション取引などの場合は、それぞれについて項目が定められています。
・注文伝票の作成

金融商品取引業者は、顧客から売買を受託した場合は注文伝票を必ず作成しなければなりません。
注文伝票は、売買が成立するかしないかは関係なく作成します。
この注文伝票の記載事項も決められています。
【注文伝票に記載すべき事項】
・自己または委託の別
・売付けまたは買付けの別
・受注日時
・顧客の氏名又は名称
・受注数量
・約定日時
・取引の種類
・約定数量
・約定価格
・銘柄
・指値又は成行の別
※一定の要件の下に注文伝票を電磁的記録により作成することもできる。
・契約締結時交付書面
契約締結時交付書面は、売買が成立した場合に、書面を作成し遅滞なく顧客に交付し、写しを1部保存しなければなりません。
なお、顧客から承諾を得て電子的方法により提供することができます。
契約締結時交付書面の主な記載事項は以下の通りです。
【契約締結時交付書面に記載すべき事項】
・金融商品取引業者等の名称又は氏名
・銘柄
・対価の額
・金融商品取引業者等の営業所又は事務所の名称
・取引の種類
・売付け買付けの別
・顧客の氏名又は名称
・約定数量
・取引の内容を示すための必要な事項
・自己又は委託の別
・単価
・受渡し

株式の売買が成立し、株券の引き渡しと引き換えに代金を収受することを受渡しといいます。
取引所において普通取引で売買したときの受渡しは、売買成立の日から起算して(売買成立日を含む)3営業日目に行われます。

・手数料
株式の売買が成立した場合は、金融商品取引業者は顧客から手数料を受け取ります。
この手数料は委託取引と仕切取引の2形態に分類できます。
・委託取引
売買を委託され取引を執行した場合に、顧客と合意した委託手数料を受け取る。
委託手数料は完全自由化されている。
・仕切取引
取引所外で金融商品取引業者と顧客が相対売買をする。
以下の2つの方法がある。
1.委託手数料と同様に手数料を受け取る方法
2.手数料分を売買値段に含めて約定し、別途徴収しない方法
本日はここまでにします。
次回も引き続き「株式」について記載していきます。
よかったら参考にしてください。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
