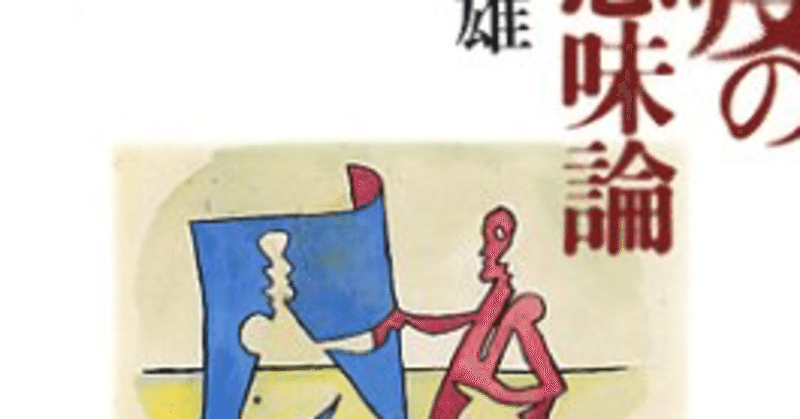
免疫のお話!
「姫ー、今日は免疫のお話しましょうよ。」
「妾、そんな気分では無いんじゃけどのうのう。」
「免疫って、日常会話でもよく使われますよね。たとえば、『田舎の高校で一番、お勉強できて、ウブな女の子だったから、男に免疫がなくて』とか、『学問一筋の硬派少年だったから、カルト免疫なくて、ちっちゃな可愛い女の子に上目使いで覗き込まれながら、”チョットお茶でもしながら、大切なお話ししませんかぁ?”とか言われるとノコノコと鴨がネギ背負って、ついていく』とかね。」
「なんか、例が偏りすぎているような気もするが、おまえ、なんかあったんか!?!?!?」
「いえ、俺が若い頃の日本って、特に、東京って、こういうのもバブってましたよねー!w」
「ま、知らんけどな。で???」
「しかし、免疫ってそもそも、なんなのか?あんまりきちんとは知られていない気もするんですよね。」
「もちろん、医学の世界では、免疫の研究は大きなテーマだから、ずっとやられてきてるよな。妾も、臨床の専門家ではぜんっぜん無いから、詳しくは知らないよ。でも、たとえば、1901年に第一回ノーベル医学生理学賞を受賞したエミール・フォン・ベーリングは、その受賞理由が
”ジフテリアに対する血清療法の研究”
が認められたことだったけど、これは、免疫でいう抗原と抗体の同定じゃな。ジフテリアはウイルスではなくて、細菌じゃが、その抗原とそれに対応する抗体をきちんと同定したわけじゃ。そして、その後のワクチン開発の基礎を作った。」
「あ、それは聞いたことありますね。確か、日本人の研究者の方が同様の研究は早かったというようなエピソードとともに、NHKなんかでも特集組まれてたことがあるような・・・・・・・・。」
「北里柴三郎先生じゃろ?それは、ここであんまり詳しく語る気がせんが、日本人の仕事は、戦前は軽く見られがちだったよな。ま、簡単な参考ページがある:」
「原始的なワクチンの製造方法は、北里先生が一番に開発されたんですねー。」
「そうそう、ワクチンも今では、mRNA法など、より細胞・分子レベルの原理原則に即して、より工学的に簡便な方法が編み出されてきているけど、北里先生の方法は、少しずつ、抗原を動物に注射して、抗体が作られた頃に、その血清を取り出すという手法じゃった。しかし、返す返すも、訳のわからない政治で、良い仕事がコンテンポラリーに評価されなかったのは残念じゃな。」
「ま、大小問わず、また、分野も問わず、こういうことって繰り返されているんでしょう???そんなことより、免疫の話しましょうよ。政治の話はつまんないです。」
「しかし、20世紀ってのは、中世以来の医学の懸案に大きな進歩があったんじゃ。19世紀まで、特に、中世では、感染症ってのがやっぱり、病気の中では1番の恐怖だった。」
「コレラ、チフス、マラリア・・・。伝承されているヨーロッパの民話にも、大きな感染症と関連したものが結構あるような???」
「”ハーメルンの笛吹き男”とかね、有名じゃよな。どうも、感染症対策を進歩させた現代の目で見ると、この話は、ネズミから(ノミを介して)伝染って大災害をもたらす””ペスト””のエピデミック、さらには、パンデミックが起こることが現象的に知られていて、それを未然に防ぐために、感染の疑いのある人たちから、子供たちを一斉に隔離したんじゃないか?っていう説もあるようじゃよな。」
「ま、”ハーメルンの笛吹き男”自体は、いろいろな研究があって、いろんな説があるみたいですけどね。」
「14世紀には、ヨーロッパの人口の 1/3 がペストで死んだので、な。昨年あたり、NHKでも、特集やってたよな。」
「感染症の原因が微生物(細菌やウイルスなど)であると特定され、その傾向と対策の進歩は、20世紀の医学の大成果ですよね。」
「そこから、分子生物学的な進歩とも相まって、より分子・細胞レベルでの”免疫”の研究がなされてきたのですよね。」
「臨床医学的な専門の深いことは知らんけどな、当然。リベラル・アーツの世界に”免疫”のメカニズムやダイナミズムの一般的な興味を持ち込んだのは、日本では、多田富雄さんじゃな。」
「1993年に出版された”免疫の意味論”ですよね。これ、すっごい読まれましたよね。」
「多田先生自身は、世界的にも著名な免疫学者であってな。専門的な論文も多数、著されている。しかし、多田さん、それだけでは気が済まなかったのかな?現代社会において、免役のシステムやダイナミクス、それに伴う大小の医学的な意味のみならず、社会的な意味を知らしめるべきとお考えになられたように思うのう。」
「それは、河合隼雄さんなどとの対談などでも、御自分でおっしゃられているね。」
「文系的というか、リベラル・アーツの世界への理解もあって、造詣が深かったですよね。」
「脳科学ばかりでなく、伝統芸能の能などにも詳しくて、白洲正子さんと能についての対談なんかもされておるな。」
「白州さんは、有名な白洲次郎の奥さんだった人で、日本にちゃんと貴族がいた頃の風貌を持った最後くらいの世代ですかね?白州ご夫妻の風貌やご発言、生き方や在り方など見ていると、現在ではこのような文化はもう復活しないだろうな、とは思いますね。今の貴族っていうと、麻生先生くらい??? やはり白州先生などと比べてしまうとどうしても、お品が下がるというか・・・・・・・。」
「なぜか、富山TVで、特集が!www 何か、縁のある人がおるんじゃろうな???」
「彼のような人がいれば、ボリス・ジョンソン英首相のような英国の真の貴族(彼はイートン校首席卒業、物心ついた時から、何人もの専門的(ラテン語やギリシャ語などを含む)な家庭教師が付いているようなヨーロッパの真の貴族階級の出身じゃ!)に対してでも、間違った判断で行動するようなら、綺麗なクイーンズイングリッシュで怒鳴りつけたりするんでしょうね???」
「ま、それはどうでもええけど、閑話休題。話し、戻そうぞ。」
「そうそう、多田先生だけど、若い時、”世界の警察官”としてもノリに乗っていた時期のアメリカへ、1960年頃の米国留学されていて、デンバーでの思い出など、脳梗塞を経験された後に書かれた本も読み応えあるぞ:」
「ちょっと、話それ過ぎですけど、俺も、1999年から2000年にかけて、アメリカで過ごしたことがあるのですけど、その時、同僚だった人に、この”免疫の意味論”を読めって教えられて以来ですよ。彼は、分子生物学者でしたが、あの時の縁をもっと大切にしときゃよかったな、とか、細菌、いや、最近よく思い出します。」
「あの頃、認識なかったよね。やりたい仕事も、別にあったしな。しかし、今となっては、あの頃、読んだ多田先生の本とか、河合隼雄さんの本とか、自分の”教養の核”っみたいになっていて、人生の後半戦の拠り所にもなっているからなーwww」
「人生、何がどう転ぶかわかりませんね。」
「おう!なんか、”免疫の話”ってタイトルで話始めたけど、なんか、今回はこれでもう、終わりでええかな?」
「ああ、本当は、分子レベルの研究が進んで、その最先端にいらっしゃった多田先生は、リベラル・アーツの世界に、その成果の社会的な意味をも持ち込もうとされて著書を著された。そして、まず、免疫のシステムの機能ってのは、
”自己と非自己との峻別”
だと明確に述べてくださった。それで、目が覚めるような思いをしたものじゃ。」
「ま、続きは、上記に紹介した御本を興味に従って、各自、読んでいただければいいんじゃないですかね???」
「ただ、しかし、1993年から、30年弱。この世界、つまり、細胞・分子レベルでの”免疫学”というのは、ものすごく進歩していて、多田先生の御著書のリベラル・アーツ的な意味は全く減じておらないにしても、臨床的な医学専門家としての知識としてはいささか、古いことは念頭においておいて欲しい。」
「そのくらいでやめましょう。3000文字超えて、疲れてきました。」
「なんだそれは!根性ないのう!!!」
「その”根性論”、多田先生が最も、お嫌いだったものですよ。河合隼雄さんも、文化庁の長官までやられたけど、日本的な根性論はいかんのうっておっしゃってました!」
「うるさいは!もちろん知っておる。しかし、妾がお前にいうのはええんじゃ!」
「なんですか?それは差別ですか?」
「伴侶というのはそういうものじゃろう?だから、じゃな。」
「まあそれならね、聞いときましょ。」
「ではまた似たテーマで会話しょうぞ。」
「ええ、今度は、話それないようにしないとね!www」
「ああ、気をつけよう。」
「しかし、富山TVの番組、面白いな!あんなのあるの知らんかった。」
「これ、それにひと月ほど前に on air されたばかりじゃないか!」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
