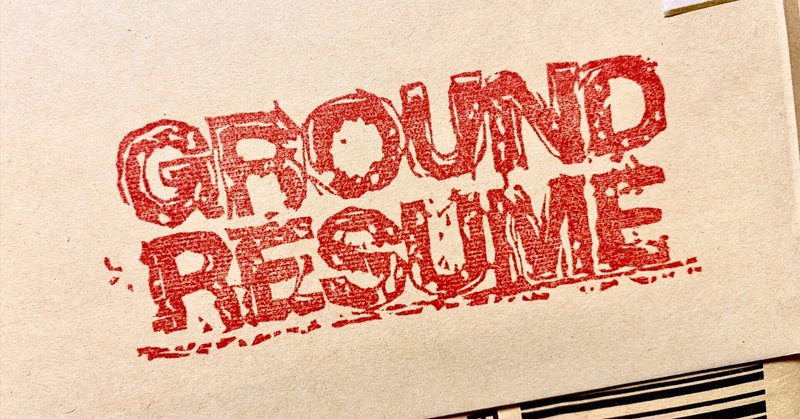
「PicoN!」という専門学校の媒体に紹介されてたのを契機に、現在整理している事案を書き綴ってみた♪
今回は、インタビューを受けたのが記事になったので、ご紹介いたします。
昨年の後半から、まったく写真の専門学校には卒業生がうろつくものではないと理解してから、一年ほど経ちましたが、中野北口の「サンクオーレ」というタワーマンションの2階のカフェでインタビューを受ける事になったのが少し以前。中野北口もいくらか大学ができましたし、旧陸軍諜報部隊育成機関の跡地を利用して防災拠点にもなっていますので、街が少し若くなりましたね。
ただ、都市を構成するときにあれだけのビル風を計算しないというのも、戦後から続く無計画な経済至上主義の弊害でもあり、毎度、陸軍用地だったころの、荒地に残る大木をこぎれいな広場に見るたびに、他の大木はどこにいったのだろう?などと思いを馳せるのは、長く中野に住んだものとしては日常的な疑問でもあるのだけれど。
さて、そのインタビューを受けた事は大変に光栄な事で、まだしも、まったく、相手にされないよりは良いものです。応援されているのも理解できたので、嬉しい事です。
改めて、感謝・御礼申し上げる次第です。
また、あやふやにしていた「目安の一年間の計画」について、この際に記載しなければならないと思いますので、簡潔にまとめました。(私見をお世話になっている方にお話ししました)
※ざっぱな内容はこちら(多少、加筆しています)
【「仮想」○○先生へのお手紙】
僕は、今までの国内の写真を観てきて、どの写真展を見ても、海外の受け売りであったり、欧米・ことアメリカの写真の真似事にしか、見えなくなってきているのが実際です。また日本独自といえば、八百万の神様の韻を踏んだ表現や浮世絵の二次元性が現代のサブカルチャーとつながっているようなイメージの表現あたりまでしか知らないというのが実際です。
そして、写真というものの内側に潜む可能性というのは、森山さんや、中平さん、岡田隆彦氏や、諸々の昭和の面々がやりつくしているので、それ以上の内省的な可能性はあまりないと思っています。ドキュメンタリーの写真はもはや日本の写真レベルでは世界に通用していないとも感じています。
もとい、欧米でも、ベッヒャーシューレの方々がやっているように、可能性の探求は続いていると思います。写真がこれだけ民主化した時代に、古典的なアウラを表現する写真を探求する事に、継続的に意義がある事は認めます。それは時代が変貌すれば、表層が変わるというサーフェースの話だと感じています。
僕がやりたい事は、写真はあくまで主役ではない、アートの文脈(アルスというべきかもしれません※ギリシャ時代からのアートの原点ですね)のモチーフとして表現に組み込まれながら主張をして、世界の価値観のバランサーとしての役割を担うべきだと考えているのです。ただ「僕の場合はその主軸が写真」だと云うだけの事です。
ですから、撮影はプリミティブに実行し、撮影された写真を如何に活用するか?というその後のアプローチをこの一年程度を目途に、色々と難儀しているのです。野蛮な申し方をすれば、写真の内省性はもう十分だろうと思うのです。社会とのエフェクティブな関係をもっと強くしていくべきだと、僕は考えています。
この一年、または一年で構想が成立するかは予定段階ですが、今までの写真の文脈で展示をしないという事は、それを指しています。
世界は、いまだに構造的な現状維持を試みようとし続けます。現状維持は、長期にわたる「無意識の衰退」だと、僕は考えていますので、日本でも世界でも同じですが、アーティスト個々人の本然的に目指すものの成果物が、未来の世界のバランスの一助となる事を願ってやまないのです。
したがって、僕の写真の扱いもそのように今までのままの路線の上では表現しないという事を明確な意思のもと提示いたします。
そのような観点に至ったので、守旧的な発想の写真集団から、すべて離れたというべき事案が、結果として、神田や四谷、そしてニコンやオリンパス、リコー、ソニー、すべてのメーカー系ギャラリーでの展示に重要性を見出せないという意味なのです。
どうしてもそこで展示をさせたがる方々が非常に日本写真の指導者層に多いので、はて、如何にしてこういったお話しをしたらよいか?
と、難儀な事と常日頃感じています。
つらつらと書いてしまいましたが、大した事でもありませんので、気軽に眺めてくださると幸いです。
何れにしましても、その方針は変わらないというは明確な意思です。それは私の意思で「個人主義的」です。日本では「個人主義」と「利己主義」の判別が存在しないと中学生の時代に、かけもちでやっていた合唱部の顧問の「中嶋先生」という忘れもしない方に知らされた時に、はっと気づきました。
これが、文化の違いなのだ。と。それ以来50歳になる今に至っても、それは変わらずにいます。そしてその文化の違いの源泉は「島国で農村社会」を基盤としている地域と、「大陸で狩りを前提にしている社会」で、物事に反応する感度が違うという事でした。中高生時代からの友人などはこの辺りの考えの違いをきっかけにほぼすべて私のもとから去っていきましたが、それが「村社会」だと結論付けることが最早理解できているので、当然の事として過ごしてきたのも事実です。
視点を変えます。
この島国の歴史時間軸を少しばかり長めに見出すとき、「縄文時代」は相当に長期にわたり続いた時代でした。それはアフリカ大陸発祥の人類がいち早く地球の表面に進出しつくした最初の時代だろうと云われています。
日本人の遺伝子解析(ゲノム解析)の統計によると「縄文時代のタイプ(狩猟民族系)の遺伝子構成をもつ日本人は、10%に満たない」と云われています。残りはゆっくりと半島経由でやってきたひとびとである事はあまり考えずとも理解に苦しむこともないでしょう。
日本史の記述の中で最低三度は、半島に直接的に関与してきたのが教科書にも書いてあることですので、一般的な常識というべきかもしれません。
加羅、任那、百済、新羅、高句麗などの半島の混乱期に一時、直接的にその勢力と連合を結んだのは明らかですし、秀吉が半島出兵をしたのも誰しも知っている事です。さらに言えば現代史ではもっと露骨ですね。東アジア圏は「儒家文化圏」ですから、ほぼ骨肉の争いのようなものです。
それ以前に(弥生時代以前)スピード優先でいち早くこの島国が「島」になる前程度の時期に、縄文人はやってきましたが、大陸から島になった時点で、今のような状況に落ち着いたとみるべきだと云うのは、歴史を大学で学んだ人間にとっては、至極当然のことです。
後からやって来たものが、先住より時間をかけてやってくるので、武器や農耕についての道具としての素材も成熟した状態でやってくるのは、時系列でみれば当然の事でしょう。
ですから「縄文時代由来のDNAの日本人というのはゲノム解析では10%程度」というのも理解ができます。恐らく僕のような外に出たがるタイプは、その10%にあたりそうですが、調べるような無粋な事をしても意味がありません。
結論として、申し上げるべきことは西洋で云えば「アートの語源たるアルス」というものは、全方位の学問とフィールドワークだったと云われていますが、現代においては「テクノロジー」のみ「技術」と呼ばれて地域によってはもはや「信仰の対象」と云っていい程度の影響力をもたらしています。
その背景に拝金主義があり、現在の政府の実態もそれに倣って「テクノロジー」と「ポリティクス」の結合、または「資本・政治・官僚機構」のカルテル的な振る舞いによって社会構造を支配的に管理しています。また、その世論形成を担う中間業者たる広告代理店も競争原理が働くなり、抜け目なくその一員となっていると見えます。
そのような現代の前提を見つめた時に、如何にして「アート」(アルス的な発想)を、いびつな社会バランスから回復させ得るべきか?これがアーティストの仕事だろうと、認識を深めるばかりでもあるのです。
資本主義は合理的ではありますが、成長を前提としていますので(成長しようとしまいと方法論は同じ)、世界中の資本(すべての資源)を原資にして食い尽くしていまいます。その結果は想像に難くないものでしょう。そして、その代替案は未だに見つかっていないか、もしくは見つけようとしていないか?という状況です。
ですから、未来にひとびとは存在しないかもしれませんね。私は展示タイトルで「緑について」や「空き地について」などを発表した後、かなり視座が広がり、その結果、我々が所有していると勘違いしている資源と、地球表面上の生命体すべての資源配分のいびつさのバランスを回復するために、今もっている手段で、何ができるか?と、方針を転換せざるを得ないと確認したのが昨年末までの活動でした。
今年一年を目途に、何かしらの手がかりを見出せないか?と、フィールドワークを継続しているのが現状ですので、明確なプランニングが出来ているものではありません。ですから本来なら滅多な事でこのような内心の試案を提示する事はありませんが、今回はちょうど良い機会になりました。ですからインタビューを受けた際にも、一年は黙って考える。という趣意の事しか述べる事はしていません。
しばらくはそのプランが見えてくるまで予定の一年程度で済むかは分かりませんが、6割から7割の道筋が見えたら動き始めなければならないと考えています。例えば100%の事業計画を立てて新事業を起こしても、ほぼ必ず計画は変更せざるを得ない事はビジネスでは当たり前のことであるのと同じ事です。
それより大枠で、見えたものがあるなら走りださなければなりません。プランの変更は当然のようにやってくるのです。それはサラリーマンのキャリアプランと同じです。因習にしがみついているうちに、沈没するのが地球船というものです。
さて、今年も梅雨がさり気ない降雨の種類であれば撮影にもっともよい時期ですので、他の事案はさておき、モチーフたる東京23区の撮影を継続して参ります。ただ、ここまでに書き述べた中にある通り、今までの気候に今年恵まれるかなどとは、以前の状況から勘案してあまり期待はできません。その中でもやれる事はやり切っていきたいと再確認したところです。
くれぐれもご自愛くだいませ。喜多研一
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
