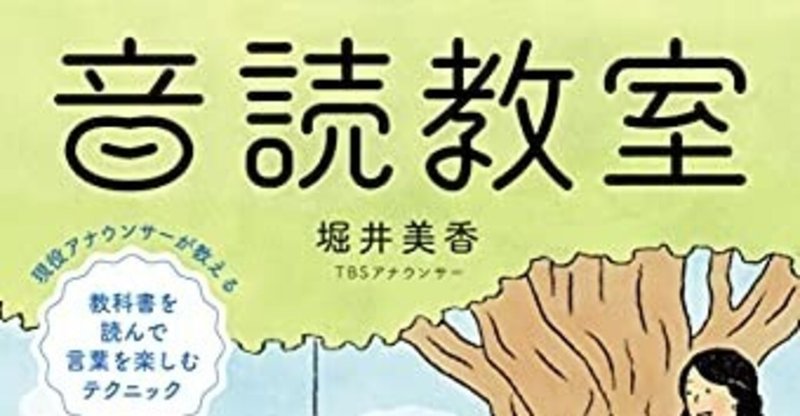
現役局アナによる音読解説本を読んでみた
ついに、ついに…!
前々から気になっていた書籍を読みました!!!
著者はTBSの堀井美香アナウンサー。
堀井アナといえば、noteで教科書に載っている作品の朗読解説を記事にしていました。
書籍ではこの2作品の他に、宮沢賢治「雨ニモマケズ」の音読解説が収録されています。
「雨ニモマケズ」といえば、朗読検定4級を取得した記念で調子に乗ってスタエフで生朗読した結果、「グズグズすぎてショックでした」とダメ出しをもらった作品。
その後、リベンジで収録したのですが「行ってその稲の束を負い」を「背負い」で読んでいたことが判明し、こちらも失敗した結果となりました…
(私が見た原稿では「背負い」表記だったんです…)
いずれの作品も全文収録しているので、再々リベンジをしたいところですね!
音読解説本とありますが、あくまで堀井アナが読んだらという話。
「堀井アナの解釈ではこういう読みをする」のであって、それが正解ではないことをお忘れなく!
というのも、作品の読み解きに答えはありませんから、万人共通の解釈は存在しないのです。
私がやっている「note朗読」でも口酸っぱく言っていることですが、文章を声に出すことは、その読み手によって言葉の雰囲気が激変します。
つまり、私がAの解釈をしても、違う人がBの解釈をしていたら、読み方が変わるのは当たり前。だから、解釈議論が生まれるのは必然なんです。
ダメ出しでは、「自分の物にしていない状態のまま朗読を披露するのは聴く方々に失礼すぎる」と言われました。
というのも、その方がいう朗読とは「暗誦できるようになるくらい読み込むもの」と教わったそうです。作品を読み込むことで、作風・雰囲気・情景描写等の表現を作り、表現するのを大切にしている方でした。
ですが私はというと…与えられた文章に対して、センテンスごとに強弱や抑揚を付けて雰囲気を作り、作品自体のテーマを自分なりの解釈で表現するといった感じでやっていました。
作品を黙読する作業はしていますが、どちらかというと下読みのほうに時間を費やしています。
早い話が、作品を読み込んでいなかったんです。
しかも「雨ニモマケズ」は、小学校の時に校内一丸となって暗誦させられた作品。ほぼ初見でもイケるだろうと思っていたのですが…慢心していました…
「作品を読み込む」ことについて。
何回も、何十回も、何百回も読みまくって、作品解釈の答えを導き出せるのかといわれれば…胸を張ってノーと言える自信があります。
あくまで私の考えではあるのですが、一回朗読した作品をまた同じように朗読することは絶対にできないからです。
過去に読んだ作品に再度触れると、そこからの人生経験によってまた違う解釈が生まれることもあります。
極論をいえば、ある作品に初めて触れた時は文中でやっていることを経験したことがないから想像で解釈するしかなかったけど、それなりの人生経験を経てから再読してみると、文中の出来事を実際に経験したから別の解釈になった…ということもあるわけです。
それを読みで表現するとなれば、読みの変化も現れます。なんだかぬか漬けみたいで面白いですよね。
これについては堀井アナも本著で言及していました。
「蜘蛛の糸」解説の〆の文章です。
「ラストの収め方は解釈によって何通りもあるでしょう。若い頃の自分なら、また違う読みをするはずです。
(中略)
きっと七〇歳になった自分はまた違う解釈をするのだろうと思います。同じ人間でも人生のときどきで読み方が違ってくる。それもまた音読の楽しさです。」
堀井美香著「音読教室 現役アナウンサーが教える教科書を読んで言葉を楽しむテクニック(株式会社カンゼン)」p124~125より引用
ダメ出し時、「この状態だと朗読検定2級は絶対に受からない」と言われました。
朗読検定2級には、初見原稿を読む課題があります。
初めて触れる作品に当たることがないように、如何に普段から古典文芸と接しているかどうかが問われているように思えます。
芥川龍之介、太宰治、宮沢賢治、江戸川乱歩etc…その時々で作品を「読め」と言われた場合、私はどのような表現をするのでしょうか。
「読み込む作業」というのは、朗読の基盤だからこそ非常に難しい、終わりのない旅なのかなと思いました。
だからこそ、しっかりと読み込む力を身に着けていきたいものです。
この本は「テクニック本」ではありますが専門書籍ではありませんので(違ってたらごめんなさい)、声に出して文章を読むことに興味を持っている方はぜひ読んでほしい一冊です!
虹倉家の家計を支えてくれる心優しい方を募集しています。 文章と朗読で最大限の恩返しをさせていただきます。
