
捨てる勇気のススメ | やるべき論より捨てる議論
こんにちは。noteを始めてからというもの、過去のことをよく振り返っている気がします。まぁネタを考える一環です。
以前の記事でも触れましたが、noteって自分の考え方や経験の棚卸しに良いのかもしれませんね。内省という観点で、大義での“マインドフルネス”に含まれないんでしょうか。

はじめに
もう20年くらい前の記憶なんですが、高校の現代社会Bという授業で、『風土』(和辻哲郎)という著書について学びました。
《Wikipediaより引用》
風土をモンスーン(日本も含む)、砂漠、牧場に分け、それぞれの風土と文化、思想の関連を追究した。『風土』の中に見られる「風土が人間に影響する」という思想
私達の文化や思想に、その土地の気候や環境が影響を与えるという考え方です。我々の考え方のクセも大いに影響を受けているということになります。
中でも、文化の違いによって『取捨選択に対する考え方に違いがある』という点が結構印象に残っています。

増やすコトより捨てるコトの方が難しい
仕事において『〇〇をやるべき』はよく議論されがちだと思います。
一方で『〇〇はやるな』『やらなくていい』という捨てるコトまで言及できる人は意外に少ない印象です。今でこそ働き方改革で勤務時間の有限性(笑)が意識され始めましたが。
『やるべき』と『やらないべき』はセットになって初めて上手く機能する気がします。我々は少し『やるべき』論に偏りがちなのかもしれません。
そこでこのnoteでは、これまでワタシが何かを捨てる際に自らに問う『自問自答三選』を紹介したいと思います。
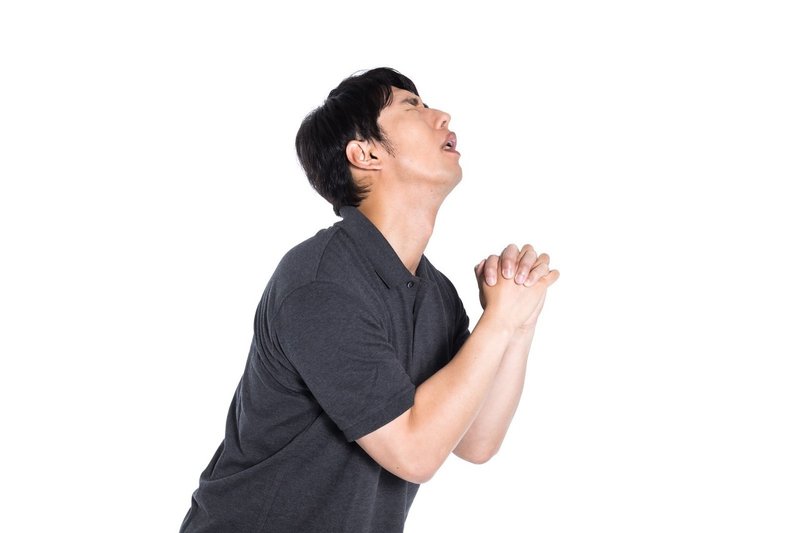
100点を目指さない
『その努力は自らを苦しめていませんか?』
私の中学は田舎の公立校でした。当時の成績は、入学当初で中の上くらいでしょうか。
鳴かず飛ばずの成績に業を煮やした母に対して、ワタシはこう諭してたらしいです。(覚えてません。笑)
・僕の頭は洗濯用洗剤と同じ
・大量に使ってもその分汚れが落ちるわけではない
・洗剤も勉強も適量が大事
我ながら気の利いた事言ってたなぁと感心した一方で、こいつ生意気だなと感じました。笑
当時のワタシを擁護するつもりはありませんが、常に100点を目指すのって場合によっては非効率な気がしてます。常に全力投球だと高校球児も肩を壊すんじゃないでしょうか。
中には天性の素質に恵まれた逸材もいますが、ごく稀です。我々凡人にとって、努力の方向性とバランスの視点が大事だなとつくづく思ってます。ただ、それが人生となると…上手くやれているんでしょうか。
《まとめ》
その努力はアナタを苦しめていませんか?

怒られる事を許容する
『その選択の責任を取るのは誰ですか?』
小学生から続けていたこともあり、高校では空手部に入部しました。私は趣味程度に続けたかったんですが、そうは問屋が下しませんでした。
特に節目の試験(中間試験、期末試験)は土日を勉強時間に充てる必要があるんですが、これが部活の大会や試合とよく重なりました。
当然、ワタシはいかなる時も試験勉強を優先(要は試合を欠席)してました。笑 その結果、指導熱心な先生や熱血漢の先輩から怒られるのが常でした。
当時のワタシにとって、スポーツに捧げる若き青春のために、1年間(以上)浪人するという運命は受け入れられないものでした。大学入学後にやればいいですし。
ただ、この健全な“青春“を放棄するという選択が、本当に正しかったのか、誰にもわかりません。
《まとめ》
アナタの選択の責任を取るのは誰ですか?

皆がきちんとやっている事は、基本やらない
『自分が参加して、結果は変わりますか?』
大学4年から研究室に所属しました。そこでは研究活動を円滑に進めるため、実験器具の洗浄や滅菌処理などの地味な作業を当番制でこなさなければなりません。要は掃除当番です。
私は、この当番をあまり熱心にやらずに先輩から物凄く怒られた記憶があります。笑
この場合、先程の部活の例とは異なり(笑)、先輩が正論です。当然、心を入れ替えて最終的には掃除当番を真面目にこなすようになりました。笑
もういい大人なのでさすがに掃除当番をサボる事はありません。しかし、皆がやっている事に自分がさらに加わる行為については、未だに抵抗感があります。
私無しでその場が機能するのであれば、私は参加せずに他の事をしたい衝動にいつも駆られてます。
《まとめ》
アナタが加わるコトで結果は変わりますか?

さいごに
『三つ子の魂百まで』と言いますが、昔の考え方は今でも変わっていないようですね。
ここで紹介した三選は、私の個人的な自戒の念として捉えてください。
『捨てる』視点は、ケースによっては弊害や軋轢を生みます。ご自身の心に従った選択をするための、あくまで参考にしていただければ幸いです。それではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
