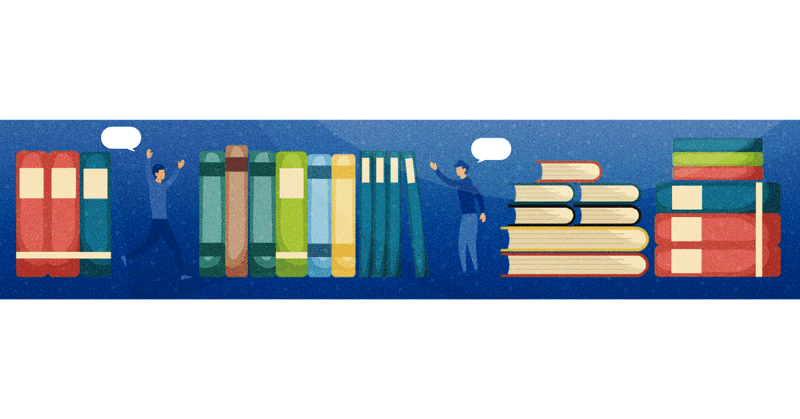
中小企業診断士 勉強法 序章 受験遍歴
皆さまこんにちはこんばんは。キノPです。
本日、2回目の投稿となります。初回の投稿から約2週間で27名の方に「スキ」をいただきました。誠にありがとうございます。
顔も名前も知らない誰かに、少しでも興味をもってもらえたことに、非常に感激しております。
拙い文章ではありますが、今後も見てくださる方に少しでもプラスになるような内容をお届けしたいと思います。
はじめに
さて、今回からは、具体的に中小企業診断士の勉強法を投稿していきたいと思います。
私の診断士受験は、市販の参考書による独学で受験仲間も一切作らず、セミナーやその他コミュニティにも一切属さず、ただひたすら一人で黙々と取り組むスタイルでした。資格学校や通信教育のような何年ものデータの積み重ねや独自の合格メソッドを持ち合わせているわけではありませんが、独学なりに色々な試行錯誤を重ね、あらゆる媒体を活用し、最終的に合格を勝ち取りました。私の実体験を共有することで、今後、診断士試験の受験を考えている人や、現在の勉強がしっくりこない方の参考になればと思います。
前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。
本日のタイトルは「序章 受験遍歴」としております。初投稿の自己紹介でも受験遍歴については触れておりますが、今回はより詳細な受験遍歴を記載していきたいと思います。そして、この受験遍歴を基に、それぞれのテーマで私の実体験や勉強法を複数回に分け投稿していきます。今回の受験遍歴がいわゆる「目次」になると思ってください。
あくまで私の主観によるものですが、ぶっちゃけた内容も一部書いていこうと思います。
受験遍歴 詳細版
独学スタイルと言いつつ、受験1年目には通信教育を活用しました。通信教育の良し悪しは次回以降に書こうかと思いますが、通信教育が合わなかったため、2年目以降は独学スタイルに切り替えました。また、受験当初から2年計画(1年目の1次で経済・法務・情報・中小を科目合格、2年目に企業経営・財務会計・運営管理に合格、2次を2年目に一発合格)の目標としておりました。
2年目計画としたのは、家庭と仕事、資格の勉強との両立に重きを置いたことです。とはいえ、結果として、妻にはかなり苦労させましたし、合格できたのも全て妻の理解があっての事でした。3年間も私のわがままに付き合ってくれて本当に感謝しかありません。
話を戻します。私の受験遍歴の詳細については下記の表にまとめてみました。実際の点数や、テキスト等にかかった費用等、記載してみました。

見ていただいてわかるとおり1次2次ともに平凡な点数です。(法務の80点と事例Ⅱの69点はそこそこ立派?)平凡すぎて、皆さんに偉そうにことは言えないかもしれませんが、少しでも何かの気づきやヒントになれば幸いです。
勉強時間はちょっとやりすぎ感がありますね(笑)特に2次試験は2か月ほどの期間でかなりやりこんでます。費用に関しては、完全に通信教育が足を引っ張ってます。通信教育での失敗があってこその、独学スタイルですので、これも勉強代だということでしょう。なお、通信教育を否定するつもりは全くなく、通信教育で合格されている方も多数いらっしゃるでしょうし、むしろ通信教育で合格できなかった自分に落ち度があるのも承知しています。ただ、自分には合わなかったということです。
1年目
ここからは、受験遍歴をさらにかみ砕いていきます。正直ここからは、私の日記的な要素もあるので、飛ばしていただいてもかまいません。
受験1年目は先にも述べた通信教育を活用し、勉強に励みました。スマホを使って学習することができましたので、通勤時間と帰宅後の1時間程度毎日勉強していました。科目合格を狙うということで4科目を受験予定でしたが、結果3科目を受験し、科目合格できたのは経済学のみ。受験当日は帰宅して、自己採点して、1~2問足りないことがわかり、かなり落胆しました。
受験科目数を4から3に変更したのは、受験日の前々日に第一子が産まれ、コロナ禍ということもあって、妻が長く入院できず、受験日当日の中小の時間には病院に迎えに行かなければならないという状況だったので、やむなく受験を断念しました。しかし、今思えば「中小くらいなら来年受ければいいや!とりあえず3科目受かってしまおう!」という妻の退院を言い訳にした軽い気持ちでの判断でした。
1年目の敗因は明らかに勉強のやりこみ具合の不足です。前年に宅建士に合格していた私は、「過去問を3、4年×3回程度こなしておけば、1次の選択式は大丈夫だろう!」と高を括っていました。
それなりに真面目に勉強したにもかかわらず、1科目しか合格できなかったという屈辱を味わいました。
2年目
1年目の苦い経験を受け、正直診断士をあきらめようかと思ったこともありました。しかし、意地もあってか、結局あきらめずにチャレンジすることにしました。2年目は気持ちを新たに、1年目で合格できなかった3科目(法務、情報、中小)の科目合格を狙いました。
通信教育の延長はせず、この年から、市販の参考書のみで勉強を開始します。
結果3科目に科目合格し、ある程度、自分の中で診断士試験の勉強法が確立できました。
どの資格にも共通するのでしょうが、これまでわかっているようでわかっていなかった、全体像を把握し、過去問を徹底的にやりこむことが重要だとようやく気付けた年でした。そしてこの年にはファイナルペーパーを作ることも試みました。
3年目
2年目で確立できた自分なりの勉強法で残りの3科目(企業経営、財務会計、運営管理)の合格、そして2次試験の一発合格を狙います。
1次試験は2年目に引き続きの勉強法でしたが、試験の2~3か月前に別の参考書に出会い、さらに効率的に勉強ができるようになりました。
2次試験も独学で臨んだわけですが、ここでYOUTUBEや受験生支援ブログに出会います。この2つには本当に感謝です。YOUTUBEは野網先生の動画を参考にしてましたし、いくつかある受験生支援ブログも皆さん素晴らしい記事を掲載されています。
診断士の2次試験は情報戦的な要素もあると思っています。いかに上記のような無料のコンテンツを使いながら理解を深め、勉強法やヒントを得て、過去問を通じて実践していくかがカギを握ります。私のこのブログもそのような使い方をしていただけることを目指して書いていきたいと思います。
おわりに
今回の投稿では、私のより詳細な受験遍歴をお送りしました。
先に述べたとおり、今回の受験遍歴は私のブログの目次的な要素になると思っていただければと思います。1年目の通信教育の良し悪しから、2年目の独学勉強法、3年目の2次試験まで、次回以降で複数回に分けてお送りします。特に2次試験はかなり費用も抑えた形で合格できてますし、私としては力を入れて書きたいと思っているパートです。
今回の投稿が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
それではまた
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
