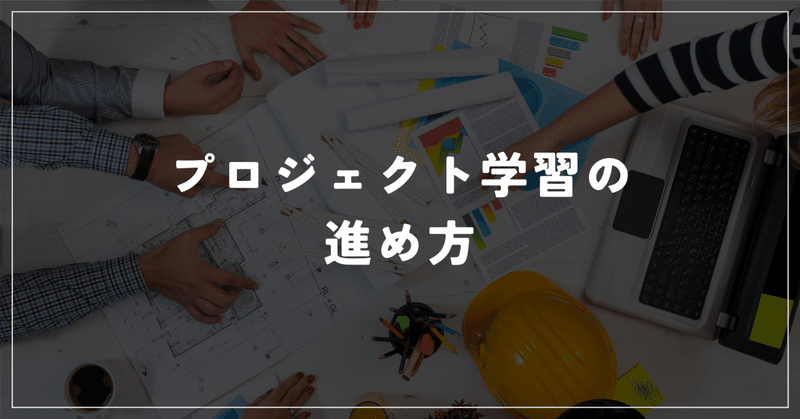
プロジェクト学習の進め方
※プロジェクト学習すなわちProject based learning(PBL)より、広義な意味でプロジェクトというものを捉えています。(キルパトリックの「プロジェクト・メソッド」に近い)
ここ数年実践している、プロジェクトの進め方についてまとめています。
・授業準備の負担を減らしたい
・子ども達が楽しく学べるようにしたい
・ICT活用が苦手
どれか1つでも当てはまった方に読んでいただけたら嬉しいです。
毎時間、本気で授業を考えていた。
初任〜2年目辺りの頃の私です。
この時期があったからこそ今があるのは間違いないのですが、やはり大変でした。修行といっても良かったです。
明日の授業を考える際に、板書計画、指示、発問、予想される子供の発言…全てを自分のノートに書き込んでからでないと、気持ちよく明日を迎えられませんでした。それがうまくいく場合もあれば、もちろんうまくいかないこともあります。そうやって自分の授業を改善していくこと自体には充実感もありましたが、授業の「ぶつ切り感」も感じていました。
コロナ禍→GIGA端末の配布
コロナ禍で私が目の当たりにしたのは、「自ら学ぶ力」がついている子とそうでない子の学力差がどんどん開いていくという現実でした。
学校に「先生から勉強を教えてもらいに来ていた子」は、学校に来れなくなった瞬間に何をすれば良いのか分からなくなったのです。
「自分の学びを自分で調整する力」を学校でつけていく必要があると、心から感じた時期でした。
そして、幸か不幸か、1人1台端末の時代が到来しました。
「この端末の活用がカギになる」と確信しました。活用方法について考えを巡らせている時に出会ったのが、PBL(Project Based Learning)でした。
GIGA端末は毎時間の授業で指示を与えて使わせるものではなく、子ども達自身が使い所を判断していつでも使える状態にあるということが重要だと感じていたため、PBLとの相性は抜群だと当時考えたのです。
教員が端末を使って授業をするのではありません。子どもが端末を使って学習をするのです。
なぜ、プロジェクトなのか。
私が行っているプロジェクトでは、後述する7項目を「骨組み」として、子ども達自身があらゆる選択を行いながらゴールに向かって突き進みます。
1つのプロジェクトの中で、子ども達は進んだり、戻ったり、真似したり、質問したり、読んだり、書いたり…自分にとって必要だと思うことを選び取って自分の学習を進めていきます。教員の仕事として大切になるのは、「7項目」の吟味と、授業中のファシリテーターとしての振る舞いです。
「なぜ、プロジェクトなのか。」と問われれば、「子ども達自身が、自分の学びを自分で調節する機会が豊富だから。」と答えます。ゴールは決まったものであっても、そこに到達するための道のりはどんなものを選択しても良いわけです。教科書で学んでもよし、動画で学んでもよし。手書きで成果物を作成してもよし、パソコンで成果物を作成してもよし。子ども達一人一人それぞれに学び方があり、それぞれに伸び方があるということを認めて力を伸ばしていけるのがプロジェクト学習の魅力です。
また、教員の負担も減ります。
プロジェクトは基本的に「単元ベース」で授業を考えていきます。毎時間毎時間板書計画を考えるような授業づくりとは考え方が少々異なるわけです。(1時間単位の授業を否定する意図は全くありません。私も行っています。焦点化して述べているだけです。)
プロジェクト学習では、「子どもが成果物を完成させる」「子どもがアウトプットを準備する」という活動がメインになるため、あるタイミングで子ども達が自走し始めます。勝手に学び始めるわけです。軌道に乗ってしまえば、毎時間の授業を時間をかけて考える必要性は薄れてくるわけです。放任ではありません。この辺りの表現は難しいのですが、時間や心の余裕は確実に増えます。
プロジェクトの準備(7項目)
アメリカ、サンディエゴのハイ・テック・ハイ(High Tech High)という公立校があります。プロジェクト型学習を教育の中心に据えている学校で、先進的な実践を行っている学校です。ハイ・テック・ハイにおけるプロジェクト学習導入時のディスカッションを参考に「プロジェクトシート」を作成して単元デザインをしています。

プロジェクトシートに書かれてある7項目が1プロジェクトの「骨組み」になりますので、この部分の確定には時間をかけます。
「ゴール」を決める(目的意識)
「対象者」を決める(相手意識)
「成果物/場所」を決める(当事者意識)
「オプション/材料」を決める
プロジェクトを貫く「問い」を決める
必要な知識(学習内容)を洗い出す
評価方法/評価基準を決める
この7項目が「骨組み」だとすれば、子ども達はプロジェクトの中でこの骨組みに「肉付け」をしていくイメージです。
以前、3年理科「つくってあそぼう」の単元にて、「理科おもちゃプロジェクト」というプロジェクトを行いました。
このプロジェクトでの7項目は以下の通りになります。
「ゴール」…………………おもちゃイベントを成功させる
「対象者」…………………下のフロアの2年生全員
「成果物/場所」………おもちゃ・パンフレット(Canva)/体育館
「オプション/材料」………膨大なので省略
「問い」……………………「どうすれば2年生に『来年の理科の学習が楽しみだ』と思ってもらえるだろうか?」
必要な知識…………………これまでに学習した理科の知識
評価方法/評価基準……おもちゃの設計図・パンフレット(基準は後述)
結論から言いますと、とんでもなく盛り上がりました。
「このおもちゃを作って2年生を喜ばせるんだ!」という目的意識が子供達の中でしっかりと共有できていたことが要因の一つとして確実にあります。
「もっと面白くするにはどうすればいいだろう?」「理科で学んだあれを使えばうまくいくかも!」と、これまでの学びをフル活用しておもちゃ作りに取り組んでいる姿が印象的でした。




プロジェクトの可能性
プロジェクトの進め方について、簡単ではありますがまとめてみました。プロジェクトには、これからを生きる子ども達にとって必要な力を育む要素がたくさん詰まっていると感じています。GIGA端末との相性が良いという点も大きいです。
他校とのコラボレーションや、地域に働きかけるような企画など、工夫次第でより大きなプロジェクトに発展させることも可能です。もちろん、教科書をメインに社会の1単元でまずやってみよう!という小さな企画も可能です。
今後も実践を積み重ねてまとめていこうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
