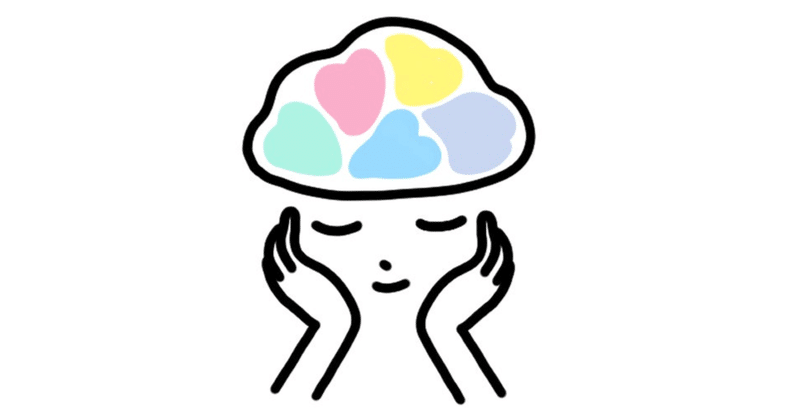
言語学の学習理論について
言語学の学習理論は主に4つあると言われています。
・行動主義 (Behaviorism)
・生得主義 (Nativism)
・認知主義 (Kognitivism)
・インタラクション主義 (Interaktionism)
以上の4つの学習理論について今日はまとめていきます。
行動主義 (Behaviorism)
行動主義とは、人間の行動は、一定の刺激を加えることで行われていると考えられている理論です。
パブロフの条件反射などがこの理論にあてはまります。
刺激が脳に伝わり、脳が行動を呼び起こすというプロセスです。
この理論は後に出てくる認知主義とは異なり、脳がどう機能して行動が呼び起こされるのか?という点については興味はなく、一定の刺激が脳へ伝わり、その刺激に関連する行動が起きるというとてもシンプルな理論なのです。
喉が渇いている→水を飲む
いい匂いがする→お腹が空く
などといったものも例としてあげられるでしょう。
この理論を言語習得に当てはめると、
我々は真似をすることで言語を習得する。
という考え方になります。
母親が“ママ”と言う
↓
赤ん坊が“ママ”と真似をする
母親が自分を指さしママと言う
(一定の刺激を与える)
↓
脳が情報を処理
↓
母親を見た子供はママと言う
(刺激が行動につながる)
しかしこのセオリーはとてもシンプルすぎて言語習得には実際当てはまらいことが多いのではないか?(言語習得はより複雑なプロセスを説明する必要がある)ともいわれています。
生得主義 (Nativism)
ノーム・チョムスキーによって提唱された理論です。
行動主義とは反対の立場を取り、人間は真似をして言語を習得しているのではなく、そもそも子供は生まれながらにして言語能力を備えている為(特に文法の能力)、言語を学習する必要が無い。という考え方をしています。
子供が生まれながらにして言語能力を備えているとは、要は文法の型が脳内に埋め込まれており、ある言語との接触(保護者などとの関りで聞こえてくる言語)がその脳の機能をONにし、言語が自然に習得されていくという意味です。
また、言語能力は他の脳の認知発達とは全く関係ないもので、独自の、単一システムとして発達していくものだという考え方をしています。
しかし、言語の機能がONになるのは一体脳の何の部分なのか?という証拠が無く、この理論も言語習得にはあまり当てはまらないのではないかともいわれています。
認知主義 (Kognitivism)
認知主義は、人間は既存の知識と新しい知識との関連を紐づけていくことで知識を習得していくという考えです。
刺激を脳が受け取り、脳が行動を呼び起こす。というシステムになっていると提唱しています。刺激を受け、行動が呼び起こされるという考え方であれば、行動主義と一緒でないか?と思うかもしれませんが、異なる点があるのです。
それは、認知主義は脳の機能に着目しているという点です。
刺激を受ける
↓
脳がその刺激を保存、もしくは情報を処理
↓
行動を起こす
というように行動主義では少し曖昧だった、人間は刺激を受け行動をするが、脳はどう働いているのか?ということに重きを置いているのです。
これを言語習得に当てはめると、
四つ足のふわふわしたものを見る
(刺激)
↓
以前その動物を“犬”と呼んだので犬だと感じる
(既存知識と新しい知識との関連付け)
↓
犬と呼ぶ
(行動)
というように、既存の知識を新しい情報と結び付けて単語を学んでいくのです。
しかし、子供は何を見ても一定の単語しか言わないときがあります。例えば、人を見ても車と言い、車を見て車と言い、猫を見て車と言うなど。この状況は over generalisation と呼ばれ、すべての子供に見られる現象です。
新しい情報を刺激として受け入れる際に既存知識と関連付けるのですが、新しい情報は既存知識と全く異なる物なのか?(車ではなくゾウさんなのか)似ているけれども異なる物なのか?(車ではなくトラックなのか)という情報を脳内にどんどんカテゴリ分けしていくわけです。
その際に間違い(動いているモノは全て車だと認識し動いているモノをすべて車と呼ぶ)を繰り返し、関りのある人達からその間違いを訂正され(車じゃないよ、あれは猫だよ。と言われるなど)車とトラックは異なるものだと考えらえるようになったりしていくわけです。
そうやって、この世界で自分が見ているモノには一つ一つ名前があるのだと認識し、単語を一つずつ習得していくのです。
この過程には、物の永続性(Object Permenence)やシンボルの理解(Symbol Verständnis )も関連します。(自分が見ている物体は、自分には見えていないときにも存在し、また絵本などで見るものが実世界にもモノとして存在することを認識する能力)
従ってこの理論は、Nativismとは異なり、言語発達は脳の他の機能と共に発達していく。という見方をしているのです。
インタラクション主義 (Interactionism)
この理論は言葉の通り、赤ん坊は大人とのインタラクションを通して学んでいくという理論です。
言語習得に当てはめると、保護者や普段から関りのある人と、まだ言葉が話せない時期でもインタラクションすることで、コミュニケーション能力や必要な言語構造を学んでいくという見方になります。
認知主義や生得主義とは異なり、子供が置かれている環境が言語習得に多いに影響を与えるという考えをしています。
以上、4つの学習理論を言語習得と当てはめて説明をしてみました。学習の参考になれば幸いです。
