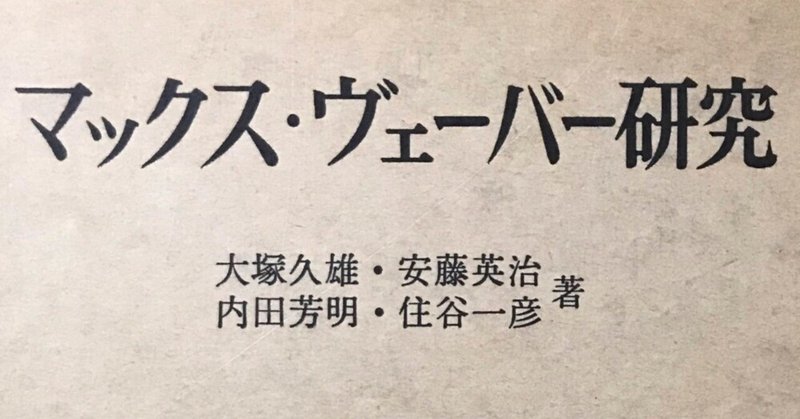
大塚久雄「マックス・ヴェーバーにおける資本主義の「精神」」『マックス・ヴェーバー研究』第二章脚注(7)について――あるいは、ヴェーバーにおけるカルヴァンとカルヴィニズムについて
最近、古本屋さんを巡ることを趣味にしている。そこで、思いがけない本との出会いがあった。大塚久雄, 安藤英二ら『マックス・ヴェーバー研究』(岩波書店, 昭和47年)である。

知らない人にはちんぷんかんぷんだろうけれど、大塚久雄(敬称略、以下同様)と安藤英二、内田芳明に住谷一彦という錚々たるメンバーの論文集だ。まだ全然読めていないけれど、僕の知的好奇心はグングン高まっている。
さて、そのうちの一稿。大塚による「マックス・ヴェーバーにおける資本主義の「精神」」という論考に、気になる記述を見かけた。詳細に言えば、この論考の脚注(7)である。ちょっと引用してみよう。
ヴェーバーは、カルヴァン自身の見解とカルヴィニズムとをはっきり区別しているばかりでなく、こうした区別は彼の宗教社会学においてきわめて重要な看点とされている。たとえば、Max Weber, Die protestantische Ethik und der 》Geist《 des Kapitalismus, Gesammette Aufsätze zur Religionssoziologie, Ⅰ, S. 89 Anmerk. 1. 梶山・大塚共訳、ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫、上、一九頁註三を参照。
太字は僕
僕が太字で強調した部分に注目してほしい。ここで大塚は、ヴェーバーにおいて、カルヴァンの思想とその信仰者の思想とが峻別されていたと主張している。
この見解は学会では共通認識なのかもしれないが、あいにく僕はよくわからない。僕の卒論はヴェーバーがテーマだったのだけれど、この点について詳しく述べている書籍や論文は(官見の限りでは)見つけられなかった(もちろん、この点を指摘している論考はあったと記憶しているが)。
(ついでに言えば、厳密にはヴェーバーはテーマじゃなかった)
しかし、このカルヴァンとその追従者たちの思想的差異というか、見解の相違は、大塚の言う通り結構重要なのである。というか、ここに差があるということを知っていないと、論理的に読解できない文章が山のようにあるのだ。
(もっとも、僕が認識しているその「差」は、大塚自身が言及している差と同じかどうかは分からない。この記事はむしろ、この点を問題にしている。つまり、ここで大塚が、ヴェーバーにおけるカルヴァンとカルヴィニズムとの間に、どのような「区別」を設けているかが分からなくて困っているのだ)
例えば、次の文章を見てほしい。矢嶋喬四郎編『近代思想の展開』(勁草書房, 1983年)からの引用である。
これにたいして人間は、この自分について神がどのような選びの決定をくだしているのかを、まったく測り知ることはできない。神の予定についてのカルヴァンの立場は完全な不可知論である。
太字は僕
太字部分を頭に入れた後、続いて次の引用文を見てみよう。
すでに述べたように、カルヴァン自身は救いの確かさについて、徹底した不可知論の立場に立っていた。これにたいしてピューリタンたちは、何としてでも救いの確証を得たい、自己確信の客観的なあかしを得たい、と願ったのであった。そして彼らは、この自己確信の確証は、実は、絶えまない職業労働において得られるとしたのであった。
太字は僕
以上、二つの引用部分において、僕が太字で強調した部分を見比べてみる。すると、これらを論理的に理解することが、どうやら難しそうだということが分かるだろう。
カルヴァンは救いについて不可知だとする。つまり、自分が救いに予定されているのか、いないのか。人間には知る由もないというわけだ。一方その追従者であるピューリタンたちは、救いの確信を得られるとする。自分が救いに予定されていると確信することができる、というわけだ。
このアポリアは、いったいどのように理解されるべきだろうか。
無理やり論理的に解釈しようとすれば、「知る」ことと「確信する」ことを峻別する方法が考えられるだろう。つまり、「知る」ことはできないが、「確信する」ことはできるというわけだ。この思想こそ、カルヴァンの見解でありピューリタンたちの信仰なのだと。主観においては、いくらでも「確信する」ことはできるのだから。矛盾はない――だろうか。
しかしそれだと、「客観的なあかし」という表現の意味が取れない。ピューリタンたちは「自己確信の客観的なあかし」を求めていたらしいのだ。彼らは、ただ主観的に「確信する」だけで「客観的なあかし」を得られたのだろうか。うーん、この読解には、やっぱり無理があるような気がする。自分は志望校に受かっていると「確信する」ことができても、それを「客観的なあかし」とは普通思わないだろう。
であるならばやはり、ヴェーバーにおいて、カルヴァンとピューリタンたちとの間には見解の不一致があったとする方が自然であると思う。つまり、カルヴァン自身の見解とカルヴィニズムは、異なる思想的体系を成していたと考えるわけだ。カルヴィニズムは普通はカルヴァンの思想そのものを指す言葉だと思うけれど、その常識はいったん横に置いておく必要があるかもしれない。
というところまで来て、僕らは本稿の最初に戻ってくる。ヴェーバーにおいてカルヴァンとカルヴィニズムとは、いかに異なるのか。そしてそれは、どのような意味を持つのか。もう一度、冒頭の大塚の脚注を引用しよう。
ヴェーバーは、カルヴァン自身の見解とカルヴィニズムとをはっきり区別しているばかりでなく、こうした区別は彼の宗教社会学においてきわめて重要な看点とされている。たとえば、Max Weber, Die protestantische Ethik und der 》Geist《 des Kapitalismus, Gesammette Aufsätze zur Religionssoziologie, Ⅰ, S. 89 Anmerk. 1. 梶山・大塚共訳、ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫、上、一九頁註三を参照。
太字は僕
どうやら、梶山・大塚共訳の『プロ倫』を見れば、参照すべき文献なり論考なりが分かるらしい。さて、見てみよう。上巻の19頁の註三だ。確かに、18から19頁にわたって、註三があった。そこには、次のように書いてある。
私の門下の一人オッフェンバッハ―が、この點について、現在もっとも詳細な統計資料であるバーデンの信仰統計にもとづいて詳細な研究をおこなっている。すなわち、$${\textit{Martin Offenbacher}}$$, Konfession und soziale Schichtung. Eine Studie über die wirtschaftliche Lage der Katholiken und Protesanten in Baden, Tübingen und Leipzig, 1901. (Bd. Ⅳ, Heft 5 der volkswirtschaftlichen Abbandlungen der badische Hochschule.)がそれである。以下の敍述󠄁で引き合いに出す事實と數字とはすべてこの論文によるものである。
(岩波書店, 昭和45年),18-19頁
オッフェンバッハ―の論文らしい。ドイツ語だ、自信ないな、時間もないな、と困ってしまう。しかしそれ以上に困ってしまうことがある。果たしてオッフェンバッハ―の論文に、ヴェーバーがカルヴァンとカルヴィニズムとの間の見解の不一致を指摘している箇所を見つけられるのだろうか。疑問が氷解する展望が持てないのだ。
そこで、ちょっと不思議に思うのである。
本当に大塚先生が脚注で示したかったのは、この註なのだろうか。
0.0000001%くらいの可能性で、本当は別の註を示したかった可能性はないのだろうか。(などと僕は、知的に全く怠慢に言っている。自分の勉強不足を人のせいにしていると批判されても文句は言えない)
そのために、僕は本稿を書いている。具体的に言おう。
どなたか、町に一人はいたという噂の「ヴェーバーを読めおじさん」がふらっと寄ってきて、助けてくださらないかなと思っているのである。
本当に大塚先生が指したかったのはこの註なのか。それとも、本当は別の註なのか。彼が述べているカルヴァンとカルヴィニズムとの相違は、救いの確信についての相違だと考えて良いのだろうか。
(だから別に、誰かを批判する意図があるわけではないし、何かを主張する意図があるわけではない)
もちろん、僕がどこかで間違えている可能性は(大いに、大いに)ある。参照するべき書籍を間違えていたり、参照するべき部分を間違えているかもしれない。ひょっとしたら、とても基礎的で、全く不真面目で、ほとんど教養のない間違え方をしているかもしれない。
(というか、たぶん僕が間違っているから、どなかた指摘して頂けないかなとすら思っている。遠慮なくガンガン指摘、批判をしてほしい)
あるいは、オッフェンバッハ―の論文にカルヴァンとカルヴィニズムとを峻別する根拠が書かれていて、勉強不足の僕がただそれを読んでいない(読めない)だけかもしれない。
繰り返し言うけれど、別に僕は「大塚久雄は註を間違えている」なんて言うつもりは全くない。ただ、自分の理解が正しいのか間違っているのか、どなたかのご意見をお伺いしたいと思っているのみである。その点、どうか誤解のないようにしていただけるとありがたい。
そのうえで、良ければ助けてほしい。改めて疑問を整理しておく。
疑問①:ヴェーバーにおけるカルヴァンとカルヴィニズムの相違というのは、何のことだろう。救いの確信を得られるとするか得られないとするか、という相違だと考えて良いのだろうか。
疑問②:そしてそれは、オッフェンバッハ―の論文に書いてあるのだろうか。
