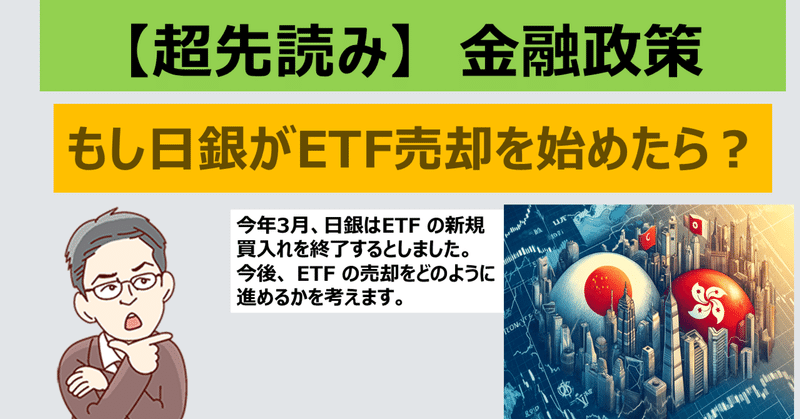
もし日銀がETF売却を始めたら?
歴史は繰り返さないが、韻を踏む。
これは「トム・ソーヤーの冒険」で知られる米作家マーク・トウェインの言葉と言われている。
先日、伝説のファンドマネージャー坪田さんとの会話の中で「日銀がETFの売却を行ったら」、という話があった。
まだ、少し早いかもしれないが、過去の事例からどんな手順が踏まれ、市場にどの様なインパクトがあったのか、勉強しておきたい。
ちなみに、私はこういう事を始めるのが、やや早すぎる傾向にある。
マイナス金利に関しては、大学時代のゼミの教授に教えていただいて、1996年に、調べ始めた。
1972年にスイス中央銀行がマイナス金利を導入事例などだ。
日本では安倍首相が2012年ごろからマイナス金利を検討すべきと発言しだし、実際に採用されたのは2016年だった。
なんと、私が調べていた時から20年も後だ。。。。
早すぎるリサーチは、その時は投資の役には立たないが、頭の片隅に置いて置き、いつでも引き出せるようにしておきたい。
そのような蓄積がある事で、変化が起こった時に迅速な対応が出来るからだ。
それに、日銀のETF売却開始が20年後という事はないだろう。
公的部門によるETF売却には香港の事例がある
政府や中央銀行などの公的部門が大量の ETF を売却した事例は、すでに香港にある。
香港では、1998 年8月、香港金融管理局(以下、HKMA)が株式市場と株式先物市場で大規模な市場介入を実施した。
ただこれは、当初から香港ドルへの大規模な投機的攻撃に対する一時的な措置とされ、金融市場の動揺が徐々に収束すると、すぐに、保有株式の早期削減に向けた議論や計画の策定が進められた。
香港の株式市場介入と日本銀行のEFT買入の比較
HKMAの株式市場介入と日銀の ETF 買入政策では規模感も異なるので、少し両者を比較しておきたい。
香港ハンセン指数はそもそも33銘柄しかったが、その介入規模は1180億香港ドル、買入期間は10営業日だけである。ただ、この額は香港証券取引所の時価総額の5.9%、1997年の名目GDP対比では8.6%にあたる。当時香港にはETFはないので全て個別株で購入している。
つまり、短期間で経済規模を考えると極めて大きな金額を買入れたことが分かる。
一方日銀は2010年12月から買入を開始、新規の買入を終了するとしたのは2024年3月であるから実に13年以上に亘って、この政策を続けた。
買入額は推計で2024年2月末時点では約72兆円、東証の時価総額比では7.4%、2023年の名目GDP対比では12.2%となっている。
買入の額も時価総額に対する比率も日銀の方が大きいが、時間をかけている分、短期的にマーケットに与えたインパクトは香港の方が大きかったと言える。
香港における出口戦略
出口戦略にあたり香港当局はまず、第三者機関であるEFILを設立している。
これは、香港はETFの買入ではなく、個別株を買入れていたので、市場参加者や海外の金融当局から、株式市場介入及び上場企業への公的関与に対する非難が相次いだことがある。
香港政府は、第三者機関を設立することを通じて一定の中立性や透明性を確保するとともに、早期の売却意向を明確に示した。
透明性を示すため、1998 年 10 月、EFIL はHKMAが購入した全 33 銘柄の保有株式数と保有比率、平均購入単価の情報を開示。さらに、保有株式の議決権の代理行使に関するガイドラインを公表し、経営関与等に対する懸念の払しょくに努めている。
1999 年6月、EFIL は ETF の組成を通じて保有株式を売却するという方針を決定した。これは、EFIL が設立されてから約8ヵ月後のことであり、ETF の組成という当時としては前例のない株式売却スキームであったことからも、検討作業は極めて迅速に進められた。
ETFは2つのスキームで売却された
1つ目はIPO、当初は100億香港ドルを売り出す予定であったが、投資家からの人気があったことから333億香港ドルに引き上げられた。
このIPOに申し込んだのは18万人、18歳以上人口の3.6%に相当する。これは日本の人口に換算すると約370万人だ。初めて投資を行う個人投資家もかなりの数に上ったと言われており、この IPO は、家計の貯蓄から投資への行動を促すことにつながったとされている。
申込者数が増えた要因としては、①5.25%割引、②追加のユニット(ETFの口数)を2回無料付与、③政府の大々的な宣伝活動、が挙げられているが、私が面白いと思うのは追加のユニット(ETFの口数)を2回無料付与だ。
これは IPO から1年間保有すると 20 口ごとに1口、2年間保有すると 15 口ごとに1口が追加付与される「ロイヤリティ・ボーナス・ユニット」というインセンティブだ。
これは、個人投資家が短期で売却することで市場への影響を抑えることや、継続保有を促して長期的な資産形成につなげることを目的としている。
実際に1回目は、申込者数の約 71%、2回目は約 69%に割り当てられており、EFILの思惑通りになったと言える。
もう1つのスキームがタップ・ファシリティというスキームによる売却だ。
取引時間中の平均株価(5分間隔)という単一値で投資家がETFを購入できるようにし、その購入分に対して為替基金の保有株式を拠出する形で株式売却を行うという仕組みである。
タップ・ファシリティを通じた株式売却の上限枠(ユニット)は、2000 年から 2002 年にわたり四半期ごとに設定された。この方式の場合には、IPOのような割引は適用されていない。
香港証券取引所によると、この2つの方式で1404億香港ドルの売却を行っている。つまりタップ・ファシリティという、現在の感覚で言うと時価で、VWAP(出来高加重平均取引)で売却するのと似たスキームで1071億香港ドル売却しており、IPOの3倍以上の額を売却している事が分かる。
ETF売却による市場へのインパクト
ここから先は
いただいたサポートは主に資産運用や経済統計などの情報収集費用に使わせていただきます。
