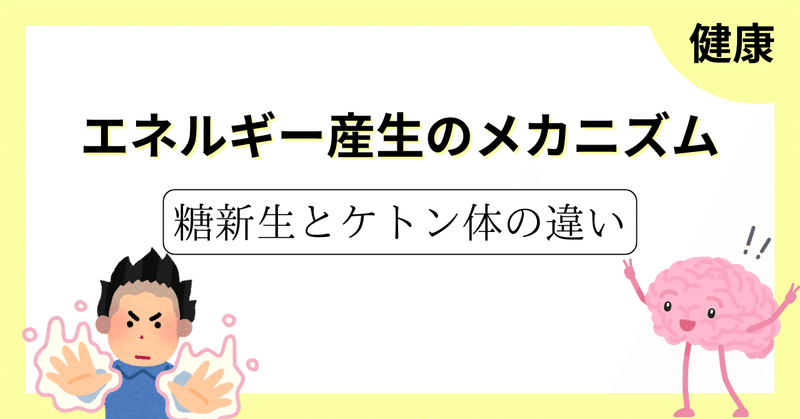
栄養素の吸収とエネルギー産生の機序②
こんにちは、ちょらです。
前回「栄養素の吸収とエネルギー産生の機序①」で食事から摂取した栄養素の吸収過程を紹介しました。
今回はその続きとして、エネルギーがどのように作り出されるかを簡単にまとめていきます。
糖質を主としたエネルギーの産生回路
エネルギーは基本的に糖質から作られ、エネルギーを産生する回路は大きく分けて3つありますが、どれもATPと呼ばれる電池のようなものを作ることが目的です。
解糖系
解糖系はグルコースを酵素などの力を借りてピルビン酸を生成する回路です。
グルコース1つからATPが2つ、ピルビン酸が2つ作られます。
クエン酸回路
クエン酸回路は解糖系で作られたピルビン酸をいくつかの化学反応を受けて、最終的にオキサロ酢酸を作る回路です。
この際にATPが2個作られます。
作られたオキサロ酢酸は次のピルビン酸から作られるアセチルCoAと結合してクエン酸となり、ATPが作くられると共に、オキサロ酢酸が生成されます。
このように循環しているため、クエン酸サイクルなどと呼ばれます。
電子伝達系
解糖系やクエン酸回路ではATPの他にNADHやFADH2という電子が作られます。
電子伝達系はこれらのNADHやFADH2をATPに作るための回路です。
ATPの作られる数は臓器によってことなり、筋肉や脳は効率が悪く、肝臓や腎臓よりも作られる数が少ないです。

糖質以外からのエネルギー産生
グルコースがなくなってエネルギーが作られなくなると、低血糖となるため、肝臓に貯蔵されたグリコーゲンを分解し、グルコースを作り、血中に放出します。
それでもエネルギーが足りなくなった場合は、筋肉や中性脂肪を分解してエネルギーを作り出し、これを糖新生と言います。
それでもエネルギーが足りない場合はケトン体を生成します。
糖新生
運動などでグルコースからピルビン酸を作り出す(解糖系)と筋肉の酸素が減るためピルビン酸が還元され乳酸となります。(通常であれば酸化されクエン酸回路へと進む)
また筋肉を分解しアミノ酸、中性脂肪を分解しグリセリン(グリセロール)を作ります。
この乳酸、アミノ酸、グリセリンから酵素の働きでグルコースを作ることを糖新生と言います。
こうして糖質ではないタンパク質や脂質からもエネルギーが作られます。
ケトン体
ケトン体はタンパク質や脂質から作られる物質で脳のエネルギーが不足すると生成され脳へと運ばれます。
アミノ酸にも糖原性とケト原性のアミノ酸、その両方を持つアミノ酸があります。
また中性脂肪を分解するとグリセリンと脂肪酸ができます。
糖原性のアミノ酸やグリセリンは糖新生で使われますが、ケト原性アミノ酸や脂肪酸はケトン体の材料として使われます。
まとめ
グルコースから解糖系、クエン酸回路、電子伝達系によってエネルギーが作られる
糖原性のミノ酸やグリセリンから糖新生が行われる
ケト原性アミノ酸や脂肪酸からケトン体が作られる
少し難しい単語も出てきましたが、シンプルに言うとグルコースからいくつかの化学反応を経てエネルギーが作られる。
グルコースが不足するとタンパク質や脂質からエネルギーを産生するということです。
ケトン体は脳のエネルギー源となるため、良い物質でもありますが、増えすぎるとアシドーシスを起こす原因となるため注意が必要です。
ケトン体やアシドーシスに関しては次回詳しく紹介していきます。
それではありがとうございました。
健康生活をお過ごしくださいっ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
