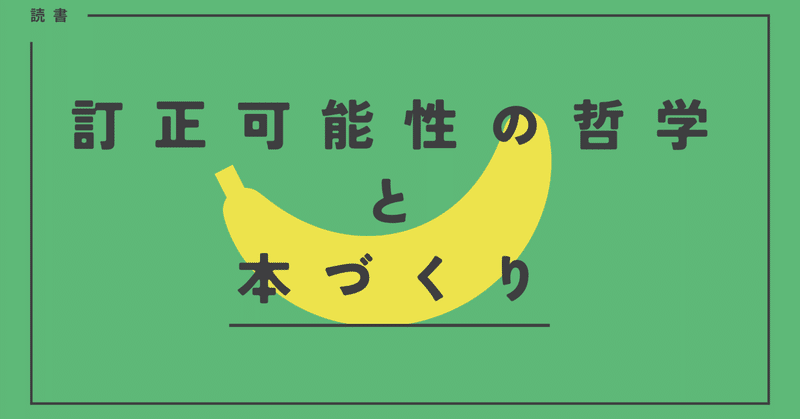
『訂正可能性の哲学』を読んで思う、僕が授業で本づくりを目指す理由。
はじめに
初任者の頃から読書家の時間、作家の時間にチャレンジし続けてきた。そうした学びを経て1年間の国語を終えたとき、どんな収穫があったらよいのだろう。そう問い続けてきたけど、最終的に生徒の作品を本にして読み合いたいというのが今年の目指すところだ。1年間の授業を終えて、生徒に本を手渡せたらどんなにいいだろう。学びの足跡が目の前に質量をもって存在するというのは、達成感や充実感に溢れた体験だと思うのだ。
いや、でも手渡すって言うと、僕のつくった本をみんなに手渡す感じだ。そうじゃないな。みんなでつくった本をみんなで読み合いたいのだ。そっちの方が大事だ。
昨年も様々な人の協力を得て、総合学習のクラウドファンディングで123万円を集め、僕も本づくりに携わらせてもらった。生徒のつくった作品(俳句や川柳)も掲載してある。
でも正直、どこか生徒の手作り感は薄かった。プロダクトとしての完成度は申し分ないし、関係者には感謝しきりだ。でも、今年は子どもたちが「大切にしたい」と思える本づくりにチャレンジしたいと思っている。
30代を目前にして、僕にとっての人生におけるキーワードが浮かび上がりつつある。その中に「本」という言葉は間違いなく入ってくる。なぜ、こんなに僕は本づくりを大切にしたいのだろう。個人的に出版社をつくりたいと思うくらいだ。25歳くらいからずっとそう思っているから、そろそろ形にしたいと思っている。その話はまた今度でいいけど。
そんな中、僕に考えるヒントをくれたのも本だった。まさか、この本を読んで自分が本づくりに拘る理由を見つけるとは思わなかったけど。東浩紀の本は読んだことがなかったので、単純に読んでみたかったことと、訂正可能性という概念に興味があって買った。あと装丁も好き。
世界を覆う分断と人工知能の幻想を乗り越えるためには、「訂正可能性」に開かれることが必要だ。ウィトゲンシュタインを、ルソーを、ドストエフスキーを、アーレントを新たに読み替え、ビッグデータからこぼれ落ちる「私」の固有性をすくい出す。『観光客の哲学』をさらに先に進める、『存在論的、郵便的』から四半世紀後の、到達点。
この本に関する読書体験があまりにも刺激的だったので、書き残しておくことにする。個人的な備忘録めいた内容になるが、僕なりに本づくりの重要性について述べたいと思う。『訂正可能性の哲学』や東さんに興味がある人にも届くといいな。
僕と本
僕は大学の人文学部を卒業して教員になった。それ以前の学生時代も国語・英語・社会が好きな筋金入りの文系人間である。人文学と呼ばれる領域が好きで学んできたし、今の僕があるのは人文学あってこそだ。僕の価値観を構成しているのは本であるといっても過言ではない。
それから、僕の人生は言葉に支えられてきた道のりでもある。中学生のときにiPodを両親が買ってくれて、それから音楽は僕を支えてくれる柱になった。生きていると何度も折れそうになる瞬間がある。そんなときにロックバンドが僕を支えてくれた。
勿論、実際に出会う人がくれた言葉も大切な僕の支えになっている。ある先輩は「彼は希望ですよ」と言ってくれた。「ああ僕は希望なんだ、じゃあこんなところで負けていられない、折れていられない」と何度も思った。辛いときもその人の言葉が僕の中に反響して、打ちひしがれた僕を甦らせてくれた。そして、奮い立たせてくれた。
あと、爆笑問題と伊集院光のラジオを中学生のときから聴いている。今は霜降り明星のオールナイトニッポンを聴きながら、土曜の午前に家事をこなしてしまうのが習慣だ。辛い時期は彼らのくだらない話に何度も助けられた。書き言葉だけではなくて、話し言葉にも僕は恩義を感じている。
デザインやアートは勿論、写真や動画を撮るのも好きだし、編集するのも好きだ。だから、フォントの種類、紙質、タイポグラフィ、そういった装丁全般のことにも興味がある。

本は僕の「好き」を詰め込んだ存在だ。僕は言葉に救われてきたからこそ、今度は誰かの支えになる言葉を発していきたいし、書いておきたいし、残していきたいと思う。遠い誰かの本ではなく、手作り感のある、僕たちの本をつくりたい。
以上に述べたように、好きで、得意で、人の役に立つことが僕にとっては本づくりなのだ。教員は僕の本職だが、この出版業というのも人生を賭けて取り組んでみたいテーマである。それを授業に生かしたいと思って、本づくりを国語に取り入れようと考えている。
寝ても覚めても授業や学校のことを考えている僕にとって、教育とは正に業(カルマ)。本や出版業に関しても、そういう業めいたものを感じるのだ。なんで本をつくりたいのか。なぜ出版社をつくりたいのか。2023年現在、『訂正可能性の哲学』を土台にその理由を考えてみた。一言で言えば、人文学の復興を僕は望んでいた。そのことについて書いていきたいと思う。
書店で探したけどなかったので、ネットで注文した『訂正可能性の哲学』が届いた!装丁が好きなのと、東さんの本は未読だったので購入。初っ端から難しそうな議論なんだけど、なぜだかそんなに難しく感じない。自分の中の正しさや常識がどんどん壊されていく感じがする。https://t.co/NZhr3AQ9Bg
— Kohei Kamiyama (@kikuuiki0131) September 5, 2023
生命維持的な持続可能性
東はクリプキとウィトゲンシュタインを引用しながら、訂正可能性の概念について説明している。彼らの思考は確かに難解だけど、この本は一定の読解力があれば理解が途切れることはなく読める構成になっている。これは東さんの意図した書きぶりが絶妙だからだ。敬服するほかない。
本書で訂正可能性と呼ばれているのは、簡単に言うと次のような性質を指す。現在どんなに高く評価されているものだろうと、逆に世間から忌み嫌われているものだろうと、時間や空間、状況の変化によっては評価が変わり得るということだ。
過去に是とされていたものが突然ひっくり返ることはままある。例えば、スポーツのルールが毎年のように更新されるが、それはプレイヤーや観客にとってよりよい試合が展開されることを期待してのことだ。
5年前と比較しても、「職場に毎朝出勤するのが常識」という価値観は、感染禍によってひっくり返った。リモートワークが当たり前になり、東京と地方の二拠点で働く人々が増えた。現在の常識でさえ、1年後には通用しない可能性がある。誰もが訂正され得る可能性を孕んでいる。

さて、僕が注目したのはクリプキとウィトゲンシュタインというよりは寧ろ、デリダとアーレントに関する記述であった。ジャック・デリダについては、この本の中では注釈で書かれているくらいで、あまり詳しく触れられているわけではないのだが。
デリダは話し言葉(パロール)と書き言葉(エクリチュール)を対置した上で、西洋哲学はエクリチュールを軽視してきたと批判している。現代においても、YouTubeやTikTokといった映像メディアや、ラジオなどの音声メディアが隆盛を迎えていると言ってよい。テレビでは何より面白いトークが重要視されているし、カラオケ番組は増加の一途を辿っている。文字を読む文化よりも映像や発話に関する娯楽が享受されている。僕もラジオは好きだが、こうした背景を見ると出版業界は逆風必至というのも頷ける。
さらにここで触れておきたいのが、ハンナ・アーレントに関する東の指摘だ。アーレントは人間が活動的な生を送るうえでの営為を労働(レイバー)・制作(ワーク)・活動(アクション)の3つに分類し、その中でもアクションが人間的営為において特に重要だと述べた。
この三つの営為はけっして対等ではない。アーレントは、そのなかでもっとも重要で、もっとも人間的なものは「活動」だと主張した。ひとは労働でも制作でもなく、活動を通してのみ、公共に接続しひとりの人格として「現れる」ことができるというのである。あえて現代日本の例で言い換えれば、ひとは、小遣い稼ぎのためにコンビニでバイトしたり(労働)、自己満足のため孤独にイラストを描いたり(制作)しているだけではだめで、世間に出て、見知らぬ他者とともに共通の社会課題について語りあったり政治運動に参加したり(活動)するようになってはじめて、充実した生を送ることができる。これがアーレントの主張だ。
東はこのアーレントによる主張を批判している。現代におけるクリエイティブ産業は多岐に渡っており、その影響力は計り知れない。したがって三つの営為は三項鼎立の状態にあり、比重の軽重はつけるべきではない、と。例えばファッション業界で言うと、LVMHの世界的な経済影響力は大きい。制作(ワーク)を生業とする人々が活動(アクション)に携わる人々に劣るというのは、少々強引である。

先ほどのデリダが行った批判と併せて考えると、制作(ワーク)によってエクリチュールは形を成すことができ、エクリチュールなしにはパロールが存在および発展することはないということだ。出版業界に置き換えて考えると、書き手が書く行為によって本が生まれ、その本が新たな議論やコミュニティの生成、人々の政治的参加を促すということである。
訂正可能性について前述したように、ある知識が固着したまま万人から正しいと見做され、動かないという保証はどこにもない。ある概念や共同体が形を変えて持続するために訂正可能性が必要になってくるのだが、それは何も決めず、何もつくらず、もやもやとした霧のような状態を続けるというわけではない。何も正しくなく、ものづくりが成されず、形あるものは必要ないというわけではない。それならばルールも技術も不要になり、人類は狩猟採集民族に回帰するということになる。それでは普遍闘争状態に陥るだけだ。
ルールや技術は、形はなきにしろ制作されたものであり、何者かの叡智が詰まった結晶である。その存在はそれとして重要なのだ。ただし、今あるものを無批判に受容し続けていると、時代や状況の要請によってそのルールが適用されなくなる事態が必ず発生する。技術もアップデートする必要に迫られる。つまり、訂正可能性の失われた状態というのは持続可能性をもたないというのが東の主張だ。
これは現代における組織論、『ティール組織』や『ジェネレーター』といった、組織や場づくり自体を生命のメタファーとして捉える考え方と重なってくる。生命は代謝を繰り返しながら傷を癒したり、成長したりして、機能を維持していく。それは常に変化を受け容れているということであり、訂正可能性に満ち溢れた状態だ。訂正可能性とは生命維持的であると言えるだろう。
組織の中で「自分は間違っていない、完璧だ」と振る舞う人は多い。批判されれば怒り狂って自分の正当性を主張し、強いリーダーとして振る舞おうとする。でも、それは長い目で見れば、自分の首を絞めているのと同じだ。いつか自分の常識は古くなり、錆びついてしまったとしても、そのことを誰も指摘してくれなくなる。
目に見えないものを、制作によって形あるものに変える。形を成すということは固定するということだ。僕にとっては出版するということである。形を成した本は、今の時代を生きる人々の拠り所になるかもしれない。しかし、100年後には猛烈な批判を浴びせられているかもしれない。しかしそれでよいのだ。後述するが、そういう形で人文学は、学問は、発達していくからだ。
人文学の復興
最後に、僕にとってのパンチラインを挙げておく。この一節が、僕が本づくりに拘る理由として決定的だった。
二〇二三年のいま、日本では人文学の評判は落ちるところまで落ちている。言論人や批評家にかつての存在感はない。有名な学者もほとんどいない。世に出てくる文系学者といえば、活動家まがいの極端な政治的主張を投げつける目立ちたがりの人々ばかりだ。SNSを開けば、文系はバカだ、非科学的、役にたたない、他人の仕事にケチをつけているだけだといった罵詈雑言が溢れている。ぼくは文系学部の出身だが、もしいま一〇代の高校生だったら進学先に文系を選ぶことはありえなかっただろうと、そのような言葉に接するたびに真剣に思う。
人文学は信頼を回復しなければならない。人文学には自然科学や社会科学とは異なった役割があることをきちんと論理的に伝えなければならない。じつは本論はそのような意図でも書かれている。
僕が本づくりを目指すのは、ごく単純な理由だが、これが堪らなく悲しいということであった。僕を支えてくれた本が、人文学が蔑まれつつあるというのは嘆かわしい。文系軽視の流れは長年続いている現象である。
人文学の考え方(研究方法)は、かつて誰かが唱えた仮説について異を唱えたり、別の角度からの検証を提案したりして知を積み上げていくものだ。それは訂正可能性そのものだと思う。人間は誤るものであり、今は正しいとされている考え方も100年後は鼻で笑われているかもしれない。そういう可変性や可塑性を前提にして議論するというのが人文学の本質である。
文系は今ある概念を疑うことで、新しいものを創り上げていく学問だ。それには、健全な批判に開かれていることが重要なのだ。人文学にとって固着とは死を表す。完全な事象に考察の余地はなく、そこに知的な興奮も快楽も存在しない。そこで思考は止まり、持続可能性は閉じられてしまう。
訂正可能性を抱えるというのは、先人の誰かがつくり出した肩書きや権威、常識に依りたい人々にとっては避けたい考え方であろう。既得権益を啜って生きていく方が楽に決まっている。正義の側に立って批判だけしていれば、自分の立ち位置が脅かされることはない。
僕は、インターネット上にそのような人々が跋扈しているのを悲しく思っている。間違ったら再起不能になるまで叩き潰し、燃やし尽くしてしまう。でも、誰もが誤る可能性があるんだから、もう少し許容し合った方がみんなが生きやすいはずだ。逆に訂正可能性をもたない人や共同体は、昨今のビッグモーターのようにゆっくりと滅びていくのではないか。
僕が本をつくる理由
最後に、この読書体験から得た僕の考えをまとめておく。僕が本づくりに拘る理由だ。まずは、制作(ワーク)の重要性を僕自身が実感したいからだ。現代人は社会の担い手・作り手であるという意識が薄い。僕も多分その1人だ。だからこそ、自らつくったものが他者や社会に影響を与えたという体験をしてみたい。それが社会をつくるということだからだ。
それから、やはり僕は人文学を盛り上げたいのだ。ジョン・デューイは子どもがもつ衝動的欲求を次のように分類した。社会的本能(話したい)、構成的衝動(つくりたい)、探究的本能(やってみたい)、表現的衝動(表現したい)である。このうち後半の3つが制作(ワーク)との強い関連性をもっていることが分かるだろう。子どもの興味・関心から生まれる欲求を、教師が教材と融合させることで深い学びが生まれるのだとデューイは述べている。
僕は東のアーレント批判に乗っかる。活動(アクション)こそが重要というのは、デリダもパロールの優越性を批判しているように、エクリチュールの軽視である。デューイがつくることを重要視したように、今こそエクリチュールの復興を目論むべきだ。重要なのは、ここで二項対立に陥ってはならないということ。ヘーゲルの弁証法的に考えたい。右派か左派か、保守かリベラルか、パロールかエクリチュールかで対立している限り、訂正可能性は閉じられてしまう。
本を制作して形づくることを、僕も経験したいし、子どもたちにも経験してもらいたい。そうすることで、つくることの喜びやエクリチュール(書くこと、本)について知ってほしい。その営為には訂正可能性がつきまとうけれども、それでよいのだ。それが人文学の営為そのものだからだ。それは、僕が最も大切にしてきたものだし、これからも大切にしていきたい。
おわりに
東さんは読み手に「考える読書」を求めているらしい。読書を単なるインプットとして捉えるのではなく、読んだ内容について自分の頭でしっかり考えてほしいということである。少しはその期待に応えられたのではないだろうか。
国語では本づくりを、総合学習ではPBLを通して、僕は子どもたちに作り手になることを要求している。デューイに強い影響を受けていることは分かっていたけれど、訂正可能性、デリダ、アーレント批判との繋がりが生まれるとは、この本を読むまでは想像だにしていなかった。でも、『訂正可能性の哲学』を読んだことで、やっぱり僕には本づくりなのだと納得できた。
子どもたちにはエクリチュールだのなんだのと言うつもりはないし(笑)「人文学の復興」という大それたテーマで生きていくにはまだまだ未熟だ。でも僕が人文学を好いているのは本当だから、今はそれに向かって生きていくことにする。東さんにとても感謝している。姉妹編の『観光客の哲学』も気になっているので、どこかで読もう。『訂正可能性の哲学』、ぜひ読んでみては。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
