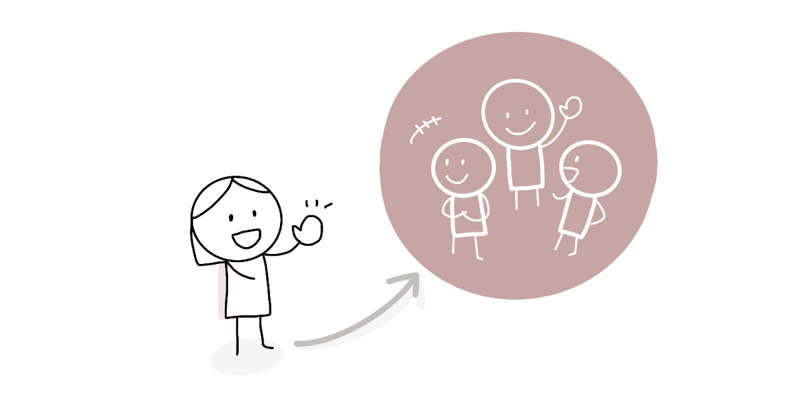
実践コミュニティ理論からLSPコミュニティを考えてみた。
上掲書によれば、「実践コミュニティ」とは「共通の専門スキルや、ある事業へのコミットメントによって非公式に結びついた人々の集まり」と定義される。
レゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドを学んだ人々(トレーニング修了認定を受けたファシリテーター達)もこの実践コミュニティを作っている。私もその一員である。
この本では、実践コミュニティの特徴や存在意義など広範な話題について語られているが、その中でも実践コミュニティの開発をどうすればいいのかという問題が私にとっては興味深い。
著者たちによれば、まず領域、コミュニティ、実践の3つの観点から見ていくことが重要だとする。
そして、それぞれの観点において問うべきことがあるという(日本語訳86-87頁)。
(A)「領域」において考えること
①本当に大切なのはどのテーマや問題なのか
②(組織に付随している場合)組織の戦略との関係はどのようなものか
③われわれにとってその領域はどのような利益があるのか
④最先端の未解決問題は何か
⑤その領域において指導的な役割ができているか
⑥その領域にどのような影響を持ちたいのか
(B)「コミュニティ」において考えること
①メンバーはどのような役割を果たすべきか
②コミュニティはどのくらいの頻度で会合をもつべきか
③メンバーはどのような方法で継続的に連絡を取り合うのか
④どのような活動が活力や信頼関係を生み出すのか
⑤どのようにメンバーの異なるニーズのバランスをとるのか
⑥対立をどのように処理するか
⑦新参メンバーをどのように迎え入れるか
(C)「実践」において考えること
①どのように知識を分かち合い、生み出し、記録すべきか
②どのような学習活動を組織化すべきか
③知識の体系をどのようにメンバーにアクセスしやすくするか
④どの点について標準化し、どの点は差異を許容するか
⑤コミュニティとしてどのような開発プロジェクトを推進すべきか
⑥コミュニティの外部にある知識やベンチマークをどこに見出すべきか
レゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドの実践コミュニティと重ねてみる
まず、レゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドの実践コミュニティ(以下LSPコミュニティ)が関わっている「領域」はかなり広いと感じる(もともとは企業の戦略構築だったが現在では、そこから大きく広がるとともに、最も多い活用場面は一部の調査などによれば、企業のチームビルディングと思われる)。教育や福祉、スポーツの領域でも導入事例は増えている。また、導入の狙いもチームビルディング以外にも、個人の能力開発、イノベーション、メンタルセラピーなどがあり、掛け算的に広がりを見せている。
そのため、最初の(A)の「①本当に大切なのはどのテーマや問題なのか」から、不明瞭になって来ている。それが実践コミュニティの発達を妨げているのだとしたら、これについて考え定め直していかねばならない。
領域の広がりは、あちこち領域に先行している競合とのぶつかりをうむ。その中で(A)の「⑤その領域において指導的な役割ができているか」についていえば、他の手法を凌駕しリードできるような指導的なポジションは確立できていない。LSPコミュニティは、まだ領域においてはマイナーでありチャレンジャーとして、メソッドの理解と普及の段階とどまっている実践コミュニティといえる。
その実践コミュニティの領域での存在感を支えるのが(B)のコミュニティと(C)の実践の各項目である。
(B)については「①メンバーはどのような役割を果たすべきか」は特に定められてはいない。それぞれのメンバーに関わり方はゆだねられている。それゆえに⑤ユーザ間のニーズの食い違いや対立はあまり起こっていない。義務を課すことがない分、要求の声も強くあがりにくい。またこれといった義務もないため、「⑦新参メンバーをどのように迎え入れるか」の点についても仕組み化はまだそれほど進んでいない。
トレーニングを受けたファシリテーターについては上記のような感じだが、ファシリテーターをトレーニングするトレーナーたちにはメンバーの義務は強く求められていそうである(この点について、私はそこまで詳しく知らないので憶測である)。
(C)については、ファシリテーターにおいてはまだ十分に制度化されていない。これはメンバーシップが緩いから仕方ないところであろう。ここでもコミュニティを先導しているのは、トレーニングを提供しているマスタートレーナー協会のトレーナーたちである。ただしトレーナーたちも、コミュニティの運営からは収入が得られない仕組みであるので、優先順位はどうしても低くなってしまうことが、コミュニティの質的な発展を鈍らせている(これも主観だが)一つの原因になっているのではないかと思われる。
私もLSPのコミュニティについてはいろいろ関わってきているが、あくまで個人プレーであり、組織的に動いている感じではない。責任があるわけではないので、その点は気楽でありがたいのだが、その気楽さが発展を遅らせていると考えると複雑な気持ちになる。
実践コミュニティ論の観点から、LSPコミュニティの診断を試みてみた。すべてを細かく論じたわけではないが、「領域」「コミュニティ」「実践」の観点とそれに関わる問いは、コミュニティの今後を考えるために有益な問いかけだと感じたので、今後も期間をかけて問い直してみたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
