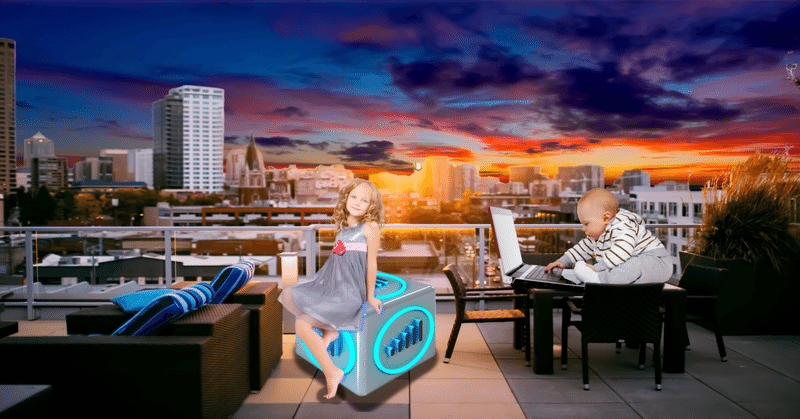
レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドはフューチャーセンターを支える
「フューチャーセンター」という場づくりについての思想をご存知でしょうか。
下記の本によれば、フューチャーセンターという言葉は、スウェーデンのレイフ・エドビンソン教授によって初めて使われたといわれ、それは「未来の知的資本を生み出す場」として構想されたとされます。
上記の本では、エドビンソン教授が考える「知的資本」を以下のように位置付けています。
知的資本は、人的資本・構造的資本・関係性資本の三つからなるといわれています。未来の人的資本は「人の成長」であり、未来の構造的資本は「ビジネスモデルなどのアイデアの創出」、そして未来の関係性資本は「新しい人と人とのつながり」を生み出すことになります。
つまり、「未来の知的資本」を生み出すフューチャーセンターは、人が成長し、アイデアが創出され、人のつながりが生まれる場なのです。
未来の人的資本になる「人の成長」は他の人との対話の中からもたらされるものです。同じ問題に関心を持ちつつ、普段ちがう立場に身を置いている人であればあるほど望ましいとされます。
ちがう立場の人同士の対話は、自分の知らないことやものの見方を知る可能性が高くなるので、お互いに恩恵をもたらすものでありますが、一歩間違えれば「お互いに分かり合えない」まま終わりになります。当然、アイデアも出ませんから「未来の構造的資本」は生まれせんし、未来の関係性資本も生まれないわけです。
ですので、フューチャーセンターでは、問題意識をもった人が集まるだけでなく、そこで展開されるプロセスも非常に重要な場の要素になります。
フューチャーセンターのプロセスと原則
「単なる人の集まり」を乗り越えるために、本書では「目的の再定義」を進めています。たとえば「未来の街づくり」を構想するとしましょう。立場の違う人々が集まるのですが、それぞれ心に描いている未来の姿は異なります。それを丁寧にお互いに出しながら、ひとつにまとめていき、皆で目指すべき大きな絵を描いていきます。そうすることで他の人がなぜ未来をそのように描いたのか、自分の描く未来とどう関連しているのかがわかり、共通の目的が見えてくるというわけです。
そして、より多くの、より多様な人々がお互いに納得する目標であればあるほど、他の人々を惹きつける可能性が高く、その達成が人々にとって恩恵をもたらす、すなわち「善い」目標になっていくというわけです。
善い目標が見えてきただけでは、フューチャーセンターはその力を十分に発揮できません。加えて、その目標に多くの人が巻き込まれていく仕組みが必要です。そのためにそれぞれの体験や知恵から、目標達成に少しでも近づくための具体的な活動を試作的に計画します。より多くの人が参加しやすく追加のアイデアを出し易いように、試作的なものとして活動を位置付けるところがポイントです。
そして、試作的に計画したことにおいては、参加者の一人一人が自分に何ができるのかを考えさせて、行動にコミットメントしてもらう(約束通りに行動)必要があります。そしてその行動は、フューチャーセンターの参加者の周りの人々に影響を及ぼしていきます。それは「未来のステークホルダー」との関係性をつくると表現されます。
そうしてつながった「未来のステークホルダー」が、また目的の再定義プロセスに組み込まれ、さらに多くの人を巻き込んでいく、という流れを生み出していくことになります。
こうしたプロセスを、先ほど紹介した本では「原則」として以下のようにまとめています。
❶フューチャーセンターでは、想いを持った人にとっての大切な問いから、すべてが始まる
❷フューチャーセンターでは、新たな可能性を描くために、多様な人たちの知恵が一つの場に集まる
❸フューチャーセンターでは、集まった人たちの関係性を大切にすることで、効果的に自発性を引き出す
❹フューチャーセンターでは、そこでの共通経験やアクティブな学習により、新たなよりよい実践が創発される
❺フューチャーセンターでは、あらゆるものをプロトタイピング(試作)する
❻フューチャーセンターでは、質の高い対話が、これからの方向性やステップ、効果的なアクションを明らかにする
レゴ®︎シリアスプレイ®︎にできること
このフューチャーセンターが実現するために、なかなか難しいのは(1)テーマにそった多様な人を集める、(2)多様な人の想いと知恵を引き出し、(3)想いや知恵を活動のカタチにもっていく、の3点かなと思います。
このうち(2)について、レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドは大きな力を発揮しそうです。ある問い(未来のまちをどうしたいか?や今のまちの不満はどこにあるか?など)に対する考えをブロックによる作品をつくってもらってそれを見せながら話してもらうことによって、人々の発言に込められた感情や他の発言とのつながりをより理解できるからです。また、考えが作品になっているので、皆がそれを作れば、お互いの発言の関係性を、より明確に検討できます。
レゴ®︎シリアスプレイ®︎では、お互いのことがよくわかるようになるので、ワークを重ねると、心理的安全性は高まり、自然と和んできます。
そして、全員が納得できる「目標の再定義」まで、かなり安定的に進んでいけるのです。
次に、(3)の活動をカタチにするという点においてもアイデアやコンセプトレベルまでであれば、大きな貢献ができます。具体的には、参加者で「創り上げたい未来」を作品で可視化し、一方で「現状」を作品で可視化するのです。その2つの間に何が起こっていけばいいのか、どのような活動や仕組みがあれば2つが結ばれるのかもまた、作品で可視化しながら確認することができます。
未来の「姿」や活動の「様子」は、「姿」や「様子」という言葉が示すように、いずれもイメージがベースになっています。イメージをかき立ててアイデアやコンセプトに結びつけることについて、ブロックによる表現は非常に優れています。
このようにフューチャー・センターという場作りにおいて、レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドは非常に大きな貢献ができます。
私も実際に関わらせてもらったことがありますが大変相性が良いと実感しています。また、検索をかけてみると、フューチャーセンターの文脈で、実際に行われた例もいくつかみつかります。「フューチャーセンター レゴ シリアスプレイ」で検索をしてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
