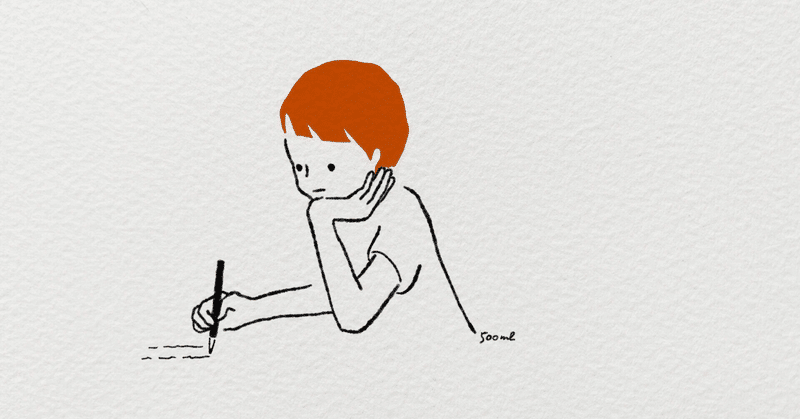
「知識のないところから才能は生まれない」放送作家大井洋一さんが語る、不安と戦いながら企画で生きていくための心がけ
どうしてだろう。
第一線で活躍している方ほど「自分なんて、まだまだです」とよく言う。
その発言の源は、もっといい仕事をしたいという貪欲さなのだろうか。
とにかく謙虚であり、自らの活動に慢心せず、学ぶことをやめない。そうして彼らは常にアップデートを繰り返し、さらなるチャンスを掴んでいく。
「企画でメシを食っていく2022(以下、企画メシ)」第2回目。
今回は放送作家の大井洋一さんをゲストにお迎えし、「放送の企画」をテーマに講義にのぞみました。
前半は、放送作家を目指すまでの秘話や、下積み時代のお話。
後半は、提出課題の講評でした。
今回も、約2時間に渡る講義の様子を振り返ります。
レポートライターは、『言葉の企画2019』卒業生、しんみはるなです。
よろしくお願いします!

「敵の少ない道へ」が原点に
「今ほどSNSが普及していない時代に、有名人と関わりを持てる唯一の方法が、ラジオでハガキを送って読まれることだったんです。爆笑問題さんとか、伊集院光さんとか、今でいうサマーズさん(当時はバカルディ)とか、今田さん、東野さんとかのラジオにハガキを出し続ける。それで、 読まれて嬉しいみたいなことを感じていたんですよね」
これまで数々の人気番組(『はねるのトびら』『笑っていいとも!』『水曜日のダウンタウン』など)に、放送作家として携わってきた大井さんがこの職業を目指すきっかけとなったのは、「ラジオのハガキ職人」。
高校時代、友人の兄の影響で聴き始めたラジオ。憧れの有名人と関わりを持ちたい一心で、「採用される数の目標を決めてハガキを送るのが日課」になるほどのめり込んでいました。
ハガキが読まれることに喜びだけでなく、次は、どうしたら読まれるか?を考えるようになり、選ばれなかった時は、選ばれた投稿のパターンを分析し、選ばれる方法を学んでいきました。そんな風にハガキ職人としての腕を磨いていった大井さんが、放送作家を志すようになったのは、大学生になってから。
「一浪して大学に入学したんですけど、同級生が『この大学を卒業しても、有名な企業には入れない』って話していたんですよ。それがきっかけで就職について考えるようになって。学歴で弾かれるなら、何かで当てるしかないぞ!と」
今でこそ、フリーランスで多様な働き方が当たり前になっていますが、大井さんが学生だった当時は「いい大学に入って、いい会社に入る」ことが1つの正解とされていました。そんな中で、自分なりの未来を模索します。
「芸人さんがラジオで、『放送作家の誰々が儲かっている!』とかいう話をするんですよ。それで、放送作家という仕事を知りました。あまり世の中に知られている職業じゃないから敵が少ないだろうって思ったんですね。それに、ハガキも読まれるから、感性はズレてないんじゃないか?っていうところで。ちょっと、そこに賭けてみようかなっていう思いでしたね」
敵の少ないところで戦うという発想は、自信のなさからきているという大井さん。だからこそ、「1000人の中から一人に選ばれるのは無理でも、20人の中の一人だったら選ばれるかもしれない」。そんな想いを持って、放送作家への道を辿り始めます。
売れっ子演出家と出会い、テレビの世界へ飛び込む
スタートは、大学一年生の時。吉本興業の運営する『渋谷公園通り劇場』の舞台に、芸人として立つところから。ですが、舞台に立ち始めて数ヶ月が経った頃、劇場が閉館に。それを機に、劇場にいた放送作家の方に「本当は放送作家になりたい」と打ち明け、作家見習いとして活動を始めました。劇場で見習いの仕事をする日々が続きましたが、とある演出家との出会いから、テレビ業界へと舵を切ることになります。
「とんねるずとかでお馴染みの、マッコイ斉藤さんという演出家の方がいるんですけど、僕はその方と早い段階で知り合えて。極楽とんぼの番組をやるときに『タダでいいなら来ていいぞ』って言われたんで、 行ったんですよね。本当にタダでしたけど、そこで何年か番組を手伝いました。テレビの世界に触れたいと思っていたので、お金のことは考えず、飛び込んでみましたね」
放送作家の世界において、「実力は重要だが、誰と出会うかはもっと重要」だそうです。大井さんの場合は、マッコイ斉藤さんに出会ったことで、憧れの世界に足を踏み入れるチャンスを掴んでいきました。
放送作家として生きていくために心がけていること
放送作家の仕事は、「誰かから依頼されないと始まらない仕事」です。テレビだと、ディレクターや演出家から「こういうことをやりたい」「何をしたらいいと思う?」と相談がきて、そこで初めて、放送作家の出番が訪れます。
その出番をものにするために、大井さんが下積み時代から心がけていたことを教えてくださいました。
①会議はポイント制で、無理をしてでも発言する
ハガキ職人時代、毎月、採用される数の目標を決めてネタづくりに取り組んでいた大井さん。放送作家になってからも、似たようなルールで会議にのぞんでいたそうです。
「若手の時に会議で発言するって、めちゃくちゃ勇気がいる。喋れないですよね、マジで。一言も喋らずに帰るなんて、しょっちゅうだったんです。だけど、それではマズいと思ってポイント制のゲームにしたんですよ。『ネタいいね!』って言われたら5ポイントとか、ネタ通らなかったけど、喋ったことウケたら2ポイントとか。ポイント制にして、今日6ポイント取ったとか、今月取れてないとか振り返って。会議をポイント制にすることで、無理やり頑張るようにしていました」
一言も発言することなく終わる会議、多くの人が経験あると思います(私もあります)。そういう時って、自分がいる意味はあったのかな?と思ったりしませんか。せっかく参加するなら、そこにいる意味を持ちたいですよね。だからこその、ポイント制。
大井さんの場合は、「フリーランスだから、喋らなくても怒られはしないけど、次に呼ばれない(=お金を稼げない)」ことが、無理してでも頑張らないといけない!と自分でお尻を叩く原動力になったそうです。
つまらないとか、才能がないと思われたくなくて発言できなくなってしまうのは、きっと誰にでもあること。だけど、恥を捨てて打席に立って、空振りでもいいからバッドを振る。その勇気が出せるかどうか。
打率を上げるために、打席に立つ経験を積み重ねるのです。
②相手が何を求めているか理解する
「リクエストに応えられなかった時は虚しくなる」というほど、相手ファーストでネタを考える大井さん。「あの人、こういうテイスト好きだよな」と相手の趣味に合わせたり、「今の時代に足りないものはなんだろう?」と時事に目を向けたりして、ネタを作るそうです。
「相談してくれた人にハマる企画を投げないとって意識でいます。もう、全員にハマりたい。だから、まずは相手が何を求めているか理解するところから始めます」
ネタの出し方としては、 「みんなの頭の中に最初に思い浮かぶネタを、こんな風に変えてみました」というものを出すそうです。当たり前の発想にひねりを加えることで、オリジナルになる。あまりにもサラッとおっしゃっていましたが、それこそがプロの芸当では?としびれました。
知識のないところから才能は生まれない
後半は、企画生が事前に取り組んでいた課題『新しいドッキリを考える』について、大井さんからフィードバックがありました。
課題をみた全体の感想として、
「ドッキリっていう捉え方が人それぞれだなっていうのは思いましたし、 そんなに意地悪な人がいなくてよかったです。ただただ追い詰めて楽しむみたいなことがなかったので、それはいいことなんじゃないかなと思います」
ひとりひとりのネタに丁寧にお話されていた中で、
ドッキリの作り方のコツとしては、
・タイトルや、絵を見ただけで、意味が伝わる。
・くだらないけど、いいもの見た!と思える。
・いいことをしたら、いいことが戻ってくる。
・なんでこれをやるんだっけ?を決めてエッジをたたせる
(例:水曜日のダウンタウン⇒“検証”という建付け)
・すでにあるドッキリに掛け算、足し算、引き算する
などを挙げられていました。
全体への感想に通づるところがありますが、フィードバックを経て、「誰かを傷つけないこと」をいつも考えながらネタを考えられているのかな?という印象を受けました。
企画生たちのドッキリネタに対しても、『夫婦でドッキリを仕掛け合う』や『誕生日に憧れのスターが登場する』など、誰かの幸せを前提として作られたドッキリ企画について、「こういうのは、いいに決まってる!」とニッコリされていました。
自分の中で明確なルールを持った上で、50名近くの作ったドッキリ企画に対し、「こうすれば、たぶん、もっとよくなる」と瞬時に回答していた姿に、頭の中の引き出しはどうなっているんだ…?と驚きました。
大井さんは、「知識のないところから才能は生まれない」という思いから、日々、テレビのチェックを欠かさないこと。コミュニティを絞らず、いろんな人と関わることを意識しているそうです。
自信のなさは、伸びるための助走になる
「放送作家の仕事を始めて二十数年経ちますけど、これでメシを食っていけそうだと思ったことは一度もないです。毎年、正月を迎える度に、今年は大丈夫かな?と思いながら生きています」
私は大井さんに対して、「運も実力もあり、順風満帆な人」というイメージを持っていましたが、この発言を聞いて、衝撃を受けました。
不安と戦いながらも、長年に渡り活躍し続ける大井さん。
不安だからこそ学ぶことを怠らなかったり、自分を駆り立てるためにポイント制のルールを作ったり。自信のなさが、頑張るための力となり、常に第一線で仕事をする結果につながっています。
そんな大井さんにとって企画とは、
・名前を聞いて、楽しそう!と思えるかどうか。高揚感があるか。
・これ、どうなるの?と思われて、結果、想像以上のことが起きる。
ことだそうです。
私も自分に自信があるほうではありませんが、なんとなくネガティブに捉えがちだった「自信がない」という感情も、大井さんのように工夫をすれば、きっと、伸びていくための助走になる。
そんな学びを得ることができた、第2回目の『企画メシ』でした。
放送作家 大井洋一さんのTwitterはこちら↓
※ここまで読んでくださってありがとうございました!
よければ、前回のレポートもみていただけるとうれしいです!↓
お読みいただきありがとうございます! 2023企画生が気づきや学びを発信中の noteマガジンもぜひご覧ください🍙 https://note.com/kotaroa/m/m4404fe17fb59 いつか企画で会いましょう〜!
