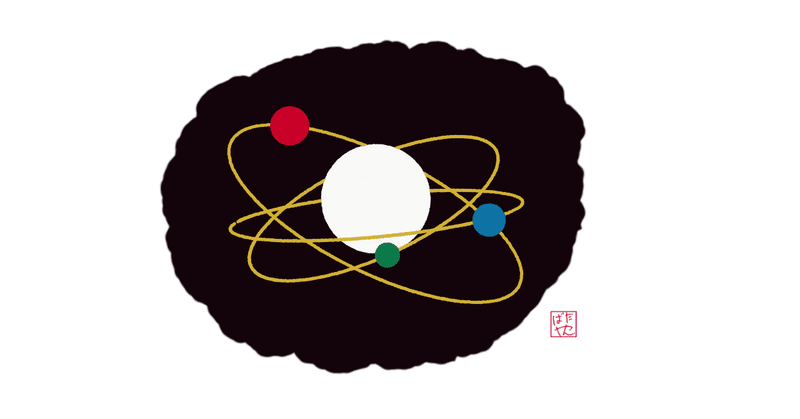
理解できそうでやっぱり分からない、うるう年の仕組み。
今年はうるう年だ。明日だよね。
4年に一度の2月29日は。
これ、説明できそうでできない。ギリギリできない。太陽とか公転とかの話だよね? と思いながらも「じゃあ説明をお願いします」と言われると「うっ」となる。
うるう年の仕組みを理解するためには、まず天文学の基礎から始めなければならない。
地球は太陽の周りを公転しており、これが365日かけてぐるりと一周するのにかかる時間を「1年」と呼ぶ。しかし、この1年、きっちり365日なわけではない。実際には365日と約6時間ちょいなのである。
この6時間が積もり積もって、地球の本来の位置を調整するために4年ごとに「うるう年」として1日が加えられるわけ。
アンダースタン?
このシステムが導入されたのは、実は古代ローマ時代にまでさかのぼる。当時の人々は、季節と暦が一致しなくなると、農業など季節に依存する活動に大きな支障が出ることを知っていた、らしい。
そこで、ユリウス・カエサルが紀元前45年に導入したのが、うるう年を含むユリウス暦だ。これによって、暦と季節のズレを修正することが可能になったのである。
アンダースタン?
さて、うるう年をもっと身近な例で考えてみよう。大丈夫、理解できるよ。
たとえば誕生日に友だちから4枚の大きなチョコレートをもらったとする。このチョコレートはそれぞれ365枚のチョコ板が合体したチョコレートで、1日に1枚ずつ食べると365ピースでちょうど1年間かけて食べられることになる。
しかし、実はこのチョコレート、1年で食べきるには大変で、1日に1ピースのペースで食べても、あまりにデカすぎるからか4年目には余分に24ピースが残ってしまう。
そこで、4年に1度、この余分なチョコレートを全部食べる日を設けるわけだ。これがうるう年の1日、つまり2月29日にあたる。
もちろんわかってるよ。
ギリついてこれてないよね?
ギリギリ理解できなくなったよね?
というか説明間違ってない?
同じです。私もです。
これ、AIにお願いしました。
「うるう年を中学生でもわかるように解説して」
こんな雑なプロンプトで明快な答えがでると思った私が間違っていた。
AIは続けてこう言う。
このように、うるう年は天文学的な精度と古代人の知恵が融合して生まれたシステムです。地球が太陽の周りを一周するのに正確に365日と6時間かかるというこの事実を基に、暦と季節のズレを修正し、私たちの生活をより一層便利にしてくれているのです。
うーーーーん。
分かりそうでわからない。
AIに言わせれば、私は中学生以下だ。
チョコレートの例え話がきたとき「お! なんか分かりそう!」って思ったでしょ?
甘くないんだなぁ、チョコだけに。

〈あとがき〉
2月29日うまれの人に会ったことがあります。4年に一度しかない誕生日ですが、2月28日に祝っていたそうです。そっかそうだよね、と思った記憶があります。うるう年に関しては、そもそもなぜうるう年と言うのか? その仕組みは? というところをきっと「じゃむむ」さんが解説してくださると思います。今日も最後までありがとうございました。
【関連】ビタっと理解できる解説が読みたい
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
