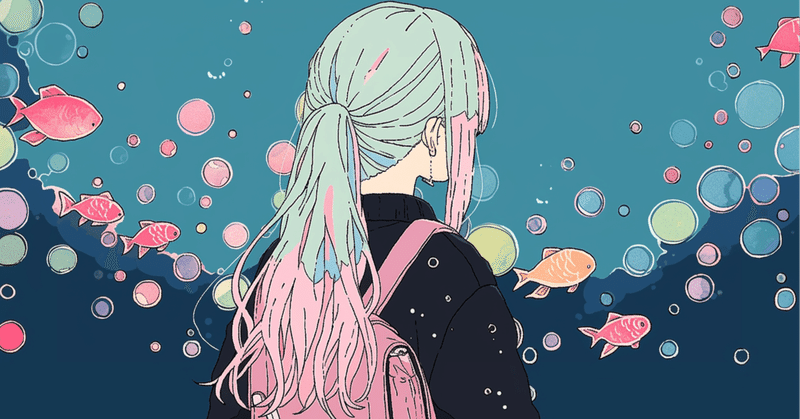
水族館と私
水族館のよさがずっとわからなかった。
いつからだろう。
ひとりで行くのが当たり前になるほど、好きになったのは。
友達と遊ぶとき「水族館に行こう」と自分から誘うようになったのは。
小さいころ、よく水族館に連れて行ってもらった。
だけど、魚を見たところで何も感じないし、たくさん歩かないといけなくて疲れる場所としか思わなかった。
そんな私が大学で選んだ学部は、水産系。
といっても、魚や海が特段好きというわけではない。
環境問題に取り組む研究者になりたくて、陸地よりも研究がされ尽くされていない海洋をフィールドに選んだ。
大学に入って誤算だったのは、周りの人たちが魚好きばかりだったことだ。
船上での調査は船酔いもするし、調査機器を1つ回収するだけでも水の圧力や重みがかかって、体力がかなりいる。くたくたになった夜、イカ釣りができると言われてみんな外へ出て行ってしまう。船酔いしていても、イカ釣りを優先させる同級生たちを見て「入る学部、間違えたな」と思った。
もちろん魚好きな同級生たちは、水族館も好き。
一緒に行こうと誘ってもらって、付いていったりもした。
だけど、相変わらずよさはわからず。
同級生たちは、場の空気をよくするため、興奮しているふりをしているんじゃないか、とすら思ったほどだ。
そんな私だったが、あるときから突然「水族館ってめっちゃ楽しいじゃん」と思うようになる。
研究室生活がはじまって、二枚貝とナマコとカニを飼育するようになったのがきっかけだと思う。
「今日は元気かな」「昨日のエサは合っていたかな」と観察するうちに、種類ごとの性格はもちろん、個体ごとの性格もわかるようになってくる。
水族館の生き物たちも、種類ごとに性格がある。
好奇心旺盛だったり、のんびりしていたり、神経質だったり。
さらに時間をかけて見ていると、個体ごとの性格もわかってくる。
とにかく落ち着きがなかったり、マイペースだったりと。
〝 違いがある 〟と気づいてから、生き物との向き合い方がわかるようになった。それが水族館を楽しめるようになった理由だろう。
*
水族館を楽しめるようになった理由は、もうひとつあると思っている。
それは、「自分以外の存在に興味を持てるようになった」ことだ。
大学生の中頃までは、自分を生きるのに必死だった。
他人への興味は、自分への興味の延長線上でしかない。
誰かがそばにいてくれないと、自分に存在価値がないような気がして、とにかく不安だった。私の話に耳をかたむけてくれたら、それだけで誰でもよかったのだ。
だから、その人らしさや個性なんて、見ようともしていなかった。本当の意味で、他人に興味はなかったのだ。
大学院に進学して、友達がみな卒業してしまい、当時お付き合いしていた人とも遠距離恋愛になる。遠距離恋愛の辛さは、パートナーに会えないことではない。誰にも依存せず、自分の弱さと向き合うことだ。
誰かの一部でしかなかった私。まずは人から切り離して、何もない自分を認識することから始めなければいけなかった。何でも持っているように振る舞っていたせいで、現実とのギャップが辛かった。
「あぁ、本当に自分は空っぽなんだな」と現実を受け入れられるようになった頃、今からでも自分の空箱に少しずつ物を集めていくしかないと心を決める。まずは、自分の好きなものを見つけてみることに。それまで、誰かの好きなものを真似することしかできなかったけど、とにかく興味のあることをどんどん始めてみた。
好きなことがたくさん増えた頃、人との違いを恐れなくなる。
自分の存在を否定されるのが怖くて、人と比べてばかりだった私。「こっちが正しいから私もそうするべき」とか「こっちが正しいからあの人は間違っている」とか。そんなことばかり考えていて、人と違うことがとにかく怖かった。
だけど、ひとりでも楽しい時間があることを知り、「私は私」と思えるようになってから、人と自分をしっかり分けられるようになる。人との違いを楽しめるようになったのだ。
それからだ。本当の意味で、自分以外の存在に興味を持てるようになったのは。水族館が大好きになったのも、この頃からなんだよね。対象は人だけでなく、他の生き物たちにも当てはまったみたいだ。
ひとり時間の楽しみかたを知ったこと
誰とも比べることなく、自立できるようになったこと
この2つがあったからこそ、違いや個性の面白さに気づけるようになって、今の私がいるんだな、なんて思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
