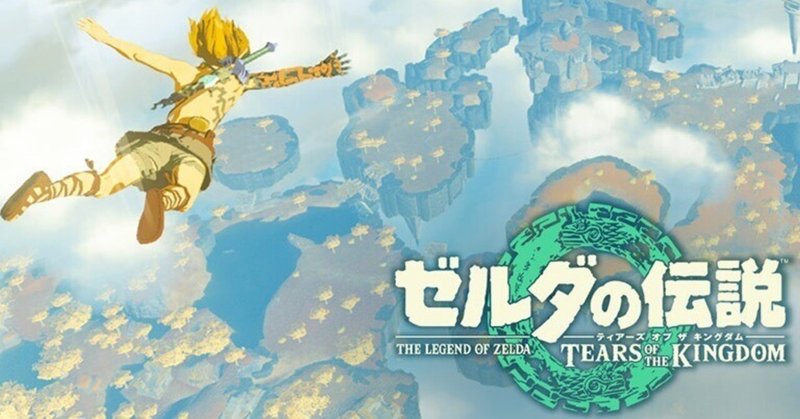
任天堂様のティアキン様 『ゼルダの伝説 ティアーズオブキングダム』を考える(ネタバレなし)
おかしい
それが最初の感想だったなあと。
ものを作る、ということを考えた際に、期間や予算、人員の制約下で作らざるを得ないのが普通。
ティアキンは一般的な制約が外れてるんじゃなかろうか。って思ってしまうほどのゲームの要素があり、完成度があった。
刺さったゲームとか好きなゲームとかは別として、史上最高のゲームと言っても良い出来にあると思った。いや、めちゃめちゃめちゃめちゃ楽しんでます。
・一般的に最高の作品の続編はなんか残念なことが多い
・そもそも前作のレベルが高すぎる
・任天堂は時々やらかす(おもにハード戦略だがSFC→64/Wii→WiiU。ちなみに私バーチャルボーイ持っていた民)
こんな心配ばかりしてました。ただそんなこと、造り手も100も承知でしたでしょうに。
なんで作れるのだろう
任天堂の文化と組織
徹頭徹尾、おもちゃ屋さん。宮本茂さん・横井軍平さんたちが作り上げた文化は、おもちゃを触るこどもの目線をずっと忘れていない。
いかに面白いと感じてもらえる商品を作るかを徹底している、と思う。
そしてそれを許す組織の力もある。年によって売上に浮き沈みがあるとはいえ、利益最優先で動かす必要はない。ソフト・ハードが目立つが、IPも世界に冠する企業。つまり固定収入に近いものがある。資金は潤沢で、トライアルができる。
また強いブランドがある。それは市場とのクオリティの約束みたいなもの。90点台のメタスコアのタイトルを大量に持つ企業はそうそうそうない。
まして史上最高のメタスコアは時のオカリナ。今みたいにレビューサイトが多くなかった時代とはいえ、常にその完成度を突き詰めてきた。
まもらないといけない約束のレベルが高すぎる。
また、ブランドは強いヒトも集める事ができる。1980年代以降盛り上がった任天堂ブランドを幼少期に通った人たちは、今は働き盛りだ。
プロデューサー青沼さん、ディレクター藤林さんのメディア披露が多いが、それ以外にも実際は良い造り手が多いんではないか。
かつ、任天堂自体が独自新規タイトルをバンバン出す体質ではないから既存のものを積み上げ改善し、作るようなウォーターフォール的な大規模開発に向いてる人も集まりそう。
前作の資産
ブレワイは何よりとんでもなく世界中を驚かせたゲームだった。6年経っても売れ続ける異常なタイトル。
ゼルダのアタリマエ、オープンワールドのアタリマエ、ゲームのアタリマエ、そうしたものに挑んで超えた。
例えば、、、
・ゼルダのアタリマエ:難しい謎解き、リニアな展開、アイテムでルートがひらくレベルデザイン。ビンとかフックショットとかお馴染みアイテム。緑の服。
・オープンワールドのアタリマエ:オープンといえどもハリボテワールド。行けないとこは行けない。マーカー追いゲーム
・ゲームのアタリマエ:AAAタイトルはリアル、ビジュアル至上主義。また制作者の用意した物語、ロジックに従わせる。
個人的にはそんな感覚。超えたものはまだまだあると思うけども。
結果ゼルダの30年以上の歴史の中で、一般評価も一番ついてきた。SNSで感想や面白いネタを展開しやすい時代と内容がマッチして側面もありそう。
めっちゃうまいけど個性あって敷居が高い老舗蕎麦屋が、リニューアルして洒落て技術はそのままにラーメンとそばを掛け合わせた新メニューも提供しだして、超バズる的な?うーん、例えがうまくない。
評価された成功体験、ゲームクリエイターからの評価、SNSやYouTube一般の感想、反応が次の方向性を読みやすくしたと言えるのだと思う。
作る際には、おそらくコストがかかる世界観・コンセプト、方向性、マップデザインなどはゼロイチでない分、決まっている。その分、どういう方向性の遊びを作るかだけを研ぎ澄ますことはできたんだろうなと。
もちろんゼロベースじゃないから制約も大きいし難しい面もあるのかも知れないけれど。エンジニア達やデバッガーが物凄く頑張ったのかもな。
一般に、難しく苦しい作業は働く者にとって敬遠されるものだが、史上最高のゲームシリーズという自負がその途方もない技術的な難しさを乗り越えるモチベーションを生んでる気がしてる。
なんでこんなにおもしろいんだろう
仕事に関する理論だが、ハーズバーグの二要因性理論では、「達成すること」「承認されること」「仕事そのもの」「成長」などに動機づけられる=モチベーションを感じる。
こうしたことは、ゼルダでは頻繁に起きてる気がする。これらから、ヒトの根源的欲求に訴求していると思ったので、ちょっと当てはめて考えてみる。
承認される
特にティアキンからの「承認」の度合いは、群を抜いている。
学校教育で「自分ではあってるつもりだけど、なんでこれでバツなの?」ってがっかりした経験って多くの人があるんじゃないか。仕事においても、文脈を読み切れないと、往々にしてダメになる事がある。
一般的なゲームをクリアすることも、その文脈をクリアすることが基本的なもの。
でもゼルダは個人の発想や課題を、好きなように解かせてくれる。しかも直感的に。「直感的になんかして評価される」なんて、小さい子どものときに親からしてもらえるくらいで、その後の人生ではどんどん難しくなる。
直感的に試して、上手いこと行かないかもしれないが、やっていれば正攻法でなくても次に進み、短い祠やクエストでの成功がある。自分の考えへの承認を感じさせるレベルデザインがとても上手い。(ほんとに無理なら避けることもいくらでもできる)
あとは、SNSでも承認が得やすいゲームデザインでもありますよね。
達成する
あらゆるゲームはこれがある。ただし簡単に達成できることには意味がなく、達成できるかわからないことを達成することがモチベーションになる。いわゆるコンフォートゾーンでもパニックゾーンでもなく、チャレンジゾーンにあるということ。コンフォートゾーンが続く場合は「作業ゲー」になる
ゼルダをやってて「これ本当にうまくいくのか?これでいいのか?」→「やってみたらなんかできた!!」みたいなことはたくさん出くわす。
この絶妙な味付けが、秘伝のタレ的に効いている。
おそらく自然な誘導の作り方もとても上手。プレイヤーの認識の手順の設計や、周囲を探せばなんか見つかることで、着想が生まれやすくなっている。うまく設計されたデザインによって、自ら達成を感じられるようにな
っている。(どの手順で攻略して手持ちアイテムなくても基本的にはOKだし。)
自由すぎても何すればいいのか不安に感じるもの。ゴールが明示されない、取っ掛かりが明示されない、ベーシックなルールも教えてもらえないというのが例か。
ゲームのベーシックなルールの伝達は数時間のチュートリアル。
チュートリアル=世界の文脈を理解する部分はRTA勢が足掻いてもスキップできない作りになってる。
基本ルールをガチガチに教えこんで、後は自由に動いていい。
その後も大〜小のゴールが、自由に動いた後に出没する。難しいものは多少のヒントがある。そこが本当に丁寧に丁寧に作られてる。
もちろんゴールに沿わず自由にやることも選択できる。
最初以外に強制力は一切働かない。自由だからこそ、逆説的にやることは主体的に選んだ状態が生まれる。主体的にやることを判断し、頭をひねってクリアし、達成感を得られる。
言われたからやりました、感が極めて少ない作りになっている。選択肢沢山なので、みんなゼルダ助けに行かなくなっちゃう。
仕事=ゲームプレイそのもの
動かしていて楽しい、のはその証明かと。
景色がきれい
空を飛ぶのが楽しい
飛行機で飛びたい
ロケットをぶっ飛ばしたい
時をコントロールしたい
そうした誰もが憧れる、心地よくなる気持ちには常に満ちてるように作られてる。
ゼルダのブレワイ・ティアキン「探索が楽しい」というのはよく言われること。ただの探索だけならばしんどいが、探索すれば何か見つかり興味が生まれ、何かを得、悩みながら達成する。そうしたループが生まれ続ける。
余談だけど、ティアキンはブレワイよりハテノ村の山が近く感じた。ブレワイを起動してみると、確かに山が霞がかってて遠く感じる作りになってた。
ブレワイはシーカータワーや山の上からパラセールで発見・移動できる範囲を基本とする単位で、横の広がりを作る演出になってて、ティアキンは空から見渡せる状態を作る=空と地上の行き来と移動と発見を感じられる演出の仕方なんだねぇ、とか思った。
成長
ゼルダは「プレイヤーが成長するゲームである」。
これはずっと変らないコンセプト。経験値はプレイヤーの中にたまっていく。いわゆるPDCAを回すことで、成功体験を積み、それが蓄積されて、ゲームが進んでいく。経験値ではなく経験知が積まれていく。
ブレワイの話ではあるが序盤では絶望的なガーディアンが、経験知を得た後では、序盤の装備でも勝ててしまったりする。そうしたことがたくさん転がっている。
色々書いてみて思うのが、あの4つの能力にすることは、どうやって決めたんだろう。ということ。
とことんまで絞り込まれていて、かつ拡張性を生み出している。
それも、前作の能力より圧倒的に有用。ブレワイでは個人的にはほとんど使ってなかったしな。コログとか祠とか用って感じ。あまり本質的ではない能力って、前作ですらある。
それが今回は4つすべてが有用な設計になってる。
もしかすると、それができたのは前作の遺産なのかも。
藤林さんが言ってた「前作の世界でまだできることがある」という、作った世界がポテンシャルをまだまだ持っていたことがあったこと。それを活かしつつ、空にも話を広げるというコンセプトがあったこと。
また前作の批判点も回収できていたこと。
やりたい遊びの形と課題が明確だからこそ、逆算で作れたのか。としても、途方もない開発作業を生み出す道を選んでるのはえげつないけど。
どうやってあの4つの能力に意思決定したのかは、誰かインタビューしてほしいなぁ。もっとあって絞ったのか?どういう順番で決まったのか?
マジックハンドから決まっていった気がするけど。
かなり想像を含みながら個人的な角度から考えてみた。
人の心を動かすことの仕組みづくりの多層さがすごい。
こんなの作れるなんて、ただただすげえなぁ。って心から思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
