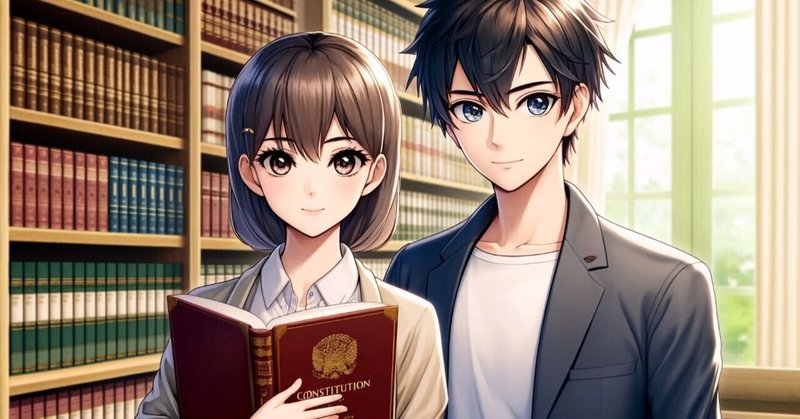
日本国憲法を勉強す📚(#2)〜三権分立〜
先日、【 日本国憲法を勉強す📚(#1)〜憲法は僕らの味方〜 】を投稿しました👇
日本国憲法は、私たちの権利を守るための基盤となるものです。現在、多くの人々が感じている漠然とした不安を解消するためにも、憲法の理解は非常に重要です。
しかし、政府は憲法改正を検討しており、その改正が行われれば多くの問題が生じます。特に、私たちが当たり前のように享受している基本的人権、たとえば言論の自由や表現の自由が制限されるリスクがあります。
憲法改正が具体的に何を意味し、何が変わるのかを理解するには、憲法についての知識が必要です。この機会に深く学んでいきたいと思っています。
こちらの動画は、今年の3月3日に行われた、深田萌絵氏と秋山弁護士による【憲法改正反対の勉強会】になります。今回も、この動画の文字起こしを元に自分なりにまとめてみました。16分25秒からの内容について語っていきます。
憲法はなぜあるのか?なぜ必要なのか?

憲法の存在意義は「制限規範性」にあります。これは、憲法によって国家権力の行使を制限し、その乱用から個人の人権を守ることを指します。「規範」はルールや法律を意味し、「制限」は国家権力を制限することを表しています。要するに憲法は、人間が生まれながらにして持っている「個人の尊厳」「人格の尊厳」を保護するため、国家権力からこれらを守ることを目的としているのです。
人権とは、「人間が生まれながらにして持っているもの」と、現在の憲法は謳っています。これを「天賦人権」と言い、天や国家によって与えられたものではなく、人間が本来から持つ権利なのです。
私たちは、憲法を「国民が守りなさい」ではなく「国家権力が守りなさい」という、国家権力を縛ってる法だということを、知ることが重要です。
なぜ憲法が生まれたのか?

元々、世界中には各地の王様などが権力を持っていました。良い王様もいれば、悪い王様もおり、悪い王様はしばしば政治を理由に国民にさまざまな負担を強いていました。これに反対して市民たちが立ち上がり、自分たちの権利の尊重を求め、徐々に国家権力を削減していったのです。
元々は一つの強大な権力があり、国民はその権力に従っていました。この中で直接国民と関わる行政権から立法権を分離し、「行政は法律に従わなければならない」という縛りをかけました。しかし、ただ法律が存在するだけでは、その法律が守られなければ権力の乱用は止まりません。そのため、政府の権力からさらに司法権を分離し、裁判所が行政が法律に従って行われているかをチェックするシステムが確立されました。これが三権分立です。
三権分立
⇩
国家権力を以下の3つに分けて、
それぞれを別の機関が分担する仕組み
・法律を定める「立法権」
・法律に沿って政策を実行する「行政権」
・法律違反を罰する「司法権」
憲法の体系について

憲法の発想は、国家権力をなるべく非行率に行使させるために制約をかけて、国家権力を乱用しないように、非行率なシステムを作るというものです。
憲法の体系
・「個人の尊厳」が目的
・「人権規定」は、その具体化であり手段
・「統治規定(三権分立)」は、制度的な担保
「個人の尊厳」は、私たち一人一人が安全に、自由に、そして幸せに暮らすためにあります。それを支えるために「人権規定」が設けられています。私たちが思ったことを言えなかったり、言いたいことを表現できなかったら、真の意味での幸せは実現されません。このために「表現の自由」が不可欠です。憲法13条の「個人の尊厳」を保護するため、憲法21条という「表現の自由」があるのです。他の「人権規定」もこれを支える役割を果たしています。
そしてさらに「統治規定」という三権分立に関する規定があります。これは、国家権力が効率よく動作しないように、制度的に権力の行使を制限するために設けられています。まずは「個人の尊厳」を目的とし、「人権規定」はその具体化および手段であり、「統治規定」はこれらを保障する制度的な枠組みとされています。
人権規定について

「人権規定」には様々な規定がありますが、その中でも「消極的自由権」と「積極的自由権」がります。
「人権規定」
・「消極的自由権」
国家権力によって妨害されない権利
表現の自由、思想・良心の自由、学問の自由等
・「積極的自由権」
国家権力に行為を求める権利
生存権(25条)、教育を受ける権利(26条)、の一側面等
消極的自由権
「消極的自由権」とは、国家権力によって邪魔されない権利です。
たとえば、私たちが自由に集会や発言をしているとき、警察が来て中止させるよう命じたら、それは私たちの活動を妨げることになります。このように、国家権力によって妨害されない権利が、学術的には「消極的自由権」と呼ばれます。
ちょっと分かりにくいのですが、消極的というのは「~するな」という意味です。たとえば、「表現の自由を国家権力に守ってくださいって」と、お願いするのではなく、むしろ国家権力に「邪魔するな」ということなのです。
同様に「思想・良心の自由」では、私たちが自由に思想し、自由に良心を持つことに対して、国家権力が「介入するな」ということです。逆に、江戸時代の踏み絵は、人々の内面を強制的にチェックする行為であり、現代の憲法19条における「思想・良心の自由」に反する行為と言えるでしょう。
「学問の自由」についても、国に「学校を建ててください」と依頼するのではなく、親が子どもを教育する自由、または自主的に集まって教育活動を行う場合に、国家権力が介入しないようする権利です。「この方法でなければいけない」と国が指定することなく、教育活動に干渉されないことが保証されています。
積極的自由権
「積極的自由権」とは、国家権力に行為を求める権利です。
現在の憲法は、資本主義と自由競争を前提にしており、国民が自由に経済活動を行うことが経済発展につながるとされています。しかしこのシステムでは、競争に適応できない人々が出てくることもあります。これらの人々が適切な生活を送ることができなくなると、「個人の尊厳」は保たれないことになります。それを補うものとして、国家に行為を求める権利というのがあるのです。
この代表が「生存権」と呼ばれるもので、憲法25条に「…最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されています。
この「生存権」は、私たちが生きていくことを国家権力によって邪魔されないという消極的な側面(消極的自由権)と、経済的に自立が困難な場合に国に保護を求める積極的な側面(積極的自由権)を持っています。「生活保護法」はこの生存権を具体化した例であり、経済的に自立できない人々が国から支援を受けることを可能にしています。
ただ、「生存権」や「教育を受ける権利」のように、国に積極的な行動を求める権利が存在しますが、これらは例外です。積極的自由権が増えるということは、国が私たちの生活に深く介入してくることを意味します。その結果、国の権力が生活に入り込むほど、その乱用の危険も増大します。憲法の本質は「邪魔するな」ということであり、この原則を忘れてはなりません。
つづく・・
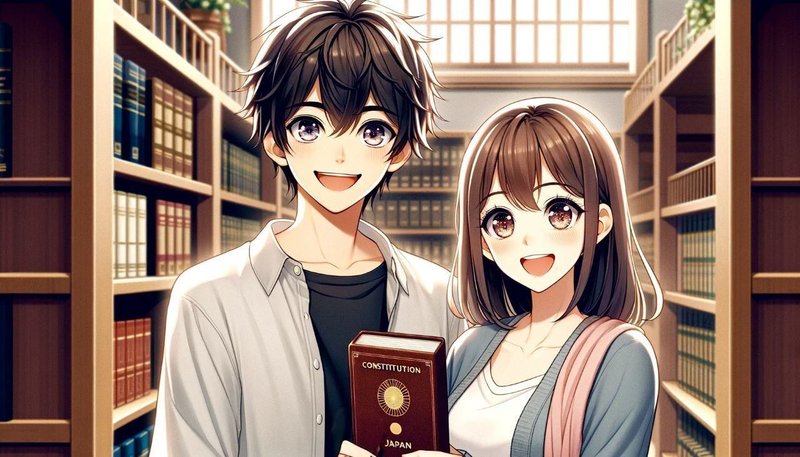
今回はここまでです。
次回は、動画の26分27秒の「表現の自由(憲法21条)」から進めていきます。
憲法の勉強は始めたばかりで、まだ聞きなれない用語や表現に慣れていないため、記事を書くのに時間がかかります(笑)。しかし、このnoteでの投稿を目的として勉強すると、単に勉強するよりも捗りますね 😁
次回も深い学びを続けていきます。
👇 kindle出版しています 👇
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
