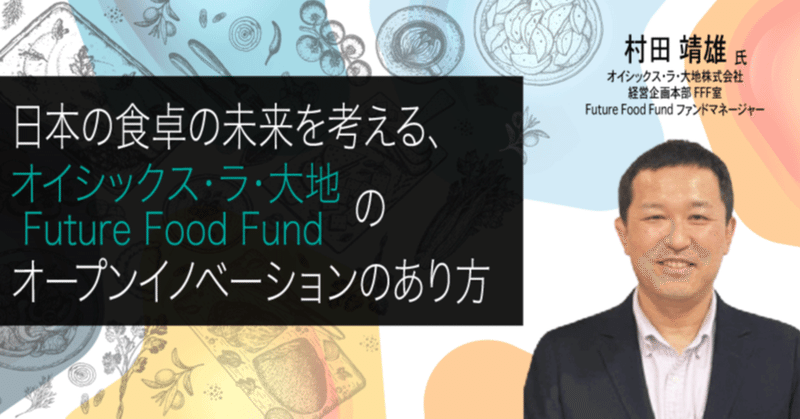
日本の食卓の未来を考える、オイシックス・ラ・大地(Future Food Fund)のオープンイノベーションのあり方
近年、国内スタートアップ投資「1兆円市場」への期待が高まっており、スタートアップ、VC、CVCの存在も世間に認知されるようになりました。一方で、諸外国に比べるとスタートアップへの投資額や起業数などで遅れを取っています。
私たちケップルは、オープンイノベーションを促進するきっかけを作ることで、スタートアップエコシステムに関わる人たちが増え、その結果スタートアップが資金調達や協業に対してより前向きに取り組んでいくサポートができればと考えています。
今回は、8月に開催したウェビナーのレポートをお届けします。オープンイノベーションやCVC、食領域に関する理解をぜひ深めていただける内容となっておりますので、ぜひご覧ください。
村田 靖雄氏
オイシックス・ラ・大地株式会社(代表:髙島宏平、以下オイシックス)
経営企画本部FFF室
Future Food Fund株式会社 ファンドマネージャー
らでぃっしゅぼーや(株)、オイシックス(株)の双方で商品開発に関わる業務に従事。(株)リクルートとのJVや、Oisix香港事業での仕入れ等にも携わり、2014年より、店舗事業部にて事業管理と商品開発、2018年よりフードテックファンドセクションにて、主に農業分野のソーシングと、出資先の支援を担当。
Future Food Fundでは、アグリテック分野のソーシング経験を生かし、出資先アグリテック・フードテック案件の成長支援、LPとの窓口を担当。あわせて、オイシックスECのクラフトマーケット部門の商品仕入れに従事。

スタートアップ向けインキュベーションファンド『Future Food Fund』誕生
ー まずオイシックスの取り組み内容や事業についてお聞かせください。
村田氏:オイシックス・ラ・大地株式会社は、元々2000年に創業したスタートアップです。ネットの宅配事業と言われる食材のサブスクリプションサービスを中心に提供しており、今では海外を含めて様々な事業を展開しております。
その中で、「より多くの人が、より良い食生活を楽しめるサービスを提供する」というミッションを元に、インキュベーションファンドとしてスタートアップを支援するために、Future Food Fundというオイシックスの完全子会社の投資会社を設立しました。
私たちは、通販を得意としていますが、インキュベーションしていくためのノウハウがないため、パートナーとして食品企業を中心に14社(オイシックスを含む)からLPとして出資いただき運用しています。
現在、20億という小さな規模で1号ファンドを運営しており、これから2号ファンドの設立を想定しております。
ー 最初はベンチャー投資から始められていますよね。
村田氏:はい、2016年にFood Tech Fundというファンドを立ち上げて、ベンチャー投資をしておりました。
元々スタートアップだった我々は、当時「ネット上の八百屋」を運営していました。しかし一つの事業だけで会社を拡大をするのは難しいということもあり、他のスタートアップの知見を生かしながら事業展開していくことを決め、ベンチャー投資を始めました。
良いスタートアップに出会えるアメリカのエコシステムを日本版で再現
ー その後、ベンチャー投資をするにあたって、どのような課題が出てきましたか?
村田氏:BSからの投資を加速している時、2年間赤字の場合減損というルールに該当したことで、減損の問題回避を解決する必要があったのは大きな課題です。それに並行して大地を守る会、らでぃっしゅぼーやの経営統合を進めていたため、少額投資が縮小してしまいました。
その他、投資をしたいと思える食関連のスタートアップに出会えないという問題が当時ありました。そのため単純にファンドを作ればいいという訳ではなく、いいスタートアップに出会える環境を作るという前段階の活動も含めて取り組まななければならないという課題がありました。
ー その環境は何を参考に作られているんですか?
村田氏:アメリカを参考にしました。アメリカでは、大学発スタートアップに対してエンジェル投資が行われ、インキュベーションされます。ベンチャーキャピタルが投資することでスタートアップが大きく成長し、エグジットするというエコシステムが整備されています。その結果、より良いスタートアップを多く輩出してきました。
日本でも同様のスタートアップエコシステムを作ることで、より優良なスタートアップが増えていくと考え、弊社では成長支援と事業提携に力をいれています。

JR東日本と提携、食品工場併設のフード特化型シェアオフィス「Kimch, Durian, Cardamom,,,(K,D,C,,,)」
ー 成長支援や事業連携に関する具体的例を教えてください。
村田氏:新大久保の駅ビルに、2021年にJR東日本さんと協業して、FoodLabo「Kimch, Durian, Cardamom,,,(K,D,C,,,)」(キムチ,ドリアン,カルダモン,,,)というちょっと変わった名前のフード特化型のシェアオフィスを開設しました。
このオフィスは、アメリカで出会った「KitchenTown」というインキュベーション施設の日本版です。KitchenTownはWeWorkの食品版とも言われており、食関連のスタートアップが成長するにあたって必要な場所や人との出会いを提供し、メンターと一緒に仕事ができるような環境を作っている施設になります。
ここには、日本の中小企業並みの食品工場が併設されており、そこをスタートアップが自由に使うことができます。最初に起業した段階で工場に投資したり、何か製造委託しなくても自分でその施設を利用して作った商品をそのまますぐに販売することができるのです。

ー 施設を始めるにあたって、課題はありましたか?
村田氏:資金調達が大変でした。アメリカでこのような施設を作る場合は、「寄付感覚」で資金調達ができていたと思いますが、日本ではこういった施設の重要性がまだ理解されていなかったこともあり、資金調達が困難でした。
新型コロナウイルス感染拡大の影響によりLP募集苦戦するも、モスバーガー、SMBCベンチャーキャピタル等有名企業が参画
ー 設立時のLPからの資金調達は難しいイメージを持っていらっしゃる方もいるかと思いますが、実際はどうでしたか?
村田氏:新型コロナウイルス感染拡大が始まる直前の2019年に組成したこともあり、LPの募集には大変苦労しました。
しかし、モスバーガーさんとSMBCベンチャーキャピタルさんが加入されたことで、ある程度信頼や期待を獲得でき、その後のLP募集に繋がりました。
モスバーガーさんは野菜の仕入れ先が近いこと、また事務所が近所だったため、たくさんお話させていただけたことで、興味を持っていただけました。
また、SMBCベンチャーキャピタルさんはオイシックスへのベンチャー投資をしていたため、食関連のソーシングを一緒にしていこうと言っていただき、加入が決定しました。
ー LP募集後も課題があったとお伺いしておりますが、具体的な課題を教えてください。
村田氏:自社の方針を踏まえつつ、参画しているLPの方針も考慮して投資先を選ぶ必要がありました。また、投資先との協業も1対nより、n対nを意識して繋げていく、まさにオープンイノベーションをしながら、投資先とLPをしっかりと繋げていくことも課題でした。
K,D,C,,,内、LP紹介、イベントによるさまざまな協業支援からスタートアップへの価値提供
ー 協業の具体例として先ほどK,D,C,,,(FoodLabo)をあげてくださいましたが、K,D,C,,,内では実際にどのような協業が行われていますか?
村田氏:K,D,C,,,は食のコワーキングスペースであり、売り場があることが大きなポイントです。
通常、スタートアップの商品には与信などさまざまな問題があり、大企業はすぐに買売したがりません。そのため、K,D,C,,,では商品を売るルールや安全規定などの仕組みを優先的に作りました。この仕組みにより、多くのスタートアップが実際にK,D,C,,,で物を作り、販売できるようになりました。
こうすることで、大企業はスタートアップから直接話を聞き、実際の商品やサービス、その販売状況などをその場で確認することができ、その後の協業に繋がっています。現在30〜40件のスタートアップがK,D,C,,,にて商品の作成、販売などを行っています。
ー 協業以外で、スタートアップに対してどのような価値提供を行っていますか?
村田氏:クラフトマーケットとよばれるイベントを開催することで、スタートアップ同士の接点や、LPと投資先全体の交流を促していたり、K,D,C,,,に参画している会社さんと一緒に、ソーシング先や食のピッチイベントなどを行っています。このようなイベントはスタートアップだけでなく、我々のネットワーク作りやソーシング活動にも繋がりますし、皆で情報発信することでPRも広がります。

LPの得意分野を活かした協業事例
ー Future Food Fundの投資先とLPの事例も是非教えてください。
村田氏:他のLP x 投資先の協業事例としては、離乳食のMiLさんとセブンイレブンさんです。
セブンイレブンさんでは離乳食を販売しないため、グループ会社のアカチャンホンポさんに商品販売をしてもらいました。また、豊田通商さんに製造などの企画を受けてもらうことで、シナリオを作ることをお手伝いいただきました。
また、MiLさんは弊社、オイシックスとの協業も成功しています。弊社のベビー&キッズコースという離乳食を販売しているコースと協業し、MiLさんの離乳食をオイシックスにて売り、年間売上1億を出しました。
我々の会社規模の場合、ベビーフードは隙間商品となるため、商品開発チームも手をつけずに放置してしまっていました。この隙間にMiLさんが上手に開発チームとして入ってくれたことで成功しました。
他にも、LPのJALUXさんには投資先のHiOLIさんと協業していただきました。
コロナの影響で行き先がなくなった宮崎のマンゴーをアイスクリームにし、JALUXさんと弊社で販売しました。このように、我々流通会社は物を作って売ると言うのが得意なため、協業しやすいです。
出資ポイントはいかに「美味しい」を極めているか
ー そのようなイベントで出会ったスタートアップに出資をする際のポイントがあれば教えてください。
村田氏:弊社は「オイシックス」という会社だけあり、「美味しさ」が一番大事だと考え、出資先を選んでいます。フードテックや代替肉は確かに環境に良いかもしれません。しかし、美味しくないと消費者は買わないと思いますので、「美味しさ」というところを実は一番重視して検討しております。
例えば、植物肉の開発・製造・販売を手がけるグリーンカルチャーの「Green Meat(グリーンミート)」は、大豆たんぱく等を原料とした動物性原料不使用の植物肉ですが、美味しいだけでなく、どんな料理とも相性がよい商品を提供しています。
また、美味しいものを提供している企業はもちろんのこと、美味しさを追求するためのサービスを提供する企業にも出資をしています。
例えば、農業IoTソリューションを提供するファームノートさんは、農家さんに対してFarmnote Colorというサービスを提供している会社です。そのサービスを導入している企業の牛乳がすごく美味しかったことが出資の決め手になっています。農家さんにはやはり美味しいものを作ることに集中してほしいため、そこをサポートする技術にも積極的に投資しています。
今後は機関投資家を入れ、規模を拡大し出資していきたい
ー 最後に、現在2号ファンド組成中とお聞きしておりますが、1号の経験から今後に活かしたいことはございますか?
村田氏:まず、1号ファンドは初めてのファンドだったため、手におえるようにと考え、規模を20億と小さめで始めました。2号ファンドは、もう少し大きな規模で進めていきたいと思ってます。
また、1号ファンドに出資いただいている多くが事業会社になるため、2号では機関投資家の方々にも加入いただくことも視野に入れながら、さらに大きな規模の投資も幅広くできるようにしたいなと考えています。

ー 村田さん、本日はお時間いただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
