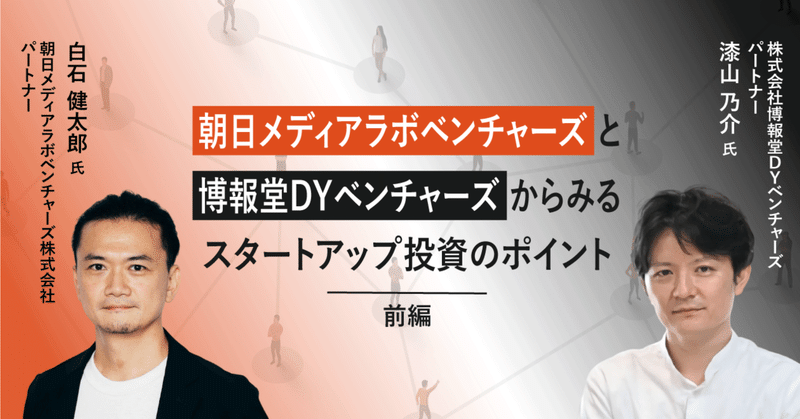
朝日メディアラボベンチャーズと博報堂DYベンチャーズからみるスタートアップ投資のポイント【前編】
私たちケップルは、オープンイノベーションを促進するきっかけを作ることで、スタートアップエコシステムに関わる人たちが増え、その結果スタートアップが資金調達や協業に対してより前向きに取り組んでいくサポートができればと考えています。
今回は、2月に開催したウェビナーのレポートを2回に分けてお届けします。朝日メディアラボベンチャーズと博報堂DYベンチャーズ。 いずれも事業会社発ではありますが、ファンド設立の経緯や形態、運用方針も実は全く異なる2社。そこで今回は、朝日メディアラボベンチャーズの白石氏と博報堂DYベンチャーズの漆山氏をお招きし、両社の取り組みについて深掘りしました。
前編となる今回は、CVC設立の背景や立ち上げ当初に取り組まれたことなどについて詳しく伺っています。ぜひご覧ください。(後編はこちら)
▼スピーカー紹介文
■白石 健太郎 氏
朝日メディアラボベンチャーズ株式会社|パートナー
2001年朝日新聞社入社。同社販売局にて600店以上の新聞販売店のエリアマネージャーを担当。2013年新規事業部門のメディアラボに参画。2017年より朝日メディアラボベンチャーズ設立に携わり、現在は2号ファンドを運用中。日本と北米のスタートアップを投資対象としている。
■漆山 乃介 氏
株式会社博報堂DYベンチャーズ|パートナー
博報堂DYグループにおいて、メディアビジネス開発やベンチャー投資を推進。また、同グループの社内公募型ビジネス提案・育成制度である「AD+VENTURE」の審査員及びガイドとして複数の新規事業開発・立ち上げを支援。同グループへの参画以前は、ベンチャーキャピタルにてパートナーとしてベンチャー投資業務に従事。それ以前には、大手人材サービス企業で複数の新規事業・サービス開発を経験。
数々の成功や失敗を経て培ってきた知見
ー CVCが設立された背景と活動方針についてお聞かせください。
白石氏:当社はCVCを立ち上げて6年目を迎えようとしています。2017年に1号ファンド、2022年に2号ファンドを設立しました。1号ファンドではシードからレイターまでオールステージ扱っていたのですが、2号ファンドではシードからミドルくらいを中心に国内と米国に投資を行っています。
設立の背景としては、まず2013年に朝日新聞社で新規事業部門が立ち上がりました。当時から新聞事業以外の新しい売上をどう作っていくのかが課題となっていて、2つのミッションがありました。一つは自分たちで事業を創出すること。もう一つはスタートアップや事業会社と連携して新たな事業を作るというものでした。いきなりスタートアップ投資はできなかったので、当初はLP出資から開始しました。しかし、なかなか欲しい情報を得られなかったので、2014年から新聞事業とシナジーがありそうなスタートアップに直接投資をしていく方針に変更しました。

漆山氏:博報堂DYベンチャーズは2019年6月に設立し、HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUNDを組成してCVC活動を行ってきました。ファンドサイズ100億となっていますが、これはいわゆる中期経営計画期間の中でお預かりしている拠出額になっており、組合をいくつかに分けながらファンドを運用していくというスタイルです。支援先も今50社ぐらいに迫ってきました。投資の仕事の山も谷もいろいろなことを経験してきて、日々七転八倒しています。そういったところをお話しできればと思っています。

ー 朝日メディアラボ立ち上げ当初のスタートアップ投資は、振り返るとどのような状況でしたか?
白石氏:2013年頃は事業会社による直接投資は少なかったと思います。そこに突然、朝日新聞社が投資をしようとしても怪しまれる部分がありまして、「なぜ新聞社が投資をするんだ」と言われることもあれば、逆に「朝日新聞という名前が入っていてくれた方が信頼できます」と言っていただけることもありました。CVCが盛況な現在とは違い、「どうして朝日新聞がうちに投資をしたいのですか?」という説明を求められることが結構ありましたね。
ー これまでのスタートアップ投資において失敗談があれば教えてください。
白石氏:私は元々新聞販売店のエリアマネージャーのような業務を行っていました。販売店にはいわゆる「アイドルタイム」という販売店の社員の方が稼働していない時間帯もあったので、そこを活用したスタートアップに投資をして、販売店の方を巻き込んでいきました。最終的に関東を中心とした新聞販売店100店舗ぐらいで実施をしました。しかし、当時投資した先がシード期のスタートアップだったので業務のオペレーションが毎週変わるような状況でした。そのため、販売店の社員の方も毎回作業を覚え直す必要があったり、販売店の経営者の方も「スタートアップって何?」と混乱していく中で、「本社が言うのでやっているけど、なんだかよくわからない」という厳しい意見もいただきました。一方、販売店によって提供されるサービスの質にかなり差が出ることもあり、お客さまに対して均質のサービス提供ができない点が課題となっていきました。結果として満足するサービス提供をできない販売店も増え始め、最終的には取り扱い店がゼロになるという状況になってしまったのです。販売店をしっかりと巻き込めず、うまく継続できなかったというのが自分の中の失敗体験となっています。
ー その後どういう形でCVCの立ち上げの方に至ったのですか?
白石氏:その後シナジーありきで投資したいスタートアップがいても、その組み先となる部署との連携がなかなかうまくいきませんでした。ちょうど投資の進め方を模索していた頃に、創業3年目のスタートアップをM&Aする機会を得ました。M&Aは少額出資よりもあからさまにシナジーを求められる部分もあり、関連する部門をしっかりと巻き込むことができました。それ以降、会社として戦略的投資のM&Aを中心とするチームと、私たちのように周辺領域に純投資するチームの2チームに分かれることになりました。一方は本体の経営企画室として機能し、一方が別会社として独立したのが私たちCVCとなります。この体制は今も続いています。元々同じチームだったので、定期的にお互いの情報を共有してうまく連携できていると思います。
ー これまで、さまざまなM&Aや出資をされていて、以前はアクセラレータープログラムも実施されていたんですよね。
白石氏:そうなんです。そこが私たちの転換期になったと考えています。他社さんの見よう見まねでアクセラレータープログラムを実施しました。今ではもう絶対やりたくないですが(笑)、当時は6ヶ月間アクセラレータープログラムの伴走をしていました。スタートアップ投資では、月1回の株主定例しかないのに対し、アクセラレーターでは週1回1時間、合計24回(月4回×6ヶ月)のかなり深いコミュニケーションを短期間で取ることができます。その結果、スタートアップの人たちがどう動くか、またプレゼンで言っていたことが本当にできているかどうかなど、どういう点を注目して見ておくとよいかというナレッジを蓄積できました。自分たちで独立できた強みになっていると思います。
少額投資でもまず行動を起こすことで得られる学び
ー これからCVC立ち上げられる方々に向けて、自分たちに合うかたちを見つけていくためのアドバイスをするとしたらどのようなポイントでしょうか
白石氏:金額を少額にしてもいいので一旦投資をしてしまうのがいいと思います。最初だと数千万とか大きな金額を投資しなければいけないのではないかと考えてしまうと思います。しかし、スタートアップ側も事業会社と一緒に組みたいというときには、そんなに金額を求めてない場合もあったりするので、少額でも株主になってその中にしっかり入っていった方が学びは多いです。スタートアップ投資についてご相談を受けたときは「少額でもいいのでまず投資したほうがいい」とお伝えしています。
ー 博報堂DYベンチャーズはこれまでもグループ全体でさまざまなスタートアップとの関わりがあった中で、一番最初のCVC立ち上げに向けた起点はどのようなものでしたか?
漆山氏:博報堂DYグループには、博報堂や博報堂DYメディアパートナーズ、大広、読売広告社、DACなどさまざまな事業会社が存在しています。その中で各社とも個別に投資活動を行っていました。当時課題だったのは、いかにスピード感を持って起業家と向き合えるか、ということでした。私にはシード系VCファームでの投資経験がありましたので、起業家にとって資金調達はいかに重荷で早く終わらせるべきものであるかは身をもって感じていました。こちらが当事者意識と素早い意思決定構造を持たないと、起業家からすれば優先順位は下がってしまいます。そのような中で、スタートアップに出資したときに協業する現業部門を巻き込んでいく必要があります。2017年頃は、オープンイノベーションの気運がやっと出始めたぐらいで、それがあまり必然性を持たないような空気感があったので、かなり時間がかかっていました。1件投資するのに半年、1年ざらにかかってしまう状況で、「これだとスタートアップエコシステムの中で存在感を出すのは難しい」という問題意識がありました。
ー 漆山さんご自身が入られたときはCVC設立が決まっていたわけではなく、入社してからCVC立ち上げに動かれたということですか?
漆山氏:そうですね。入った時はスタートアップ投資の座組みは全然決まっておらず、手探りでした。2年程模索を続ける中で、2019年に5ヵ年の新しい中期経営計画が始まり、そこで外部連携によるイノベーションの加速という方針とともにCVCをスタートさせることができました。
協業先行よりも新しい良いビジネスを作ることに注力
ー 関係者がかなり多い中で、立ち上げのご苦労もあったかと思いますが、振り返られたとき、やはりタイミングも重要だったと感じられていますか?
漆山氏:タイミングは大事だったと思います。やらなければいけないと社内でも多くの人が感じていたと思います。広告領域もメディア領域だけでなく、得意先もスタートアップとの協業によるイノベーションの芽は出始めていました。ただそれは目に見える動きで、それを大きな流れの中でどういったタイミングとストーリーで具体化させていくのか、振り返るととても地道な作業の積み重ねでCVC設立のリアリティーをつくることが大切だったのだと感じます。
ー CVCを立ち上げて、実際に出資検討や出資した後の取り組みなどを行う中で見えてきたことを教えてください。
漆山氏:CVCなので、やはり協業で何ができるのかというのを考える必要があります。しかし、本当に協業できるところがあるとすれば、投資しなくてもよいというのは、よく言われている話です。協業の在り方にもよるのですが、むしろ投資が協業の邪魔になることもあるわけです。
意義のあるビジネスや技術に、博報堂DYグループのケイパビリティを使ってもらって伸びていくことができるのであれば、手の込んだシナジーを考えることは不要だとも思います。投資と協業の両輪が上手く噛み合うような中長期の展望と関係性を共有できるか、というのが肝要だと感じています。そのベースがあれば、お互いの波長や事業成長のタイミング次第で協業が一気に深まるケースも出てきています。
次回後編では、スタートアップ投資のポイントや今後の取り組みについて伺っていきます。ぜひご覧ください。(後編はこちら)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
