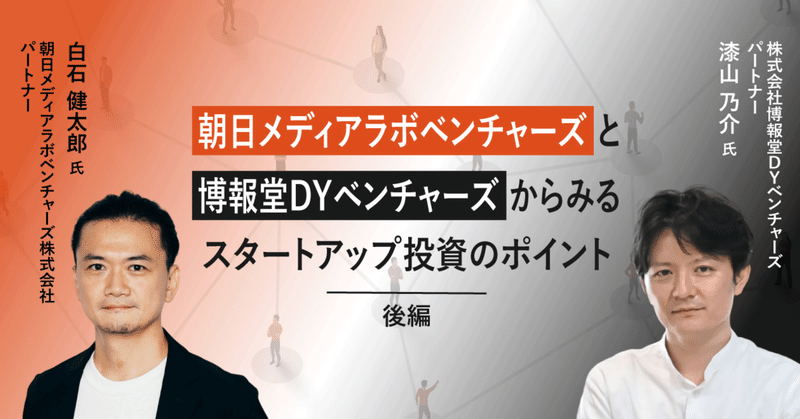
朝日メディアラボベンチャーズと博報堂DYベンチャーズからみるスタートアップ投資のポイント【後編】
私たちケップルは、オープンイノベーションを促進するきっかけを作ることで、スタートアップエコシステムに関わる人たちが増え、その結果スタートアップが資金調達や協業に対してより前向きに取り組んでいくサポートができればと考えています。
今回は、2月に開催したウェビナーのレポートを2回に分けてお届けします。朝日メディアラボベンチャーズと博報堂DYベンチャーズ。 いずれも事業会社発ではありますが、ファンド設立の経緯や形態、運用方針も実は全く異なる2社。そこで今回は、朝日メディアラボベンチャーズの白石氏と博報堂DYベンチャーズの漆山氏をお招きし、両社の取り組みについて深掘りしました。
後編となる今回は、スタートアップ投資のポイントや今後の取り組みなどに伺いました。ぜひご覧ください。(前編はこちら)
▼スピーカー紹介文
■白石 健太郎 氏
朝日メディアラボベンチャーズ株式会社|パートナー
2001年朝日新聞社入社。同社販売局にて600店以上の新聞販売店のエリアマネージャーを担当。2013年新規事業部門のメディアラボに参画。2017年より朝日メディアラボベンチャーズ設立に携わり、現在は2号ファンドを運用中。日本と北米のスタートアップを投資対象としている。
■漆山 乃介 氏
株式会社博報堂DYベンチャーズ|パートナー
博報堂DYグループにおいて、メディアビジネス開発やベンチャー投資を推進。また、同グループの社内公募型ビジネス提案・育成制度である「AD+VENTURE」の審査員及びガイドとして複数の新規事業開発・立ち上げを支援。同グループへの参画以前は、ベンチャーキャピタルにてパートナーとしてベンチャー投資業務に従事。それ以前には、大手人材サービス企業で複数の新規事業・サービス開発を経験。
知見を活かし、進め方の改善や取り組みの拡大へ
ー これまでの経緯も踏まえて、今後どのような取り組みを行っていきたいと考えられていますか?
白石氏:今まではフォロー投資をかなり実施していたのですが、2号ファンドではリードもしっかり取っていこうとチームで話をしています。私たちはアメリカでも投資をしていて、アメリカでは一般的なのですが、いわゆるリード投資家がM&Aする際にがっちりといろいろなことを決めてしまって、少額投資の投資家たちを排除する動きが結構あったりします。今、日本でもすごい数の投資家が出てきていて、M&Aのときに同じようなことが起きはじめていて、今後さらに増えていくだろうと思っています。やはり起業家の皆さんとEXITの方向性をしっかり握って進めていくことはとても重要です。私たちも1号の案件で多くの学びがあるので、どのように組み立てていこうかと話しているところです。
漆山氏:私たちは、社内の仲間を巻き込み、社外の方々とも一緒になって商売をつくっていくということを重視してスタートアップ投資を行ってきました。スタートアップ投資を始めてみてから、成功も失敗も見えてきたことがいろいろとあり、例えば投資契約一つとっても、現場を経験して初めてわかる活きた知見が蓄積されてきています。私たちは現在国内中心に活動していますが、実際投資先にすでにリリースされているArriba Studioという日本人起業家が設立したシンガポール拠点のWeb3アクセラレーターがいます。そのようにビジネス領域によっては海外も自然と見るようになってきている流れはありますね。
スタートアップの将来性をしっかり見据えるための活動
ー スタートアップ投資のポイントについてお聞かせください。
白石氏:スタートアップのフェーズによって、見るポイントが全然変わってくるので、今回はシードに限ったお話をさせていただきます。最初にお伝えした通り、私たちのファンド規模が20億ぐらいなので、「この起業家の方はすごいな」と思うことがあっても、まだ事業が立ち上がっていなかったり、事業内容が曖昧だったりすると、独立系シードVCのようにシード期の起業家に全張りするというようなことはなかなかできません。そこで、その時に何をしているかというと、その事業の対象となるユーザーにインタビューを実施しています。これには、自分たちだけでユーザーヒアリングする場合と、起業家と一緒に実施する場合があります。ビジネスがBtoBでもBtoCでも行っていて、質問内容に関しては基本フォーマットがあります。あとは対象によって少しずつその内容をアジャイルしていくかたちで実施しています。
もしユーザーから良いインサイトを掴めて、その企業の顧客が存在するとわかったら、そこに特化してマーケティングしてもらうように、投資する際に起業家にお願いをします。投資直後は、"いろいろやってみよう"となって資金を使ってしまうんですよね。実際、自分たちの過去の失敗パターンとして、なかなか成果が出ず、気づいたら資金がなくなり、事業が全然成長していないとなってしまい、次の調達が難しくなることが結構あります。やはり事業成長の確からしさがないと以前のようには投資を受けられない状況にあるので、シード期でも顧客をしっかり見定めて、ここに投資すればいけそうだと判断できたときに投資を行っています。
漆山氏:私たちはまずデューデリジェンスですね。財務数字の資料をいただいて、その会社計画の蓋然性を見ます。数値面の検証をするわけです。それをCVCのキャピタリストメンバーで行っています。また、レファレンスもできるだけ行わせてもらっています。社内のキーマンや、取引先などへも行います。経営者の方が優秀なのは間違いないと思うのですが、現場で実務を取り回している社内の部長やマネージャーなどのクラスの方々にもしっかりお話を伺って、組織が機能しているかというのを見ています。ポイントとしてはCEOやCFOの作った計画や経営戦略がどのくらい現場に浸透しているかですね。それができていないと、やはりアクションにちゃんと繋がっていかないのです。経営者は優秀で魅力的な方が多いので応援したくなってしまうのですが、やはりそこは冷静に、仲間はどんな人たちで仲間から見たときに、会社の戦略をどう落とし込んで自分の行動に繋げているのかというのは率直に聞きます。弊社に対してどのような印象を持っているかも聞いたりしますね。
質の良い新しいコミュニティに入ることが肝心
ー スタートアップ投資をはじめられたばかりの頃は、どのようにスタートアップと接点を持つようにされましたか?
白石氏:一番わかりやすいのはIVSのようなスタートアップカンファレンスに出て、名刺交換していくのがベストだと思うのですが、結構コストもかかります。私も新規事業部門立ち上げ当時は、お金をかけずに接点を持つために、あらゆるスタートアップ登壇イベントに顔を出していました。調べると結構いろいろなところでピッチイベントが開催されています。イベントでは起業家、投資家だけでなく、普通の投資家がリーチできない層にコネクションのある会計士の方などにお会い出来たりするので、ひたすら名刺を配るということを行っていました。
漆山氏:これは近道がないんじゃないかなと本当に思います。私も2015年ぐらいからはじめて、白石さんと同じでイベントに行っていましたね。
白石氏:モーニングピッチとか辛かったですよね(笑)
漆山氏:当時はとにかく足を運んでいました。意識していたのは、リアルイベントではその場独特の情報が得られるという点です。特にクローズドイベントならではの情報が取れると思っていて、そういうところにしっかりアクセスするよう頑張っていました。最初に頑張って質の良い新しいコミュニティに入ることができると、その後乗数効果が出てくるんです。徐々に動き回る必要がなくなってくることはあると思います。ただ、若い方々になかなかアプローチできなくなってきてるという問題意識は感じているので、そこは頑張らなきゃいけないと思っていますね。
CVCならではの利点を活かし、よりよい投資活動へ
ー CVCを立ち上げなければできなかったことあれば教えてください。
白石氏:一番はやはり投資の意思決定がとても速くなった部分だと思います。CVC立ち上げ前は、最長で6ヶ月ぐらいかかったこともありました。当時の投資委員会は3名で合議されていたのですが、その前に10数名の役員に事前に説明する必要がありました。そこで、いろいろとフィードバックを受ける中で、事業の方向性が変わってしまうこともありました。しかし、今では投資委員会にかけるまで、最短1~2ヶ月あれば決められるようになりました。もう一つは長くCVCを運営しているとざまざまな知見が貯まってくるので、それを本体にフィードバックしたり、本体から人材を預かって育成することもできるようになってきているので、そこは良かったと思っています。
ー 最後に、これからCVC活動に取り組まれる方々に伝えたいことはありますか?
白石氏:いろいろな情報があって、最初は何をすればいいんだろうと悩むのですが、アドバイスとしては「少額でもいいのでまずはスタートアップに投資してしまう」ということです。それをするまでが難しいという声もあると思いますが、その辺の突破方法については私たちも、多分漆山さんも当時取り組んでいたことがあり、かなり知見を持っています。ぜひその辺りは個別にご相談いただければと思いますが、そこを突破してしまえばあとはそれで経験が積めるはずです。
まずはどのように最初のスタートアップ投資を実施するか、私たちが見つけたように抜け道が各社あると思うので、そこにたどり着いてもらえればと思います。
漆山氏:私たちも立ち上げのときに白石さんをはじめCVCの先輩たちに知見を共有してもらい、本当に助けていただきながら運営してきました。その当時と比べると、国の機運自体も高まっています。業種業態の垣根を超えて、暗黙知化されてしまってる知見を持ち寄ったりしながら突破していく部分もあると思いますので、ぜひ横の連携をとって一緒に盛り上げていけるとありがたいです。
ー 白石さん、漆山さん、本日はお時間いただきありがとうございました。
前編記事はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
