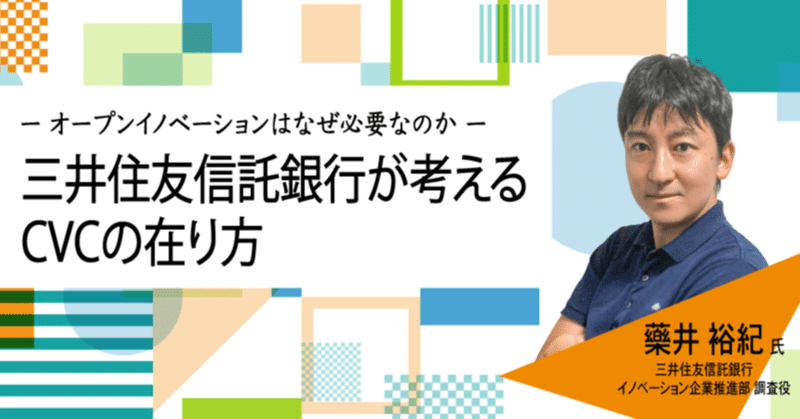
オープンイノベーションはなぜ必要なのか、三井住友信託銀行が考えるCVCの在り方
私たちケップルは、オープンイノベーションを促進するきっかけを作ることで、スタートアップエコシステムに関わる人たちが増え、その結果スタートアップが資金調達や協業に対してより前向きに取り組んでいくサポートができればと考えています。今回は、10月に開催したウェビナーのレポートをお届けします。三井住友信託銀行の取り組みやCVC設立の背景、スタートアップがCVCと組む理由など理解を深めていただける内容となっておりますので、ぜひご覧ください。
▼スピーカー紹介文
藥井 裕紀(やくい ゆうき)
三井住友信託銀行|イノベーション企業推進部 調査役
2009年に三井住友信託銀行へ入社後、東京、大阪で事業法人RM(営業)を経験。2020年4月よりイノベーション企業推進部の立ち上げメンバーとして、三井住友信託銀行初のCVCファンド設立やピッチイベントの開催、社内ビジネスマッチングの枠組み構築、スタートアップサーベイの企画等業務に従事。CVCファンドでは、投資担当として複数件スタートアップ投資を実行。
資金の好循環をスタートアップマーケットにも
-まず三井住友信託銀行の取り組み内容や事業についてお聞かせください。
藥井氏:三井住友トラスト・ホールディングスの傘下で、2012年4月に設立された専業信託銀行です。他のメガバンクグループに属さず、銀行業務と信託業務を主な事業領域としています。
専業信託銀行という特色を生かして、個人、法人、投資家という当社顧客に価値提供を行うことで、資金の好循環を促し、金融市場、資産市場、資本市場をそれぞれ拡大させていくことを目指しています。スタートアップマーケットにおける資金循環も今後注力して取り組んでいきたいことになります。

「イノベーション企業推進部」を2名で立ち上げ、機動的なスタートアップ投資を目的としてCVCファンド設立
-設立までのお話をお聞かせください。
藥井氏:当社はもともと2000年前後にスタートアップ投資はしていましたが、直近では2015年から社内のR&D枠のような投資枠を使って、当社事業に近しい領域に投資をするVCファンドや一部スタートアップ投資を進めていました。また同時期に、当社業務のデジタル化を進めるべく「フィンテックPT(プロジェクトチーム)」を組成し、スタートアップ情報を受け入れる体制も作っております
上記のような活動を通じて、この領域に徐々に手応えも感じ、また当社としてもサステナブルな成長を遂げるにはスタートアップとの更なる連携・関係強化が必要だと感じ、2020年4月に当社のスタートアップ支援の枠組み作りをミッションとして「イノベーション企業推進部」が設立されました。当時は、部長との2名体制で「自分たち自身もスタートアップだ」という気持ちで、毎日刺激的でした。
VCファンドへのLP出資でスタートアップ連携・投資の感覚をつかみつつ、個別出資もいくつか重ねる中で「更に機動的にスタートアップへ投資できる枠組みを」ということで、CVCファンドをSBIインベストメント(以下、SBI)さんと共に、当社初のCVCファンドを設立しました。
-設立にあたっての社内の反応はどうでしたか?
藥井氏:当社においてスタートアップ企業との接点は限られていたため、そもそもスタートアップ領域に対する知見も少なく、投資へのリスクに対する意見はありました。社内を説得するために、まずはCVC投資がいかに有用であるかを外部の有識者に沢山お話を伺いました。多い日は、一日に10件くらい面談してましたね。そこから得られた他社の情報を共有することで、少しずつCVCファンドの立ち上げの目的や運営イメージの解像度が上がり、社内の理解者が増えた気がします。この経験から、社内を説得するには、やはりまずはその領域の有識者の情報を粘り強く聞きにいくことが大事だと感じました。
-SBIさんとの2人組合で設立された背景、また役割分担を教えてください。
藥井氏:色々理由はありますが、当時CVCファンドにアサインされたメンバーは、スタートアップ投資の経験もなく、恥ずかしながら目利き力も未熟だったので、既にVCファンドへのLP出資で関係性を持たせて頂いていたSBIさんにお声がけし、二人組合の形で設立しました。
役割分担は設立当初から徐々に変わりつつあります。当初は、スタートアップ投資の経験や知識が乏しかったため、SBIさんに先導してもらいながら伴走して投資検討を進めていました。設立から2年経った現在では、完全にSBIさんにおまかせしている部分は、契約書等のドキュメンテーションになり、DDにおける事業やバリュエーションの検証は、双方で対応をしています。
-投資領域を教えてください。
藥井氏:設立から2年で約400社の企業に出会い、投資実績は22社になりました。その投資実績企業を見ていただくと、投資領域を絞っていないことが明確かと思います。AI、IoT、フィンテックだけではなく、脱炭素などのエネルギーや、フードテック、ヘルスケア、バイオ、半導体などにも投資しています。
弊社の事業シナジーや弊社のお客様に展開できるようなビジネスという判断軸もありますが、ミッションとして、当社の将来の顧客基盤を築くこともありますので、国内で事業展開を行うアーリーステージ以降の企業であれば、あまり領域を絞らずに投資対象としています。

スタートアップ投資ポイント:IPOの蓋然性や事業連携の可能性というプラスアルファ
-実際に投資する際のポイントはなんですか?
藥井氏:弊社は通常のCVCのように事業連携メインで投資を進めるだけでなく、VCに近い形で「EXITができるのか」「リターンは出るのか」という、IPOの蓋然性を見ながら投資をしています。
事業連携の可否やIPO蓋然性の他にも、事業計画、市場規模、見込めるパイプラインやユーザーの多さなどもしっかり見させていただきます。
ケップルから引き継ぐ、上場企業の総会運営という事業連携
-ぜひ事業連携についてお聞かせください。
藥井氏:連携事例はいくつかありますが、本日は私が投資を担当した3社との連携事例を挙げさせていただきます。
ケップルさんは「株主総会クラウド」という非上場株主総会の電子化ツールを提供していらっしゃいますが、我々自身が証券代行業務で上場企業の総会の運営をしていますので、上場前は株主総会クラウド、上場後は弊社の総会運営が引き継ぐという事業連携のイメージができました。
この連携は2022年9月に実現し、株主総会クラウド上に弊社が用意した株主総会のひな型や、上場企業の総会運営、またガバナンス対応に関するコンテンツなどが提供されています。株主総会クラウドの利用者が増えることで、弊社の上場後の証券代行業務の認知が増えるという連携を想定しています。
-ケップルとの連携には他部署の協力も必要だったかと思いますが、その辺りはスムーズでしたか?
藥井氏:自らが属する法人部門とは、他部門である証券代行部門の協力が必要でしたので、出資検討の段階で事業連携のロードマップを作成し共有しました。その当時想定していたよりも連携実現には時間はかかりましたが、最初にロードマップを共有していたことで、検討が止まらずにうまく行ったと思います。また、社内の事業連携に関わる様々なレイヤーに連携の意義や課題感を粘り強く伝えたことで、社内の応援者や味方を作ることができたことも、スムーズに進んだ要因でもあります。
ケップルさんとの連携の他にも、サイキンソーという腸内フローラの検査キットを販売するスタートアップ企業とは、情報銀行業務での連携をしました。また、HIROTSUバイオサイエンスという線虫によるがんの検査キットを販売するスタートアップ企業とは、当社関係会社の三井住友トラストクラブが提供するダイナースクラブの会員向けに特別なプログラムを作るような連携も進めました。前者は、サイキンソーが収集した個人の腸内データを利活用できないかという観点で実証実験を進めております。また後者は、健康意識が高いダイナースクラブ会員に対する付加価値提供に繋がっています。

SMTBが取り組む様々なオープンイノベーション活動の形
-スタートアップとの事業連携以外のオープンイノベーション活動は何をされていますか?
藥井氏:CVCファンドによるスタートアップ企業への投資、事業連携の活動以外にも、当社はオープンイノベーション活動を進めています。
まず第一に「Trust Base」というデジタル戦略子会社を設立し、独立したシステム開発環境を構築し、当社のDXを推進しています。銀行本体では、セキュリティに関する社内ルールも多く、開発環境も制限されてしまうため、機動的な運営を実現しています。
また「未来フェス」という社内向けビジネスプランコンテストも実施しています。年齢、業務内容、雇用形態に関係なく、社員なら誰でもビジネスプランを出し、勝ち残れば事業化の検討を進める社内ベンチャー制度のようなものです。
他にも、インパクトエクイティ投資も推進しております。事業内容のご説明でもお話しましたが、弊社は資金の好循環を生み出すことを目指していますが、社会や環境にポジティブなインパクトを与えられるような企業やプロジェクト、ファンド等に積極的に弊社が出資を行い、それを呼び水に、投資家の資金を集める取り組みも行っています。
最後に、法人営業の社員中心に「SuMiTURST Innovation Program」という社内研修を開催し、VCのキャピタリストやイノベーション事業推進部のメンバーが講師としてスタートアップ領域のリテラリー向上を目指しています。受講者の多くは、普段接点のないスタートアップの起業家やVCファンドからのお話を受けて、刺激や実感が湧いたと好評でした。

イノベーション企業の経営戦略や振り返りに活用できるベンチマーク「スタートアップサーベイ」
-最後に、直近の活動で伝えておきたいことはありますか?
藥井氏:弊社はスタートアップ企業の取り組みについての大規模な調査である「スタートアップサーベイ」を実施しています。前回は、500社を超える企業に参加頂きました。今後も定期的に取り組むことで、スタートアップの経営情報のベンチマーク化を目指します。11月末より第二回を開催予定です。参加費用は無料になりますので、ご関心のある方は是非ご連絡いただければと思います。

藥井氏:当社のスタートアップ支援や連携の枠組み作りは、まだまだ途上ではありますが、色々と幅広く取り組んでおります。このような活動を通じて資金の好循環を生み出し、スタートアップの領域が盛り上がれば、日本の経済はもっと強くなっていくと思います。一役買えるような取り組みを、今後も積極的に行っていきたいです。
-藥井さん、本日はお時間いただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
