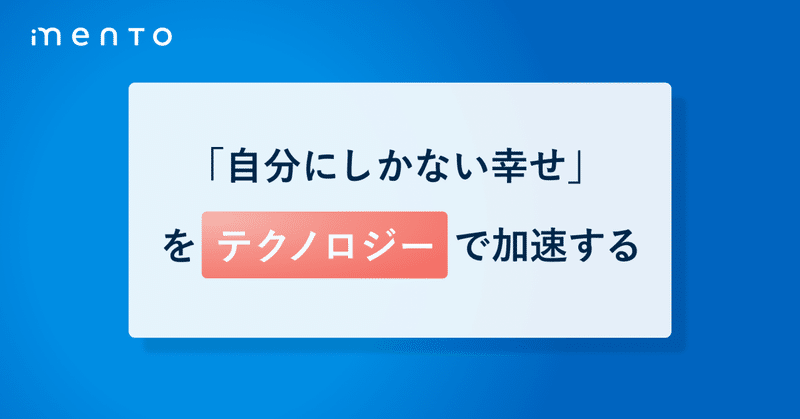
「自分にしかない幸せ」をテクノロジーで加速する
シリーズAの調達とビジョン・ミッションの制定をしました!
mentoは4/6にシリーズAとして3.3億円の資金調達を発表し、会社名も株式会社ウゴクから株式会社mentoに変更しました!
そしてビジョン・ミッション・バリューもゼロから作り直しました



作成のプロセスはCOO 丹下さんのnoteで詳しく解説されているのでぜひそちらもご覧ください
今回はミッションの「コーチングとテクノロジーの力によって日本の主観的ウェルビーイングを世界No.1にする」について話していきます。
そもそもウェルビーイングってなに?
ウェルビーイングってあんまり馴染みが薄かったり、聞いたことがあっても定義がよくわからなかったりするんじゃないかなと思います。
ウェルビーイングは「健康」や「幸福」とよく訳されますが、ただ単に身体的に健康なだけではありません。
ウェルビーイングの定義としてよく利用されるのが世界保健機関(WHO)憲章の前文の一節です。
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。(日本WHO協会仮訳)
ただ単に健康というだけではなく、肉体的、精神的、社会的に満たされたHealth(健康)がウェルビーイングな状態だということですね。
主観的ウェルビーイングって?
じゃあただのウェルビーイングじゃなくて「主観的」ウェルビーイングというのはどういう意味なのでしょうか?
主観的ウェルビーイング (Subjective Well-being)という言葉はアメリカの心理学者 Ed Dienerさんによって提唱された概念で
People’s cognitive and affective evaluations of their lives.
=人々の生活に対する認知的および感情的な評価
と定義されています。
簡単に言うと自分の生活がどのくらい幸せなものと感じているかが主観的ウェルビーイングであり、自分の人生にどのくらい満足しているかや日々どれくらいポジティブな感情になっているかなど、客観的にではなく自分自身の主観によって測定されます。
主観的ウェルビーイングについてより詳しく知りたい方は
Ed Dienerさんの記事 https://nobaproject.com/modules/happiness-the-science-of-subjective-well-being や
BetterUp社の記事 https://www.betterup.com/blog/what-is-subjective-wellbeing
が網羅的でわかりやすいのでおすすめです
なぜ日本で主観的ウェルビーイングが大事か
今年発表された世界幸福度報告2022 で日本は先進国の中でダントツに低い54位 (53位はウズベキスタン、55位はホンジュラス、1位はフィンランド)でした。
この調査では人生の満足度を最高が10点、最低を0点とした時に何点かを主観に基づいて聞くキャントリルのハシゴという設問が使われています。
10点満点中、日本は6.039点(1位のフィンランドは7.821点)となっていて、物質的に恵まれているはずの日本で主観的な人生への満足度がいかに低いかが見て取れます。
そして、mentoでクライアントさんと直接お話しさせていただく機会などを通じて感じることとしては、SNSなどによって情報が溢れている中で、「他人の幸せ」を目にすることで自分を比較してしまって、不幸せになっている人がとても多いということです。
どんなことに幸せを感じるかは一人一人違うことなのに、自分の幸せが何かを考えずに苦悩し、他人の人生を生きている人が多く感じます。
自分が何に幸せを感じるかをそれぞれが認識している世の中を作り、主観的ウェルビーイングを上げていくことが、日本全体の幸せにつながると思っています。
じゃあどうやったら主観的ウェルビーイングが上がるのか
それぞれのウェルビーイングの形がある以上、これをすれば良いという特効薬はありません。
しかし、共通して言えることは自分が何に対して幸せを感じるのか、ウェルビーイングと感じられるのかを認識することが最初のステップだということです。
とはいえ自分が何に対して幸せを感じるかがすぐにわかるほど簡単なことではないでしょう。
mentoでコーチングで変化していく人を見たり、自分でコーチングを受けていて思うこととしては、自分が何に対して幸せを感じるかを理解するためには
行動してみたことからフィードバックを得て
そこから自分がどんなことに幸せを感じるのかを理解し
また次の行動につなげる
というサイクルが必要だということです。

しかし、このサイクルがうまく回らない人は
自分自身が何がしたいのか理解できていないので行動に納得感がなく続いていかない
行動から受けてのためを思った適切なフィードバックを得られる環境がない
フィードバックから自己の認識へつながる気づきを得られない
ということが多くありがちです。

コーチングという手法はこのサイクルを加速すると思っています。具体的には
コーチという伴走者がいるので行動が継続しやすい
行動からのフィードバックをコーチとの対話によって引き出すことができる
コーチの問いによって内省が深まり、フィードバックからの気づきを得られる

このサイクルが回ることによって、自分が何に対して幸せを感じるかについて理解が進み、新たな行動によって人生の満足度が上がっていきます。
再現性のためのテクノロジー
従来のコーチングでもこのサイクルを加速することはできると思います。
しかし、コーチングは人と人とのものなので相性の良し悪しによって効果は全く異なるものになります。
そして、プロのコーチとの一対一のコーチングはどうしても高価になってしまい、受けられる人や回数が限られてきます。
そこでmentoはデータとテクノロジーによってコーチングの効果の再現性を高める、つまりいつでもどこでも誰でも手軽に安価に効果を得られる状態を作ることで、コーチング体験を民主化し、より多くの人の主観的ウェルビーイングを向上させるということをミッションとしました。
具体的には
コーチがいなくても自ら行動の継続ができる仕組みを作る
データに基づいたプロダクトや組織づくりによって周りの人からのフィードバックの質を向上させる
自分自身で内省が進むような問いとプロダクトをつくる
によってコーチングの効果をより多くの人に実感してもらうプロダクトにしていきたいと思っています。

一緒にプロダクトを作っていってくれる仲間を募集します
とはいえ、まだまだ提供していくものの解像度が粗く構想段階から練っていくフェーズです。
主観的ウェルビーイングにダイレクトに、包括的にアプローチしているサービス、プロダクトはまだ日本にはないと思っています。
mentoは日本の主観的ウェルビーイングの向上に向かって一緒にプロダクトを作っていってくれる人を募集しています。
僕たちの作っていきたい世界観に少しでも共感される方はぜひ、以下の採用情報からカジュアルにお話しさせていただければ嬉しいです。
▼採用情報/CultureDeckはこちら
一緒に日本の主観的ウェルビーイングを世界No.1にしていきましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
