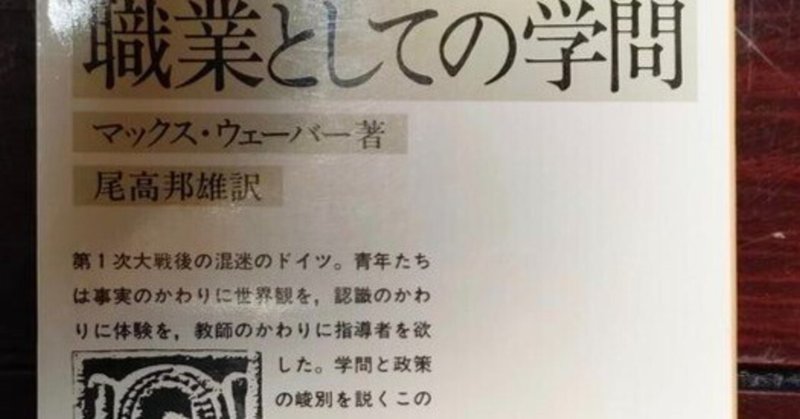
【32冊目】職業としての学問マックス・ウェーバー著尾高邦雄訳
【諸々】
・ウェーバーが学生向けに講演した際の書き起こし
【気になったところ抜粋&感想("→"以降)】
①P27 学問の領域で「個性」をもつのは、その個性ではなくて、その仕事に仕える人のみである。しかも、そのことたるや、なにも学問の領域にばかり限ったことではない。芸術家でも、自分の仕事に仕えるかわりになにかほかのことに手を出した人には、われわれの知る限り偉大な芸術家は存在しないのである。いやしくもその仕事に関するかぎり、たとえゲーテほどの偉大な人でも、もし自分の「生活」そのものを芸術品にしようなどどあえて試みるときは、必ずその報いを受けなければならない。(中略)「体験」で示してやろうと思ているような人、つまり、どうだ俺はただの「専門家」じゃないだろうとか、どうだ俺のいったようなことはまだだれもいわないだろうとか、そういうことばかり考えている人、こうした人々は、学問の世界では間違いなくなんら「個性」のある人ではない。(中略)しかしその結果は、かれらがいたずらに自己の名を落とすのみであって、なんら大局には関係しないのである。むしろ反対に、自己を滅しておのれの課題に専念する人こそ、かえってその仕事の価値の増大とともにその名を高める結果となるだろう。
→正しい。ネットを見ると誤解されて解釈されている記事を見るが、もう少し分かりやすく書くと、目の前の仕事の進歩にのみ専念することで初めてその道を切り開く業績を得られるということ。現代もその風潮は強いので自戒すべきであろう。
②P30 学問上の「達成」はつねに新しい「問題提出」を意味する。それは他の仕事によって「打ち破られ」、時代遅れとなることをみずから欲するのである。(中略)たんにわれわれに共通の運命でなく、実にわれわれに共通の目的なのである。われわれ学問に生きるものは、後代の人々がわれわれよりも高い段階に到達することを期待しないでは仕事をすることができない。原則上、この進歩は無限に続くものである。
→つい、機械工学を学んでいると何か永久に変わらない定理を発見するのが学者の夢かと思っていたし、通っていた大学の学科の先生はそういうタイプの人が多かった。社会学者はこう考えているとは意外だったが、その通りだろう。
③後半部分で、学者は学生には学問を教え、反論の余地のある自分の考えは述べるべきでないとの論述があった。これは、講義においての論述であろう。院生の論文指導やゼミにおいてはその内容は変わる。
④今まで、ウェーバーの本は読みにくいと思っていたし、あとがきにもそう書いてあるが、翻訳のおかげかとても読みやすかった。翻訳は最新版を買うことにしよう。プロ倫の「鉄の檻」も、大塚さんの旧訳版には「鉄のカーテン」か何かと記載があり、後日、「鉄の檻」と言われてもピンとこなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
