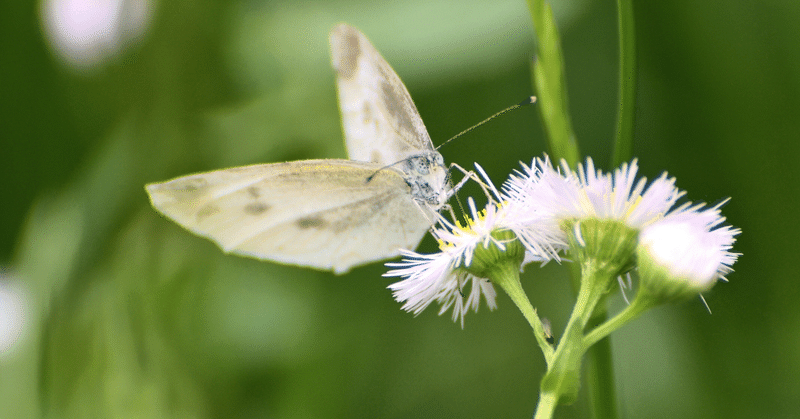
先月、以前勤めていた保育園の卒園式に出席してきた。一年ぶりに子ども達と会う機会ができて嬉しかったな。多分もう保育園で働くことはないし子どもと関わる機会も当分ないだろうけど、それでも子どもは好きなのでたまに専門書を読んだりして今でも勉強はしているんだよね。今日は自分がしたい保育、目指す保育はどんなものなのかを、新たな知見も踏まえて考え直してみたいと思う。
現代社会の一員として
保育とはなにか? と調べると「乳幼児を適切な環境のもとで、健康・安全で安定感をもって活動できるように養護するとともに、その心身を健全に発達させるように教育すること」とある。
健康や安全に関しては大前提であるし、今さら僕がなにかを書くまでもなく有識者の手でマニュアル化されていると思うので書くことはない。正直に白状すると、僕は既に答えが出ていることにはあまり興味を持てない性格だから特に真剣に考えてもいなかったと思う。
しかし心身の健全な発達に関しては俄然、それはもう真剣に考えてきたと思う。それは生命の根幹に踏み込む壮大なテーマでもあるからだ。人間の成長には方向性があり、また人間には環境適応力が備わっているから、保育者が健全な発達とはどういうものかを理解していないと間違った方向に子どもの育ちを導いてしまうリスクが大いにある点にも気をつけなければならない。
ではいったい、今日の保育とはどうあるべきなのだろうか。
***
子どもの心身の健全な発達について考えるなら、まず前提となる「人間とはなにか?」を突き止めるところから始めたいと思う。人間とはいったい何なのかを知らなければ、どこへ向かうべきかもわからない。
この星に生まれてくる全ての生命は、時代や地域や生物種や遺伝子や性別といった一切を選択権なく決められてはこの世界に投げ込まれ、万物の法則やあらゆる諸条件に否応なく従って生きていく。ご存じの通り社会的動物である人間は、社会に適応しなければ生きていくことは難しい。この時代の日本で人間に生まれた僕達は、条件に合わせて現代社会を渡り歩くことが生きる上で必要になってくる。
「置かれた場所で咲く」というのは個の時代には歓迎されない向きもあるが、よくよく考えれば誰しもが行っていることだ。大人が第二言語の習得に苦労するのに対して学習のノウハウを持たない幼児が日に日に喋れるようになるのは、脳研究によれば人間の脳は生まれた環境に適応するための余白を持って生まれてくるからだという。
国際言語は英語でも日本に生まれたならまず日本語を覚えるように、広範な用途よりも目の前の現実に則して子どもは成長をしていく。世界の中立というものは存在せず、現環境に投げ込まれた一個体は周囲に適応する術をまずは身につけるだろう。
ではやはり、「置かれた場所で咲く」を指針にして子どもの育ちを支えることが保育の正解なのだろうか?
人類史を振り返ると、時代とともに社会は変容を繰り返して価値観の変遷が起こり続けていることがわかる。今ある日本社会もまた時代の過渡期であり、いつまた価値観の転換点を迎えるかわからない。世界人口の増加と科学技術の発展によって時代の変化は加速度的に進んでおり、一般常識や社会倫理もまた「今日の常識は明日の非常識」といった具合で変わっていくのだろう。
もし保育者が「社会に出たらこうだから」と思考停止に保育方針を決めてしまえば、それは昭和の時代に横行した体罰や、「運動中は水を飲むな」と根拠のない根性論を言い出す体育教師や、LGBTを笑いものや病気の一種として扱ってきた時代背景や、男の子は男の子らしく女の子は女の子らしくとジェンダーロールを当たり前に押し付けてきた平成の学校教育のように、子ども達が大人になる後代から見れば時代錯誤な悪しき教育論を振りかざしていた老害だったとなりかねない。
ましてや子ども達が一番初めに体験する社会である保育園や幼稚園で保育者の誤った社会観に晒されて育てば、幼い心に植え付けられた固定観念の影響は後々まで大きく尾を引いてしまう可能性がある。たとえ善意のつもりでも間違った善意は悪意よりも離れがたい強い呪いとなって、子どもの人生に暗い影を落とすこともあり得てしまう。
なので僕は声を大にして言いたいのだが、保育は現状の社会倫理や価値観を無批判に受け入れず、より良い未来のために絶えず人間と社会のあり方を考えていかなければ成り立たない仕事だ。子どもの心身の健全な発達とはどういうものかを考えることは、前提として社会のあり方や地球の未来を問われ、人間とはなにか? という生命倫理や宗教、道徳、哲学といった多岐に渡る世界観から紐解かなければ答えを出せない難題だと思う。
人間の本質とは
とはいえ、未来ばかりを夢想していても現実と折り合いをつけることは難しい。
村の掟がいかに非合理で理不尽なものでも、生まれた村の掟には従わないとたちまち村八分にされてしまう。ジェンダー平等が唱えられてきても現実はまだまだ古くから続く男女観を踏襲しているのだから、男らしさや女らしさを身につけることは役に立つ。今日の常識は明日の非常識とはいえ、明日の常識を考えて今日を生きるのはなにかと不都合もあるだろう。厳しい社会の中でこれから生きていく子ども達の人生を、未来を変えるための駒として大人が利用してはいけない。
子ども達もいつかは大人になり、社会に出て活躍していく。社会の価値基準で評価を下されて、それに応じた報酬を得て生活する可能性が高いことは否めない。置かれた場所で咲くことと同じく、生まれた時代に乗ることは幸せに近づく手段として効率が良いのも確かだろう。
社会的評価を得ることは対価として地位や収入という利益を生むから、親が早いうちから子どもの適性を見出して利益率の高い専門分野に絞って教育していくことは合理的ではある。自我が形成される前から特定のスポーツを仕込んで鍛え上げれば活躍するチャンスは増えるし、幼少期から英才教育を受けた子どもは高学歴エリートになりやすい。東大卒の平均生涯収入は中卒や高卒の平均を大きく上回るし、社会的成功を収めて高い年収を得る人ほど比較して人生への満足度は高い。
サラブレッドが競馬で活躍することのみを求められて馬場を速く駆けるトレーニングに明け暮れるように、初めから社会に照準を合わせてコスパの良い生き方を送る人ほど利口だと言われてしまえば反論し難いのも事実だ。文化の成熟度に比例して個々人の人生の環境依存度は高まり、マタイ効果で差はますます拡大していく。
だけど僕はそれでも、育成という名目で子どもを社会形成のためのロボット化しているようで強い拒否感がある。子どもの人生を社会変革のための駒にしてはいけないように、いかに報酬で釣ろうと社会保持のための駒にしてもいけないと思うのだ。人のためにできた社会は有史以来どんどん大きくなり、いつしか社会のために人が動く状態になって久しい。生命は、人間は、いったい何のために生まれてくるのだろうか。
現代社会にはまだ、人間の愚行権は残っているだろうか。
既定路線を歩んだ先にしか人生の幸福はないのだろうか。用意された台本通りに演じて踊る舞台役者になるのが賢い生き方なのだろうか。社会に価値を定められて、評価を得なければ生きる資格はないのだろうか。
子どもに品行方正な振る舞いを覚えさせ、社会のルールとマナーを教え込み、社会的価値に準拠した塾や習い事をさせる教育ママの姿に誰しも心当たりがあると思う。多くの保育者が既に舗装されてある道ばかりを子どもに歩かせたがるのは、何もこの世界にはもう未開拓な荒野は残されていないからではなく、大人自身が保守的になり未知を探求する知的好奇心を失っているからではないか。何度転んでもおぼつかない足で立ち上がり、火傷の痛みと共に火の怖さを覚え、溺れかけながら泳ぎ方を覚えていくはずの子ども達の未来が、未知に手を伸ばす機会のない答えが出ている道しか残されていないのだとしたら、なぜ生まれてきたのかわからなくなるだろう。
正しい道を選ぶのが、正しい。だけど正しい道しか選べなかったら、なぜ生きているのかわからない
現代社会の虚構を暴け
今日の常識にも明日の常識にも縛られずに、人間の本質を突き止めて育ちを支えることが本当の保育ではないだろうか。
大人自身が人間の本質を見つめずに、世間に踊らされて自分を品定めされたがっている。流行する顔やメイクに価値を感じて自分の容姿に悩んだり、特異な身体を持つスポーツ選手に憧れて不自然な筋肉をつけようとしたり、身長や胸にコンプレックスを抱いて小さいことが恥ずかしい気持ちになったり、仮初の華やかさに夢中になって虚飾を追い求めたりと、人間の本質から外れた価値観を子ども達にまで植え付けて生の歓喜を失わせ、生きづらい想いをさせることは絶対に間違っていると僕は思う。
人間はもっと自由で、あるがままを肯定されて生まれてきたはずだ。虚構を崇める現代社会の狂騒に子ども達が参加しなくてもいい未来がいつか訪れることを切に願う。保育者はどうか子ども達には、どんな君でも愛おしいよと言ってあげてよ。
他人の容姿に憧れたり自分の容姿に悩む人は多いが、よく考えてみてほしい。一昔前に人気を博したスタイルやメイクやファッションを今見ると色褪せて古臭く感じるように、時代と共に人気の容姿は流行している。美容業界のプロパガンダによって変遷する流行を追いかけて、審美眼を養う暇もなく世間の基準での美人になりたがる大人は実に多いが、そこに美の本質はないのではないか。
過熱するルッキズムは美の本質から外れた競争を作り上げ、美の探求者ではなくルッキズムの奴隷を生み出す。時代に迎合した容姿と振る舞いを身につければカーストの頂点に立てるような社会は日本中の不幸や不景気や知能の低下にもつながっているように思う。人種的多様性の少なさが余計に固定化したルッキズムを助長しているのもあるだろう。
また、画一的な基準で進んで激化した競争は歴史的にも纏足や首長族のように異性の好みからも遠ざかった不自然で極端な方向に走ることがある。整形症候群や拒食症もそれらを踏襲しているのだろう。古今東西の民族の風習にもあるように、それもある意味で人間の本質を象徴してはいるのだろうが、やはり自分の頭と心で人間のなにが美しいかを知り、感じていけるようになるのが真に人間らしい生き方だと思う。
ルッキズムの中で報われるために過ごした生き方は、ふとした折に子どもの容姿に対しても自分の価値観を向けるようになる。幼少の頃に大人から容姿を否定する呪いの言葉を吐かれて育てば、それは生涯響くトラウマになるかもしれない。また、良かれと思って言った悪意なき言葉も子どもの心を束縛してしまう。
「肌が白くて羨ましい」「まつげが長くていいな」節々から出るそういう言葉によって子どものルッキズムが形成されていく。条件付きの賛辞しか貰えなかった子どもが急き立てられるように勉強やスポーツを痛々しくも健気に頑張るように、肌の白さを褒められれば子どもは日焼けを嫌がり外で遊ぶことを躊躇うようになる。自分の半生を否定できないまま彼らはいつか大人になり、自分の努力を正当化して次代へと価値観を伝承させていく。それは人間が社会に吞み込まれた未来を創る、不幸の連鎖ではないだろうか。
身体さえも現代社会では多くの人が自然本来の状態から遠ざかっているように感じる。
スポーツ選手といえば子どもの憧れの職業だろう。その歴史を紐解くと、現在盛んに行われている競技の多くが西洋の文化として生まれたことがわかる。エンタメとして成立するためにファスト化した競技性もあって、筋骨隆々な欧米人が有利なのが実情ではないだろうか。もちろん一つの文化として素晴らしいものではあるが、あくまで社会的価値であって人間の本質を問う能力だとは限らないよな、と近ごろはよく思う。
「日本人離れした身体」が運動能力の高い日本人アスリートへの称賛になっているのは、日本人であることへの劣等感を形成してはいないだろうか。そして日本人離れの筆頭ともいえる欧米人並みの大柄な体格の持ち主が西洋文化の中心で活躍を成し遂げると、彼みたいになりたいと子どもは目を輝かせ大人は彼を教育のお手本のように扱う。まるで名誉白人になりたがったかつての日本人のようだ。
また、ジムに通って不必要に大きな筋肉をつけるための努力がカッコいいことだとされるのも、欧米コンプレックス塗れのルッキズムに端をなす。肉体崇拝の文化芸術を持つ西洋には筋骨隆々とした彫像がたくさんあるのに対し、東洋では性別を超えた存在であるのっぺりとした身体の仏像が彫られてきた。ルーツを失えばいくら筋肉をつけてもコンプレックスしか生まないのではないか。特大のホームランを打てなくたって、中腰でずっと田植えをしても堪えない丈夫な身体だって素晴らしいじゃないか。西洋文化に端をなす画一化した価値観が、日本人本来の身体を歪ませているように感じる。
学校の体育の授業がスポーツ化していることにも僕は反対だ。体を動かすことの本質はスポーツに勝つことではないのに体育のほとんどが勝ち負けを競うスポーツになっていることで運動が嫌いになった子は山ほどいる。健康な生活に貢献して、自分の身体を思い通りに動かせるようになればそれでいいのだ。なにも共通のルールを定めて競わせる必要はない。それよりももっと純粋に、体を動かす楽しさを子ども達に知ってもらうべきではないだろうか。
男性の身長と女性の胸のサイズはよく引き合いに出される。どちらも大きい方が魅力的だとされるが、本当にそうだろうか?
世界最古の小説でもある源氏物語に登場する、光り輝く美貌を持つとまで称される光源氏は長身で細身だと書かれてある。このことからも古くから男性の高身長は魅力的な外見の条件であることがわかる。しかし人類史や進化の歴史から考察すると、決してホモ・サピエンスは大型化していった訳ではない。高身長がモテて繁殖に有利ならば種として大型化していくはずであるが実際に確認できるのは地理的条件による大型化くらいなので、男性の高身長が女性から持て囃される理由は遺伝的優位性ではないと考えられる。
野生動物が満足な栄養状態で過ごすことは珍しく、栄養失調により十分に発育できなかった場合が多い。人間も同様に、数十万年の歴史のほとんどを飢餓と隣り合わせで生き延びてきた。かつての人類は現代よりも平均身長がずっと低く、その中で高身長の男性は十分な食事を得られたことで健康的で発育が良く、狩りに長けていたりコミュニティのアルファだった可能性が高い。高身長が魅力的に映るのは優れたオスと交配するためのメスとしての本能で、栄養状態が良く十分に発育している個体が大半を占める現代では意味をなさない本能の名残りになっているんじゃないだろうか。さらに、スポーツをはじめとした西洋文化の影響でもデカさこそ正義の価値観は強まっている印象だ。
また、日本で女性の乳房が性的な意味を持つようになったのも西洋文化が流入してきた明治以降だという。僕にもすっかり染み付いている現代人の感覚では到底理解し難いが、江戸時代以前は女性の乳房に対して性的な視線は向けられなかったという。春画で描かれるのは性器ばかりだし、考えてみれば広く混浴文化があったことも裸体に性的な関心がなかったから成立していたのかもしれない。そもそも乳房は生殖としてのセックスに不要なのだから、性的関心を寄せることの合理性はあまり見出せない。
中でも巨乳が流行ったのは遥か後年、1980年代だという。時代と共に流行りの容姿が変遷しているのと同じく、体型さえも流行り廃りによって価値を決められている。なんてくだらないのだろう。
今さら「おっぱいなんて興味ない」だなんて口が裂けても言えないけれど、巨乳女性が好きな男性も高身長男性が好きな女性にも何も文句を言う資格はないけれど、でも自分がジャッジされる側なら、そんなくだらない価値観に一喜一憂しないで、ありのままの自分を肯定すればいいじゃないか。移り気な世間の価値観に振り回されながら必死に縋りついて人気を得たところで、最期に残るのは意味のなかった空虚な人生でしかない。
人間が自分で意味を与えないかぎり、人生には意味がない
健全な発達とは、人生の本懐とは
では子どもの健全な発達とはどういうものだろう。保育者が意図して働きかけた保育は、実際にどのくらい子どもの育ちに影響を与えるのだろうか。
双子の研究では、別々の環境で育った一卵性双生児には大人になっても驚くほど多くの共通点があるとされる。知能指数や運動能力のみならず、性格や趣味嗜好、癖や異性の好みまで似通っているという。それほど遺伝子の影響が大きいのであれば、個性を押さえつける全体主義がいかに非合理で間違いであるかがわかると思う。
しかし今後ますます遺伝子解析が進み、もし一人ひとりに合った最適な育成方法が確立されたとしても、僕はその通りに保育をしたいとは思わない。それがどれほど正しくて合理的だとしても結局は社会的価値に基づく目標設定に依存した育成方法なのだから、それはサラブレッド育成論に類似したものでしかなく、子どもを社会保持の駒にする。
バレエやフィギュアスケートなど、10代に全盛期を迎えるスポーツ競技は環境依存度がとても高いが、大半の子どもは経験することなく気がつけば全盛期が過ぎ去っているだろう。もし遺伝子解析によって才能の有無がわかれば、埋もれた才能は世に見出されて最適な練習環境を与えられ、不世出の天才プレイヤーになるかもしれない。どんな分野でも、過去類を見ないほど輝かしい活躍が遺伝と環境の意図的なマッチングによって作られていくかもしれない。
けれど僕たち人間は、社会的価値の高い存在を目指して生まれてきたわけではないはずだ。別に背が高い遺伝子を受け継いでいるからといってバスケットやバレーボールを選ばない自由がある。音痴でも大声を響かせて歌っていいし、下手っぴでも好きなように絵を描き続けていい。子ども達は自分の心が喜ぶ場所を自分の力で見つけて歩んでいって欲しい。
大人が意図や目的を持って導こうとせずに、母なる自然と生きる力に任せて子どもがひとりでに育っていくのを邪魔しないことが本当の保育ではないだろうか。子どもは罰から何も学ばないし、強制しても何も育たない。ぶら下げた人参は創造を生み出さない。大人が子どもにできることは豊かで多様な自然を隣で共に感じながら、子どもに憧れの未来を想起させる大人になって健やかな愛を与え続けることだけじゃないだろうか。
愛こそ貧しい知識から豊かな知識への架け橋である
そして更に言えば、幸福至上主義のような保育方針にもあまり賛成はできない。幸せがなんだと言うのか。人間がもし本当に幸せになるために生まれてきたというのなら、なぜわざわざ不安や緊張や恐怖を感じる心があるのか。
安全が約束された世界では一切の危機管理能力は必要なくなり、鈍い人間だけが幸せに暮らすだろう。足は萎え、拳を握れず、筋肉は衰え、贅肉を蓄えて、知能を退化させて欲に溺れ、卑しい笑顔を見せる終末の人間になって得る幸せに価値があるのだろうか。傷ついて血を流しても瘡蓋を作って治す力が備わっているのに、生きる力が不要な世界に子どもを連れて行くことが正しい保育なのだろうか。動物がみな苦しい思いをして出産するのはなぜなのか。
時には悩み、時に傷つき、倒れたら立ち上がり、生の能力を使い切ることこそが人生の本懐ではないだろうか。
人生を危険にさらせ!
現実的な取り組みは
待機児童問題や潜在保育士数など深刻な保育士不足は日本の眼前の課題であり、保育は広義の意味で社会インフラとも呼べる必要不可欠な仕事だ。令和2年度の調査によると有資格者は全国に167万人いるが、それでも保育士不足が叫ばれ続ける改善が急務の現状では、上記の壮大なテーマを一人ひとりへ背負い込ませては到底成り立たない。また、社会インフラである以上は認可・認可外に関わらず明文化された規範が必要になってくるわけで、定められた保育方針に基づいて業務にあたる数的労働力の確保が保育の現場では必要とされているのが実態だ。
組織的な観点から言えば保育方針を掲げて保育園を開設した以上、従ってもらわないと困るはずだ。日本社会においても盲従は社会人の処世術であり、一から自分の頭で考えることはなにかと軋轢を生みやすい。保育士の女性比率の高さや実感としても、規範的、保守的な性格傾向の人が多く、多くの保育園では子どもの創造性を伸ばすことを大切にしているものの働く保育士においては現代日本を象徴するように創造性より従属性を求められており、創造と模倣の二律背反は模倣が多勢を占めている。
保育というのはヴィジョンを持って理想を描いていくべき仕事だが、重労働の現場仕事という側面もあって子どもの面倒を見ることに追われもするので、割合としては現業職に向いていそうな実務的な人が多い。保育園と保育士は施工主と現場職人の関係で、街づくりへの関心は無く渡された設計図を元にただ建築に取り組むような保育士は多い。とはいえ、保育士不足の現状を鑑みると保育士の絶対数をまずは増やさなければ創造的保育への取り組みは後回しにされてしまいそうだ。
しかしだ。各々がより良い保育を考えることは不要ではないはずだ。無能や低能は許容しても反乱分子は許容しないというのであれば革新性は生まれない。子どものためを第一に考えるのであれば、規律に従うだけの人ばかりが重宝されるのは間違っていると僕は思う。
自由の気風はただ多事争論の間に在りて存するものと知る可し
保育士不足解決のためにはどうすればいいのだろうか。保育士不足の一番大きな理由は給料の安さだとされる。子ども達に好きや興味を見つけて夢中になることを推奨している保育士の不足理由が給料の安さなんだから笑っちゃうよね。本音と建前が見事に分かれている。それでも仕事に選んで働く保育士は素晴らしいよ。
給料の問題は不景気や少子化といった日本の政治や経済の状況にも大きく左右され、保育の範疇では解決できないところも大きい。日本が経済優先で進んできた皺寄せが子ども達に降りかかるのだと思うと心苦しい。
この資本主義の社会はなかなか変わらないだろうけど、あらゆる価値を金銭的な価値で判断し、挙句自分自身さえも社会に価値判断を委ねてしまう人がとても多い。くだらない呪縛に子ども達が罹らないように、我々大人も呪縛を解いて真に人間らしい生き方を模索していくべきじゃないだろうか。
西アフリカにあるニジェール共和国は、長らく世界最貧国の一つに挙げられ2024年のGDP(国内総生産)では統計が取れる194ヶ国中189位とされる。これはほぼ人口が同数のオーストラリアよりも一人当たりのGDPが100分の1以下という貧しさだ。しかしそれほど貧しい国にも関わらずニジェールの出生率は世界1位の6.82を記録する。1人の女性が平均して生涯で7人近く産む計算になる。
もっとも、ニジェールの出生率が高い現状は児童婚の問題や女性の人権軽視、子どもが労働力として期待されている側面が大きく、7割の子どもは初等教育すら受けられずに労働へと駆り出される。男女平等からもほど遠く、成人女性の識字率は7%という低さだ。日本の比ではない人道的な問題がたくさんある。
しかし不景気を理由に出生率低下に歯止めがかからない日本を尻目に子どもがたくさん生まれていることを鑑みると、我々はこんなに素晴らしい日本を作った日本人なんだから、金銭的に厳しいだなんて理由で少子化が進む現状を歯がゆく思う。行き過ぎた意図や狙いといった目的意識が強迫観念になって、「〇〇を小さい頃に習わせないと将来が不安」「良い大学に入れないと大人になって困る」など子どもを育てるための必要条件を勝手に作り出して躊躇しているんじゃないか。大丈夫、人間はそんなヤワじゃないよ。
この競争社会の渦中で産声を上げた子ども達が、社会の評価に惑わされず自身の持つ感性を指針にして自由に生きていけるような世の中にしていくことが本当の保育、ひいては大人の役目ではないだろうか。
子ども達もいずれは冷たい社会に放り出されて、大人の無理解や無神経な態度に打ちのめされる日もあるだろう。その時に、大好きだった大人との出会いが記憶の片隅に残っていれば、きっと世界のどこかに自分をわかってくれる人もいるはずだと希望を持てるかもしれない。
そのためには大人が自身の感性を指針にして美しくあろうとし、本当に大切なものを見失わずに日々を営んでいくことだ。自分なりの美しさを求めて今を懸命に生きる大人が子どもの側にいることで、子どもは美しさを見つけることができるのではないだろうか。誰との比較でもなく自分らしさを美しく感じ、自分を誇りに思える子どもがどうか少しでも増えて欲しい。
僕は自分の生き様で人間の底力を証明したいし、生きる歓びを伝えたい。僕がかつて救われたように、素晴らしい作品を世に残したい。それが僕にできる子ども達への保育だと考えている。
生とは、問いを焼き尽くすことだ
サポートしていただくと泣いて喜びます! そしてたくさん書き続けることができますので何卒ご支援をよろしくお願い致します。

