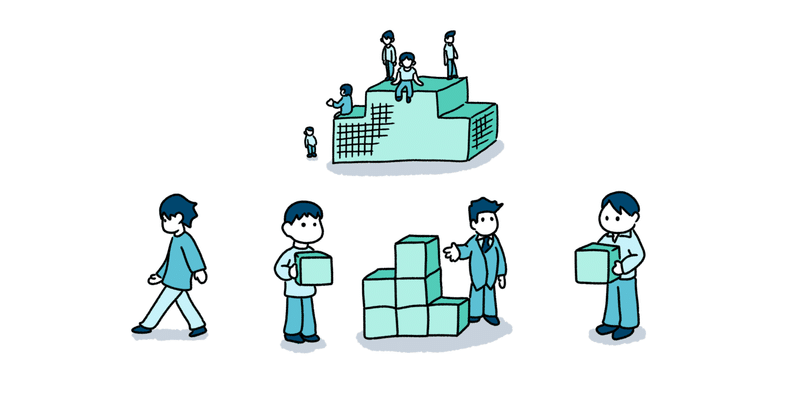
【仕事の流儀】チーム運営のすべての基礎は、人間関係の構築にある
チーム運営、組織運営において、見落とされがちでありながら非常に重要な鍵があります。重要な秘密といってもいい。
それは、「チーム運営のすべての基礎は、人間関係の構築にある」ということです。
マネジメントの失敗体験
チームのマネジメントを任されるようになって数年になりますが、最初の1年以上はひたすら失敗の連続で、僕はずっと霧の中にいました。
当初、僕のチーム運営は、相当に独りよがりで悲惨なものでした。
メンバーに寄り添うことなど全く考えておらず、目指していたのは、「メンバーを自分のコピーにする」ということ。
自分がそれまでプレイヤーとして積み上げてきたやり方こそ正義。自分のやり方が認められてチームを任されたのだという錯覚。恐らくこれは、プレイヤーからマネージャーとなったときに陥る罠のひとつではないかと思います。
自分と同じやり方で仕事することをメンバーにも要求し、あらゆる仕事の進め方を指示し、メールの文章の言い回しまで言及し、他部門との調整方法は混乱を招かないよう仔細に指示。メンバーのできていないことを日々指摘し、改善すべきことをひたすら言い続けました。
ところが、やればやるほどメンバーとの関係性は悪化し、大した成果も上がりませんでした。そのころ、人間関係の構築はそもそも目指しておらず、目の前の膨大なタスクをいかにやりきるかということしか頭にありませんでした。メンバーからの信頼を得られる要素はなく、僕自身もメンバーを信頼できていませんでした。
メンバーが思うような成果を出さないなら自分が頑張ろうということで、マネジメントよりもプレイヤーとしての業務に精を出し、チームのマネージャーでありながら自分の成果ばかりを追及していました。
チームの雰囲気もよくない中にあって、事務作業をお願いしていた1名の派遣社員も定着せず、1年ちょっとの間に4人の入れ替えが発生。チームが維持できずに解散する可能性も当時の上長から示唆されており、綱渡りの状態が長く続いていました。
霧が晴れた瞬間
なぜメンバーが自分と同じようにできないのか。メンバーの能力のなさを日々嘆き、チームは混迷の度合いを深める一方でした。
霧が晴れたのは、デール・カーネギーの名著「人を動かす」に出会い、学ぶ機会を得られたことがきっかけです。
もちろん、同じ言葉であっても、それと出会うタイミング、自分の心の状態、姿勢によって、響くか響かないかは人によると思いますし、何を自分が取り入れるかは常に人それぞれだと思いますが、その時の僕にはジャストミートでした。
チーム運営のすべての基礎は、人間関係の構築にある。
人間としての信頼関係がない状態では、どんなに仕事で成果を上げたいと思っても、大きなものを築くことが決してできない。
このことは、それまでの自分のやり方を根底から覆す概念でした。
以前の考え方はこうです。
仕事なのだから人間関係に関係なく、好き嫌いは置いといて、仕事としてやるべきことがなされるべき。
自分はチームのマネージャーなのだから、メンバーは自分の指示通りに従って動くべき。
でも、その考え方は全くの間違いでした。今思うと恐ろしいほどに真逆です。仕事を進めていく上で人間関係の構築が土台になっている。それなくしては何事も前に進むことはない。このことは衝撃的な事実でした。
自分が考えている「あるべき姿」をメンバーに強要しても何も変わらない。必要なのは、メンバーの話を聞き、共感し、寄り添うこと。
実践して変わったこと
遅ればせながら、このことを知ったその日から、自分のそれまでの行動を改め、学んだことを即実践し始めました。何をどうしたのかといえば、これだけです。
相手に誠実な関心を寄せる。
すると、本当に驚くべきことに、その効果はすぐに出ました。自分が変わり、チームが変わりました。
変えるべきはメンバーではなく、まず自分なのです。チームとして成果を出していくためには、まずひとりひとりの人間と向き合い、関係性を作っていくことが絶対に欠かせません。
たとえば、チーム運営の手法のひとつに、1on1ミーティングと呼ばれる、上長と部下が1対1で話す場を定期的に設けるやり方があります。僕は隔週に一度のタイミングで各メンバーと1on1を実施しています。
実は、この1on1はチーム発足当初から継続的に実施していました。ただ、やればよいというわけではない。その進め方やメンバーに向かう姿勢を改めました。
上長が業務の進捗確認や改善すべき点を指摘する場所から、メンバーの心身の状態や考えを聞かせてもらう場所に。その内容は必ずしも仕事の話である必要はなく、日常生活での出来事やその時々で感じたことについても興味を持って聞き、お互いの人間を知る場にしていく。
対峙から共感へ。このことはチーム状況の改善にも大きく影響しました。
大事なのは、ツールそのものではなく、そのツールをどう使うか。
今の僕がメンバーに対して心掛けているのは、カッコつけないこと、自分をオープンにすること、常に上機嫌であることです。これらを意識的にやっています。
さらに言うと、機嫌の悪さで周りをコントロールしようとしないことです。最近僕の周りでは見かけないものの、時々いるタイプで、すごく機嫌が悪い姿をわざと部下に見せて、「なんで俺が怒っているか分かるか?」みたいに凄んで見せる昭和なタイプの上司がいますよね。ちょっと想像してみて下さい。ストレスの伝播力は凄まじいものがあります。
機嫌の悪さで周囲をコントロールしようとしたり、察することを強要したりすることは、決してやってはいけない。
最後に
大事なことなのでもう一度言います。
人間関係の構築がチーム運営のすべての基本。
ここだけは絶対に外さないこと。メンバーの心理的安全性が確保されていないと、その後のチーム運営に繋がりません。
人間関係の構築ができているところに、組織としての理念があり、その理念についてメンバーが腹落ちしている状態に到達していることが望ましいです。理念の策定は、一般的には人間関係の構築より先行することが多いと思われますが、理念なしに動いている組織も意外と多い印象です。
なお、理念については、次のエントリで触れています。
ところで、ここまで書いてみて、改めてデール・カーネギーの「人を動かす」を読み返してみたところ、なんと、「組織運営のすべての基礎は人間関係の構築にある」という言い回しはどこにも見当たりませんでした。
自分は一体何を見たのか…。
もちろん、カーネギーの教えの中にも同様の結論にたどり着く言及はたくさんあります。「他人を批判しない」「相手に敬意を示す」「相手の意見を尊重する」「共感を示す」といったところが一例で、これらを総合していくと同じ結論が導き出されることになるでしょう。
ともあれ、この教えが僕を救ってくれたことは間違いない。
大事なのは、言葉を知ることでもなければ、頭で把握していることでもありません。心に深く刻み、実践に繋げていくことです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
