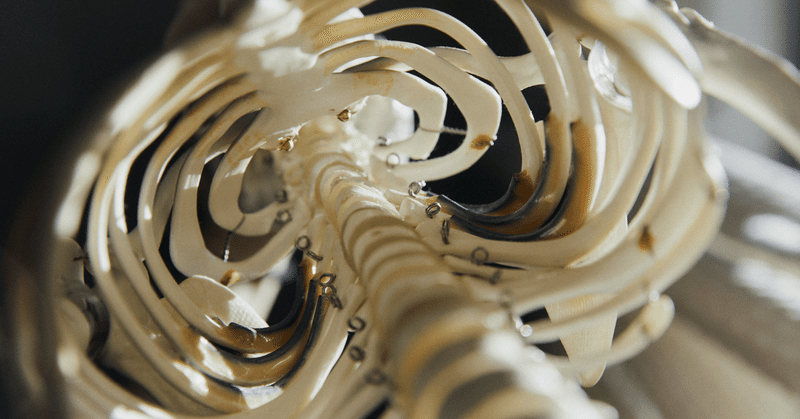
縮退される世界には内なる道徳律を
テクノロジーやサービスの発達によって、私たちの生活は便利になり豊かになっているはずなのに、合理的な選択の連続に対してどこかで虚無感を感じている。
心のどこかで「このままではいけないはずだ」と思いながら、見ないふりをして今日も自分なりに最適で最高な行動を選択し続ける。
こんな私たちはどこから来てどこに行くのだろうか。
今日はそんな思いに言葉を添えたい。
液状化するライフスタイル
僕自身のライフスタイルは今や液状化が極まりつつある。
鎌倉の庭付きの古民家で妻と二人、たまに野良猫がやってくるような環境で悠々と暮らしている。
時間に縛られることもなく起きてから「今日は何をしようか」と考えるような日々だ。
時間も空間も限りなく自由に近く、老後のような生活でもあり、ニートのような生活ともいえるだろう。
僕のキャリアは最初から液状気味だった。
大学院を卒業するときに就職したい企業がどこにもないことに気づき、結果的にやったこともないのに自分達でデザインコンサルティングを名乗りはじめた。そこから大手企業や地方自治体の仕事を知り合い経由で受注したりしながら、マイプロジェクトとして三つほどコミュニティを立ち上げた。
金銭資本としては豊かではないが、社会関係資本はわりかし豊かな方だという自覚はある。社会関係資本をうまく運用しながら、なんとかどうにか金銭資本にも変換しつつここまできた。
ここにきて、お金についての恐怖が抜けてきた。要は現時点の収入を受け入れてそれ以上の支出をしなければいいだけだったのだ。
お金が扱えるようになると、野望も客観的に見えて萎んでくる。
大層な志があったとしても、世界にその希求がなければそれは自分の野望だろう。
野望として無理に現実化するくらいなら人様に迷惑をかけずにのたれ死んだ方がマシかもしれない。
もしくはゲームの中で誰にも迷惑をかけずに発散した方がいいかもしれない。
世界に対して何度もプロポーズしたけど、返事はそっけないので結果的に老後みたいなライフスタイルになった。
以前まではそこに悔しさや自負心みたいなのもあったけど、お金の話と分離しながら、今はそれが等身大の自分なんだと受け入れてからは随分楽になった。
世界は虚無に向かっている
僕のライフスタイルは今の時代観からみたら少し早すぎるものなのかもしれないが、多かれ少なかれ人々はそのようなライフスタイルになっていくだろう。
誰でもやりたくない仕事はやりたくない。楽をできるなら楽をしたい。
できるだけ怠惰でありたいというのは、人間の強い本能的欲求である。
今は社会が移行期だからまだ嫌だと思いながらも働いていることによって生きがいは受動的に担保されている。
しかし、ベーシックインカムなどの普及が整備されると全世界ネトゲ廃人になる未来が待っているかもしれない。
一方で自己実現をしたい。お金持ちになりたい。他者から認められたい。自分を表現したい。
そのような在り方が是とされる空気が今の社会にはある。
自己愛を受容して欲望をそのまま解き放つことが美徳であると説いたのがアメリカのフロンティア精神であり、それがテクノロジーでSNSネットワークが補強されることで世界全体をその価値観が包み込んでいる。
兼ねてより僕はCiftでもNestoでも近代化によってもたらされる個別化に対するアンチテーゼとしてのコンセプトをつくってきた。近代化によってライフもワークのあり方も大きく変化している。
共同体はどんどん分裂していき、最終的には個人の心と体も分離され、生まれてから死ぬまで快楽カプセルで過ごすようなディストピア的な未来へと向かいつつある。
会社はどんどん専門化され、大きなプラットフォームが世界を斡旋し、多様化を謳いながら結果的に寡占状態をつくりだし世界を画一化していくグローバリズムの危機が迫っている。
時を経るごとにこの考え方はより現実味を帯びていると感じるところである。

縮退こそが最大の近代病
長沼伸一郎氏の視座は自分の感覚を構造的にも直観的にも補完するのにとてもありがたい存在だった。
直近は「世界史の構造的理解」をAudibleで拝聴したが、前作の「現代経済学の直感的方法」にも触れられていた縮退という考え方が僕に言葉を与えてくれた。
縮退とは希少性を燃やして富を産む不可逆性の行為、と理解している。
化石燃料などはわかりやすい例だが、それと同じ構造でより深刻なのは社会構造の消費だ。
つまり、これまでつくりあげてきた弱いもの同士がデリケートに支え合う生態系を外から強力な外来種が一気に寡占化するという構図だ。
商店街におけるスーパーマーケット、国内企業とGAFAなどそのモデルはフラクタルに世界中に展開されている。
そのエネルギーを養分に近代は技術が一気に発展したが、その代償として過去の先人たちが丁寧に積み上げてきた道徳律が失われた。
宗教が拝金主義を嫌うのは個人の精神的バランスと社会の構造的バランスを慮ってのことである。
先人たちは縮退化が起きないように政治的社会システムや宗教的世界観を駆使しながらなんとかバランスをとりつづけていた。
日本史において特に傑物なのは260年の安泰の世をつくった徳川家康だろう。彼は儒教をベースに封建的身分制度を確立させた。
渋沢栄一は論語と算盤の中で士魂商才を掲げた。侍の志と商人の能力を統合させようとしたのだ。
武士は矜持に溺れすぎず、商人は卑屈になりすぎず、お互いから学び合い統合していくという方針を示した。
しかし、世界は時を経るごとに算盤の方に傾き矜持は廃れていった。一度境界線を外すと世界は低き方に流れる。
資本主義における液状化は私たちの首を真綿に絞めるようにやってくる。
最終的にはグローバリストたちが寡占したプラットフォームの上で全世界の人々がアヘン窟に埋没する未来が口を開けて待っている。
そこまでいったら人類史は終わりである。
依存的な階級制度は差別を生むが、完全な平等主義もまた虚無を生む。
今こそ新しい形での個人と社会の道徳律の実装が必要だ。
自分の内側に道徳律を持つこと
僕たちは外側から与えられる道徳や規範などにはもう従うことができない。
先史時代には盲目的な信仰も機能したが、それに比べて私たちはあまりに賢くなりすぎた。
科学的エビデンスがなければ、もうこの社会で画一的な共通認識を持つことは難しいだろう。
生態系を保持するための社会システムの拠り所は、信仰から道徳律へと継承されたがそれも資本主義によって瓦解された。資本主義がその在り方に対して世界観のレベルで認識が変わらない限りは縮退化への道は待ったなしである。
そんな社会の状況の中で僕たちが等身大ではじめられることはなんだろう。
僕たちは内側から道徳律を積み上げなくてはならない。
そして、やがて訪れる虚無に打ち勝つ為の自律の準備をしなければならない。
それは宗教における神と同じような役割の拠り所を自分の内側に持つことと同義である。
平素な言葉で言えば内なる良心を拠り所に生きるということだ。良心は自分の中に自分を超えた存在を感じさせてくれるアクセスポイントだ。
内なる道徳律の復活こそがポスト近代であり、その要は宗教に匹敵するような強い良心の発露へのコミットメントである。
宗教の代わりになるコミットメントの拠り所は現在においては科学であろう。科学的事実の上で自ら理性的な認識をし、内なる確信を持ってオリジナルな道徳律を立ち上げる。
人から一方的に押し付けられる世界観では強固な道徳律を養うことはできない。

家族になったり習慣を持ったりとあえて面倒くさいことにコミットさせようとするCiftやNestoの構造の意図はそこにある。
ただし、これはその世界観にご縁があって準備ができた人々だけが門を叩くことができる構造になっている。
ゆえに現段階のマーケットとは相性が悪いということはNestoを2年間続けてあらためて自覚することである。
それでも僕が思う未来の人類の在り方への実践的な祈りの行為としてCiftもNestoも等身大のところでやっていきたい。
理があれば自ずと開けるだろうし、なければ野垂れ死ぬだけだ。
人間の良心を信じる。
まずは自分から実践する。
それしか現時点で僕はできることを思い付かない。
Nestoラボのお誘い
Nestoラボでは、ほぼ毎日僕がこのような日記を限定公開しています。
それ以外にもNestoリズムの経営状況のシェアや、普遍的なウェルビーイング・新しいコミュニティ・資本主義の未来などの探究を220名程度でしています。
あなたの智慧と経験と挑戦もシェアしてくれると嬉しいです。
詳細はこちらから
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
