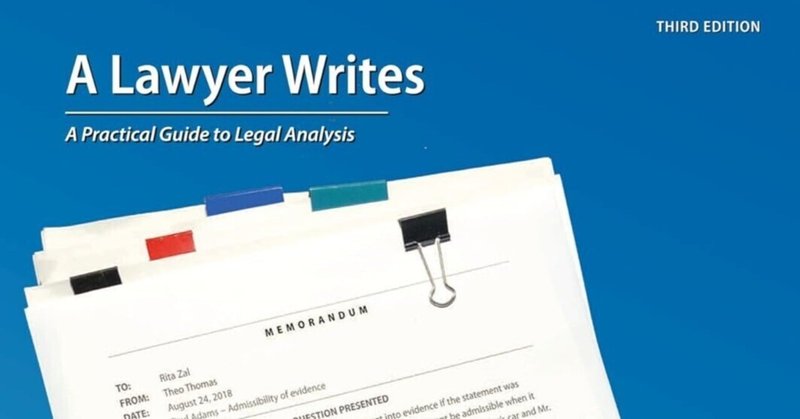
Fall 2023 授業振り返り② - Legal Research & Writing
今回は、Legal Research & Writingについて振り返りたいと思います。
この科目は、Texas Barを受験する上での必修科目です。おそらく他の州のBarでも同じだと思いますので、どこのロースクールにも同様の科目が存在しており、かつ、授業の内容もそんなに大差のではないかと推測します。なお、Texas Barの受験要件等がどのように履修科目選択に影響したかについては、過去の記事をご参照下さい。
概要
授業名のとおり、Research、Writingの技術を学ぶことが目的です。別途詳細なSyllabusは存在しますが、時間の関係で省略するとして、簡単にまとめると以下のとおりです。
まず、Researchについては、授業の中で触れることはあまりなく、むしろ、リサーチツールであるWestlaw、Lexis Nexisが学生向けに作った勉強モジュール(動画)を使って、リサーチの際のTipsを自習する(宿題)という形でした。こっちのほうが効率的だと思います。別途書こうと思いますが、今学期はPaperも執筆しており、その際、相当量のリサーチをしましたので、そのような実技と相まって、実用的なスキルが身についたと思います。
次にWritingですが、第一に、Citationの方法論(Bluebook)を学びました。これも、Paperを書くときに大いに役立ちました。その上で、Offie Memoの書き方を学びました。Office Memoの書き方(いわゆるCREAACなどの文章構成)は、各ローファームで差はあるものの、概ねスタンダードが存在するため、それを習得することが目標です。以下のA Lawyer Writesという教科書を使いました。
座学に加えて、Hypotheticalな事案をベースに、Office Memoを2つドラフトしました。各事案とも、参考になる先例があるので、先例をもとにルールを抽出した上、具体的事案に当てはめていくことになります。
感想
非常に役に立った
上記にてPaperとの関係でも述べましたが、授業の内容は、非常に実践的で、論文を書く上で即効性のあることが学べ、かつ、今後の実務でも役に立ちそうです。日本での実務の中でも英語の文書を書くことはそれなりに多かったのですが、そのような経験も踏まえて、多くの気付きが得られました。
内容面に加え、細やかな指導を受けられたのも高評価です。ドラフトを提出すると、講師とTutor(JD 2Lの学生)がそれぞれ的確かつスピーディーにフィードバックをくれるので、初稿から最終稿まで仕上げていく上でいいサイクルを回すことができました。また、オプショナルではありますが、Writing Centerにドラフトを送るとコメントをくれます。何回か書き直して煮詰まったときに、Writing Centerにレビューをお願いしたら、新鮮な目で見れくれたので役に立ちました。
なお、Writingのスキルに特化した授業が存在するというのは、アメリカの法曹教育の特徴だと思います。日本では一義的には司法試験を通じて、各自がなんとなく我流で身につけるというのが実情だと思います。これに対し、アメリカでは、Writing教育が独自に発展している結果、司法試験でWritringのスキルを問うことはなく、むしろIssue spottingにフォーカスが当てられているように思います。実務では、WritingもIssue spottingもどっちも大事なので、それぞれを別のプロセスで集中的に鍛えるというのは、優れた教育メソッドであるように思いました。
また、少なくともOffice Memoについては、「型」がしっかりしていて、なぜそのような「型」になっているのかについてもしっかり言語化されているのが、アメリカのLegal Writingの特徴だと思います。慣れるのに時間はかかりますが、慣れてしまえば、かえって楽に書けるようになります。この点は、司法修習で体験した検察起案に似ています。
教科書が素晴らしい
"A Lawyer Writes"は素晴らしいです。
めちゃくちゃ実務的で、Law Firmで働き始めたジュニア・アソシエイトの目線が強く意識されています。レビューワーの問題意識にどのようにアプローチするかなどの示唆に富んでいます。Emailを書くときの注意点なんかも書いてあって、お役立ちTipsも多いです。
当然ながらコモンロー固有の記載(caseからどのようにruleを抽出するかなど)は多いものの、日本法弁護士(ジュニア)が読んでも得られるところが多いのではないかと思います。
ただ、それでもよくわからん米国流のWriting
基本的には徐々に慣れてきたのですが、それでも「型」にはめすぎじゃね?と思うこともしばしばあります。例えば、①Statement of Factsをナンバリングしてはいけない(その結果、いくつの事実が書かれているのか一見して分かりにくくなる)、とか、②一つのパラグラフは必ず2つ以上のセンテンスで構成しないといけない(その結果、Conclusionが一つのセンテンスの場合、直前のパラグラフに統合する必要が生じる)とか。
また、Common law特有の考え方に慣れるのが特に難しいです。最も大きな特徴は、case lawであり、すべての法的推論において過去のCaseとの整合性を意識しなければいけない点です。この観点が現れる一つの例として、複数のCaseからRuleをSynthesizeするという作業があります。当然ながら、自分自身の言葉で「作文」することが不可避的に伴うわけですが、Civil Lawから来た実務家としては、自分の言葉でルールをステイトすることにはためらいがあるところです(むしろ、ルールについてはauthorityが何を言っているかが肝心で、その後の当てはめのところが各自の腕の見せどころ)。
加えて、Bluebookが定めるCitationのルールも不可解です。例えば、Journalの名称の一部なのにAbbreviateする必要があるとか(✗ Texas Journal of Oil Gas and Energy Law →◯TEX. J. OIL GAS & ENERGY L.)。まあ、これはルールなのでしょうがないですが。
アメリカのデータベースは使いやすい
本授業での座学や、Paper執筆に当たっての実際のリサーチを通じて、データベースはだいぶ使えるようになりました。
総じて、アメリカのデータベースは、日本のそれと比べて使いやすいです。例えば、判例をデータベース上で見ると、掲載されたReporterにおけるページ番号がちゃんと書いてあり、当該判例をCiteするときに役立ちます。
今後について
Writing、Researchいずれも学習効果が高いことが分かったので、引き続き学び続けたいと思います。ただ、来学期に何か履修するかと言うと、他科目との関係でそこまでは難しいところです。来学期もPaperを書くことにはなると思うので、その中で各スキルを磨いていくということになると思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
