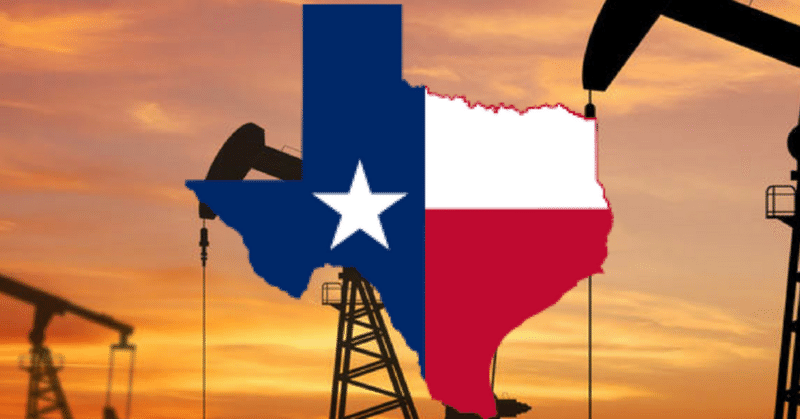
Fall 2023 授業振り返り④ - Paper
今回は、今学期を通じて調査・執筆してきたPaperについて振り返りたいと思います。
一口にPaperと言っても、実は、2つのPaperに取り組んでいました。一つはSecured Credit Workshopの授業の課題として書いたもの、もう一つはゼミであるEnergy Law and Seminarの課題として書いたものです。
それぞれ受講の経緯は過去の記事をご参照下さい。
本記事では、Paperを書き終わるまでの経緯、すなわち、ざっくりとしたトピックの設定、そのブラッシュアップ、データベース等を用いた調査、調査結果に基づく執筆といった各プロセスで何を考えたかを振り返ります。他方、肝心のサブスタンス(Paperの中身)の話は、専門的すぎるので、基本的には割愛することにします。
ざっくりとしたトピックの設定
まず、ざっくりトピックを決める必要があります。Secured Credit、Energyいずれについても、少なくとも講義の内容に関連したものを書く必要がありますので、それぞれ担保取引、エネルギーという分野レベルまでは絞られています。しかし、そこから先は各自の判断に委ねられるところです。
思いつくままに
ファーストステップとしては、これまでの実務経験や、UTに来る直前のYale Summar Sessionで関心を持った論点(Federalism)なども踏まえつつ、実際に調査・検討してみてどれだけ深められそうかは一旦度外視して、思いつくままに列挙していきました。
また、担保取引に関する基本法典であるUCC Article 9については、日本で最もArticle 9に精通しているうちの一人と思われる弁護士がちょうど同僚にいましたので、「昨今の担保法改正の議論の中で、UCC Article 9でここを調べたら面白そう、とかありますか?」という感じで、教えてもらいました。
その結果、以下のとおり、粒度は全く異なるものの、いくつかのトピックが浮かび上がりました。なお、結局最終的に選択したトピックはいずれでもなかったです。
1. Energy関連
洋上風力の公募プロセス
工事請負契約等に関連してInflation riskがどのようにアロケートされているか、また紛争の諸相
風力発電所への反対運動
環境法分野における連邦法と州法の相克
Small Modular Reactor
脱炭素に向けた連邦レベル・州レベルのポリシーの違い、政策決定プロセス
Corporate PPA
環境変動訴訟
2. Secured Credit関係
洋上風力発電設備(特に浮体式)への担保設定
Intangible Assets(のれん(goodwill)や、知財)への担保設定
次に何を考えるべきか?
思いつくままに列挙してみたものの、更に調査をして絞り込んでいく必要があり、その中では、以下の視点が重要と考えていました。
自分が面白いと思えるかどうか
日本での実務に役立つかどうか
Texasならではの要素があるかどうか
先行文献があるなど、調べやすいかどうか
Case lawの国なので、Caseを調べる技術を磨けるかどうか
日本法・米国法いずれからスタートするか?
また、トピックをナローダウンしていくに当たって、「論点」のようなものを見つけ出す必要がありますが、これには、大きく分けて2つの方向性があるようにも思いました。
日本で既に問題となっている「論点」を頭に置きつつ、アメリカだとどうなっているか?という問題意識で調査していくアプローチ OR
純粋にアメリカで最近話題になっている「論点」を探していくアプローチ
日本での実務経験を持つ者としては、1つ目の方が、やりやすいのは間違いなく、また、うまくいいトピックを設定できれば日本法からの比較法的な視点を提供できるという効用もあります。しかし、日本で問題となっている論点がアメリカでも等しく論じられているとは限りませんし、仮に誰かが論じているのだとしても、アメリカ法の「素人」が手を出しやすいほどに容易に情報が入手できるとも限りません。
他方で、2つ目のアプローチであれば、Law JournalなどのSecondary Sourceを順番に見ていけば、必ずどこかで面白そうな論点に遭遇できる、という安心感はあります。また、どれだけ深掘りする余地があるのかも、一つ網羅的なSecondary Sourceを見つければ、その脚注などから関連文献の量を確認できます。ただ、日本とのインタラクションがどれだけ望めるのかは未知数というのがネックではあります。
以上諸々を総合考慮して、最終的には、2つ目のアプローチを基本線にすることにしました。それを念頭に置きつつ、Texas大学のLaw Journal (Texas Journal of Oil, Gas, and Energy Law)や、Secured CreditのTopic list (Professorが学生の便宜のために用意したもの)などを見ていき、何か関心を引く論点がないか探っていきます。
リサーチ・執筆に要する負担感からくる現実的な制約
ところで、冒頭記載のとおり、今学期の履修計画の下では、2つPaperを書く必要がありました。しかし、履修計画がFixして少し経ったあたりで、学期中のWorkloadの感覚がつかめるようになり、結果、「全く違う観点で2つのペーパーを今学期中に書き上げるのは無理」ということに気づきました。
そこで、これまで書いてきた諸々の視点・アプローチはありつつも、現実的な制約として、Secured Creditと、Energyの双方でリサーチ結果を共有できるよう、なるべく近接したトピックを設定する必要が生じました。なお、トピックとしてはオーバーラップするものの、各Paperで字数制限も異なりますし、フォーカスも異なりますので、出来上がりのPaperとしては全く別物にはなります。あくまでリサーチ結果を共有できるのがメリットです。
以上の制約を踏まえたとき、既述した「洋上風力プロジェクトへの担保設定」というトピックはqualifyするように思いました。また、Topic Listの中から、「Oil & Gasへの担保設定」というトピックも発見しました。
この2つで悩んだときに、以下の理由から後者にしました。
Energyのゼミの方は、再エネというよりOil & Gasにフォーカスしており、Professorからのフィードバックも後者の方が期待しやすい
Oil and Gasの方は、Topic Listに載っていたくらいだし、既に判例(First River Energy)が存在するので、論点がわかりやすく、リサーチもしやすそうだった。
https://www.ca5.uscourts.gov/opinions/pub/19/19-50646-CV0.pdfOil and Gasの方は、UCC Article 9に対する例外を定めるTexas州法がイシューになっていることが一見して分かった。Texas関連なので興味を持ちやすかったし、原則論と特別法の交錯を検討する中で、原則論(Article 9)への理解が深まるという効用を期待できそうだった
上記「判例」は、第一審がTexasのBankruptcy Courtだったが、ちょうど当該第一審を担当したJudgeと近日中に面会する予定があった
トピックのブラッシュアップ
ということでざっくり大枠は決まったのですが、とりわけSecured CreditのProfessorからは、字数制限があるので適切なスコープにナローダウンする必要があると指摘され、ここからは上記トピックをブラッシュアップしていくプロセスに入ります。
ここでも難航する
このプロセスもなかなか難航しました。既述のとおり、論点は明確であり調査もしやすそうではあったのですが、それはとりもなおさず、既に誰かが論じてしまっている、ということでもあり、新規の論点というのはなかなか見つかりません。
また、そもそもの限界として、アメリカ法のことはよく知らないのです。例えば、判例からは一旦離れて、Article 9と、当該Texas州法を全般的に比べてGap分析をしてみて、その差分から何か論じられないかとも考えました。条文同士を比べてギャップ分析するというのは、Structured Financeを専門とするLawyerとしては手慣れた手法ではあります。しかし、原則論であるUCC Article 9の方もまだ良くわかっていない(←それを学ぶのが今学期のSecured Creditの授業の目的)ので、これはワークしなかったです。ちょっとやってみたところ、色々解明を要するようなGap(一見、Texas州法の方を改善したほうがよさそうに見える点)はあるものの、本当にSubstantialなGapなのかが判断がつかず、その先まで踏み込めない、という感じでした。
結局やりやすそうなところに落ち着いた
結局、アプローチとしては、ある意味比較法的な観点に戻るのですが、「当該Texas州法と同じような法律を持つOklahomaの裁判所で問題となっている論点が、Texasの裁判所ではどのように判断されそうか」という軸で論点を絞り込んでいくことにしました。やはりCaseというものは、論点があるからこそCaseになっているわけで、Caseを立脚点にするのがやりやすいのは間違いないと思います。
なお、唐突にOklahomaが出てきたように見えますが、実は、「Oil and Gasへの担保設定」に方向性を決めた時点で既に頭にあった判例(First River Energy)にヒントを得ています。当該判例は、OklahomaとTexasとで似たような州法を持っているものの、裁判所の判断が分かれた(Oklahoma wins, Texas loses)という興味深い判示を含んでおり、また、当該判断の後、TexasがOklahomaの州法をパクったというこれまた興味深い経緯もありました。なお、さらに視野を広げると、Texas、Oklahomaは隣接している州だけあって、色々な面でRivalryの関係にあると思われているようです。例えば、Footballでは、Oklahoma大学とTexas大学では、年に一度Red River Rivalryなる「伝統の一戦」があります。
ただ、それで何か新しいことが書けるかと言うと、やはりそう簡単でもない
以上のとおり、Oklahoma v. Texasという視座は定まったのですが、実際に検討していくと、やはりなかなか新しいことは書けないですね。大きな理由としては、上記のとおり、Texas州法はOklahoma州法をパクっているので、新規の検討を要するような優位な差というのを見出しがたかったです。
結局、それ以上調査検討するには時間的制約もあり、他方で、字数制限の下限もクリアする必要があることから、ペーパーのアウトラインを組んだ時点で、前置きに当たる部分(前提となる法制度の説明、caseの解説)を厚くする形にせざるを得なかったです。アウトラインの段階で、Analyticalというより、Descriptiveなものになることが決定しました。
リサーチ・執筆
リサーチ手法
以上のトピック設定のプロセスと並行してリサーチも進めてきたわけですが、リサーチに当たっては、Librarianから役に立つデータベースを教えてもらいました。また、データベースの使い方は、Legal Research & Writingの授業でも学びます。詳細は、別記事をご参照下さい。
具体的には、データベースはWestlawを使ったのですが、キーワード検索したり、また、鍵となる判例をキーにして、関連するCaseやSecondary Sourceを探したりしました。特に重要そうな文献については、脚注記載の文献も更に当たっていく、というアプローチで進めていきました。
執筆
調査が終わった段階でアウトラインは頭の中にできていましたので、後はひたすら書いていくだけです。Citationについては、Legal Research & Writingの授業で学んだBluebookingのスキルを応用していきます。
上記のとおり、割とDescritiveなものになってしまったのですが、その分、調査結果を余すところなくPeperに盛り込むことに心を砕きました。なので、ちゃんと調べたよ、というアピールはできたと思います。実際、調査に当たっては、当該Texas州法に関するSourceは、Primary / Secondary問わずすべてチェックしており、私のPaperの脚注を読めば、当該論点に関する重要文献にはすべてアクセスできるようになっている、と思います。
Executive Summary
本記事では、プロセスを振り返ることを重視したので、あまり中身の話はしていないですが、最後にEnergyの方のPaperのExecutive SummaryとIntroductionだけ書いておくことにします(脚注は除きました。)
Executive Summary
Texas recently introduced a new chapter in “Texas Property Code” in 2021. The latest chapter provides for a statutory lien oil and gas producers can claim. The historical background of this new statute is interesting. It is a replacement of the former code , established in 1983, when Texas’s oil and gas industry was facing the economic downturn. In 2021, however, a bankruptcy case found a fatal flaw in the former code. Subsequently, the Texas legislature transformed the former code into the new code. The basic structure of the statute conforms to an equivalent Oklahoma statute named “Oil and Gas Owners’ Lien Act.” While very few cases have discussed the new Texas code to date, we can predict how the court will interpret the statute by carefully analysing the cases discussing either the Oklahoma counterpart or the old Texas code and contemplating their relevance and implication to the Texas new statute. A short observation of such analysis and contemplation would be that most precedents are still valid in delineating the new code.
Introduction
This paper discusses the relatively recent oil and gas lien statute being a part of the “Texas Property Code” (“New Code”), which replaced the old statute that has the same goal but took a different formality (“Old Code”). The first two parts will briefly overview how a security interest works over oil and gas as collateral (Part II), and what are characteristics of the New Code as a secured transaction legislation (Part III). Then, to give more context, the subsequent part will dig in the historical background of the New Code (Part IV). This paper will further shed light on a couple of legal issues surrounding the New Code. As the courts have yet to deliver copious opinions on the New Code because of its brand-new character , this paper will instead analyse (i) two recent cases dealing with the Oklahoma equivalent statute “Oil and Gas Owners’ Lien Act” (“Okla. Act”) (Part V), and (ii) three cases handling the Old Code (Part VI). Based on the historical context, it will be understood that the New Code is in many aspects similar to the Okla. Act and the Old Code respectively. Given this, the last part will conclude that the past cases this paper will specifically discuss can be largely applied to interpret the New Code (Part VII).
感想
何がよかったのかはわからない
一回切り捨てた洋上風力関連のトピックですが、今後の日本での実務への発展性という意味では、浮体式の洋上風力発電設備への担保設定は、日本ではほとんど論じられてないような気がするので、やはり捨てがたかったように思います。ごく簡単にリサーチだけですが、アメリカ国内でもそこまで論じられてないようなので、チャレンジングなようにも思いました。なお、最初期の段階で、洋上風力の担保設定について関心がある旨をSecured CreditのProfessorに伝えたところ、大変興味深そうなリアクションをされていて、詳しそうな専門家も紹介してくれそうでした。今振り返ると、こっちのトピックにした方がよかったかもしれないですね。何がよかったのかはよくわからないです。
Paperを書くのは難しい。特に、新しいことを書くのは
総括すると、別の国の法律を一から学んで新規性のあることを書くのは難しいと痛感しました。調査する中で学んだことは非常に多いのですが、学んだことを吐き出すことに加えて、更に発展的なことを書くことは叶わなかったように思います。
専門家はすごい
今回の一連のチャレンジでは、純粋に米国法の中から論点を見つけて、米国法の中だけで調査検討を完結させました。その結果、かなり四苦八苦したのは既述のとおりです。
ただ、逆に、純粋な日本法マターだと、日本にいたときは、専門家としてそれなりのものを書いていたりしていたので、これはある意味すごいことだなと気付かされました。何か発展的なことを書くためには、問題となる法律をすべて正しく理解しており、かつ、リサーチもやり尽くして知らないことはないという自信がないとできませんので。
何を得たか?
色々苦戦したものの、Paperを書き上げた経験は貴重なものです。書く中で、リサーチやCitationなどの基本スキルを磨くことができました。また、これはトピック設定時の目論見どおりですが、UCC Article 9の原則論についても理解を深めることができました。加えて、Oil and Gasへの関心も高まりましたので、Energy Law and Policyのゼミを始めとし、UTでEnergyを学んでいくことのモチベーションも高まりました。
なお、例によって、作業時間を測っているのですが、Paperの調査・執筆に要した合計時間は、およそ85時間でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
