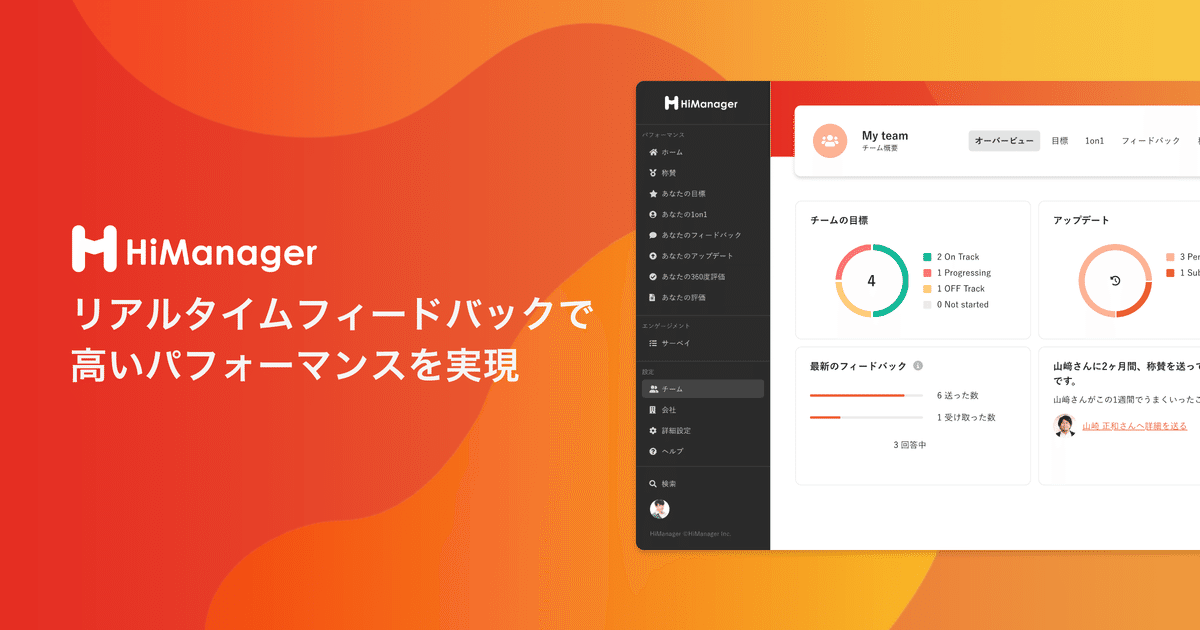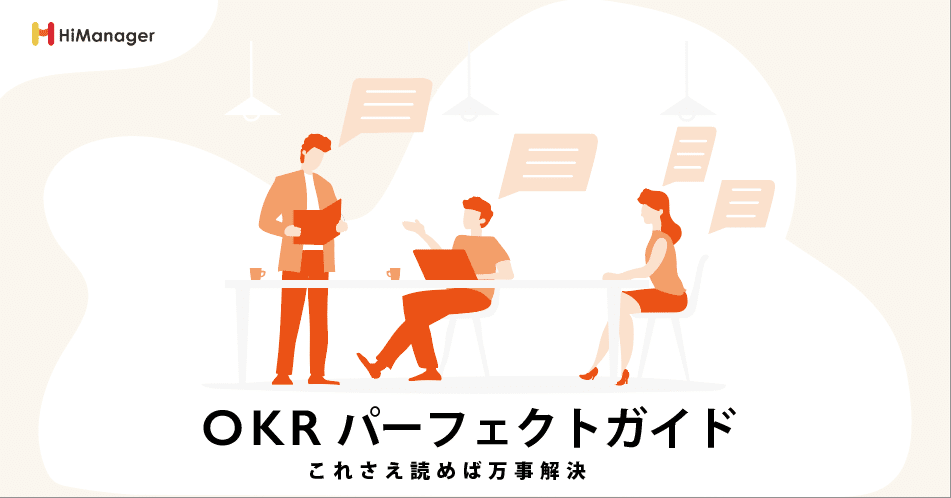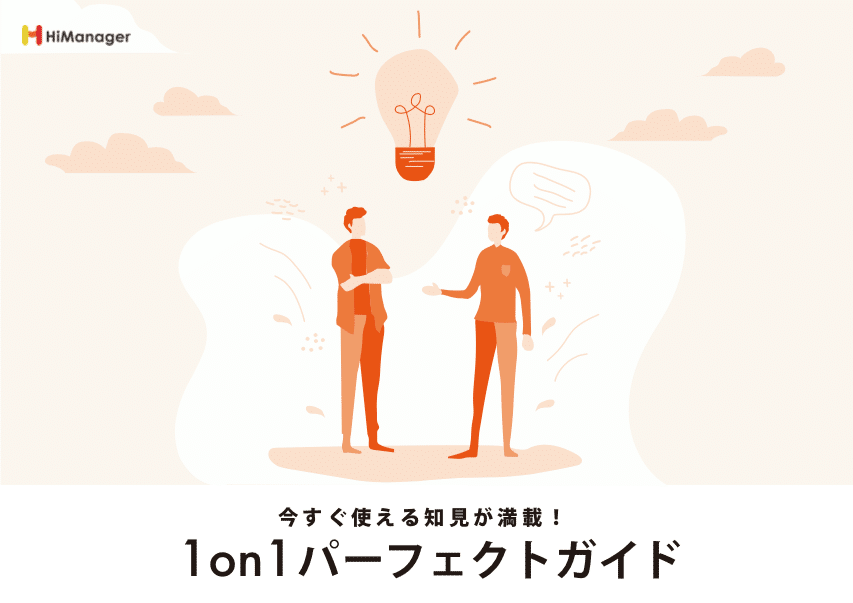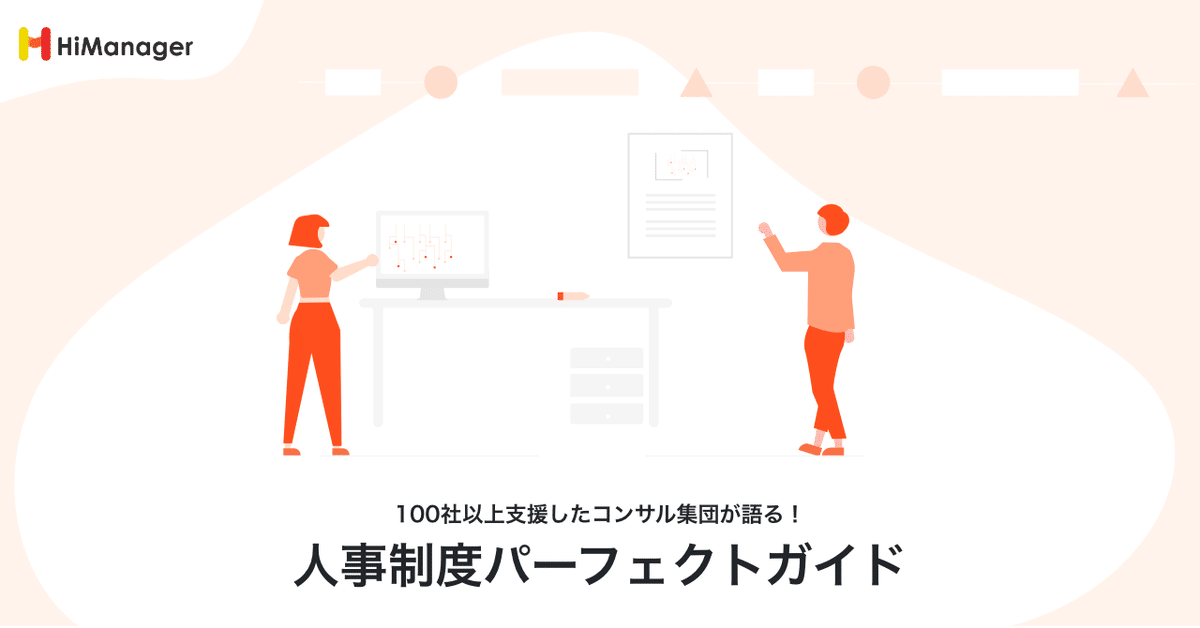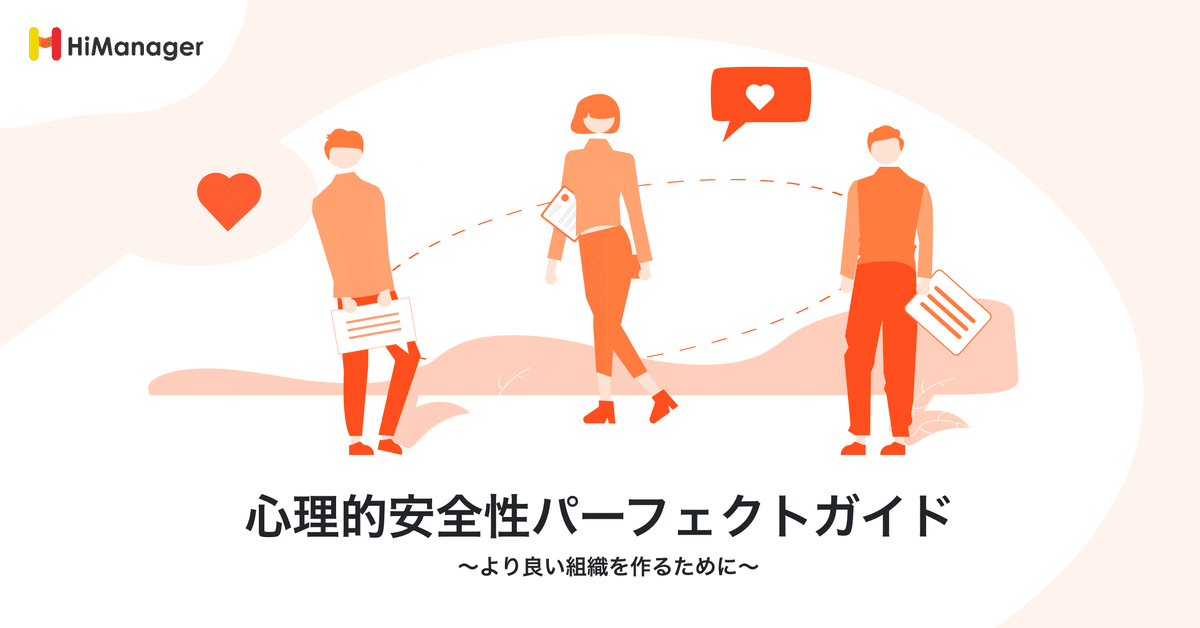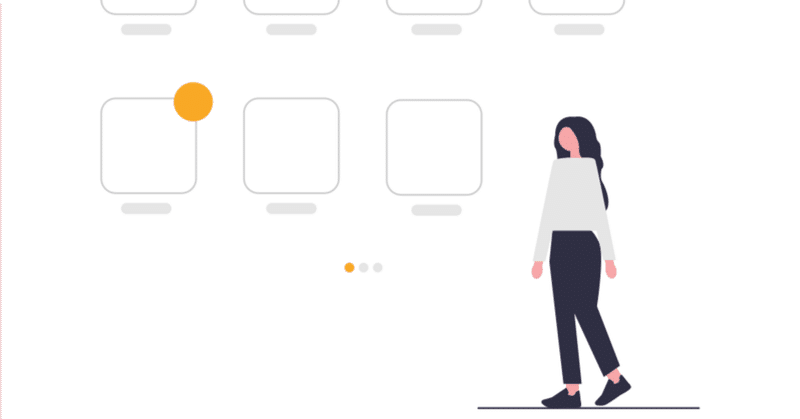
OKR大質問会!ニーズの高い質問にお答えします【第4回 OKR集中講座レポート】
OKRや1on1、リアルタイムフィードバック、人事評価等などパフォーマンス・マネジメントを実現するオールインワンクラウド「HiManager」を提供するハイマネージャー株式会社では、経営者・人事担当者様の人事戦略への理解を目的にした、「【無料オンラインセミナー】OKR集中講座」を開催。
OKR集中講座では、HiManagerを通じて100社以上支援していく中で見えてきた、「日本型のOKR導入」について計4回に渡って解説をしました。
本記事では、2023年9月に開催させていただいた第4弾「OKR集中講座~OKR大質問会」でお話させていただいた内容を元にレポート形式でお届けします。
質問①「OKRと評価の連動方法について教えてください」
本日はOKR大質問会ということで、まずは事前にいただいたご質問の中でもニーズの高いものからご紹介させていただきます。
その上で、この場でみなさまからいただいた内容に関しても時間が許す範囲でお答えできればと思っております。よろしくお願いいたします。
一つ目に、「OKRと評価の連動方法について教えてください」というご質問についてです。

まず結論から言いますと、OKRと評価については3パターンのやり方があります。またその中で、実際に達成率を直接連動するのは、難しくなっていると考えています。なので、OKRの達成度を参考にした上で、成果評価を行うやり方が実際には多いです。
その際に、期初の期待値をすり合わせるという点が一番重要なポイントになっていますので、期待値が必ず変わるタイミングでは、改めてすり合わせを行っていただくことが評価の納得感を保つ秘訣となりますというのが今回の回答になっています。

具体的に実際の活用パターンをご説明します。評価に連動させないパターンが1つ入ってるんですが、大きく三つあります。
一つ目は、これはよく教科書にも書いてある評価に連動させないよというやり方ですね。評価から切り離して、他のMBOを別途用意する、または目標での評価はやめにして行動評価だけで評価をしていく、役割評価だけで評価していくなど、目標は評価と切り離すというやり方にしていくというパターンです。
二つ目は、先ほど申し上げた達成度はあくまでも参考値とし、マネージャーが総合的に判断して成果評価を実施していくやり方です。
そして、三つ目は、いわゆるMBOと同じでOKRの達成度に応じて、デジタルに評価を決定していくというやり方です。
それぞれに適したケースはどれかというと、パターン1については部門導入など、全社で行わない場合で、むしろ選択肢がなくこれになっていくと思います。
一方でパターン2については、基本的に全社導入を行う場合にはこのやり方がいいんじゃないかと思っています。
実際、私が見てる中でも8割以上の企業がこのやり方をしていると思っています。
最後のパターン3は、例えば、「MBOなんだけど、目標の公開をしたり、運用の仕方はリアルタイムのコミュニケーションでやっていて、OKRっぽくやっていく」といった場合は、良いと思います。
これはなぜ良いのかというと、まず完全に切り離してしまうと目標を追いづらい状況になってしまうと思っています。
例えばMBOとOKRを両方やると、やはり人は、報酬に基づくMBOをまず達成したいっていう思いの方が強く働いてしまうと思いますので、OKRの良さが発揮できなくなってしまう可能性があります。
特に、国内ではMBOがとても普及しているので、目標は報酬に紐づくという意識が高く、その中で報酬に繋がないと採用しづらい、または、なかなかこれでうまくいく会社は少ないと思っています。
また評価をデジタルに行ってやってしまうと、チャレンジな目標を立てる意義がなくなってしまう可能性があるという点でも、パターン3は、選択しづらいと考えています。

そういった面を踏まえて、パターン2が主流になっていて、例えば達成率が60%,40%,80%になった時に、平均達成率を出してデジタルに決めるのではなく、右のような成果評価の基準として、期待通りの成果ならB評価、大きく期待を超えたならS評価にするという形をとっています。
あくまでも期待に対して成果がどうだったかを判定していく形で、その目安として60%70%あたりをラインに置くのが良いと思っています。
これがデジタルでつけるのと何が違うのかというと、70%だからBだねってつけていいように思うんですが、例えば期中に目標に変更があった場合、変更があり難易度が上がった一方で、50%だったからCとなってしまったり、逆に簡単になったから、80%以上達成なのに、それをSとしてしまうといったことが発生してしまうと考えています。
そこは、そうではなくて、あくまでも達成率は目安で、変更したときの期待やその期待を期末までに見立てたかどうかで判定していきますというのが違いになります。
ただ、マネージャーの主観的な判断が入ってしまうケースはあるので、ちゃんと期待値が何だったのかを明文化したり、ちゃんと部下とコミュニケーションが取れているかを、特に、人事の方も細かく見ていかなきゃいけない部分があるとも思っております。
質問②「OKRは未達前提で良いのか」
続いての質問は、「OKRは未達前提で良いのか」についてお話させていただきます。

こちらについても結論からお話させていただくと、OKR自体は達成不可能な目標を立てるわけではないというのが重要なポイントです。
ムーンショット=達成不可能と、皆さん思いがちですけど、あくまで達成不可能ではなく、達成可能ではあるんだけど限りなく難しい、なかなか一筋縄ではいかないというのが、OKRなので、達成不可能ではもちろんないです。
達成すること自体を目標にしていく、これは忘れちゃいけない考え方だと思います。
未達前提ではなく、絶対達成したいというものになっているか、ここはぶれちゃいけない部分です。ただ、もちろん未達になることは多いというのが実情だと思います。

そうなったときに、設定上は未達であったとしても、許容できる状態で、60%から70%あたりを通常の目標設定であれば超えていく内容にしておくというルール設計にしておくことで、未達なんだけども通常以上の成果を出している状況にということが可能になってくると思います。
ただこれに対して、成果で見たら、結果が出ているのに未達となってしまったことに違和感があると考えられてる方々もいらっしゃると思いますので、その場合の運用・設計として、コミットOKRとムーンショットOKRの2段階で設定していくという会社さんもあります。
例えば、売上170万円というOKR目標に対して、売上100万というコミットOKRを置いていただくと良いんじゃないかなというふうに思っております。
質問③「OKRに対して、必達で追うべき計画はどのように考慮して運用していくと良いのか」

こちらのご回答としては、先ほどの内容でも触れたように、ムーンショットOKRとコミットOKRを二つ設定する方法をお伝えしました。
その上で、日々のコミュニケーションをどうしていくのかですが、これはムーンショットOKRだけを見ていくのが正しいやり方だと考えています。
ここでコミットOKRを見てしまうと結局、MBOを並行して立てているのと同じになってしまうので、まずはムーンショットOKRで会話していきましょう。


ただし、運用を進めていく中で、コミットラインにももう届かないんじゃないかという可能性が見えたタイミングでは、目線を切り替えてまずはコミットOKRを達成するためにどうするかっていう視点に変えていく必要もあると思います。
イメージとしては、まず、ムーンショットOKRを目指して、大きくプロセスをチェンジする発想をしていく、そのための1on1やチェックインセッションをやっていくことがまず大事です。
その後時間が経って、仮にコミットOKRも危うくなってきたなという場合に、ムーンショットに拘って、コミットも届かないというのは会社として存続の危機になる可能性があれば、その場合にちゃんと売上100万円というところに目線を切り替えて会話をしていくのが、正しいやり方だと思っています。
質問④「経営や事業OKRはどの程度の粒度で設定するのが良いか」

こちらの質問について回答すると、これに決まりはないです。

ただ、言えることは、上位のOKRが細かすぎると、それに紐づいた個人OKRを作る際に、難しくなってしまうので、それを考慮した上位概念を設定する必要があると思っています。
例えば数値系であれば売上利益とかですし、数値化できないものも最終結果を設定するべきだと思います。
例えば、極端な例ですが、提案件数が何件、受注率が〇〇%以上、営業フローの改善に向けた〇〇施策の実施といったKRだと、これを受けて個人OKRを作る時に、決めづらいかもしれません。

なので、最終結果をなるべく置いてあげて、個人が設定できるようにしてあげる必要があります。また、個人は細分化してもあくまでも追ってるのは最終結果だという点もポイントです。
質問⑤「コーポレートと部門でOKRを発表し合う場を儲けようと思うが、同様の事例はあるか」

こちらは事例についてご紹介させていただくと、期初の発表の時に
「なぜそのOKRを追いたいのか」、「OKRを達成することで会社や組織にどんな影響を与えたいのか」、「他の部門に協力してほしいことは何か」
を、話している会社さんがいくつかありました。
私としては、熱量ある部分を伝えて盛り上げていくことが重要だと思うので、ここを担当する部門長の方が、想いやストーリーを伝えて、他の方にもその目標の意義を伝えていくのが良いと思います。
また、期末に結果とともに代表的なエピソード、こんな成果が出た、こんないいことがあった、特に貢献したメンバーや他組織の方、協力してた方を表出するケースが多かったです。
後はウィンセッションを各部門やチーム間でやってることが多いと思うんですが、期末はそれとは別に全社でやったり、月1程度は会社全体でやっている会社さんもありました。
その場合は、部門連携・部門間でよかったものを、お互い褒め合って、賞賛し合っていくことで、部門連携していく意義や、ちゃんと協力してよかったよねということを思えるような組織文化にしていく工夫をしているケースがありましたので、ぜひこういった部分を発表していく上で取り入れていただけると良いんじゃないかなと思っております。
質問⑥「OKRを設定するとどうしてもToDoのような内容になってしまう。回避方法はあるか」

まず可能性としては、手前でお話しした上位のOKRの粒度に問題があるかもしれません。
一度、上位のOKRを見直してみてください。それ以外には、目標を添削していくのが大事になってきます。
「そのToDoを行うことで得られる成果は何か」を問いかけていただいて、それで上がった成果をOKRに設定していくのが大事です。
例えば、メンバーから〇〇業務に関する改善点を洗い出しますといった、目標が上がってきたとします。
これってToDo的な形だけど、ここから得られる結果は何か?と質問して考えていくと、〇〇業務における業務フローの設計が完了することが成果なんじゃないかと出てくるかもしれません。
またこれを考えていく意味は、例えば業務フローの設計を見たときに、必ずしも最初に言っていたToDoが必要じゃないケースもあり、別の優先順位が高いものが見えてくる可能性があるということです。そういう意味でも結果は何か?と、問いを立てていきましょう。
質問⑦「バックオフィスなど通常業務が多い部署ではどのようにOKRを設計しどのように評価すべきか」
最後に、バックオフィスなど通常業務が多い部署ではどのようにOKを設計しどのように評価すべきかというご質問をいただきましたのでこちらについて回答させていただきます。
まずどのようにOKRを設計すべきかというと、数字じゃないものでも目標に置いていきましょうというところが大前提にあります。
また、通常の業務自体を目標設定してしまうとなかなかムーンショットな目標を立てられないと思いますので、基本的にその通常業務以外で新たに付加価値が出ることを入れて、目標設定するのが望ましいと思ってます。
評価においては、通常業務がきちんと遂行されていれば、それはある程度期待通りということで、B評価になりますよという期待値を握ってあげるのが良いと思っています。
ただSやAとなると、より大きな成果、大きな貢献を求めたいので、OKRで設定してるある種プラスアルファのようなものをセットし、やっていただかないと、さすがにSにはなりませんよというコミュニケーションをしていただくのが良いと思います。実際に他社の場合は、こういった形でやられているケースが多いです。
では、お時間も迫ってきましたので、今日の場は以上とさせていただければと思ってます。
お時間いただきありがとうございました。
引き続きよろしくお願いいたします。
・・・
ハイマネージャー
OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。