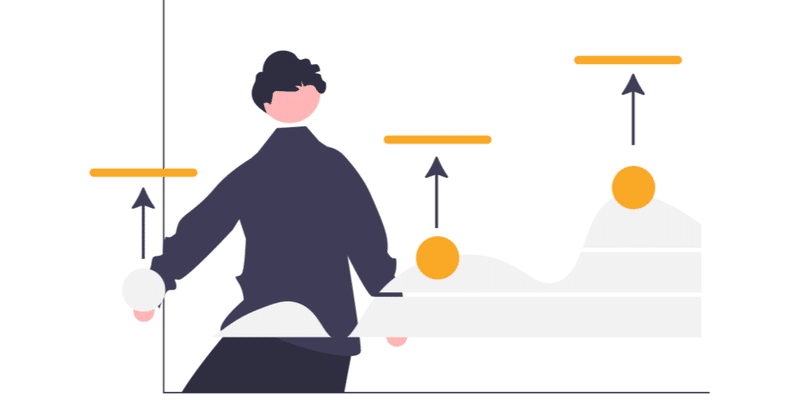
OKR活用の成功事例と失敗事例解説!成功につながるポイントとは?
OKRは、チームマネジメントや組織運営において重要視される要素であり、多くの企業が導入を進めています。
従業員に対し会社の方向性を示すためにも、全体のコンセンサスを取ってブレなく業務に邁進しパフォーマンスを向上させるためにも、もはや欠かせないものとなってきました。
そんな中今回は、OKR活用の成功事例・失敗事例を紹介します。
成功につながるポイントにも触れますので、今後OKR導入をしたい場合や、現在導入済みのOKRを見直したい場合にご活用ください。
OKRとは
OKR(=Objectives and Key Results)とは、「目標=Objectives」と「主要な結果=Key Results」を設定しておこなう目標管理手法のことです。
代表的な活用シーンとして、人事評価におけるフィードバック指標が挙げられます。
会社やチームが設定した目標に対し、どんな結果が得られたかを可視化してフィードバックすることで、双方納得感の高い人事評価ができるようになるでしょう。
OKRに関する詳しい内容については、下記の記事で細かく解説しておりますので、気になった方は是非読んでみてください!
OKRとは|MBOとの違い
MBO(=Management By Objectives)は、半年から1年程度で区切りをつけ、従業員を評価する管理手法のことです。
OKRと似ていますが、OKRよりMBOの方がフィードバックまでの期間が長く、定性的な視点を盛り込む傾向にあります。
従業員ひとりひとりMBOが異なることも多く、個人ベースの目標管理手法だと言えるでしょう。
OKRとは|KPIとの違い
KPI(=Key Performance Indicator)は、最終目標を数値ベースで可視化し、都度フィードバックをしていく管理手法のことです。
OKRがあらかじめ目標を示したうえで達成に向けて努力する過程を管理するのに対し、KPIは目標達成度合いそのものを管理します。
100%達成のために何が必要なのか、現状の達成率が何%なのかを把握するため、定量的な視点が強いと言えるでしょう。
あくまでもゴールは目標mの100%達成ではありますが、中間管理のために用いられることが多いです。
OKRとは|KGIとの違い
KGI(=Key Goal Indicator)は、KPIよりもさらに最終目標達成に重点を置いた指標のことです。
目標達成に対して必要な要素を細分化して考えることが特徴であり、目標管理手法というよりは現状を正しく把握するための指標だと分かります。
戦略立てに使われることが多く、KGIを設定したあとにKPIで中間管理、MBOで個人ベースの目標づくりをするケースもあります。
OKRを導入するメリット

ここでは、OKRを導入するメリットを紹介します。
どんな効果を得られるのか改めて把握し、自社にあてはめたときのメリットがどれくらいあるか、イメージしてみましょう。
メリット①|会社と個人の方向性をすり合わせできる
最適なチームマネジメントのためには、会社と個人でゴールを共有しておく必要があります。
会社が何を求めているのか、どんな成果を達成したいのか組織全体に浸透させたいときにOKRを導入し、会社と個人の方向性をすり合わせるのがよいでしょう。
企業理念やミッション・ビジョン・バリューを浸透させることも効果的ですが、業務成績・売上額などパフォーマンスの面で目標共有できるということが利点です。
メリット②|チーム全体で同じ方向を向いて努力できる
OKRを適切に導入できれば、チーム全体で同じ方向を向いて努力できます。
会社が求めていることが可視化されている状態であるため舵取りがしやすく、管理職によるマネジメントや研修も一定化しやすくなるでしょう。
業務に対する明確な優先順位も示せるため目標達成までのシンプルなルートを描きやすく、チーム内でコンセンサスを取ることにつながります。
メリット③|従業員エンゲージメントやモチベーションの向上につながる
やるべきことや努力すべき方向性が明確になるため、前向きなやる気を活性化できます。
従業員エンゲージメントが高まって離職率が低下したり、モチベーションが上がって短時間でもより高いパフォーマンスを期待できたりするようになるでしょう。
業務効率改善やコミュニケーション促進施策としても、有効であることが分かります。
メリット④|透明性が高く納得感のある人事評価をしやすくなる
OKRに基づいて人事評価することで、透明性が高く納得感のある人事制度として確立させることができます。
なぜ自分の給与・評価が今のポジションにあるのか明確な理由づけがされるため不満が出にくく、次の人事評価に向けて努力すべきポイントも分かりやすくなります。
上司ひとりの好き嫌いによる人事評価を避け、客観性を示すためにも効果的なのです。
OKR導入の失敗事例
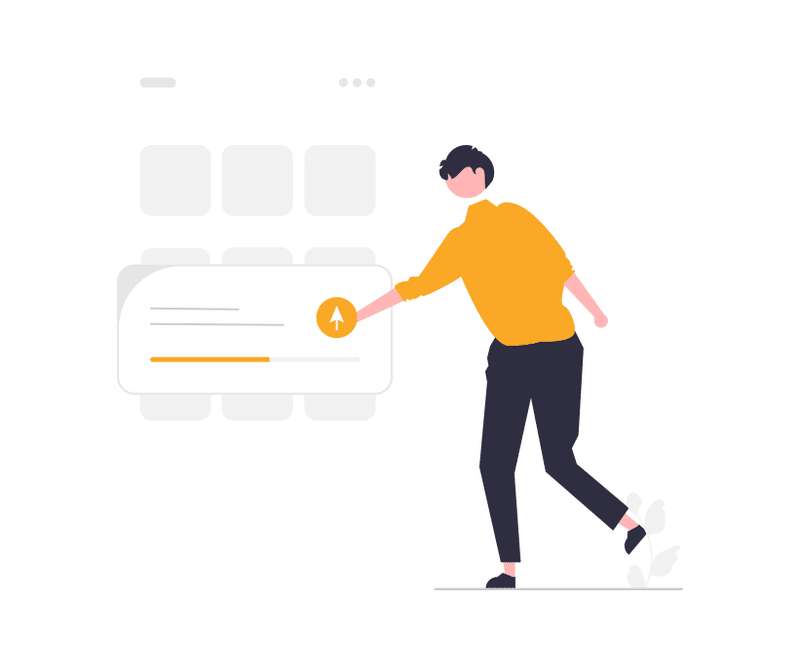
次に、OKR導入の失敗事例を紹介します。
非常に導入メリットが高いOKRですが、運用次第では期待通りの効果が得られないケースもありますので、参考にしてみましょう。
OKRの失敗事例①|フィードバック工数を確保できない失敗
OKRを成功させるためには、目標設定・進捗管理・個別のフィードバック・目標を都度メンテナンスすることが大切です。
いわゆる「PDCAサイクル」を効果的に回していくことが、成功に欠かせない要素であると言えるでしょう。
このフィードバック工数を十分に確保できないままOKRを導入すると、「導入しっ放し」「目標を立てただけ」になりかねません。
OKRが形骸化したまま自然消滅する可能性もあるため、あらかじめリスクのひとつとして知っておきましょう。
OKRの失敗事例②|スモールステップで導入しなかった失敗
OKRの導入メリットが高いからと一気に全社導入させ、管理が追い付かなったことによる失敗事例も存在します。
全社導入した場合プロジェクトの規模が大きくなり、OKRの考え方が定着するよりも前に結果を求めてしまうこともなるでしょう。
スモールステップで導入して成功の秘訣を知ってから全社導入するなど、工夫していくことが重要です。
OKRの失敗事例③|定性的人事評価を組み込まない失敗
人事評価は目標の達成度合いだけで決まるものではなく、コミュニケーションスキル・遅刻や欠勤のない勤務態度・後世の育心などさまざまな要素が絡み合います。
OKRは実力より少し上の、クリアが困難な目標を立てることで理想的な効果が現れる手法であるため、OKR達成度合いによる人事評価だけを重視するのは問題です。
OKRに向き合っている社員の方が人事評価が低くなり、クリアできそうな無難な目標だけを掲げている社員の方が人事評価が高くなるなど、マイナスインセンティブを抱えることになりかねません。
OKRの失敗事例④|流動性が高すぎる企業にOKRを導入してしまった失敗
頻繁にチーム編成やマネジメント人材に変更が出る企業や、設立間もなく今まさにチームビルディングに着手しはじめたばかりの企業は、OKRが向きません。
企業理念やミッション・ビジョン・バリューを定めて浸透しきってからでないと、OKRによる数値的な目標ばかりが先行してしまうことになるでしょう。
却って舵取りが難しくなり、自社文化の創出を阻害する可能性があるため、注意が必要です。
OKR導入の成功事例
反対に、OKR導入の成功事例を紹介します。
いくつか具体的な社名をピックアップしていますので、こちらも併せて参考にしたうえで、共通している要素を見つけていきましょう。
OKRの成功事例①|Google社
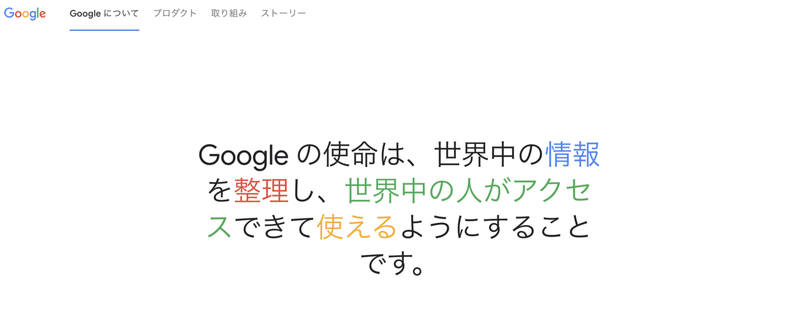
Googleでは、目標達成率60~70%程度となるOKRを理想として掲げ、ハイレベルでの導入を進めています。
成果指標は簡単に評価できるよう0から1.0までの範囲で設定し、四半期ごとのこまめなフィードバックをおこなうよう意識しました。
そのためチームも個人も今どの状態にいるのか可視化しやすくなり、やるべきことが明確になったというメリットを得ています。
あえて人事評価にOKRを組み込まなかったため強気の目標設定をする社員が現れるようになり、前向きな競争心を創出できたこともポイントです。
OKRの成功事例②|株式会社ココナラ

スキルマーケット「ココナラ」を手掛ける株式会社ココナラでは、個人目標をベースとしたOKR導入を叶えています。
「個人目標が達成されれば自然と全社目標も達成される」という考えのもとで導入をおこない、人事評価に納得感を出すことに成功しました。
全社目標と個人目標を連動させているため、会社が個人に期待している内容と反しないという点でも理想的な導入だと分かります。
OKRの成功事例③|株式会社メルカリ
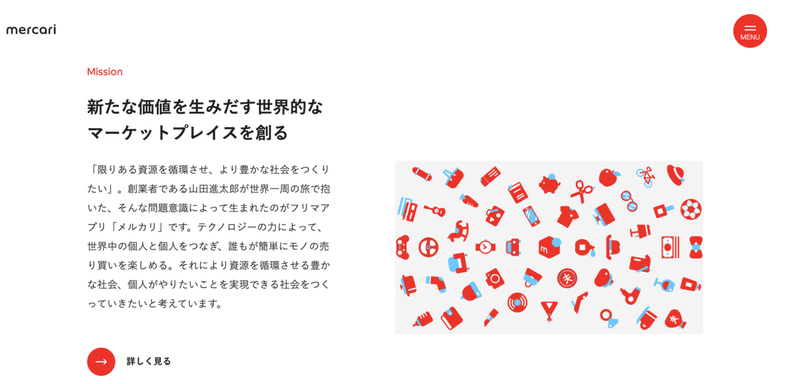
フリマアプリ「メルカリ」を手掛ける株式会社メルカリでは、3ヶ月スパンという短期間でのOKRを設定し、PDCAサイクルを回しています。
創業8年目でありながら大きな成長をしているメルカリの強みは、時代のトレンドやニーズに合わせて素早い経営判断ができる点にあるとされていました。
この強みを更に活かすために通常よりも短いスパンでOKRを設定し、こまめにフィードバックをすることでズレを早期修正できるようになったことがポイントだと言えるでしょう。
ビジネス市場における機会損失を最大限削減するための手法としても、OKRが有効であることが分かる事例です。
OKRの成功事例④|Chatwork株式会社

ビジネス向けチャットシステム「Chatwork」を手掛けるChatwork株式会社では、人事評価基準のひとつとしてOKRを導入しています。
導入のきっかけとなったのは、会社自体に元々目標設定をする企業文化がなく、上司がひとりひとりの活動を共有しながら人事評価するスタイルで続けていたことでした。
成長とともに従業員規模が大きくなり、評価工数が膨らんでいたことが問題視され、「誰が何をやっているのか」を可視化するためにOKR導入が進みました。
結果として従業員数が増えても会社の戦略・方針を浸透しやすくなるなど、人事評価制度改定以上のメリットも得られています。
OKR導入を成功させるポイント
最後に、OKR導入を成功させるにあたり、抑えておきたいポイントを解説します。
どんなスタイルで導入する場合でも下記のポイントを抑え、失敗を防ぐ手立てを打っていきましょう。
ポイント①|会社の理念や経営方針を浸透させておく
OKRにメリットがあるからと、OKR導入だけが先行してしまうと失敗しやすくなります。
事前に会社に理念や経営方針を浸透させておくことで、OKRを導入したときに「なぜこの目標が立てられているのか」「急いで達成すべき理由が何なのか」を示しやすくなるでしょう。
目標に対する納得感を得られるため不平・不満が出づらく、ポジティブなモチベーションを喚起するためにも重要です。
ポイント②|個人単位の行動にまでOKRを落とし込む
OKRは個人単位の行動にまで落とし込み、「今自分が何をすべきか」まで可視化させることがポイントです。
「会社全体→事業部→部署→チーム→個人」など会社の組織体制に合わせて落とし込み、それぞれの業務に合わせてアレンジしていきましょう。
個人への落とし込みがないと会社の目標を掲げたのみに留まり、具体的な行動が分からなくなってしまいます。
OKRが形骸化する多くの原因はここにあると考え、意識していくことがポイントです。
ポイント③|定期的な見直しを図って都度修正していく
OKR成功には、定期的な目標の見直しが大切です。
こまめなフィードバックも重要ですが、そればかりに目が行き過ぎて、本質である目標の部分が市場ニーズからズレないようにしていきましょう。
今自社が何を求められているのか、何を達成することでステークホルダーへの利益を最大化できるか考えながら、ときにはOKRで設定した目標ごと変更するような手法も必要です。
まとめ
OKRは非常にメリットの高い目標管理手法です。
しかし成功には多くの要素が必要であり、失敗を経験する企業も少なくありません。
また、定期的なフィードバックが必要であるため評価工数が大きく、自社のリソースでは導入不可能だと諦めてしまうケースもあるでしょう。
ピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」では、OKR成功の秘訣となるリアルタイム評価を支える仕組みづくりをおこなっています。
評価・フィードバックの工数を削減しながらOKRによるパフォーマンス向上を期待したい場合に、ぜひお役立てください。
ハイマネージャーが無料公開する3つのピープルマネジメントに関するパーフェクトガイド資料はこちら
・・・
ハイマネージャー
OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。





