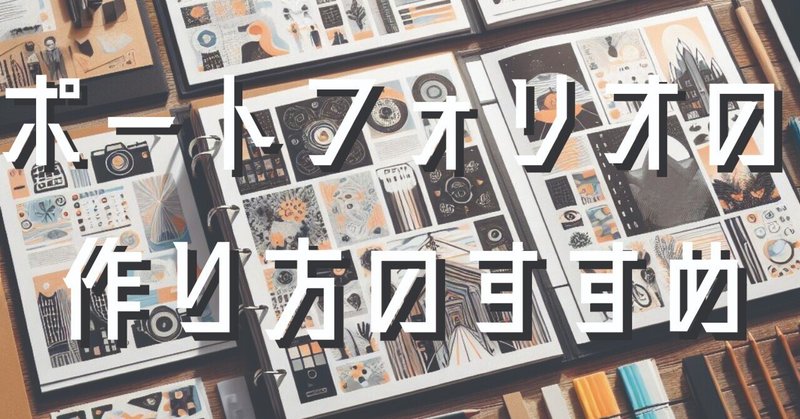
組織設計事務所に高専卒で内定したポートフォリオを公開!
こんにちはDittoです。
とある高専の建築学科に通ってます。
今回は、ポートフォリオの作り方についての記事を書こうと思います。
私はポートフォリオで組織設計事務所の意匠設計に内定できたと思っています。
社長の方にも褒めていただき、正直ポートフォリオで通ったと言っても過言ではありません。
私のポートフォリオも有料記事の方で公開しようと思うので、もしよければ買ってみてください。
さて、建築学生が就活の時期に一度は経験するポートフォリオ。
ポートフォリオは、自分の作品やイベント等、今までやってきたことをまとめたものです。
どこかの記事でも言いましたが、私は、就活の書類選考の1ヶ月前に作り始めました(笑)
どう考えてもスケジュール管理不足です(笑)
ここからは、ポートフォリオの作り方を説明します。
とはいえ、正解はなく、自分を表現できているものであれば、どんなものでもよいと思っています。
なので、今回の記事の内容はあくまで参考までに。
まずは、ポートフォリオで使った参考本、道具を紹介。
まずはa3のファイル。丈夫なのでおすすめ。
業者に頼むより安く済むのでおすすめ。学校のプリンターを使わしてもらうのが良いと思う。
図面の上にダイヤグラムなどをトレペに印刷してレイヤー上にして説明するのもあり。個性が出せる。
とりあえずこれはレイアウト決める時におすすめの一冊。
フォリオはどうしても容量が重くなるので、学校のスペックの良いパソコンでやってて、自分のノートパソコンのデータの移し替えができるので必須アイテム!
夜遅くまでパソコンとにらめっこなので、目が疲れる。100%近くブルーライトをカットしてくれるこちらがおすすめ。つけてるのとつけてないのとでは全く違う。
ここからは本題に入ります。この先に私の内定をもらった時に使用したポートフォリオがあります。
ポートフォリオはこう作るのがおすすめ
とりあえず見開きa2又は、見開きa1で作るのをお勧めします。
面接の時に見やすいからです。
ネットにありがちな横向きにレイアウトしてしまうと面接の時に見にくくなります。
教授は「最近の流行りだよね~、なんで横長でレイアウトするんだろう」と言っていました。
確かにa3横でレイアウトはしやすいですが、面接の時に横に長いと内容が入ってこないと思います。
ぶっちゃけ面接官は、内容も見てますが、作品をまとめる能力、作品の魅力を伝えるプレゼン能力を重視していると思うので、自分が発表しやすい様式にまとめた方がいいです。
良いデザインとは使う人の立場になって考え設計したものを言うとどこかの本で読みました。なので、流行りに惑わされずa3縦でレイアウトしましょう。
コンペとか出して賞を取りましたってその部分もアピールするのはいいのですが、そのプロセスやどこを評価されたのかも言えるようにする。
それは、フォリオ内に書いた方がいいかもしれません。
ポートフォリオは自分をアピールするもの
どんなまとめ方でもいいと思います。そのまとめ方自体がその人を表すので。
ただ、見る人が見やすいって言ってこそいいデザインと言われていることをお忘れなく。
人は人、なので自分のフォリオに自信を持ってください。
大学又は、大学院の場合は、設計が得意な人だけを合格にするわけではありません。
設計が苦手でも大丈夫ととある教授の方が言ってます。
ちゃんと設計課題をといたこと、他ボランティアや課外活動などで頑張ってきたことをアピールしたらいいです。
どう使うかを考える
説明してください、と言われたらどう説明するか、も作成時に考えておくことが重要!
説明可能な時間は3分程度と思っておいたらいいと思います。
全部説明できなくてもいいので、言われた時間で何を説明するかを事前に考え、フォリオを作るといいと思います。
ストーリーを考える
自分なりに就職したいところ、又は大学、その先をイメージして編集しましょう。
学生時代でやってきたこと、そして何に関心を持っているのか、その延長で卒業研究では何に取り組んだのか、又は何に取り組もうとしているのか、その先の進路でやりたいこと、将来はどう考えているのかをまとめたページを作る!
その流れが繋がるように(完璧でなくてもいいです)ストーリーを組み立ててみてください。
なぜ、そこに入りたいのかという志望理由にもつながりますし、卒業研究のテーマにも関係してきます。
設計理念などを作ってそれから活動、設計、卒研に繋げていくのがいいと思います。
例)私の場合だと「+αの機能と有機的なデザインのある建築」が設計理念だったので、私は、今まで都市にどんな「+αの機能」が必要か考えて設計してきました。
この作品では、〜に対してこういう機能があれば〜につながるのではないかと思い、こういうデザインになりました。
そんな中私は、建築史を学べる研究室に入りました。建築史は、〜が学べるので、その歴史を研究して、これからの都市に必要な「+αの機能」を考え、〜をテーマに卒業設計をしたいと考えています。
私は、今までの設計から大規模な設計で私のアイデアを活かし社会に貢献しようと思っています。
御社の企業理念は、〜に対して新しいことをしようとしていますので、私の挑戦したいことと合致しているので御社の志望を決めました。
上の例のような感じで話すと面接官のウケが良かったです。
そこがどういう人を募集しているのか、そこでは何ができるのか、何を学べるのか、ちゃんと調べて、そこから逸脱しないようにしましょう!
図面の手直しなど
・場合によっては手直しもしたらいいと思いますが、全体のバランスを見るようにしましょう。
フォリオは大事ですが、細かいところまでは説明しきれません。
最低限抑えないといけないところだけ、ブラッシュアップすることをおすすめします(図面に時間かけすぎて、他のことが疎かにならないようにするため)
最低限の図面の決まり、書くべき記号などは、絶対入れましょう。
縮尺がうまく合わない場合は、スケールバーも視野にいれましょう。方位や縮尺には注意です。
学生生活でやったことの一覧を作る!
ここから先は
¥ 500
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
