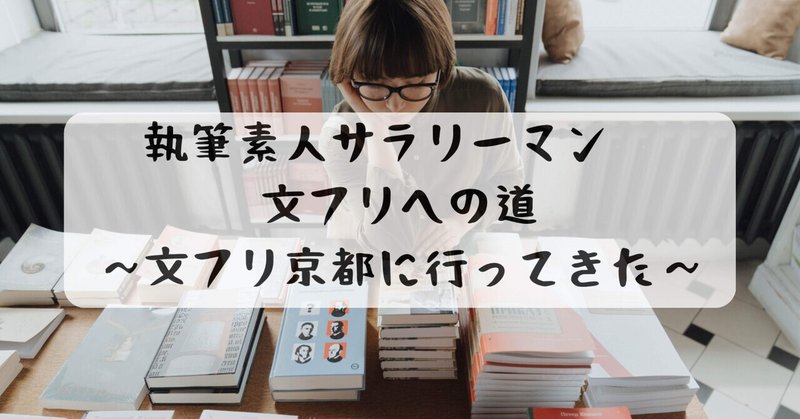
執筆素人サラリーマン 文フリへの道〜文フリ京都に行ってきた〜
楽しみにしていた2024年1発目のイベント、文学フリマ京都に行ってきましたので、レポートします。
来年出店のための参考情報もたくさん仕入れることができましたので、その辺もまとめています。
出店したいと思った経緯はこちらへ↓↓
1年ぶりの文学フリマへ
文学フリマ自体は去年にその存在を知り、初めて参加しました。
その時は会場の熱気に圧倒されました。
今回は単純に購入者として、そして来年の出展の下見という目的も含めた参加でした。
到着したのはお昼過ぎ。
行く途中でTwitterを見ていましたが、「始まりました」「出店してます」等の投稿で賑わっていました。
そして、中には「完売しました」なんていうツイートもあって、びっくりしました。
開場してまだ1時間というところ。
そんな強者もいるんだなと思いながら向かいました。
一年ぶりのみやこメッセが見えてきました。
会場から出てくる人の「あー、楽しかった」という会話を聞くとワクワク感が高まります。
前とは少し違う視点で
会場は去年と同じように入り口入ってすぐにアンケートを書くテーブル、その少し奥に見本誌が置かれているテーブルがあります。
そして、出店者のテーブルの列が出店記号の"あ"〜"そ"まで並んでいます。
見本誌コーナーで品定め。
"あ"〜"そ"毎にテーブルが分けられていて、そこに見本誌が並べられていました。
まずは見本を見たいという人が多いのか、人でごった返していました。
「出店ブースの前は緊張するから、ここで見ておかないとね」
なんて声も聞こえてきたので、このコーナーは重要なんだなと思いました。
本づくりの参考にしたかったので、いろんな種類の見本を手に取ってみました。
何冊も見ましたが、本の大きさ、フォント、質感、ページ数…
全てそれぞれ違って、本当に自由だなと思いました。
見開きの1ページの中でフォントが違う構成をしている本もあったりして、書店で買えるような本ではない味がありました。
確認したいと思っていた印刷所も奥付けで見てみましたが、十人十色。
中には「印刷所:ファミリーマートのプリンター」と買いたものもあり、自作している人がいるというのも発見でした。
また、フォントサイズが小さいものはやはり見づらく、かといって、大きければ良いというものではないので、心地よいサイズ感というのも重要だろうと思います。
あとは見本誌を物色するふりをして、他の人がどんな本に手を伸ばしているかを観察しました。
やはり、表紙のインパクトは大きく、周りの本が使っていない色の本や配色のバランスが良い作品は手に取られやすいと観察しました。
また、ある程度の厚さのあることも重要と感じました。
数枚だけの小冊子よりも、背表紙のあるものに目が行きやすいのではないかと推測しました
出店ブースで売り場の観察
ある程度目星がついたところで、出店者ブースへと移動します。今度は売り場の観察です。
まず、ブースのビジュアルがそれぞれ違いました。
出店者名や本のタイトルが印字されたノボリが立っているところ、垂れ幕を張ってるところ、フリーペーパーを配ってるところ、作品に合わせてコスプレっぽくしているところ、京都らしく浴衣を着ているところ…
ブースには、いろんな装飾が施されていて、参考になりました。
そして、次に出店者によっての違いがあったのが、接客方法。
座っている人
立っている人
前を通った人に声をかけている人
宣伝のチラシを配っている人
本を読んでいる人
いろんなやり方がありました。
出店の経験値によっても差がありそうですが、やっぱり通りすがる人に目を合わせにいったり、話しかけたり、フリーペーパーを配っているところは、誰かしら足を止めていました。
この点は作品を売ることに対する考え方はいろいろだと思うので、一概に良し悪しはないですが、売り方っていうのも重要な要素だなと思いました。
あるお店で子供の写真の表紙の本に目が止まり、あるお店に立ち寄りました。
最初は写真集かな?と思いましたが、写真と小説を組み合わせている本のようで、面白いと思い、見本を見てみました。
すると、出店者の方から声をかけていただいて、作品について話しているうちに、その方も自分と同じように写真を撮るのが好きなんだという話になって、盛り上がりました。
見本を見た時に買おうかなと思いましたが、話の中で作品のバックグラウンドを知ると、より買いたくなります。
作品を知ってもらうにあたって、コミュニケーションをとるって大事だなと感じました。
ある程度見終わり、最後に以前別の書店で買った本の作家さんのブースに行きました。
そこでは、作品がダンボールか何かで作られたひな壇のような台に見本が並べられていて、とても見やすかったです。
複数の作品があるからこその見栄えだなと思ったので、いくつか作品を持っているというのは強いなと思いました。
挨拶もそこそこに本を買って、みやこメッセを後にしました。
来年の出店に向けて
今回、購入側と出店側両サイドの視点から文フリに参加することができて、いろんな観点で学び、楽しめました。
ここにポイントをまとめます。
本のデザイン
表紙デザインは、作品を表すようなものにすることはもとより、見本誌コーナーで他の作品と並ぶことを意識したデザインにすることが大事。
背表紙がつけられるくらいの厚さにした方が手にとってもらいやすいかも。
フォントは小さすぎず、大きすぎず、行間の幅も読みやすいように考える。(市販の文庫は9pt, 行間13.5pt程度)
出店ブースづくり
何組も横並びに出店している中では、ノボリや垂れ幕はアピールするのに効果的
複数の作品を並べた方が見栄えが良い
フリーペーパーやおまけがつくのは、購入者にとって嬉しいのでは。
お客さんが本を見やすいように、本を台に並べたり、置き場をつくるのは有効
売り方
立って売る方が良い。宣伝用のチラシを配りながらもありかも。
通りすがりの人に目を合わせる。声をかける。
見本を見てくれた人にはコミュニケーションを取る。共通点を探す。
作品を作った背景を簡単に説明できるようにしておくとGOOD
以上が今回の文フリで学べたことでした。
かなり収穫がありました。
来年に向けて、頑張ろうというモチベーションが上がりました。
と同時に、正直あの場で自分の本が本当に売れるのか?という不安にも駆られました。
事務局の発表によると、今回のイベントでの参加者数は3,643人で過去最高。
来年も増えるのでしょうか。
3,000を超える人から果たして何人が振り向いてくれるのか。
来る25年1月19日の出店に向け、着実に準備を進めていきたいと思います。
最後に購入者として、お迎えした作品の写真を。
来年は誰かの写真に、自分の作品が写っていることを夢見ながら...

終
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
