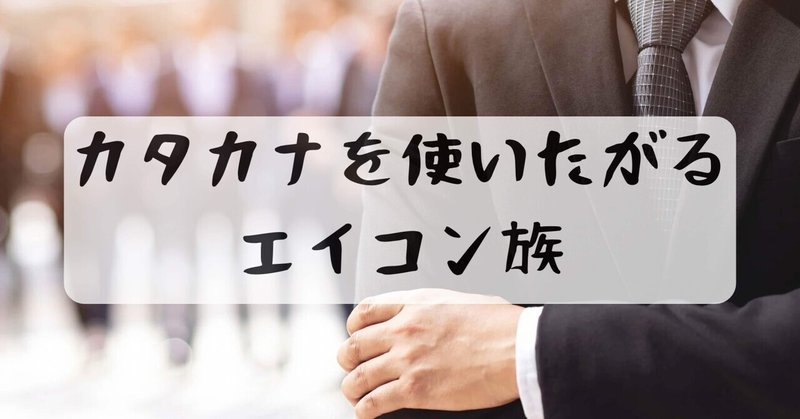
カタカナを使いたがるエイコン族
この世には、やたらとカタカナを使いたがる会社人がいる。
「次の会議で事業部と"コンセンサス"を得ないとな」
「これくらいの事業規模であれば"ペイ"できるな」
「今日の会議の内容は"エスカレーション"しないと」
僕はこう言った人たちのことを心の中でASAPなコンセンサス族(以下、エイコン族)と読んでいる。
彼らはカタカナを使うことで、できる感を出したがる。
それを使うことで、スムーズな会話を阻害していることも知らずに。
この前、チャットでこんな会話があった。
僕「〇〇の仕事、いつまでに完了させましょう」
上司「うーん、先方も急いでるからASAPかな。」
僕「承知しました。」
そのやりとりを見ていた後輩「ASAPってなんですか?」
それを知らない人は、仕事の内容ではなく、余計なところに疑問を持ってしまう。
こちらとしても、それを教える時間も割くことになる。
せっかくコンクリートで舗装された道を自転車で気持ちよく進んでいたのに、急に土剥き出しの道が現れて、ガタガタと言わせながら進まなければならないような感じだ。
お尻が痛い。
さらには、このカタカナを使うエイコン族人が管理職だったりするので、コミュニケーションを取るために非管理職のメンバーもカタカナを使う。
結果、統一した使い方がないカタカナが乱用され、本当の意味で意思疎通できているのか、分からなくなる。
「前の会議でA案は"アクセプト"されませんでしたが、B案は"アグリー"だったので、先方との"コンセンサス"は得られたと思います。次の"ステップ"としては、B案をより具体化するために"イシュー"を洗い出して、"プライオリティ"の高いものから対応していきます。」
これは、わざと誇張してカタカナを並べた文章だが、日常にはこれと似たような会話が聞こえてくることがある。
これを聞いている人からすると、できる人だな...と思うかもしれない。
しかし、往々にして、正確な情報が伝わらないし、カタカナを使うことで当人は説明をサボっている。
カタカナを使うことで、効率化が図れるのであれば良い。
例えば、「投資に対して、それを回収できる」という意味で「"ペイ"できる」というのは、まだ理解できる。
それでも、新卒の時に聞いた時は意味がわからなかったが…
ところが、「合意をとる」というのを「"コンセンサス"を得る」というのは一体何の利点があるのか。
文字面が長くなっている上に新卒の人にはなお、分かりにくいだろう。
かくいう僕も、最近までは、カタカナを多用していた。
カタカナを使うと自分が"できる"ような感じがして心地良かったからだ。
「予定」って言えば良いのに、「スケジュール」とか、
「協議が必要」と言えば良いのに、「ディスカッションが必要」とか、
「期限」って言えば良いのに、「デッドライン」とか。
カタカナを使うほど、より生産性高い仕事をしているような気分になっていた。
ところが、仕事を8年もしていると、それは勘違いだったということに気づく。
カタカナにしても結局同じことを言っているに過ぎない。
同じ意味で通じていれば、まだ良い。
たまに、違う意味でカタカナが使われる時がある。
「次の会議に"ヘッズアップ"できるように調整しておくように」
なんて、上司が言っていた。
ヘッズアップとは、「早めに報告すること」や「お知らせ」「注意喚起」のような意味がある。
しかし、上記の会話の流れでは、そんなレベルではなく、重要な話を会議に持っていく必要があったので、使い方として適切ではない。
しかも、あまり使わない表現なので、指示を受けた当人は最初、意味を取りかねていた。
こういうカタカナの使い方が間違っているし、会話がうまく進まない状況になり得るので、やはりカタカナは乱用すべきでない。
そう考えてからは、できるだけ、カタカナは使わないようにしている。
エイコン族上司A「期限迫っているから、このタスクはASAPだな」
僕「承知しました。優先して、できるだけ早く対処します」
なんて、わざわざ言い直して、小さな反抗をしてみたりするが、全く気づいてくれない。
しかし、どんな革命も小さい力から始まるものだと思う。
これからも、カタカナは使わず、会話をしていきたいと思う。
そうすることで、不要なカタカナを使わないというマインドを1人でも増やしたい。
……あ。
終
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
