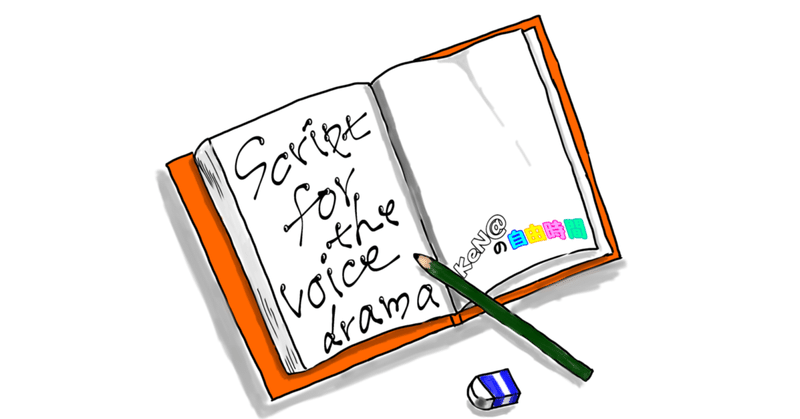
世界から僕が消えても
※この話にはイジメ、自殺未遂などの言葉が出てきます。気分が落ち込んでいる方、感情の引っ張られやすい方は読む際には自己責任でお願いします。
「ばいばい」
たったその一言で僕は世界から消えた。大多数の人は僕が消えたことにすら気付かないような世界。数日経てば気付く人も出てくるのかもしれないが、気付いたとして、そこで仮に一瞬話題にあがったとして...本当に一瞬のこと。
僕は幼い頃は誰とでもすぐに打ち解けることが出来る方だった。自分で言うのも何だが人付き合いがとても上手かったんだと思う。しかし、環境が変わるとそこに順応することができなかった。いや、正確には僕は以前と変わらず僕で在り続けた。そのことに不満を持つ人がいるということすら知らずに。そんな日常の中で突然の転機。それまで仲良く接してくれていた周りの人たちの突然の変化。幼かった僕には何が起こったのかわからなかった。だからこそ更に必死になった。それが状況を悪化させることにすら気付けずに。挨拶を交わすことさえ許されない。僕の頭の中には疑問符が浮かんでいた。そして、誰かの心に巣食う闇が少しずつ、本当に少しずつ、周りの人間も飲み込んでいく。ある日ようやく理解した。これは「イジメ」が起こっている。そしてその標的は...僕だ。理解したからと言って何がいけないのかわからない。どうすれば終わるのかわからない。それでも必死に笑顔だけは忘れないようにしていた。そうすれば誰かにその笑顔が届くと思っていたから。とある日のこと。教室へと入る入り口に鍵をかけられた。僕は考えた。外に回り込み、窓の縁へと手を掛けた。少し高さはあるものの排水溝へと繋がるパイプに足をかければ届かない高さでは無い。そして僅かに開いている窓の隙間に指を入れる。その瞬間激痛が走る。指を僅かにねじ込んだ窓を勢いよく閉められたのだ。反射的に手を引っ込める。指を見るとくっきりと窓の跡がついている。痛みを堪え、涙を堪え、大きく開いている窓の方へと走る。室内からは笑い声と誰かの「そっちに回れ」と言う声が聞こえる。先に辿り着いたのは僕だった。同じように窓へとよじ登る。そこに1つの手が伸ばされる。ふと見ると、普段から表立って助けてくれることはないが、イジメを助長することのない中谷くんの姿がそこにはあった。僕は少し反応に困りながらも中谷くんの手を掴んだ。中谷くんは安堵の表情を見せ、僕の手をしっかりと握ってくれた。-次の瞬間。僕の身体は宙に浮いていた。中谷くんが握った手を離すと、両手で思い切り僕を突き飛ばしていた。僕は背中から地面に叩きつけられた格好となり、呼吸が出来なかった。うずくまりながら混乱と悔しさと恥ずかしさから僕は泣いた。泣きながら横を見ると、その目線の僅か3センチ程先には花壇のブロックが見えた。ここに落ちて頭をぶつけでもした方がよかったのかな。そんなことを考えている間にも室内からは中谷くんと言うヒーローに向けての喝采は鳴り止まなかった。-これが、僕が人を信じなくなったきっかけ。小学一年生の頃のことだ。そしてその日からイジメは目に見えて酷くなって行った。教科書の落書きや椅子の上の画鋲なんてきっとまだ可愛い方だろう。切り付けられたランドセル。生ゴミだらけの上靴。机の中にはどこから集めてきたのか分からない大量の虫の死骸。僕はその頃から笑顔と涙を失った。そして、人を信じることもやめた。
4年生になる頃、酒とタバコを覚えた。何も不良に憧れていた訳では無い。周りにマウントを取りたかったわけでもない。この先の人生を悲観した。と言えば大袈裟になってしまうが、楽しさが分からない人生で、自分の身体を壊していく方法が当時の僕の頭ではそれしか思い付かなかった。煙が、アルコールが身体に入っていく度に、自分が蝕まれて行く気分を得ることができた。1歩ずつ、死へと近付いて行けている。矛盾しているが、それだけが生きる糧だった。そんなある日。放課後の教室で僕は1人、カッターナイフを手にしていた。自分の腕に少しだけ刃を当てる。小さな傷から血が出てくる。もう少し。別の部分に先程より少しだけ大きな傷を付けてみる。それ相応の血が出てくる。次はどこにしてみよう。そう考えているとドアの開く音がした。ふと見るとそこには中谷くんが立っていた。彼は僕に興味を示さず自分の席へと向かう。忘れ物でも取りに戻って来たのだろう。そして何も言わずにその場を立ち去ろうとしている。しかし、僕の手に握られている物に気付くと顔色が変わった。僕の自傷行為をやめさせようと思ったのか、それとも自身の身に危険を感じたのか、僕の元へと向かってきた。そして僕に向かって手を伸ばす。そう、あの手を。僕は振り払う。カッターナイフを握ったままの手で。僕の意思とは関係なく中谷くんの手を切り付けてしまった。次の日から僕はただのイジメられっ子から刃物を振り回す危険なイジメられっ子へとグレードアップした。そんなレッテルを貼られるくらいならいっその事本当に刃物を振り回してやろうかとさえ思えた。
中学校は僕の通っていた小学校ともう1つ別の小学校から全員、近隣の小学校2校から半数ずつの人達が集まることとなった。かつての僕なら物怖じせずにその中に溶け込んでいたのだろう。しかし、同じ小学校に通っていた人が全員いるのだ。入学から1週間もせずに刃物を振り回す危険なイジメられっ子の噂は広がった。そこから3年間は特筆するようなことはなかった。変わらない日々。忌み嫌われる日々。僕がお前らに何をした...?
高校生になると僕のことを知っている人間なんてごく僅かだった。変われるキッカケかもしれない。少し勇気を出してみるタイミングかもしれない。そう意気込んでいた僕はその1ヶ月後にはクラス全員の前で両手足を複数人に押さえつけられものの見事に衣服を全て剥ぎ取られていた。失っていたはずの感情が戻ってきた。何を期待していたんだろう。人を信じてこなかった自分が、人との接し方が不慣れな自分が、生きているだけで人を不快にさせているような自分が、変われるはずもなかった。淡い期待を抱いてしまった愚かな自分への苛立ち、久しぶりに僕は人前で泣いた。家に帰ると自室に籠り、両親と姉へ向けて手紙を書いた。でも遺書なんて書いたことがなかったから書き方がわからない。何枚も何枚も書いては丸め、いつしか文章を考えながら眠りに落ちていた。その眠りから僕を起こしたのは涙を流しながら僕の名前を呼ぶ姉の声だった。僕を夕食へと呼びに来て、眠ってしまっている僕の周りにたくさん丸められたルーズリーフ。そこに書き連ねられた家族へのお詫びの言葉。ただ事では無いと思ったと後日姉から話を聞いた。その日は父が帰宅するのを待ち、家族会議が行われた。僕は死ぬ方法を決めていなかった。先に遺書だけ書こうとしていた。それが見付かってしまい未遂にすら届かぬ状態で自殺を防がれた。何とも情けない。重苦しい空気の中、涙ながらに謝り続ける母。涙を流しながらも真剣に僕を叱る姉。そして無言で僕を見据える父。その家族会議は深夜にまで及んだ。それが終わると各々が自室へと戻る。僕の部屋に父が入ってくる。ドライブに行こうと家を連れ出され、無言のまま助手席に座る。しばらくすると車は人気のない駐車場に停まる。そこで父は僕に対して色々な話をしてくれた。自分の過去や親であることの責任、僕の未来...。僕は生まれて初めて父の涙を見た。翌日も仕事だと言うのに、帰宅した頃には空は明るくなっていた。
僕は学校へ行く。逃げることもしたくない。初めて少し闘おうと思った。そしてそれまでどこか客観的に見ていた自分を、自分の意思を持つことにした。しかし、反撃なんてしたくない。愚かで惨めで人の痛みがわからない可哀想で低俗な人間と同等になってしまうなんてのはまっぴらごめんだ。そんな奴らを反面教師にして、僕は僕なりの道をただ進んでいく。そう決めた。すると次第に僕への興味は薄れていった。なんだ、こんなことでよかったのか。それから様々なことが起こるが、僕は3年生の夏頃から不登校になっていた。家に引きこもり、夜な夜なパソコンを使って理想の自分を作り上げ、家族が起きてくる頃に自室に戻り眠ると言う生活が始まっていた。そこにはイジメとはまた違う理由があった。周りからの僕への興味がなくなり、高校生活を再スタートさせていた僕は、2年生の夏には部活の部長に任命され、教師からの推薦もあり生徒会役員としての活動も行っていた。少し、人から求められていると感じることが出来ていた。しかし、その1年間を過ごしたことで、どちらともを引退した時に自分の存在価値を見い出せなくなってしまった。またあの頃に戻ってしまうのではないかと言う不安もあった。そう、それが結果として僕に逃げる選択を与えた。こうして引きこもりを半年ほど続けた頃に担任と校長が家を訪ねてきた。今更何をとも思ったが、学校側としても生徒会役員を務めた人間に留年や自主退学などされたくはなかったのだろう。僕は出席日数の免除と言う条件を得て保健室登校を始めることとなった。その初日。久しぶりに家から出た僕を眩しいほどの晴天が待っていた。しかし、暗く淀んだ景色は僕の足を後ろへと引っ張る。それでも僕は進む。「約束」したから。その日から始まった保健室登校は結局卒業間近まで続いた。保健教諭からの薦めもあり、僕は幼い頃夢見ていた保育の道へと進むことに決めた。1人でも僕みたいな人間が減るように、そして1人でも僕みたいな人間を作ってしまう人間を減らせるように。
保育の短大に入った僕はやはり人付き合いが分からずに最初のうちは1人でいることが多かった。しかし、次第に周囲とのコミュニケーションも取れるようになってきていた。おかえり、かつての僕。その後精力的に様々な学校行事に取り組み、アルバイトを始め、人との関係性の構築も覚えた僕は、卒業を迎える頃には同窓会の会長に任命される程になっていた。
社会人を迎え、様々な「理不尽」という洗礼を浴びる。しかし、今までの僕があったからこそ今がある。僕は出会った全ての人間が僕を作り上げてくれていると思い、全ての人たちへ感謝しようと心に決めた。そう、それが中谷くんの様な相手でも。綺麗事だと言われるかもしれない。しかし、僕の人生を歩んできたのは僕だけなのだ。そして社会に出て10年目。僕はありがたいことに結婚をする。しかし、その生活は1年で破綻することとなる。この頃からまた僕の中で何かがうごめき始めていたのかもしれない。人への不信感を思い出す。いや、思い出すと言うよりも蓋をしていたものが外されたような感覚だった。それでもなんとか笑顔を絶やさず、時には気持ちのままに涙を流す。人間として成長しているかどうかは分からないが、自分の中に1本の軸を持つことで、自分を保っていた。
何度目かの転職を繰り返し、新たな保育園で働き始めた頃。理想論を大きく語る割には上に立つ人間の何と小さなことか。ここは失敗だった。そう思い始めていた。そんな時に世界中で新種のウイルスが猛威を振るう。これにより在宅勤務が増えた保護者が目に見えてストレスを感じているのが分かった。そしてそれは子どもにも。子どもは敏感で繊細であるが故、周りの大人の心の機微をすぐに感じ取る。それ以前よりも更に慎重に接していく必要がある。そのストレスは僕にも当然のしかかってきていた。そのストレスを発散させる為に、僕はまたネットを頼った。そこでは顔も名前も知らない相手がお互いに愚痴を言い合い、励まし合う姿が見られた。きっとみんな同じ、傷を舐め合いながら心の拠り所を探しているんだろう。ストレスと上手く付き合って行く、いつだかの僕が見たらきっと驚くだろう。いつの間にか人を信じることを拒絶することをやめていた。こうして現実とネットを使い分けながら僕自身の世界を作り上げて行く。
そんな最中、叔母が癌になったとの連絡を受けた。抗癌剤治療で髪が抜け落ちた姿を見た時にはショックで泣いてしまった。本人が気丈に振舞っているのに...。しかし、悪いことは続く。その叔母の旦那が自殺未遂を起こす。その首を吊っている状態を発見したのはそこの一人娘、つまり僕の従兄弟にあたる。従兄弟は高校を卒業したばかりだった。僕は従兄弟の気持ちを思うと胸が締め付けられた。母親が癌、父親が自殺未遂。僕だったらどう受け止めるんだろう。考え出すと眠れない日々が続いた。きっとこれは昔の出来事があったからこそ、人の気持ちを考えすぎてしまう節がある。結果、寝坊をしてしまい遅刻を繰り返す、仕事に身が入らない、そのことで自責の念が生まれてしまい眠るのが恐くなる。という悪循環に陥ってしまった。いずれ元に戻るだろうという考えは浅はかだった。次第に酷くなっていくのが自分でも分かった。周囲の人間からは病院に行くことを強く勧められた。結果、鬱病と診断され休職を余儀なくされた。
時間を持て余した僕は何をすればいいのか分からずにいた。眠る時間も起きる時間もバラバラで、でもそんな時にネットを開くとどの時間であろうが誰かがいた。その時だけは僕は本来の僕でいられたのかもしれない。だが、これが間違いであることにはこの時にはまだ気付けずにいた。どんどんとのめり込んでいく。そしてネット上とは言え、人間関係が構築され、大切な人が増えていく。その後仕事をクビになるが、その時でさえネットの対人関係で心の中の不安をかき消していた。一旦自分の現状と向き合い、リアルを優先させようとネットから離れてみた。しかし、ネットから離れようともリアルでの生活が早く進む訳ではなく、精神障害者手帳を手にしたあとでも行政とのやり取りが大きな負担となっていた。結局3ヶ月ほどでネットへと戻る。だが...みんな以前と変わらずに僕に優しく接してくれる。それはとてもありがたかった。けれど僕が心から楽しむことはできなくなってしまっていた。3ヶ月は短いようで長い。知らない空気がそこにはあった。恐らく、離れた僕にしか分からない空気。ここでまた僕の悪い部分が顔を覗かせる。「僕は誰からも必要とされていない人間なのではないだろうか。」きっとそれに対してそんなことないと優しい言葉をかけてくれる人が多くいることは分かっている。けど、決して1番なんかではない。いつでも誰かが僕の代わりになれる。いや、とても簡単に僕を越えて行くだろう。
...ほらね、やっぱり。口先だけじゃないか。みんなのいる所では心配しているような口ぶり。よくもまぁそんなにもスラスラと優しい言葉が出てくるもんだ。思ってもないくせに。なんだろう、この感覚...。あ、そうだ。中谷くんの手だ。あの時、僕を救うような素振りを見せておきながら、自分がその空気の中でのヒーロー、いや、あるいは被害者にでもなろうとしたようなあの手を思い出した。自分が1番仲が良いと思っていた相手にさえ嫌悪を感じる。いや、そもそも相手からしたらみんな好きでその中の1人に過ぎなかったってことだろう。そしてこれからもし対立したとして、表面的な紛い物の笑顔の作り方を知らない僕には分が悪い。今まで仲良くしてくれていた全員が敵に思えてしまう日が来る。そんな悲しい想いはわざわざしたくない。所詮ネットだ。逃げたって気付く人の方が少ないだろう。それに画面上から1人消えるだけなんだ。そんな奴に構っているほど暇でもないだろう。人の善意を踏みにじって、約束すら果たさずに。僕は結局嫌いな人種と同類になることに決めた。きっとみんなが忘れた頃でも、まだ僕は1人で葛藤していくんだろう。僕のそんなくだらない性格は僕が1番よく分かっている。そうだった。他人のことなんて信用しちゃいけないんだった。忘れてた。思い出させてくれてありがとう。
きっとこの世界から僕が消えてもすぐに他のことに飲み込まれて、存在していたことすら忘れ去られてしまう。だからみっともなく縋るのはやめておこう。この先自分で独りになることを決めたからこそ、必死に考えて最後に浮かんだんだ。
「ばいばい」
-END-
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
